今年(2020年)の正月にNHK・BSを何気なく観ていたら、”巨樹百景 神様の木に会う”という番組を放送していました。日本全国の巨樹を紹介していたのですが、この時「そういえば我が家には山口県の巨樹の本があったなぁー」とふと思い出し、本棚をゴソゴソ探してみると有りましたありました。その本の名は「やまぐち 祈りの108樹(2004年発行)」と「続 やまぐち 祈りの108樹(2006年発行)」の2冊です。2冊とも元山口県立山口博物館の学芸員をやっておられた 三宅貞敏さんの著作です。
本をパラパラとめくってみると、山口県にも 「国の天然記念物」になっている巨樹もあったり神社仏閣に存在してたりと、あんまり面倒なく見られるかもしれなくて面白そうだなと思った次第です。
というわけで、用事で何処かへ出かけたついでに県内の巨樹に会ってこようと「巨樹巡り」を始めました。2冊の本を参考にしながらの巡礼ですが樹木の専門家でも何でもない素人の私が探して歩くのですから、へんてこなブログになるかもしれません。
一応、私流に決め事を設定してます。
1.三宅先生の2冊の本に記述されている巨樹を目指します。
2.2冊の本に記述されている巨樹以外でも、これは載せた方が良いだろうという巨樹は【番外編】として記しています。
3.訪れた順に番号を記入していきます(年月日も)。また直近に巡った巨樹がいちばん上になってます。
4.場所がかなり分かりにくい所もあるので、全ての巨樹の地図を載せます。
2020年3月 庵主敬白
本をパラパラとめくってみると、山口県にも 「国の天然記念物」になっている巨樹もあったり神社仏閣に存在してたりと、あんまり面倒なく見られるかもしれなくて面白そうだなと思った次第です。
というわけで、用事で何処かへ出かけたついでに県内の巨樹に会ってこようと「巨樹巡り」を始めました。2冊の本を参考にしながらの巡礼ですが樹木の専門家でも何でもない素人の私が探して歩くのですから、へんてこなブログになるかもしれません。
一応、私流に決め事を設定してます。
1.三宅先生の2冊の本に記述されている巨樹を目指します。
2.2冊の本に記述されている巨樹以外でも、これは載せた方が良いだろうという巨樹は【番外編】として記しています。
3.訪れた順に番号を記入していきます(年月日も)。また直近に巡った巨樹がいちばん上になってます。
4.場所がかなり分かりにくい所もあるので、全ての巨樹の地図を載せます。
2020年3月 庵主敬白
注)5月になり三宅先生の本には3冊目(続続 やまぐち 祈りの108樹(2012年発行))があることが分かり、先生本人より寄贈していただきました。深謝いたします。これ以降は3冊を参考にして巨樹巡りを楽しみたいと思います。
 2020年5月 庵主敬白
2020年5月 庵主敬白
 2020年5月 庵主敬白
2020年5月 庵主敬白 11-⑨漢陽寺のアキニレほか(周南市鹿野上鹿野市)
倒壊消失 2025.4.17



曲水の庭で聞こえた漢陽寺です。平安時代の1374年(応安7年)に当時中国地方を掌握していた大内氏の祈願所として建立され、現在は臨済宗大本山南禅寺(京都市)の別格地として県内屈指の名刹と言われています。
漢陽寺はお庭が有名なお寺で、曲水の庭を始めとした7つの庭園は2021年(令和3年)に「国指定登録文化財」に認定されています。



アキニレですが、三宅先生の写真は2004年に撮影されて本は2006年に出版されてます。この時点で倒壊の情報はどこからか入っていたようでメモリアル扱いになっています。それでもと思い職員の方に聞いてみたのですが、やはり山門付近にあったアキニレは20年ぐらい前に倒壊してしまったとのことでした。
小さいのが鐘楼そばに在るはずなので探してみましたが、鐘楼に近寄ることができず(入館料がいる)外から探してみました。しかしニレ科の落葉樹なのでまだ葉が繁っておらずどれがどれだか分かりませんでした。山口県庁前のパークロードにもあるそうなので、機会があれば確認してみようと思います。




ちょうど外から覗っていた近くに老木ではありますか巨樹がありました。葉の様子からカヤではないかと思います。



本堂の後ろ側にも巨樹がありました。その高さや大きさからモミの樹ではないかと思います。
その他にはツガやクリの大きいのがあるそうですが、入館していないので確認できませんでした。
11-⑧森様のムクノキ(美祢市秋芳町江原) 2024.5.30



県道31号線を別府弁天池から美祢市於福方面へ行く途中に「⇦江原ウバーレ集落」という道路標識があり、以前からウバーレとは何のことなんだろうと思ってましたが、家に帰ればすっかり忘れてしまっていてそのまんまになってました。今回江原に行くのであらためてウバーレを調べてみると、ドリーネは石灰岩地等での小さな陥没地形の始まり(くぼみや穴)、ウバーレは複数のドリーネが合わさった凹地、ポリエはウバーレがさらに大きくなり低地になったもの・・ということらしいです。江原のように古くからウバーレの土地に人が住み始め、そこそこの集落を形作るのはとても珍しいそうです。ちなみに江原というのは「よわら」と読むそうで、「なんじゃそりゃー、誰も読めんじゃろー!」と独り言。
さて森様の場所ですが、これが一筋縄でいかないぐらい難儀しました。駐車場に車を停めて、ここらあたりだろうと行ってみたのですが、残念ながら行き止まりになってしまって渋々引き返します。途中に出会う人に聞けば分かるだろうと思ったのですが誰一人とも出会わず、それならば家を訪問して聞いてみようとしたのですが、これまたどこの家も返事が無く途方に暮れました。もういい加減疲れて車に戻ろうと歩いているとお寺が目につきました。ここならさすがに人が居るだろうと思い訪ねご住職の奥様にお聞きしたところ「私どもはお寺なので森様関係のお祭りには一切関与しておらず、場所も分かりません」とのことです。集落の人に誰一人として出会えず困っている旨話すと「あそこの辺りに農作業をしている人達がいるから聞いてみられたら?」と教えてくださいました。お礼を言っててくてくと言われた方へ歩いて行くと、3人の方が農作業の途中でした。一番のご老人に尋ねると「ああ、それはこの道を200mぐらい登って行くと左に石の階段があるからすぐに分かるよ」と言われました。おぉーこれで辿りつけるぞと勇んで歩き始めます。しかし行けども行けども石の階段とやらが見えません。もうなんぼ何でも違うだろうという所まで行ってからとぼとぼと引き返します。その途中に女房が「ひょっとして此処のことじゃないの」と言い出したのが最初の写真です。私たちは神社仏閣にある立派な石の階段をイメージしてたのですが、そうではなく自然石の半分以上埋もれた一段の階段だったんです。結果的にここで間違いなかったのですが「これを、石の階段て言うかなぁ―」と今でも思い出すたびボヤいています。
この入り口を入ってどんどん進んで行くと、やがていろんな巨樹に出会う場所に行き着きます。1本の巨樹にしめ縄が張ってありましたので、これが「森様のムクノキ」だと思います。



ムクノキは日本では古くからエノキと共に道の一里塚や分岐点、小祠などの日陰樹として植えられ、神社では神の依り代として保護され植栽されてきました。ここにもムクノキだけでなくエノキの巨樹もあります。



その他にはシュロやカゴノキ?なども見れます。
民俗誌によると、「上組の森は蛇、下組のそれは蛙を祀るとされる。土地の言葉で蛇はヤムシ、蛙はヒキという。いずれの森もムクノキを神木とし、集落の南北両端に位置する・・」と書かれています。カルスト地形の極端な乏水性を背景として、水神としての要素があると述べられているそうです。
11-⑦早二のクロガネモチ(美祢市秋芳町青景早二)
市指定天然記念物 解除 2024.5.30



この地には昔、嘉万八代の明教院別院が在ったという言い伝えがあるそうで、ここのクロガネモチはその当時に植えられた可能性もあります。現在は地区の集会所になっています。この場所も最初はさっぱり分からず、ストリートビューでやっと探し当てました。



クロガネモチは近寄ってみると、なかなかの大きさだというのが分かります。クロガネモチとしては県下でも有数の巨樹です。ただ残念なことに上部が写真の様に折損しており、高さ的には半分くらいになってしまったようです。それか有らぬか2017年(平成29年)に市指定天然記念物の指定を取り消されています。二十数メートルの高さが有ったみたいなので、見事な巨樹だったと思います。残念でなりません。



樹幹の下部には樹瘤が目立ち異形ですが、今まで見てきたクロガネモチの巨樹には下部に殆ど樹瘤が有りますので、私的には普通の感じです。三宅先生の写真でも内部が枯損していますが、現在ではもっと剥離がひどくなっている感じです。老木だとは思いますが、枝葉はまだ元気そうなのでぜひ長生きして欲しいものです。
11-⑥山領のヤマザクラ(美祢市秋芳町青景山領)
枯死消失 2024.5.30
三宅先生の写真では遠くからでもハッキリと見えるぐらい立派なヤマザクラの巨樹ですが、近くに行ってもそれらしきものは見れません。多分共同墓地にあるんだろうと見当をつけ探してみましたが、個人の墓地以外は草茫々となっていて探しようがありませんでした。
近所のあちこちを探してみましたが、それらしい巨樹はありませんでしたので諦めて帰ろうとした時たまたまご近所の方に出くわして、話を聞くことができました。「ああー、あのサクラは枯れてしもうたよ。なんせ100年も経ってるからなぁー、枝がボロボロと落ちてきてしもうてのー」とのことでした。
県内でも有数のヤマザクラの巨樹でしたが残念ながらまたしても間に合いませんでした。ネットで調べてみると、このヤマザクラを見に何回か通われた方のブログでは〇2013年4月:問題なく綺麗に咲いていた。2016年4月:根元で2分岐していた片一方がバッサリ切られていた。2022年11月:跡もかたも無くなっていた・・とのことでした。
11-⑤三島神社のカヤ(美祢市美東町赤佐山)
市指定天然記念物(社叢) 2024.5.30



三島神社は約300年前、伊豆の国(静岡県)三島から勧請したと伝えられています。三島社・河内社・稲荷社の三社相殿とのことですが三島社も河内社も水の神様なので、秋吉台を含む周辺地の水事情が大変だったという事が良く分かります。



カヤの巨樹は社殿の左右にあり、植栽されたものだろうと言われています。左の方が少しだけ大きいそうですが両方とも県内でも有数のカヤの巨樹となってます。
カヤの樹は古来よりその風合いの良さから、建築材・彫刻材・碁盤材として賞用されてきました。見た感じでも何か貫禄がありますよね。なかなかのものです。



社殿の背後に石灰岩の岩塊があり、カヤ・シラカシ・エノキ・ヤブツバキ・シュロ等があります。周辺地には野生のカヤがあるそうなので、背後のカヤも自然のものかもしれません。また、右の写真には「猿田彦大神」の石板が写ってますが、久しぶりに見ましたので嬉しくなりました。
11-④須賀神社のスダジイほか(美祢市美東町赤植畠)
2024.5.30




美東町の八幡池の側(県道28号線沿い)にフェンスで囲った鳥居が見えます。獣除けのフェンスなのかな?と一見奇妙に見えるこの鳥居が須賀神社の入り口になります。フェンスの門扉を開けて登って行くといきなり急登が始まり、枯葉で滑りやすくなってる登山道にタメ息が出ます。



登って行く途中にも巨樹がちらほら見えてきます。ハアハア言いながら急登をやっと登り切った所に石祠がありました。須賀神社は昔は荒神社といってたそうですが、明治に須賀神社と改められました。古くなった本殿をコンクリと石で造り変えたのは昭和44年と門柱に記載されています。



さて肝心のスダジイですが、三宅先生の写真のものがいくら探しても見つかりません。さんざん探してこれではないか?と見つけたのが上記の写真です。急坂と雑木に阻まれて近くに寄ることができず、写真もこれが精一杯でした。
本には3分岐していると書いてあり肉眼では(双眼鏡)確認してますので間違いないと思います。



その他にもモチノキ・タブノキ・ヤマモモの大きいのがあるそうです。
11-③毘沙門堂のイロハモミジ(美祢市美東町綾木四の瀬) 市指定天然記念物 2024.5.30



国道435号線をバス停の近くから綾木四の瀬の集落の方へ降りていきます。四つ角になった所に「四の瀬のイロハモミジ」の石柱が立ってます。ああー辿り着いたんだとホッとしたのもつかの間、石柱をよく見てもどちらの方へ行けばよいのか分かりません。矢印も何にも無いんです。石柱があるぐらいだからこの近くに違いないと車を停めて女房とあちこち探し回りましたが分かりません。通りがかる人を待ってましたがこれもさっぱりです。仕方が無いので遠くで農作業をしている人を見つけて大声で聞いてみました。するとその方も「ああ、それはあそこに携帯の中継局が見えるじゃろー、そこの直ぐ近くじゃけ―」と指さし大声で返されました。指さした山裾に確かにそれらしき中継局が見えます。お礼をこれまた大声で言って車で真っ直ぐ山の方へ向かいます。いい加減山に近くなった適当な場所に車を停めて歩いて目指します。そしてやっと辿り着いたのが写真の鳥居です。



階段を上がり鳥居をくぐったのですが、樹々に囲まれてとても薄暗い場所で最初は何処にあるんだろーという感じでしたが、ふと奥を見るとなにやら巨樹が見えます。思わずオオこれかーと声が出ました。



これまでもイロハモミジの大きな樹を何本か見てきましたが、これほどの巨樹は初めてです。どうしてこれほどの巨樹がこんな所に?(失礼!)と、暫くはイロハモミジがこんなに大きくなるんだと呆然としていました。



毘沙門天は多聞天ともいい、夜叉を率いて仏界の北方を守護する神様で、仏法護持・財宝富貴・戦勝の神として信仰されてきました。この樹も江戸時代に毘沙門堂回りの環境整備の時に植えられたらしく、少なくとも樹齢は200年以上
とのことです。
ぜひ紅葉の時期に来てみたいものです。
11-②大田の往還松(クロマツ)(美祢市美東町太田弁財) 2024.5.30



昔は山口市小郡から萩市への行き来はすぐ側を走っている県道28号線しかなかったので、ここの往還松(往時は大きなクロマツが3本あった)は必然的に車を運転していると目に入ったものでした。「弁財の3本松」と愛称されてたみたいですが、マツクイムシの害で今は1本が辛うじて残っているだけです。この残った1本も台風で上部が折損しており、往時の勢いは見る影もありません。
昔はどこにでも残っていた街道松としては、県内最後の1本となっています。

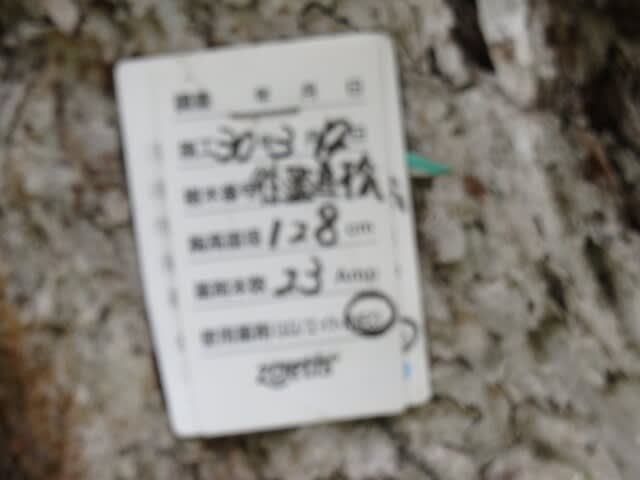

クロマツは樹皮が灰黒色で亀甲状に深く裂けて趣が出るため、古くから庭園や街道の並木として植栽されてきましたが、マツクイムシの害で殆どの巨樹・名樹が枯れてしまいました。ここのも側に行ってみるとその巨樹ぶりはなかなかのもので、3本あれば壮観だったろうにと残念でなりません。もっと早くに何らかの手を打っておけばと悔やまれます。近年ではマツ枯れからナラ枯れと続き少し前にはサクラ枯れが問題になってました。人間の手で早くに保護しなければ、いかな巨樹といえども簡単に枯れてしまうんだと今更ながらに思います。
11-①綾木八幡宮のシマモクセイ(美祢市美東町綾木宮の台) 市指定天然記念物 2024.5.30



綾木八幡宮は平安時代の末期1181年(養和元年)に宇佐八幡宮から勧請されました。今の地に再建されたのは1635年(寛永12年)と言われています。




さてシマモクセイです。初めて見ましたが案内板のように別名「ナタオレノキ」と呼ばれるぐらい硬くて器具や農具の柄として使われることが多いみたいです。樹皮を見ると本当に堅そうです。ここのは2本あり、大きい方は根元から3分岐しており1m離れて小さい1本が独立してます。




ここの樹林にはクロガネモチが多いとのことですが、他にもツクバネガシ・シイ・ウラジロガシ等の巨樹が有ります。例によりどれがどれだか分かりません。










