こんばんは。
Office Guriの諸橋直子です。
今日は「薬膳」のお話しを少し。
*
昨日寝ながらこの本を読んでました。
↓ ↓
http://officeguri.xsrv.jp/pchan/public/l.php?0001&0&320m1
そうしたらこんな素敵なことが書かれていました。
以下、前書きより抜粋。
↓ ↓
私がまだ子どものころ、
生理が近づいてくると母が食事の内容を変えていてくれました。
しょうがたっぷりのおかずを作ってくれたり、
寝る前にしょうが湯を飲ませてくれたり。
子どものころはあまりしょうがが好きではなかったけれど、
今思えば、これらはすべて、
体を温めて生理痛をやわらけるためにしてくれていたことです。
黒砂糖やあずきをよく食べさせられたのも、
血の流れを促して体のめぐりをよくするためでした。
また、今日はちょっと足がむくむな、と思ったら、
食事の塩分を減らして、すいかを食べたりウーロン茶をいつもよりたくさん飲みます。
これは水の流れを促して体のめぐりをよくするため。
ニキビができたら、解毒作用のあるゴーヤやとうがんを食べて老廃物を外に出し、
気の流れを促して体のめぐりをよくします。
そう。中国では、体のめぐりをよくするには
「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」
の3つの流れが大切だと考えられています。
この3つが滞っていると体調が悪くなり、
逆に、滞りをなくせば、体のめぐりがよくなるということです。
(ウー・ウェンのからだをあたためるレシピ 前書きより)
…。
体のめぐりを良くする。
ピンと来るような、こないような…。
もし○○さんがそう、お感じでしたら…。
ちょっと想像してみてください。
冬のさむーい日の夜、
暖房をいくら付けても全然部屋が暖まらない!という状況を。
(あ、ちなみに今このメルマガを書いている時点で
札幌の気温はマイナス8℃です・苦笑)
手足も冷たくなってしまい、何だか体の芯まで冷えてしまったなあ。
よし、こんな日は具だくさんの味噌汁だ!!
かつおと昆布でしっかり出汁をとろう。
お、大根もあるしニンジンも冷蔵庫にあるぞ?
玉ねぎもあった。
そうそう、豚バラも少しあったよね。
あれを切って味噌汁に入れるとまたいい出汁なんだよねえ…。
味噌を溶いて、おっと最後の仕上げにすりおろし生姜をたっぷり入れとこう!
くー!あったまるーーー!
何だか体の芯からぽかぽかしてきたなあ…。
はい!こんな経験、○○さんはないでしょうか?
寒い日に具だくさんの味噌汁を作って
生姜を入れて飲んだら、いつの間にか体がぽかぽかと温まり
気が付いたらちょっと汗ばむくらいになっていた。
そして、いつの間にか
手足の冷たさもすっかり飛んでいってしまった…。
こんなとき、「ちょっとめぐりがよくなっているかも?」と
感じることは無いでしょうか?
冷たかった指先に温かみが戻ったとき、
あ、血流が良くなったかも、と感じる人は多いはずです。
こんな風に、私たちが普段「何気なく食事に取り入れていること」の中にも
実は【薬膳】通じる知恵がいくつもあると言ったら
○○さんは驚きますか?
まず「生姜」。
「生姜」は多くの漢方薬の中にも配合されている
生薬(しょうやく)でもあります。
体を温める作用が強いのですが、これは
●体を温める=血のめぐりが良くなる
を意味します。
漢方薬に含まれる薬効成分の多くは、現代の医薬品同様
血流に乗って体の必要な箇所に届く仕組みです。
そのため、生薬に生姜が入っていることで
薬の成分がきちんと患部に届くことが期待できます。
これは非常に理に叶っていることです。
体の「めぐり」を「血のめぐり」と考えてみましょう。
血のめぐりが滞ると体にもあまり良い影響がなさそうなことは
容易に想像がつきますよね?
血液には細胞が必要とする酸素や栄養分が含まれています。
また、細胞から出た老廃物や二酸化炭素を回収し
適切に処理してくれる場所まで運ぶのもまた「血流」です。
その大切な「血流」が滞ってしまったら?
健康に影響が出るのは「犬」も「人間」も同様です。
私は普段、犬の食事について教える仕事をしています。
通常の講座では「現代の栄養学」に基づいた視点からのお話がメインです。
その一方で…。
もし、食材にも「身体を温めるもの」と「冷やすもの」があるとしたら?
一般栄養学とはまた違う視点で食材を見ることができたら…。
そうした「ちょっと違った見方」で食材を見ることによって
「うちの子の体質や体調に合わせた
【より】ベストな選択ができるとしたら」
○○さん、ご興味はおありですか?
うちの子の体質や体調に合わせた
よりベストな食材や調理法をチョイスするための知恵。
それが【薬膳】です。
ではその【犬のための薬膳】を学ぶためには一体どうしたらいいのか。
その方法について、明日の18時のメールで引き続きお伝えしますね。
今日はここまでです。
また明日、メールします。
ドッグホームケアセラピスト
諸橋直子
(終)
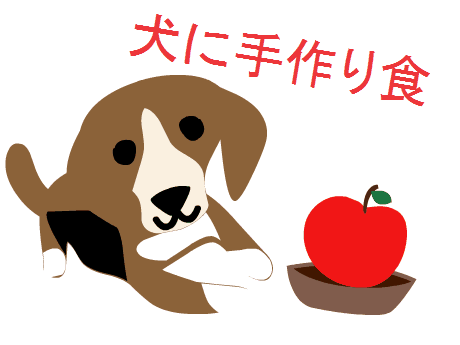
Office Guri
Office Guriの諸橋直子です。
今日は「薬膳」のお話しを少し。
*
昨日寝ながらこの本を読んでました。
↓ ↓
http://officeguri.xsrv.jp/pchan/public/l.php?0001&0&320m1
そうしたらこんな素敵なことが書かれていました。
以下、前書きより抜粋。
↓ ↓
私がまだ子どものころ、
生理が近づいてくると母が食事の内容を変えていてくれました。
しょうがたっぷりのおかずを作ってくれたり、
寝る前にしょうが湯を飲ませてくれたり。
子どものころはあまりしょうがが好きではなかったけれど、
今思えば、これらはすべて、
体を温めて生理痛をやわらけるためにしてくれていたことです。
黒砂糖やあずきをよく食べさせられたのも、
血の流れを促して体のめぐりをよくするためでした。
また、今日はちょっと足がむくむな、と思ったら、
食事の塩分を減らして、すいかを食べたりウーロン茶をいつもよりたくさん飲みます。
これは水の流れを促して体のめぐりをよくするため。
ニキビができたら、解毒作用のあるゴーヤやとうがんを食べて老廃物を外に出し、
気の流れを促して体のめぐりをよくします。
そう。中国では、体のめぐりをよくするには
「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」
の3つの流れが大切だと考えられています。
この3つが滞っていると体調が悪くなり、
逆に、滞りをなくせば、体のめぐりがよくなるということです。
(ウー・ウェンのからだをあたためるレシピ 前書きより)
…。
体のめぐりを良くする。
ピンと来るような、こないような…。
もし○○さんがそう、お感じでしたら…。
ちょっと想像してみてください。
冬のさむーい日の夜、
暖房をいくら付けても全然部屋が暖まらない!という状況を。
(あ、ちなみに今このメルマガを書いている時点で
札幌の気温はマイナス8℃です・苦笑)
手足も冷たくなってしまい、何だか体の芯まで冷えてしまったなあ。
よし、こんな日は具だくさんの味噌汁だ!!
かつおと昆布でしっかり出汁をとろう。
お、大根もあるしニンジンも冷蔵庫にあるぞ?
玉ねぎもあった。
そうそう、豚バラも少しあったよね。
あれを切って味噌汁に入れるとまたいい出汁なんだよねえ…。
味噌を溶いて、おっと最後の仕上げにすりおろし生姜をたっぷり入れとこう!
くー!あったまるーーー!
何だか体の芯からぽかぽかしてきたなあ…。
はい!こんな経験、○○さんはないでしょうか?
寒い日に具だくさんの味噌汁を作って
生姜を入れて飲んだら、いつの間にか体がぽかぽかと温まり
気が付いたらちょっと汗ばむくらいになっていた。
そして、いつの間にか
手足の冷たさもすっかり飛んでいってしまった…。
こんなとき、「ちょっとめぐりがよくなっているかも?」と
感じることは無いでしょうか?
冷たかった指先に温かみが戻ったとき、
あ、血流が良くなったかも、と感じる人は多いはずです。
こんな風に、私たちが普段「何気なく食事に取り入れていること」の中にも
実は【薬膳】通じる知恵がいくつもあると言ったら
○○さんは驚きますか?
まず「生姜」。
「生姜」は多くの漢方薬の中にも配合されている
生薬(しょうやく)でもあります。
体を温める作用が強いのですが、これは
●体を温める=血のめぐりが良くなる
を意味します。
漢方薬に含まれる薬効成分の多くは、現代の医薬品同様
血流に乗って体の必要な箇所に届く仕組みです。
そのため、生薬に生姜が入っていることで
薬の成分がきちんと患部に届くことが期待できます。
これは非常に理に叶っていることです。
体の「めぐり」を「血のめぐり」と考えてみましょう。
血のめぐりが滞ると体にもあまり良い影響がなさそうなことは
容易に想像がつきますよね?
血液には細胞が必要とする酸素や栄養分が含まれています。
また、細胞から出た老廃物や二酸化炭素を回収し
適切に処理してくれる場所まで運ぶのもまた「血流」です。
その大切な「血流」が滞ってしまったら?
健康に影響が出るのは「犬」も「人間」も同様です。
私は普段、犬の食事について教える仕事をしています。
通常の講座では「現代の栄養学」に基づいた視点からのお話がメインです。
その一方で…。
もし、食材にも「身体を温めるもの」と「冷やすもの」があるとしたら?
一般栄養学とはまた違う視点で食材を見ることができたら…。
そうした「ちょっと違った見方」で食材を見ることによって
「うちの子の体質や体調に合わせた
【より】ベストな選択ができるとしたら」
○○さん、ご興味はおありですか?
うちの子の体質や体調に合わせた
よりベストな食材や調理法をチョイスするための知恵。
それが【薬膳】です。
ではその【犬のための薬膳】を学ぶためには一体どうしたらいいのか。
その方法について、明日の18時のメールで引き続きお伝えしますね。
今日はここまでです。
また明日、メールします。
ドッグホームケアセラピスト
諸橋直子
(終)
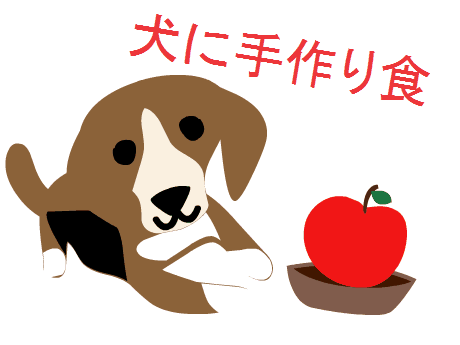
Office Guri









