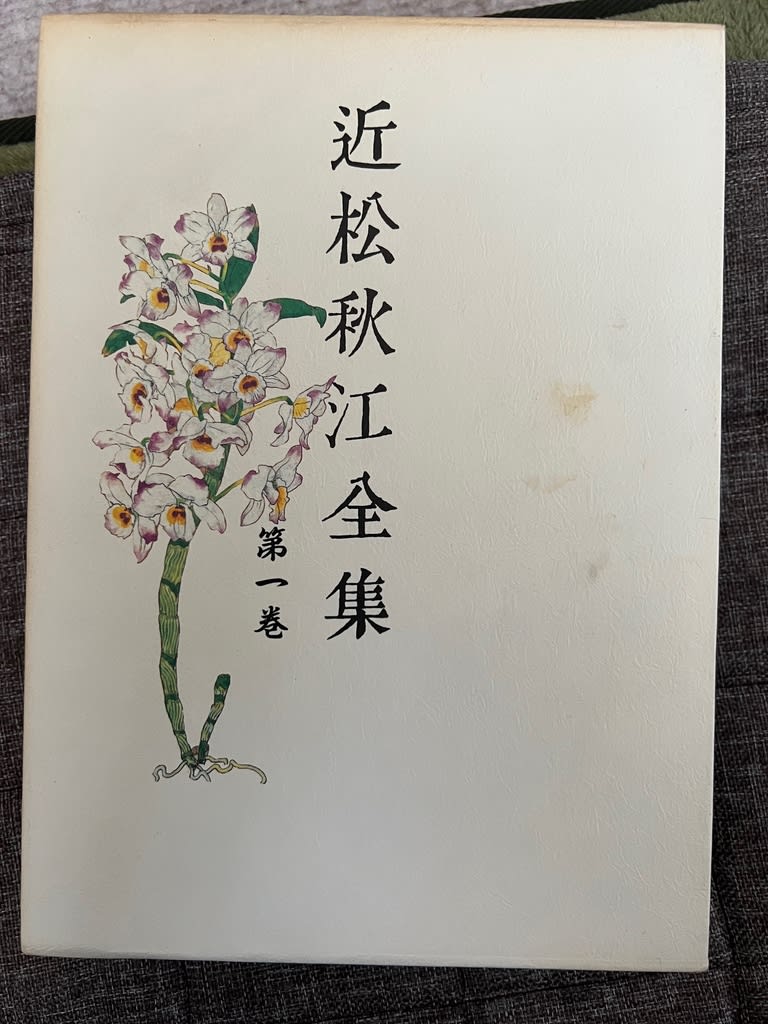
思い切って近松秋江全集をババーンと勢いで買ってしまったのである。
近年稀に見るどハマり方で、探偵小説以外の読書において、佐藤春夫、宇野浩二、横光利一など、適当に手を出してはみたが、どれもピンとこない。
この情痴文学の書き手、近松秋江を知り、私は私小説の面白さ、脈も無いのに果てしなく逃げた女を追いかけていく、ある種ストーカー文学とも言える情痴文学の魅力に、すっかり魅了されてしまったのだ。
選集では物足りない。その全貌を知るためには、全集を揃える他はなかった。値は張ったが後悔はしていない。
それにしてもこの作家の令和における埋没具合はどうか。決して埋もれさせて忘れ去られるには惜しい作家である。
まず一本目『食後』を読んだ。冒頭に置かれているので、これが商業作品一本目、デビュー作なのであろう。
ごく短いものである。
後年の作品に見られる語りの面白さの片鱗が、既に見て取れる。
作家志望と弁護士志望の男が狭い宿で同居している。昼飯を食い終わり2階に上がって寝転び、過去の女性遍歴を語る、というもの。
互いに三十くらいの年齢である。弁護士志望の男が、十四の時の、それも下宿に住んでいた家主の娘、年上の娘とのやり取りを語って聞かせる、というのが大まかな筋。
二十歳の娘は不用意に男の部屋に入ってくる。十四なので弟の様に思っているのだろう。
しかし男の方はしっかり女を意識しており、性的に悶々としている。
身体が触れたり、時には密着したり、そうしたことに耐えられず、結局寮を引き払う。隣に住んでいた仲の良い同級生は怒り、学校で会っても溝が深まって気まずい。
しかし抜け出した理由が宿の娘との関係で悶々としていた事を打ち明けるのが恥ずかしく、同級生を嫌って出て行ったと思われているのが今でも気がかりで、誤解を解けなかった事を未だ後悔している、と言う話。
一種の告白体で、それを小説に落とし込んでいる。人の秘密を聞く面白さ、語りで相手の情景を思い浮かべる様の面白さ、が眼目であろう。
デビュー作からしっかり女とのやり取りをえがいてくれている。ここからどこまで飛翔するのか。楽しみである。












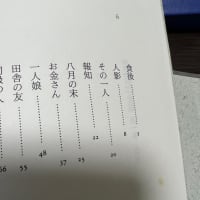


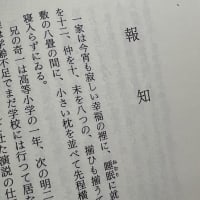




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます