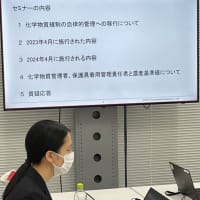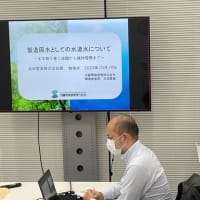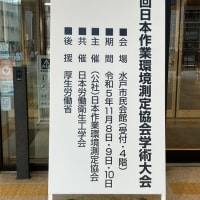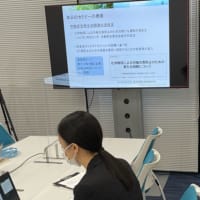今回から数回に分けて、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下建築物衛生法)の水質検査について紹介致します。
ポイントは3つあり、①6ヶ月ごとの検査、②6月~9月に行う検査、③3年ごとに行う検査があります。
初回は建築物衛生法における定期検査において、①6ヶ月ごとに1回の水質検査についてお話します。
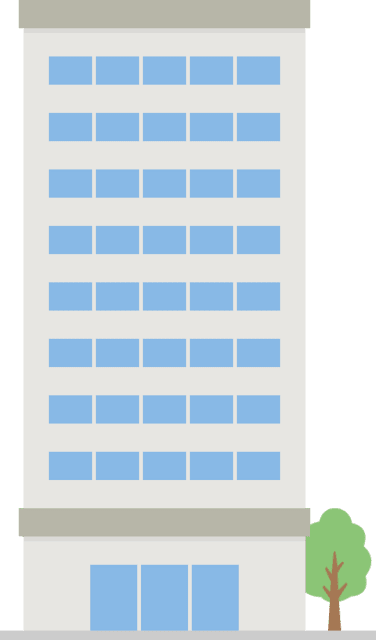
6ヶ月ごとに1回の水質検査では、対象となる項目が16項目あります。この項目は、11項目(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度)と、金属項目の4項目(鉛、亜鉛、鉄、銅)に蒸発残留物の計5項目を追加した項目となります。
この16項目について6ヶ月ごとに1回検査を行いますが、金属項目4項目と蒸発残留物は検査結果が基準内だった場合、次回の水質検査についてのみ省略できることとなっています。
従って、上記5項目が基準内の結果であれば、16項目と11項目を交互に行う形となります。
この省略については、建築物衛生法の中で明記されているのではなく、平成20年健発第0125001号(厚生労働省)にて明記されています。
また、中央式の給湯設備の場合、給湯水においても同様の検査を実施するようにと、平成15年健衛発第0314002号(厚生労働省)にて定められています。
これらについては、当社発行資料ザ・ナイツレポート「KR(08005):特定建築物における水質検査(平成26年4月1日施行)」にて取りまとめています。
是非、適切な水質管理にお役立てください。
次回、第2回では、ポイントで2つ目に挙げた「6月~9月に行う検査」として、「消毒副生成物」の話を致します。
楽しみにお待ち下さい。