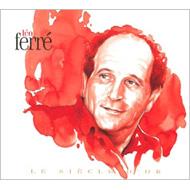
フランスのシャンソン界には、しばしばソングライター(歌手を兼ねていることが多い)と歌手との素晴らしいコンビネーションが生まれる。フランシス・レマルクとイヴ・モンタン、ジョルジュ・ブラッサンスとパタシュー、セルジュ・ゲンズブールとジェーン・バーキン(もしくはブリジット・バルドー)などが良い例である。
#320(ミラボー橋)でも触れたレオ・フェレとカトリーヌ・ソヴァージュとの関係もその一例で、しかも最も鮮やかな成功を収めた例と言ってもよいだろう。レオ・フェレは「サン・ジェルマン・デ・プレの鬼才」と言われたシンガー&ソング・ライターであり、しかも思想家、哲学者、無政府主義者であった。モナコ生まれの彼は、第二次世界大戦後すぐに、パリの酒場やキャバレーでピアノを弾きながら自作曲を歌い始めた(画像は彼の代表曲を集めたベスト盤の2枚組CD)。しかし、一風変わった彼のシャンソンは、聴衆に受けず理解もされなかった。そんなある日、フェレが出演していた店でデビューすることになったのがソヴァージュだった。1948年のことである。
フェレはシンガーとしては声量に乏しく自分の声に自信がなかったが、激しさと洗練を兼ね備えたソヴァージュの歌声に、自作曲の歌い手としての適性を見出し、協力を惜しまぬようになる。1954年、男というものの実態をえぐりだすような痛快な歌“L'HOMME(男)”が大ヒットした。この歌の伴奏をしたのが、無名時代のミシェル・ルグランのオーケストラであった。
そして、続いて大成功を収めたのが“PARIS CANAILLE(パリ野郎)”である。この作品のセンセーショナルなヒットによって、作者のレオ・フェレ、歌ったソヴァージュは名声を確立し、編曲と伴奏を担当したミシェル・ルグランも出世の糸口をつかむことになった。
1953年レオ・フェレが作ったこの曲は、ソヴァージュが創唱し、フランス中にセンセーションを起こした。イヴ・モンタンらもレコーディングするようになり、そのヒットにあやかって1955年にはこれを主題歌にした映画「パリ野郎」が製作され、ゲスト出演したソヴァージュが劇中でも歌った。邦題は「パリ野郎」とされているが、「パリのはぐれ者」とか「パリのごろつき」というニュアンスのようである。
シャンソンの歌詞は、時折どぎつい表現が出てくるので戸惑うことがある。文化の違いなのであろうか、日本ではまず放送禁止歌になりそうな内容でも、フランスでは違和感がないのであろう。「パリ野郎」は「スリ」、「かっぱらい」「強盗」など犯罪者の歌でもある。越路吹雪が歌った岩谷時子の訳詞では基本的にはパリ讃歌になっているが、原詩では、「ごろつきどもの町パリ、手はすぐに他人様の持ち物に、警察には覚えはめでたたいよ、ネオン輝く町で、どうせろくなことはやらかさない、だけどとにかく素敵だよ、ホールドアップは1年中、特別製の車をご使用さ、パチンとはずす安全装置、ぶっぱなすさ、さあ有り金をそこに並べやがれ、さもなきゃひと思いにぶっ放すぜ…」(くわはらひかる訳)という具合である。
これが、「町中うるさくアコーデオン流れて、油断もスキもない町だが、素敵さ、リラ咲き乱れて、お上りさんから、しこたま儲ける町だよ、おおセ・シ・ボン、年中男はお祭り気分で、女は浮気に精出す、おおセ・シ・ボン…」(岩谷時子訳詞)となるわけだ。

画像は、来日記念盤として発売されたソヴァージュのベスト盤のLPで、1971年までのレオ・フェレの書いた主な楽曲を中心に収められている。1960年代になると、ロックの影響を受けたイエ・イエのブームが巻き起こり、フランスのショウ・ビジネス界を席巻し、ソヴァージュも、一時歌から遠ざかり、演劇活動に専念していた。イエ・イエの嵐が去り、シャンソン界に復帰したソヴァージュの歌唱はさらに洗練された円熟味が加わり完成度が高まっていた。
/////////////////////////////////////////////
「酔い出して一人世界を負う気分」
#320(ミラボー橋)でも触れたレオ・フェレとカトリーヌ・ソヴァージュとの関係もその一例で、しかも最も鮮やかな成功を収めた例と言ってもよいだろう。レオ・フェレは「サン・ジェルマン・デ・プレの鬼才」と言われたシンガー&ソング・ライターであり、しかも思想家、哲学者、無政府主義者であった。モナコ生まれの彼は、第二次世界大戦後すぐに、パリの酒場やキャバレーでピアノを弾きながら自作曲を歌い始めた(画像は彼の代表曲を集めたベスト盤の2枚組CD)。しかし、一風変わった彼のシャンソンは、聴衆に受けず理解もされなかった。そんなある日、フェレが出演していた店でデビューすることになったのがソヴァージュだった。1948年のことである。
フェレはシンガーとしては声量に乏しく自分の声に自信がなかったが、激しさと洗練を兼ね備えたソヴァージュの歌声に、自作曲の歌い手としての適性を見出し、協力を惜しまぬようになる。1954年、男というものの実態をえぐりだすような痛快な歌“L'HOMME(男)”が大ヒットした。この歌の伴奏をしたのが、無名時代のミシェル・ルグランのオーケストラであった。
そして、続いて大成功を収めたのが“PARIS CANAILLE(パリ野郎)”である。この作品のセンセーショナルなヒットによって、作者のレオ・フェレ、歌ったソヴァージュは名声を確立し、編曲と伴奏を担当したミシェル・ルグランも出世の糸口をつかむことになった。
1953年レオ・フェレが作ったこの曲は、ソヴァージュが創唱し、フランス中にセンセーションを起こした。イヴ・モンタンらもレコーディングするようになり、そのヒットにあやかって1955年にはこれを主題歌にした映画「パリ野郎」が製作され、ゲスト出演したソヴァージュが劇中でも歌った。邦題は「パリ野郎」とされているが、「パリのはぐれ者」とか「パリのごろつき」というニュアンスのようである。
シャンソンの歌詞は、時折どぎつい表現が出てくるので戸惑うことがある。文化の違いなのであろうか、日本ではまず放送禁止歌になりそうな内容でも、フランスでは違和感がないのであろう。「パリ野郎」は「スリ」、「かっぱらい」「強盗」など犯罪者の歌でもある。越路吹雪が歌った岩谷時子の訳詞では基本的にはパリ讃歌になっているが、原詩では、「ごろつきどもの町パリ、手はすぐに他人様の持ち物に、警察には覚えはめでたたいよ、ネオン輝く町で、どうせろくなことはやらかさない、だけどとにかく素敵だよ、ホールドアップは1年中、特別製の車をご使用さ、パチンとはずす安全装置、ぶっぱなすさ、さあ有り金をそこに並べやがれ、さもなきゃひと思いにぶっ放すぜ…」(くわはらひかる訳)という具合である。
これが、「町中うるさくアコーデオン流れて、油断もスキもない町だが、素敵さ、リラ咲き乱れて、お上りさんから、しこたま儲ける町だよ、おおセ・シ・ボン、年中男はお祭り気分で、女は浮気に精出す、おおセ・シ・ボン…」(岩谷時子訳詞)となるわけだ。

画像は、来日記念盤として発売されたソヴァージュのベスト盤のLPで、1971年までのレオ・フェレの書いた主な楽曲を中心に収められている。1960年代になると、ロックの影響を受けたイエ・イエのブームが巻き起こり、フランスのショウ・ビジネス界を席巻し、ソヴァージュも、一時歌から遠ざかり、演劇活動に専念していた。イエ・イエの嵐が去り、シャンソン界に復帰したソヴァージュの歌唱はさらに洗練された円熟味が加わり完成度が高まっていた。
/////////////////////////////////////////////
「酔い出して一人世界を負う気分」















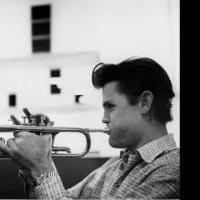


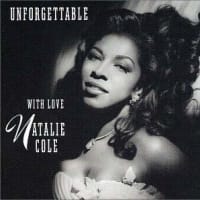
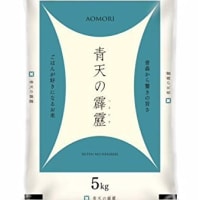
先日は、外れたコメントを書きこんでしまい、失礼いたしました。
レオ・フェレとカトリーヌ・ソヴァージュのこと、大変興味深く拝読しました。
私はシャンソンにもあまり明るくないのですが、それでも、フランシス・レマルクとイヴ・モンタン、セルジュ・ゲンズブールとジェーン・バーキン(もしくはブリジット・バルドー)のコンビの名前くらいは存じています。
これらの人たちが映画とも深くかかわっていることも大きいのでしょうが。
特に、ゲンズブールの印象は強烈でした。
その意味では、誠に申し訳のないことながら、レオ・フェレとカトリーヌ・ソヴァージュのことはあまり存じ上げず、残念な限りです。
ところで、ソヴァージュの意味は確か「野性的」とか「野蛮」みたいなニュアンスであったように記憶しているのですが、これはカトリーヌさんの本名なのでしょうか?
外れたコメントなんて、全く思っていませんので、ご安心くださいませ(笑)。
カトリーヌ・ソヴァージュは、もちろん芸名で、本名はたしかジャニーヌ…なんとかと言ったと思いますが、残念ながらそこまでは存じ上げません。
Sauvageというのは、英語のSavageと同様の意味ではなかったかと思います。
これでもはるか昔の学生時代は第二外国語はフランス語だったのでありますが、仏語の辞書はもはや手元にもなく、お恥ずかしい限りです…