3月14日、バレンタインデーですが、市役所庁舎には朝からそんな雰囲気はなく、幹部会そして9時には全員協議会、東北関東大震災の支援体制についてのものです。
前日にも書いたとおりすでに消防3名、水道から2名が被災地にて支援活動をしています。水道からの職員が友達なので、水道よりのニュースが主になりますが、みんな大変です。
給水支援の友達からは昨夜から連絡がなかったので、心配していましたが、先ほど電話があり安心しました。今日は仙台で給水支援活動をしたらしいです。仙台もずっと余震が続いていて、1時間前に通った道が給水のために帰るときには普通に陥没していたりするそうです。17日には交代の職員が現地にはいるそうです。寝不足でかなり疲れてるとのことです。とにかく無事に帰ってきてほしい。がんばれ!おっちゃん!(吉野川護岸壁画ブログより)
今日は、平成23年度の新人職員研修会がありました。去年に続いて市役所の施策の紹介と言うことで20分間話をさせてもらいました。
みんな緊張していて、フレッシュマンの緊張した雰囲気がビシビシ伝わり、怖いぐらいでした。でも、彼らも正直なところは「つまんねぇ話ばかりしやがってよ~」「4月になったらネクタイして大変なんだから、それまでは自由にさせてくれや」ってな感じなのかなあ?いやっ、そんなはずはない 真面目そうな人たちばかりだったじゃないか
真面目そうな人たちばかりだったじゃないか
僕なんかはダメだったなあ。振り返ってみたら?僕の移動歴を振り返ると、入った年の平成3年度は同和対策課、4年~6年度は保健福祉課、7年~8年度農村整備課、9年~10年度農業共済出向、11年~14年度建設課、15年~16年度総務課、17年~20年度管財課、21年22年度ドリームプラン。ん~この年度末で実に丸20年、20年も勤めているのに分からないこと多いなあ イイノダロウカ
イイノダロウカ
そういうことで(何が )、今日から何日間は職員研修で話したくても十分話せなかった内容を書き込みます。新人の方も見てくれているかも知れません。
)、今日から何日間は職員研修で話したくても十分話せなかった内容を書き込みます。新人の方も見てくれているかも知れません。
 去年のリーダー塾で小田切先生に教わった「幸福の政治経済学」の話をしました。以下はその紹介です。
去年のリーダー塾で小田切先生に教わった「幸福の政治経済学」の話をしました。以下はその紹介です。
本の説明ね
従来の経済学では「幸福」は非科学的な概念とされてきた。しかし今では、政治学、心理学、社会学から得られた理論を統合することで、極めて説得力ある議論が可能となった。その最新の研究成果といえる本書では、所得、失業、インフレ、政治システムなどが幸福に与える影響を詳細に調べ、金銭的な充実のみが幸福を決めるのではなく、より進んだ民主的な政治体制こそが人々の幸福感を高めることを明らかにしている。市場原理主義の限界が叫ばれる昨今、我々が目指すべき方向を考える上でも、本書内容は極めて示唆に満ちている。
主な調査結果ね
- 加齢とともに不幸になるということはない。むしろ若者と高齢者は中年層より幸福
- 女性は男性よりも幸福だが、その差は小さく近年消滅傾向にある
- 健康は重要な幸福要因である
- 独身者は既婚者より幸福度が低いが、近年縮小傾向にある
- 高い学歴は、幸福を保証はしないが幸福度を上げる要因にはなっている
- 外国人は、その国の国民よりも幸福度が低い
- 途上国においては幸福と所得の間に相関があるが、先進国においては幸福と所得の間に相関は認められない
- 失業は心理的・社会的なコストをもたらし幸福に多大な影響を与える
- インフレは幸福に多大な負の影響を与える
- 優れた政治制度は幸福を増大させる
- 個人の幸福は、政治に対する意思決定の結果だけでなくプロセスの正当さによっても影響される
を踏まえて、小田切先生のコラム
幸 福 の 経 済 学
東京大学大学院 助教授 小田切 徳美
いま、経済学の分野で、幸福研究(ハッピネス・リサーチ)が注目されている。「幸福」とは何か。それは、何によって決まるのか。計量経済学的な研究が新たな挑戦を始めている。
先頃、その一つの到達点であるフライとスタッツァーによる『幸福の政治経済学』が日本でも翻訳された。書店の経済学関係書「売れ筋ベストテン」にもランクされており、おそらく経済学関係者以外の関心も高いのであろう。
この書の中で、特に興味深いのは、スイスの州住民の幸福感の差違は、州ごとに異なる直接民主制の充実程度によって、かなり説明できるという計測結果である。これは、幸福感は所得等の経済的要素とは必ずしも強く結びついていないという分析を前提として導かれたものである。つまり、経済的豊かさと幸福感にはギャップがあり、それを埋めるものが、人々の政治的参加度であると解釈することもできる。
政治的参加状況が幸福感を高めるというのは、意外な結論に思われるかもしれない。しかし、本書をいち早く紹介した林敏彦教授(放送大学)も指摘されているように、日本でも高度成長期以降の1人当たりGDP急増期に、人々の幸福度は少しも上昇しなかったことを考えると、幸福感と経済的豊かさとの乖離、その要因としての政策的意思決定における住民参加の不十分性という構図が見えてくるように思われる。
こうしたことを考えると、市町村合併が進む中で、住民自治の砦として、行政との協働により「小さな自治」を築こうとする動きが、あらためて輝いて見える。京都府美山町、兵庫県加美町や広島県旧高宮町(現安芸高田市)で先発した「振興会」(美山)「地域振興会」(旧川根)や「住民会議」(加美)等である。顔の見える範囲に地域自治組織を構築し、またそれを拠点として住民が行政の意志決定にも参加していくという挑戦は、住民自らが幸福を享受しようとする動きと言える。そうであれば、「小さな自治づくり」は「大きな幸福づくり」であろう。
日本での本格的な幸福研究は今後の課題である。しかし、筆者の経験でも、いま名前をあげた地域の人々は、老若男女を問わず、笑顔が特に輝いている。日本においても、幸福研究が成り立つ可能性は十分ある。
最後に僕なりの考え
以上のことから、自分で考え自分で行動することが楽しいことがわかります。役場がかってに計画して、押しつけられたことだけをやってたんじゃ住民の人も楽しくないのよね。
例えば、橋の噴水、電柱の地中化、石畳風の道路の整備、からくり時計、足湯、これらの施設を遠くからやってきた友達に見せると、お金のかかった施設ではしゃいで喜ぶと同時に「おいおい、こんなお金の使い方して、美作市大丈夫?」とびっくりするのである。
でも、その施設を地元の人がそんな風に喜んでいるようにはあまり見えない。つまり、住民の意思があまり反映されていないから喜んでないような気がする。本当に住民がその施設を求めていたら、すごいお金がかかっている事業なんだからもっと喜んでいたはずです。「そんなことはない。コンサル会社が入ってちゃんとワークショップをやっているじゃないか」と言われるかも知れません。だけど、僕らも住民も勉強不足でした。「言っても仕方ない」とか「もう決まっている計画だから」とあきらめもあり、本当のワークショップの意味もわからないままでした。ワークショップは説明会ではなく、そこに参加した人の話し合いの中から答えを探し出すものです。
ちょっと話がずれてしまいました。住民の中には、全部市役所にやらせることが、いいことだと思っている人もいます。でも、実は「できることは自分でやる」その方が楽しくて幸せなんですよ。僕個人の意見ですが、上から押しつけられただけの仕事は楽しくありません。でも、自分が「これはやらなくては」と思えることは、いくら苦労しても充実感があるものです。
僕らはなるべく多くの人の声を聞き、みんなが求めていることを実施しなくてはいけません。実際のところ、まだまだ公と民の壁は高いものがあり、ジレンマの日々が続いていますが、その障害をどんどん取っ払ってみんなの想いを市政に生かし実現する。それが市民の幸福感につながるドリームプランだと思っています。














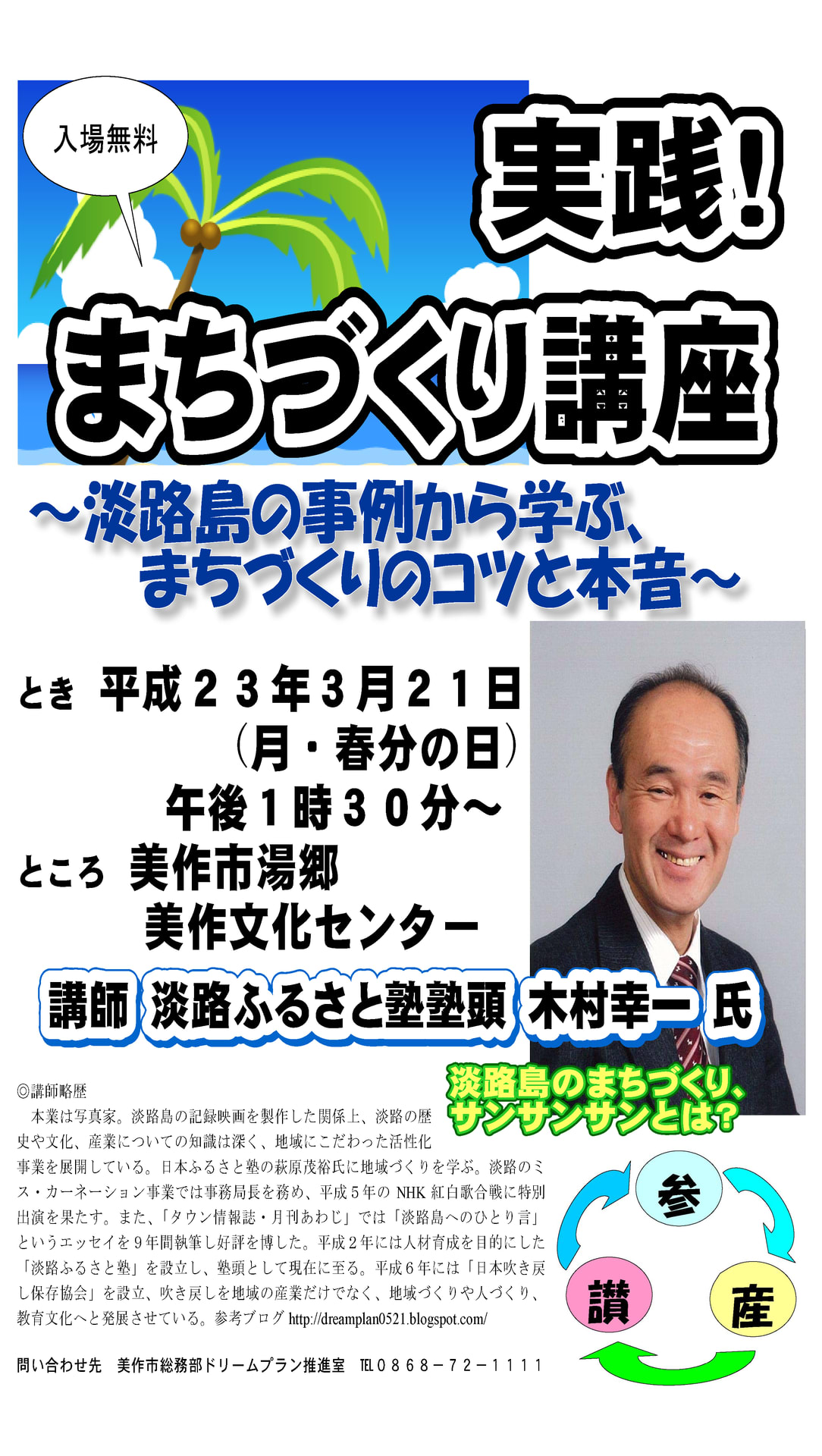


 フットワークが軽く、まちづくりに熱い意見もあり非常にうれしいです
フットワークが軽く、まちづくりに熱い意見もあり非常にうれしいです
 東大卒のエリート官僚出身ですが
東大卒のエリート官僚出身ですが 総務省時代は9to5だったらしいです。朝の9時~翌朝の5時なんてのがザラなんですって
総務省時代は9to5だったらしいです。朝の9時~翌朝の5時なんてのがザラなんですって

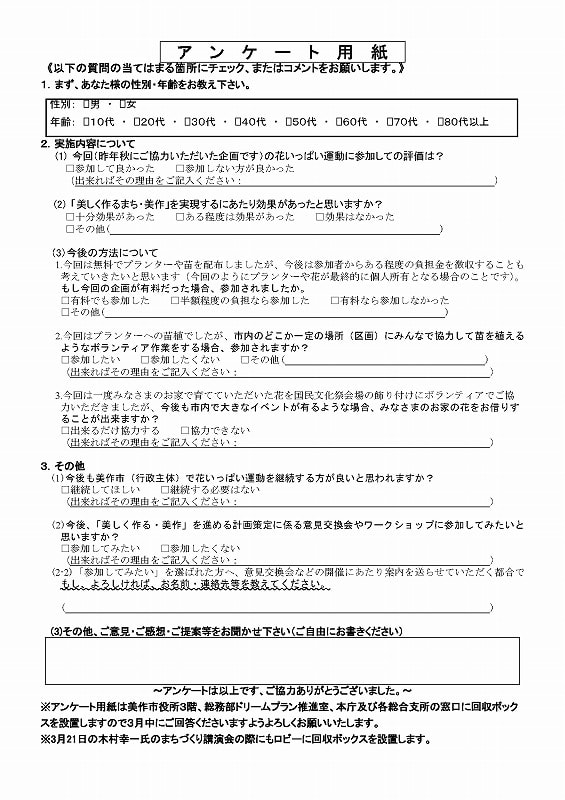




 こんなすばらしい考え方の人が美作にいたんだと改めて感じられる塾にしていきたいと思います。
こんなすばらしい考え方の人が美作にいたんだと改めて感じられる塾にしていきたいと思います。



 」なんて、妄想を膨らませながらうーんやっぱり楽しんできました
」なんて、妄想を膨らませながらうーんやっぱり楽しんできました チケット完売する前にね
チケット完売する前にね 2000円でした。
2000円でした。

 シャンデリアの街で眠れずに トランジスタラジオがブガる~
シャンデリアの街で眠れずに トランジスタラジオがブガる~