久しぶりにブログ更新です。
2度目の育児休暇をいただき、2017年7月から復職した瀧上まいまいです(旧姓・家倉)。
ちょこちょことですが、
キープのインタープリターが大事にしている考え方や
研修などのプログラムデザイン、こだわりなどを発信していきたいと思っています。

今回は、タイトルにある「指導者のかかわり方」について。
でも、関わり方ってどういうこと??
例えば、「同じものさがし」というアクティビティ。
あらかじめ指導者が拾っておいた自然物を参加者にみせ、
制限時間を決めて同じものを探してきてもらうという内容。
盛り上げる要素として、グループで協力して自然物を探すことにします。
また、探すものは1つではなく多数あり、覚える時間が設けられその後は見ることができません。
しかも、覚える時間は短時間で、グループの中から1人ずつ見にいって覚えるという形式とします。
ねらいを「自然の多様性に気づくこと」に設定すれば
探している間に目に入ってきたものも含め、
普段意識していないときには気づかないが、よく見ると自然の中には
さまざまなものが落ちているということに気づけるかもしれません。
グループで協力することで、コミュニケーションが促進されるという副次的な効果も期待できます。

では、ねらいを
「他人の考え方の違いや課題解決のためのアプローチの違いに気づくこと」に設定したら?
グループで協力することに重きを置くので、覚え方や見てきたもののシェア、どう探すか相談するなど
話し合って課題を解決するよう場を進めるでしょう。
また、実施後は自分がグループの中でどんな役割を行ったか、誰のどんな発言で場がうまくいったかなど
ふりかえりの時間をしっかりとることも必要になると思います。
探すものが自然物なので、森の中にはいろいろなものがあることに副次的に気づいてもらえる効果があります。

どうでしょう。設定するねらいによって同じアクティビティでもかかわり方が全く違ってきます。
でも、自然の中で指示された自然物を探すというやること(=コンテント)はおおまかには同じ。
このとき、設定したねらいを達成するために大切なことが、指導者のかかわり方です。
どうかかわったら、どう声かけをしたら場がうまくすすむか。
場合によっては、指導者はあまりかかわらない方がうまくいくこともあります。
同じねらいで同じアクティビティを行っても、
指導者によって得られる効果が違うのは、かかわり方の違いによるものです。
かかわり方がなんとなく得意だったり、経験を積めばうまくなったりすることもありますが、
「インタープリテーション」や「体験学習法」という考え方を知っていれば、
手探りで指導することに比べて効果がかわります。
経験に知識が合わさったとき、技術は掛け算で向上します。
上達速度も変わってきます。
体験に効果が伴ってないかも・・・
なんだか自分のスキルアップが自己努力では限界を感じる・・・
これ以上どうしたらうまくいくのかわからなくなってきた。
そんなお悩みがあるとしたら、
インタープリテーションと体験学習法を同時に学べる講座がオススメです。
年のはじめに新しい知識をインプットして、新たな年のスタートとしてみませんか?
●第65回清里インタープリターズキャンプ「体験学習法」
http://www.keep.or.jp/taiken/leader/interpreters/
瀧上まいまいでした~



















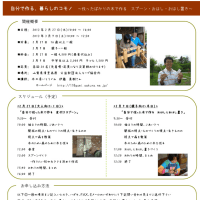
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます