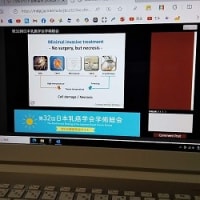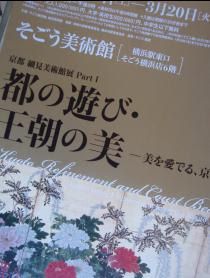
先週、横浜そごうへ美術展を観に行った後……

京都の老舗展という催事で、桜の帯揚げに出合った。
ペールブルーの地に、触れれば溶けてしまいそうな
優しいベージュピンクの絞り。
ゑり正さんのお品だ。
この、春色の一本を眺めていたら、
先日NHKで観たルノワールの特集番組を思い出した。

有名なムーラン・ド・ラ・ギャレット。(部分)
生涯、光に満ちた優しい風景や、わずかに上気だった白い頬の幸せそうな人物を
描き続けた彼だが、
実生活では普仏戦争やパリ・コミューンでの大虐殺といった
試練を乗り越えなければならなかった。
晩年、彼はこう言っていたという。
「世の中にはすでに不愉快な物事がたくさんある。
だから、新たに不愉快なものをつくる必要はないのです。」
今になぞらえ、震災=“不愉快”とは決して思わないが、
やりどころのない中途半端な負の気持ちを
節目という名目のもとにまき散らすのはやめよう、と
この言葉を見たときに思った。
創作活動の傍ら、ルノワールは内戦で孤児となった子供たちのための
施設づくりに奔走したそうだ。
私はそれまで彼を
「印象派のムーブメントにうまく乗った苦労知らずの流行画家」というような目で
見ていたところがあったが、
そうではなかったのだ。
痛みをわかった上で、敢えて幸せを描き続け人々に希望を与え続けた、
その姿勢に深く感銘を受けた。
--------------------------------
この記事は敢えて「音楽よもやま話」に分類している。
その理由は、今月10日にNHKで放送されたドキュメンタリー
「3月11日のマーラー」にも、ルノワールの番組と同じように
考えさせられたから。
震災当日、都内でも殆どのコンサートが中止される中
「一人でも聴きにきてくださるお客様がいらっしゃるなら」と
演奏会を決行した新日本フィル。
タクトを振るのは、新鋭のダニエル・ハーディング。イギリス人。
この日は彼の新日本フィルでの初指揮だった。
団員は演奏前に被災地の凄まじい状況をTVで見ており、
親類が東北に、というメンバーもいた。
電車が止まり、10㎞を歩いて会場に向かった人も。
しかもこの日のプログラムは、マーラーの交響曲第5番。
葬送行進曲から始まる重い曲だ。
「こんな状況で演奏していいのか」
「東北の親戚は無事だろうか」
「しかしやると決めた以上、最高の演奏をしなくては」
団員それぞれの、一人の人間としての悲しみや不安、痛みが
いざ演奏が始まるとプロとして奏でる音に乗り移り、
その夜は身震いするほどの、かつてない素晴らしい演奏になったという。
演奏側は95人。
そして観客は、たったの105人だった。
「しばらくの間、震災当日にコンサートへ行ったことは
誰にも言えなかった」 …後ろめたくて… と、観客の一人。
しかし、後日ハーディング氏からの次のようなコメントを見て、救われたという。
「あの日あの音楽を聴いたことは、
被災された方の痛みを深く知る助けになるでしょう」
マーラーの交響曲第5番は
葬送行進曲から穏やかなアダージェットを経て、最終楽章は希望に満ちた曲調になる。
その場にいなかった私でも、
その日、この曲が演奏されたことには確かな意味があったことを
番組を通して、感じ取ることができた。
そしてそれは私自身を楽にするうえでも、大きな意味をもたらした。
第四楽章のアダージェットは、ハープと弦楽器が奏でる別名「愛の楽章」。
もともとは、マーラーが恋人に求婚するために創ったそうです。
この演奏はベルリンフィル、指揮はカラヤン。




 Tomokoさんも観ていらっしゃったのですね。
Tomokoさんも観ていらっしゃったのですね。