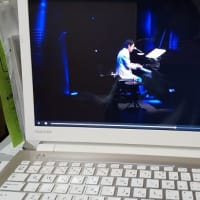こんな日は、大島が何と心地よいことか。

和キッチュさんの刺繡半衿を
今回はモダン大島に合わせてみた。
帯は仁平幸春さんの「月と わんこ」。
背中が皺っぽくなってしまい、反省…

(この後、できるだけ直しましたが)

帯締めは薄黄、帯揚げはイチイで染めたオレンジで。
半衿の色味と、合っているかな?
---------------------
さて、この日はまず、元町のえみ子先生のところ(皮膚科)へ行き、
その後、みなとみらいにある横浜美術館へ。

「江戸スピリット」をコンセプトにした
歌川国芳から鏑木清方までの作風の変遷が見られる展示が開催中。

江戸末期から明治初期を網羅するため、
文明開化がどのように、絵画に影響したかもよくわかるようになっており、
とても面白かった。
でも一番、印象に残ったのは、国芳(左2つ)とその門下生、芳年かな。

作風の違い、わかるでしょうか。
国芳の時代、何人もの浮世絵師が活躍したものの、
並べてみれば、それほど日本画に造詣の深くない私でさえ、
一目で「国芳は、ほかとは違う」と思った。
構図や、動きの捉え方(特に足の位置)が大胆で、思い切りが良く
「男っぽい」のだ。
絵画を見て、こんなにドキドキしたのはいつ以来か。ハートを掴まれる感覚。
お馴染みの判じ絵もいろいろあって、国芳の才能には改めて、
驚かされるばかり。
一方、芳年は歌舞伎でいえば女形のごとく、
優しい顔立ちにしなやかなタッチが印象的。
国芳が描いた美人画もあったが、どうも顔がごつい感じ。
女性の描き方は、私は芳年の方が好みだなあ。
もう一つ、
しみじみ感じ入ったのは、明治維新前後に人気を博した
初代五姓田芳柳とその一派。
パリとウィーン、二つの万博はヨーロッパにジャポニズムの風を
送り込んだが、同時に日本にも西欧のスピリットをもたらし、
五姓田派が描く肖像画はかなり“洋風に近い”、デフォルメを排除し
陰影も写実的な作風になっている。
でも……
そんな五姓田家の家や家族の様子が描かれた絵も展示されているのだが、
それが目を疑うほど質素で(あの時代は普通だったのかも知れないけれど)
洋風の“よ”のかけらすらないのだ。
狭い畳敷きの部屋に箱のような机、
子どもたちは寝そべって絵を描いている。
ほかに大した家具もなく、身を寄せ合うようにしている家族。
それでも、芸術一家だった五姓田家は、小さな子も真剣なまなざしで
先を争うようにして筆を走らせている。
考えてみれば当然だけれど、
何事も黎明期というのは、決して環境が整えられているわけではなく
絵を描きたい、新しいものを創りたい、という熱意だけが
原動力になっていたと言ってもいいだろう。
今の日本で、熱意だけで何か斬新なことをしようとする人を
温かく見守りサポートするような余裕が、果たしてあるのだろうか。
----------------------
さて、常設展の方はこの期間、ガラスの展示。

そして私が必ず訪れる、近代絵画の部屋。

左から、ジョルジョ・デ・キリコ、ポール・デルヴォ―、ルネ・マグリッド。
特にデルヴォ―は、私が高校生のとき、相当なインパクトを受けた画家。
美術館を出て、ランドマークタワーへ。

ここでのユーミンは「横浜の恋と……」だそうです。
11月初旬なのにもうクリスマスツリー。早すぎますよね。