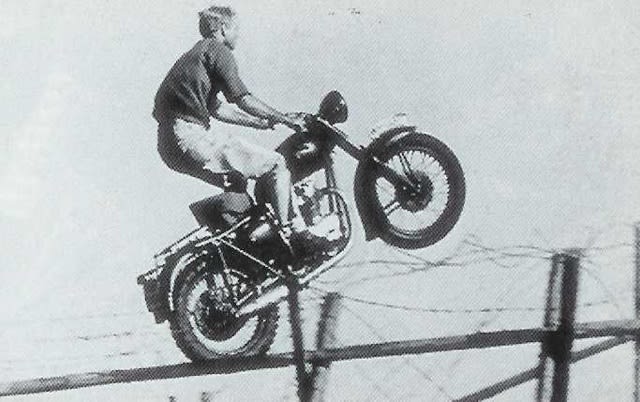オートバイではないのだけど、、
RN01 HONDA

ダウンヒル競技の自転車です。
ホンダのオートバイの開発者がつくるとこんな感じになったというものです。
HONDA Downhill Bike RN01 Debut
詳しくはこちら
http://www.asahi.com/komimi/TKY200705250353.htmlより
ーーーーーーー
モータースポーツのホンダ、なぜ自転車レースに?
2007年06月05日
モータースポーツの世界で数々の栄冠を勝ち取ってきたホンダ(本社・東京)が、自転車レースに参戦している。急斜面のオフロードを下ってタイムを競う「ダウンヒル」レース。独自に開発した「RN01(アールエヌゼロワン)」は斬新なスタイルと性能で注目を集める。なぜホンダが自転車を開発したのか。開発チームに聞いてみた。(アサヒ・コム編集部)
ホンダが開発したRN01
開発を担当した水田さん(左)と澤田さん(右)
水田さんが最初に作成したデザイン画。モトクロスバイクのエンジンを外し、ペダルをつけた
RN01(左)と一般的な自転車(右)の後輪部分。RN01には変速機がなく、転倒の影響が少ない
心臓部であるミッションボックス
惰性で進んでいる間にもギアチェンジができる。実際に乗ってみると想像以上に快適
「ここに置けば、海外の自転車雑誌みたいに写るよ」と澤田さん。遊び心が開発の原動力だ
急斜面を高速で下るダウンヒルは、マウンテンバイク競技のなかでも最も激しい種目とされる。「落ちていく」ような快感は、恐怖と紙一重だ。乗る人の力量はもちろんだが、自転車の性能が大きくものをいう。
RN01の誕生は99年、本田技術研究所研究員の水田耕司さんが趣味でダウンヒルを始めたことにさかのぼる。モトクロスバイクのデザイン担当だった水田さんにとって、当時市販されていたダウンヒル用自転車はとても頼りなく見えた。「多くの人に楽しんでもらうにはもっと高性能な自転車が必要だ。ホンダならできる」。水田さんの挑戦が始まった。
競技用自転車の開発はホンダにとって初めて。半年がかりで上司を説得し、長野県内のコースへ連れ出した。市販車と水田さんの手による改造車を乗り比べ、自転車次第で「恐怖」にも「快感」にも変わることを体感してもらった。
00年秋、水田さんら3人で開発チームが立ち上がった。元全日本モトクロス選手権チャンピオン伊田井佐夫(いだ・いさお)さんの協力で、開発は順調に進んだ。プロトタイプに試乗した福井威夫専務(現・社長)は「開発する以上はレースで勝つんだ」と檄(げき)を飛ばし、プロジェクトは大きく前進した。「商品化」に加え「勝利」がチームの目標になった。
02年、社名を伏せて国内レースにスポット参戦。赤く塗装されたプロトタイプは、様々な憶測を呼んだ。03年には本格参戦を正式発表。04年には、海外初参戦でタイトルを獲得する快挙を挙げた。RN01に試乗した海外のプロライダーは、チーム加入の誘いを二つ返事で受けたという。それほどRN01は斬新で高性能な自転車だった。
RN01最大の武器はミッション(変速機)だという。ボックス化したうえで、後輪からフレーム中央に移したことで車体バランスが向上。転倒時の衝撃にも強くなり、チェーンが外れるといったトラブルがなくなった。さらに、ペダルを止めた状態でも変速できる。サスペンションはKYB(本社・東京)、ブレーキは曙ブレーキ工業と、いずれも自動車や二輪車の部品メーカーが開発に加わった。
07年も海外レースに3台、国内レースに2台の体制で参戦している。海外では、最高峰のパーツを使用して勝利を追求。一方、国内では市販化に向けた仕様で参戦し、データの蓄積を図る。「一般の方でも購入していただける価格での市販を目指しています」。水田さんの挑戦は続いている。
ーーーーーーーーーー
ちょうどこの記事が書かれた2007年前半、このダウンヒルレーサーは確かに開発チームとしても盛り上がっていました。(他人事のようにかいているのですが、いくつもの開発チーム掛け持ちしている中、途中からではありますが、一応当時の開発チームの一員であったので…多少…)
この開発チームは熱い想いを持った方々が多くて、ダウンヒルの全日本選手権のときにはサポートやら調査ということで関係者が遠くまで集まって、ライダー(の家族)も一緒に、競技前日、壮行会を大変雰囲気良く和やかに行った覚えがあります。
本当に関わる皆でいいものにしていこうという感じでしたかねえ。
先ほどの記事中の開発者の
「市販を目指してます」
というところは、結果として、経営判断として、市販は行わないということになったのだけど…
前に書いた記事で、環境評論家の武田邦彦先生が「昔のホンダのオートバイは憧れだった」ということを引き合いに出しましたが、この意味でも、このダウンヒル自転車はホンダとして初めての領域であったけども、ホンダの開発者が夢を持って、世の中に提供するに値するものであったと(そのプロセスといい、出来栄えといい…少なくとも私自身が乗ったときに、いいものを感じる仕上がりでした)今でも思います。
その昔、昭和の大ヒット「ローラースルーゴーゴー」

こちらもホンダから出された商品だったって覚えてますか?(子どもの頃欲しかったなあ~)こういう予想外の意外性のもの好きだなあ。
このように海のものとも山のものとも分からないけれども、新しい文化と価値を世の中に問い続けていくのが経済活動だと思うのだけど…
RN01 HONDA

ダウンヒル競技の自転車です。
ホンダのオートバイの開発者がつくるとこんな感じになったというものです。
HONDA Downhill Bike RN01 Debut
詳しくはこちら
http://www.asahi.com/komimi/TKY200705250353.htmlより
ーーーーーーー
モータースポーツのホンダ、なぜ自転車レースに?
2007年06月05日
モータースポーツの世界で数々の栄冠を勝ち取ってきたホンダ(本社・東京)が、自転車レースに参戦している。急斜面のオフロードを下ってタイムを競う「ダウンヒル」レース。独自に開発した「RN01(アールエヌゼロワン)」は斬新なスタイルと性能で注目を集める。なぜホンダが自転車を開発したのか。開発チームに聞いてみた。(アサヒ・コム編集部)
ホンダが開発したRN01
開発を担当した水田さん(左)と澤田さん(右)
水田さんが最初に作成したデザイン画。モトクロスバイクのエンジンを外し、ペダルをつけた
RN01(左)と一般的な自転車(右)の後輪部分。RN01には変速機がなく、転倒の影響が少ない
心臓部であるミッションボックス
惰性で進んでいる間にもギアチェンジができる。実際に乗ってみると想像以上に快適
「ここに置けば、海外の自転車雑誌みたいに写るよ」と澤田さん。遊び心が開発の原動力だ
急斜面を高速で下るダウンヒルは、マウンテンバイク競技のなかでも最も激しい種目とされる。「落ちていく」ような快感は、恐怖と紙一重だ。乗る人の力量はもちろんだが、自転車の性能が大きくものをいう。
RN01の誕生は99年、本田技術研究所研究員の水田耕司さんが趣味でダウンヒルを始めたことにさかのぼる。モトクロスバイクのデザイン担当だった水田さんにとって、当時市販されていたダウンヒル用自転車はとても頼りなく見えた。「多くの人に楽しんでもらうにはもっと高性能な自転車が必要だ。ホンダならできる」。水田さんの挑戦が始まった。
競技用自転車の開発はホンダにとって初めて。半年がかりで上司を説得し、長野県内のコースへ連れ出した。市販車と水田さんの手による改造車を乗り比べ、自転車次第で「恐怖」にも「快感」にも変わることを体感してもらった。
00年秋、水田さんら3人で開発チームが立ち上がった。元全日本モトクロス選手権チャンピオン伊田井佐夫(いだ・いさお)さんの協力で、開発は順調に進んだ。プロトタイプに試乗した福井威夫専務(現・社長)は「開発する以上はレースで勝つんだ」と檄(げき)を飛ばし、プロジェクトは大きく前進した。「商品化」に加え「勝利」がチームの目標になった。
02年、社名を伏せて国内レースにスポット参戦。赤く塗装されたプロトタイプは、様々な憶測を呼んだ。03年には本格参戦を正式発表。04年には、海外初参戦でタイトルを獲得する快挙を挙げた。RN01に試乗した海外のプロライダーは、チーム加入の誘いを二つ返事で受けたという。それほどRN01は斬新で高性能な自転車だった。
RN01最大の武器はミッション(変速機)だという。ボックス化したうえで、後輪からフレーム中央に移したことで車体バランスが向上。転倒時の衝撃にも強くなり、チェーンが外れるといったトラブルがなくなった。さらに、ペダルを止めた状態でも変速できる。サスペンションはKYB(本社・東京)、ブレーキは曙ブレーキ工業と、いずれも自動車や二輪車の部品メーカーが開発に加わった。
07年も海外レースに3台、国内レースに2台の体制で参戦している。海外では、最高峰のパーツを使用して勝利を追求。一方、国内では市販化に向けた仕様で参戦し、データの蓄積を図る。「一般の方でも購入していただける価格での市販を目指しています」。水田さんの挑戦は続いている。
ーーーーーーーーーー
ちょうどこの記事が書かれた2007年前半、このダウンヒルレーサーは確かに開発チームとしても盛り上がっていました。(他人事のようにかいているのですが、いくつもの開発チーム掛け持ちしている中、途中からではありますが、一応当時の開発チームの一員であったので…多少…)
この開発チームは熱い想いを持った方々が多くて、ダウンヒルの全日本選手権のときにはサポートやら調査ということで関係者が遠くまで集まって、ライダー(の家族)も一緒に、競技前日、壮行会を大変雰囲気良く和やかに行った覚えがあります。
本当に関わる皆でいいものにしていこうという感じでしたかねえ。
先ほどの記事中の開発者の
「市販を目指してます」
というところは、結果として、経営判断として、市販は行わないということになったのだけど…
前に書いた記事で、環境評論家の武田邦彦先生が「昔のホンダのオートバイは憧れだった」ということを引き合いに出しましたが、この意味でも、このダウンヒル自転車はホンダとして初めての領域であったけども、ホンダの開発者が夢を持って、世の中に提供するに値するものであったと(そのプロセスといい、出来栄えといい…少なくとも私自身が乗ったときに、いいものを感じる仕上がりでした)今でも思います。
その昔、昭和の大ヒット「ローラースルーゴーゴー」

こちらもホンダから出された商品だったって覚えてますか?(子どもの頃欲しかったなあ~)こういう予想外の意外性のもの好きだなあ。
このように海のものとも山のものとも分からないけれども、新しい文化と価値を世の中に問い続けていくのが経済活動だと思うのだけど…