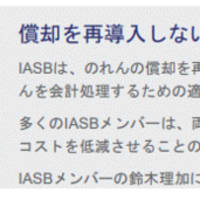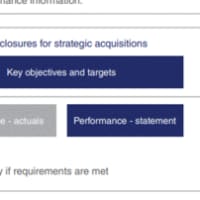実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等に寄せられたコメント
「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等の公表(2023年11月17日)にあわせて、その公開草案へのコメントと対応の概要が公表されました。
コメント提出は4者だけで、少ないのですが、興味深い論点の指摘もあるようです。
以下、ASBJ資料より抜粋。
資金(現金)の範囲について。
「電子決済手段が貸借対照表上の表示において「現金及び預金」に含まれるか否かを明確化すべきである。 」
コメントへの対応 「本公開草案では、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」における資金の範囲及び現金の定義を改正し、キャッシュ・フロー計算書上、本実務対応報告の対象となる電子決済手段を現金に含めることを提案している。一方、我が国の会計基準では貸借対照表上の現金の定義を定めておらず、表示の取扱いを定めるためには、従来より貸借対照表とキャッシュ・フロー計算書で現金の範囲が異なる点についても国際的な整合性や開示規則等との関係も踏まえ検討することが考えられる。しかしながら、その検討は電子決済手段以外の取扱いにも影響を及ぼす可能性があり、本実務対応報告の範囲を超えると考えられるため、貸借対照表上の取扱いは定めないこととした。なお、開示規則等により現金及び預金に含まれない場合には、重要性も踏まえてその性質を示す適切な科目で表示することになると考えられる。」
IFRSでは、キャッシュフロー計算書の資金は「現金および現金同等物」で、BS上の表示と一致させるのが原則のようです(一致しない場合は調整表が必要)。そのようになっていれば、BS上のキャッシュの変動原因を示す計算書がキャッシュフロー計算書だということになって、非常に理解しやすいのですが、日本基準の場合は、BS上の表示とキャッシュ・フロー計算書の資金とは別物ということになっていて、ちょっとわかりにくくなっています(基準策定のいろいろな経緯があるのでしょう)。改善してほしいものですが、無理でしょう。
さしあたりどうするのかという点については、「その性質を示す適切な科目」ということで、お茶を濁しています。金融庁が財規の改正で対応する可能性はありますが、本当にリスクがない資産なのかどうかはまだわからないわけで、そういうものを現預金に含めていいのかという意見があるでしょう。
「取扱い」の対象外の外国電子決済手段について。
「第1号電子決済手段、第2号電子決済手段又は第3号電子決済手段に該当する外国電子決済手段のうち、当該電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託している外国電子決済手段以外の外国電子決済手段について、今後、国内において取引量が増加する場合には、その取扱いについて改めて検討することが必要と考える。」
コメントへの対応「今後の電子決済手段の取引の発展や会計実務の状況により、本実務対応報告において定めのない事項に対して別途の対応を図ることの要望が市場関係者により当委員会に提起された場合には、必要に応じて公開の審議により、別途の対応を図ることの要否を当委員会において判断することとする。」
海外子会社が保有している同様の資産や発行している同様の債務はどうなるのでしょう。
金銭信託や暗号資産の預託に関する実務と取扱いが異なる理由について。
「電子決済手段等取引業者又は電子決済手段の発行者が電子決済手段の利用者との合意に基づいて当該利用者から預かった電子決済手段を資産計上しない取扱いについて、金融商品取引業者等が顧客から預かった現金に係る金銭信託や、暗号資産交換業者が預託された資金決済法上の暗号資産を資産計上している会計実務と異なる取扱いとする理由を、これらの預託の比較も踏まえ結論の背景で補足説明する必要があると考える。 」
コメントへの対応「現行の会計基準では、資産の預託に関して包括的な定めはなく、個々の資産の預託に関する取扱いを定める際に、それぞれの性質を踏まえた検討が行われている。
このような中で、他の資産の預託との比較により、総額又は純額の判断基準を明確化することは、本実務対応報告において仲介業者等が利用者から資産の預託を受けた場合の原則的な考え方を示すかのような誤解を生じさせる可能性があるため、本実務対応報告の範囲を超えることになると考えられることから対応しないこととした。」
貸倒引当金の必要性。
「近年、電子決済手段に関連するトラブルが少なからず報道され、話題となっており、換金リスクの生ずる蓋然性は一定程度あると考えられる。そのため、貸倒引当金のような取扱いを定めることが必要であると考えられる。」
コメントへの対応「審議の過程では電子決済手段に係る換金リスクの会計上の取扱いについて検討を行ったが、本実務対応報告の対象となる電子決済手段は、電子決済手段の発行等に際して所要の規制が課されているため、通常、要求払預金における信用リスクと同程度に低いと考えられること、また、本実務対応報告が改正された資金決済法の施行に合わせて当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取扱いを定めることを目的にしていることに鑑み、その会計上の取扱いを定めないこととしている。このため、換金リスクの会計上の取扱いについては、今後の電子決済手段の取引の発展や会計実務の状況により、対応を図ることの要望が市場関係者により当委員会に提起された場合には、必要に応じて公開の審議により、別途の対応を図ることの要否を当委員会において判断することとする。 」
銀行預金も銀行が倒産して戻ってこないリスクがあるわけですから(それなのに引当金は議論されていない)、それとの比較でさしあたり検討不要ということなのでしょう。