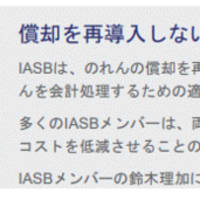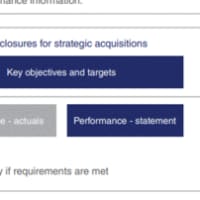実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等の公表
企業会計基準委員会は、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を、2023年11月17日付で公表しました。あわせて、企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」も公表しています(資金の範囲が変更されている)。
実務対応報告の背景は...
「(2022年6月に)改正された資金決済法においては、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有するものが新たに「電子決済手段」と定義され、また、これを取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入され、必要な規定の整備が行われました。」(プレスリリースより)
(法改正に関する解説→ステーブルコインに関する法規制の概要とポイント解説(新日本監査法人))
(この解説によると、実務対応報告に出てくる1号から3号までの電子決済手段は以下のようなものです。
「1号電子決済手段は、電子機器等に電子的方法により記録されている通貨建資産であり、電子情報処理組織を用いて移転可能なものが要件となっています。また、有価証券、電子記録債権、前払式手段等に該当しないものとされています。
一方、取引時確認をした者にのみ移転可能とする技術的措置が講じられ、かつ移転の都度発行者の承諾等が必要となるものは、電子決済手段に該当しません。また、前払式支払手段であっても、残高譲渡型や番号通知型等の移転の都度発行者の承諾等が必要になるものは電子決済手段に該当しません。
3号電子決済手段とは電子情報処理組織で移転できる金銭信託受益権であり、預金や貯金により信託財産の全部が管理されていることが要件となっています。」(2号は、「1号と相互交換できる財産的価値」)
実務対応報告の概要は以下のとおり(ASBJ資料より抜粋・要約)。
1.実務対応報告の対象範囲(2項、3項)
・資金決済法第 2 条第 5 項に規定される電子決済手段のうち、第 1号電子決済手段、第 2 号電子決済手段及び第 3 号電子決済手段を対象とする。
・外国電子決済手段については、電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限る。
・第 3 号電子決済手段の発行者側に係る会計処理及び開示に関しては、実務対応報告第 23 号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」を適用
2.電子決済手段の保有に係る会計処理
(1)取得時(5項)
・その受渡日に当該電子決済手段の券面額に基づく価額をもって資産として計上。取得価額と券面額に基づく価額との間に差額がある場合、差額を損益として処理
(2)移転時・払戻時(6項)
・第三者に移転するとき又は電子決済手段の発行者から金銭による払戻しを受けるときは、その受渡日に当該電子決済手段を取り崩す。
・第三者に移転するときに金銭を受け取り、当該電子決済手段の帳簿価額と金銭の受取額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理
(発行者からの払い戻しでは差額が生じないことが前提なのでしょう。)
(3)期末時(7項)
・その券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とする。
3.電子決済手段の発行に係る会計処理
(1)発行時(8項)
・受渡日に払戻義務について債務額をもって負債として計上し、発行価額の総額と債務額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理。
(2)払戻時(9項)
・受渡日に払戻しに対応する債務額を取り崩す。
(3)期末時(10項)
・電子決済手段に係る払戻義務は、期末時において、債務額をもって貸借対照表価額とする。
4.外貨建電子決済手段に係る会計処理(11項、12項)
期末時の会計処理
・外貨建電子決済手段の期末時における円換算については、「外貨建取引等会計処理基準」 一 2 (1) ①の定めに準じて処理を行う。
・ 外貨建電子決済手段に係る払戻義務の期末時における円換算については、外貨建取引等会計処理基準 一 2 (1) ②の定めに従って処理を行う。
(「「外貨建電子決済手段」とは、外国通貨で表示される電子決済手段をいう。」(4項(5)))
5.預託電子決済手段に係る取扱い(13項)
・電子決済手段等取引業者又は電子決済手段の発行者(合わせて「電子決済手段等取引業者等」)は、電子決済手段の利用者との合意に基づいて当該利用者から預かった電子決済手段(以下「預託電子決済手段」)を資産として計上しない。また、電子決済手段の利用者に対する返還義務を負債として計上しない。
(暗号資産の取扱業者(取引所)の場合とは違います。)
6.注記事項(14項)
・本実務対応報告の対象となる電子決済手段及び本実務対応報告の対象となる電子決済手段に係る払戻義務に関する注記については、企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」第 40-2 項に定める事項を注記する。
7.「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正(資金の範囲)
・特定の電子決済手段を現金に含める。
・特定の電子決済手段とは、資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号から第 3 号に規定される電子決済手段(外国電子決済手段については、利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限る)。
(キャッシュ・フロー計算書の「資金」の範囲が変わるのはたぶん初めてであり、その意味では、結構重要な改正なのでは)
公表日以後適用です。
日本公認会計士協会の「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」も同日付で改正されています。