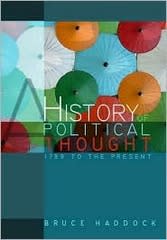
かなり久々の更新になりますが、何とか生きてます(笑
ここのところは、2年くらい前に(つまりPhD一年目に)書いた部分の大幅な改訂作業と、マンチェスターでの発表原稿をジャーナル提出用の原稿にするために資料の再調査、疑問点について英国内とアメリカの数人の先生に質問をメールでやり取りするといった下調べに取り組んでいました。前者は、カオス的に2万語弱くらいになっていた文章を、しっかり論理的構造を立て直して、3つの章へと分割する作業なのですが、1章目はイントロと結論を書き直せばほぼOK。しかし2,3章目がかなり混沌としていたので、ほとんど書き直しています・・・。ようやく先週末で2章目ができたので、今月中に最後の3章目を仕上げたいところです。雑誌原稿のほうは、問い合わせもひと段落して資料も揃い、先週から本格的な改訂に入りました。これも11月中くらいに提出したいですが、その論文で批判する先行研究の著者(故人)について確認したいことがあり、そのご夫人でかつ本人もバリバリの歴史学者の方にコンタクトをとっているのですが、一向に返事が来ない・・・。(採用になったとして)最悪ゲラの朱入れのときまでに注に入れる用意だけでもしとこうか思案中です。まあ、気長に待ちます。
そんな作業をしつつ、常に頭にあるのが結論部分をどうしようかということなのですが、その一環で最近読んだ表題の本を紹介します。これは実は私の第二指導教授の著書で、たまたま買おうと思っていたときに彼とミーティングをして、タイミングよく彼が「これもっている?」と言ってくれ、「いや、ちょうど買おうと思っていたところなんです」と答えたところ、じゃあ、ということでくれました(著者サイン入り(笑)
* * *
この本は表題の通り、政治思想史の教科書的な本で、とくに1789年(フランス革命の勃発)から現代に至る政治思想の流れを以下の順に追います。(主な対象)
(1章 イントロ)
2章 Revolution .......ペイン、カント
3章 Reaction.........バーク、メーストル
4章 Constitutional State........コンスタン、ヘーゲル
5章 The Nation-State.......マッツィーニ、フィヒテ
6章 Liberty.........トックヴィル、ミル
7章 Welfare.........マルクス
8章 Totalitarianism...........レーニン、パレート、ジョンティーレ、(カール・シュミット)
9章 Politics Chastened.......ポパー、ハイエク、オークショット
10章 Politics Fragmented......フーコー(ポストモダニズム)、ロールズ、多文化主義など
著者の問題意識の焦点はある一つの政治哲学・倫理学上の問題にあります。すなわち、政治思想におけるnormative argument(規範的議論)の可能性という問題です。別の局面から言い直すと、「社会的・文化的共同体にはめ込まれた個人としての私たちは、いかに政治的判断を行なうのか?」という問いです。
筆者はこの問題意識のもとで、フランス革命以来の政治思想史を、政治的理念・理想を追求する政治とその破局的結末という極と、そのような理念への熱狂への反動としての政治という極という二つの軸によって描くことを試みます。
ルソー・ロック・ペインといった啓蒙思想という理念の実現を目指して始まったフランス革命とその恐るべき帰結、そしてそのような政治的理念への熱狂を嫌い伝統などの'natural order'を保守して社会の安定を保とうとするバークらの反動。これがヨーロッパの保守主義の源流でもあります。
アンシャン・レジームへの回帰を含意するこの反動に対して、再び個人の自由という理念を目指し、国家を自由実現の道具ではなく雅のその自由の保護者として考えることによって王権も革命も避けるコンスタン。しかしコンスタンのリベラルなバラバラの個人に満足しないヘーゲルは共同体の一員としての個人としての利益をまもろうとし、それはやがて反動政治への反発の一形態として勃興しnationという理念を意識するようになった政治的ナショナリズムへとつながります。
このような個人の自由を制限する流れに対して、もう一度個の自由を主張しひとつの理念に縛られない多元主義へと戻ろうとしたのがトクヴィル、ミル、フンボルトなどでした。しかしこのようなむきだしの個という考え方は、産業革命期の労働者の悲惨な生活という現実に直面し、マルクスなどの再び個を国家によって包摂する理論が提出されます。さらに20世紀に入っての国際的な政治の不安定化、そして総力戦としての第一次世界大戦という経験が、国家の存在感を肥大化し、レーニン主義・スターリニズムという極左、そしてファシズムという極右において国家が極限まで増幅され、その体制下では周知のように理論上の反対者が政治上の敵へと容易に転化し、殺戮の対象へとされたわけです。
史上最悪の戦禍、ホロコースト、ドラスティックな政治的自由の制限を経験した第二次大戦後の世界では、政治的ユートピアの代償というものがいかに大きいかということが痛感されました。このような全体主義へのトラウマは、経済における徹底した自由主義を唱え、国家が個人の生活へ介入する福祉国家はいかによい意図のもとにあったとしても、必然的に全体主義への種を含んでいると考えたハイエクに顕著に現れます。彼の考えは実際1970年代の英米にて実際の政策に強く反映されるほど影響を持つに至ったわけです。ハイエクの徹底した個人主義・自由主義は、オークショットのような個の偏重への懐疑を受けたりはしますが、結局両者は理念・理想を追求するような規範的な'high' politicsが危険なゲームであり、関心を'low' politics、つまり富の再分配、権利、市民生活のための場所と機会の供給などへと向けることでは方向性は似ていたといえます。
国家理念の追求を避けるようになった現代政治哲学では、しかしロールズの正義論を契機として、自由と平等という二つの政治的価値の間で議論が展開していきます。一方ではノージックに代表される自由を重視する方向、他方ではドォーキンら平等を重視する方向という二極というように。
著者はこのようにフランス革命以来の政治思想史を、理念政治とそれへの反動の応酬という形で捉えます。フランス革命の理念への政治的熱狂、ナショナリズム、全体主義など、幾多の理念政治の悲惨な結末を経験してきた現代の我々は、政治における理念あるいは観念の危険性に(時に偏執狂的にあるいは懐疑論者的に)十分自覚的になりました。ゆえに、現代の政治哲学は社会構造や政治理念などよりも、再分配・権利保障などのミクロな問題に関心を集中する傾向が強まっています。しかし、アイデンティティー、ジェンダー、文化などの現代世界の政治で問題となっている課題は、まさに政治判断に際しての基準に関わる問題であり、社会のなかの個々人のバックグランドを捨象した単純な再分配・権利保障などの対策では解決できる問題ではない。また、個々の文化・アイデンティティ・ジェンダーなどの価値が拡散しそれぞれの行為者が気ままにcontingentな行動をする現代世界は、制御不能に陥る危険を孕んでいる。したがって、ロールズが晩年に述べたように、いかに規範的理論が過去に惨禍をもたらしてきたとしても、私たちはそれでも常に政治的な判断をしなければならず、その判断の過程において、参照すべき権威なり基準なりを考えることは不可避であるというのが筆者の結論です。
(*かなり大雑把な要約になりました。すみません、先生。)
筆者の取り上げる政治的判断と行為の関係性の問題は、philosophy of actionの分野においても、次のような問いとしてより本質的に問題となっているようです。
‘What is it for a person or some other organism to be an agent of autonomous action? And, how do we explicate the special force of reasons for autonomous action in practical reasoning—a “force” quite different from the motivating impact of an overmastering desire?’ (‘action’, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/action/)
私の研究テーマであるコリングウッドの実在論批判とは、じつはまさにこのactionとtheoryの関係性が核心部であるといえます。戦間期のイギリス哲学の主たる潮流であり戦後の分析哲学の源流たる実在論は、theory of knowledge、つまり政治哲学的に言えば政治的価値についての知識は、actionにはいかなる影響も及ぼさないと主張し、actionに関わる規範性を否定しました。このような主張は、第一次世界大戦を経験し、nationという政治的理念の恐ろしさを身に染みて痛感していた当時の時代の気分によくマッチしたのかもしれません。1930以降、ファシズムとコミュニズムというイデオロギーの政治が再び脅威を増していた状況下で、1943年の死まで一貫して実在論を厳しく批判し、「危険な」theoryとactionの連関、actionにおける規範性の擁護を試みたコリングウッドの真意はどこにあったのか?彼がファシズムを早くから一貫して執拗に批判し続けていることから、いかなる意味でもナイーヴなファシズム礼賛ではないことは当然明らかです。この答えは、彼の規範理論における、actionが参照する規範の3形式, utility, right, dutyのうちで最高の位置を占める彼のdutyの概念にあるという心証を強めています。このduty概念は、rightから区別されている点でユニークであり、規範としてのdutyがその適用対象を具体的に特定する性質のものであり、それを知るための方法として歴史的方法が重視されるなど、豊かな含意をもった概念です。このdutyの含意という課題は、最近のコリングウッド研究のフロンティアのひとつでもあります。したがって、本書によって得た政治哲学的文脈、philosophy of actionでの文脈をある程度意識しつつ、この彼のdutyの政治哲学的含意を実在論批判という視角から光を当てることが私の論文の最後の課題となりそうです。
ここのところは、2年くらい前に(つまりPhD一年目に)書いた部分の大幅な改訂作業と、マンチェスターでの発表原稿をジャーナル提出用の原稿にするために資料の再調査、疑問点について英国内とアメリカの数人の先生に質問をメールでやり取りするといった下調べに取り組んでいました。前者は、カオス的に2万語弱くらいになっていた文章を、しっかり論理的構造を立て直して、3つの章へと分割する作業なのですが、1章目はイントロと結論を書き直せばほぼOK。しかし2,3章目がかなり混沌としていたので、ほとんど書き直しています・・・。ようやく先週末で2章目ができたので、今月中に最後の3章目を仕上げたいところです。雑誌原稿のほうは、問い合わせもひと段落して資料も揃い、先週から本格的な改訂に入りました。これも11月中くらいに提出したいですが、その論文で批判する先行研究の著者(故人)について確認したいことがあり、そのご夫人でかつ本人もバリバリの歴史学者の方にコンタクトをとっているのですが、一向に返事が来ない・・・。(採用になったとして)最悪ゲラの朱入れのときまでに注に入れる用意だけでもしとこうか思案中です。まあ、気長に待ちます。
そんな作業をしつつ、常に頭にあるのが結論部分をどうしようかということなのですが、その一環で最近読んだ表題の本を紹介します。これは実は私の第二指導教授の著書で、たまたま買おうと思っていたときに彼とミーティングをして、タイミングよく彼が「これもっている?」と言ってくれ、「いや、ちょうど買おうと思っていたところなんです」と答えたところ、じゃあ、ということでくれました(著者サイン入り(笑)
* * *
この本は表題の通り、政治思想史の教科書的な本で、とくに1789年(フランス革命の勃発)から現代に至る政治思想の流れを以下の順に追います。(主な対象)
(1章 イントロ)
2章 Revolution .......ペイン、カント
3章 Reaction.........バーク、メーストル
4章 Constitutional State........コンスタン、ヘーゲル
5章 The Nation-State.......マッツィーニ、フィヒテ
6章 Liberty.........トックヴィル、ミル
7章 Welfare.........マルクス
8章 Totalitarianism...........レーニン、パレート、ジョンティーレ、(カール・シュミット)
9章 Politics Chastened.......ポパー、ハイエク、オークショット
10章 Politics Fragmented......フーコー(ポストモダニズム)、ロールズ、多文化主義など
著者の問題意識の焦点はある一つの政治哲学・倫理学上の問題にあります。すなわち、政治思想におけるnormative argument(規範的議論)の可能性という問題です。別の局面から言い直すと、「社会的・文化的共同体にはめ込まれた個人としての私たちは、いかに政治的判断を行なうのか?」という問いです。
筆者はこの問題意識のもとで、フランス革命以来の政治思想史を、政治的理念・理想を追求する政治とその破局的結末という極と、そのような理念への熱狂への反動としての政治という極という二つの軸によって描くことを試みます。
ルソー・ロック・ペインといった啓蒙思想という理念の実現を目指して始まったフランス革命とその恐るべき帰結、そしてそのような政治的理念への熱狂を嫌い伝統などの'natural order'を保守して社会の安定を保とうとするバークらの反動。これがヨーロッパの保守主義の源流でもあります。
アンシャン・レジームへの回帰を含意するこの反動に対して、再び個人の自由という理念を目指し、国家を自由実現の道具ではなく雅のその自由の保護者として考えることによって王権も革命も避けるコンスタン。しかしコンスタンのリベラルなバラバラの個人に満足しないヘーゲルは共同体の一員としての個人としての利益をまもろうとし、それはやがて反動政治への反発の一形態として勃興しnationという理念を意識するようになった政治的ナショナリズムへとつながります。
このような個人の自由を制限する流れに対して、もう一度個の自由を主張しひとつの理念に縛られない多元主義へと戻ろうとしたのがトクヴィル、ミル、フンボルトなどでした。しかしこのようなむきだしの個という考え方は、産業革命期の労働者の悲惨な生活という現実に直面し、マルクスなどの再び個を国家によって包摂する理論が提出されます。さらに20世紀に入っての国際的な政治の不安定化、そして総力戦としての第一次世界大戦という経験が、国家の存在感を肥大化し、レーニン主義・スターリニズムという極左、そしてファシズムという極右において国家が極限まで増幅され、その体制下では周知のように理論上の反対者が政治上の敵へと容易に転化し、殺戮の対象へとされたわけです。
史上最悪の戦禍、ホロコースト、ドラスティックな政治的自由の制限を経験した第二次大戦後の世界では、政治的ユートピアの代償というものがいかに大きいかということが痛感されました。このような全体主義へのトラウマは、経済における徹底した自由主義を唱え、国家が個人の生活へ介入する福祉国家はいかによい意図のもとにあったとしても、必然的に全体主義への種を含んでいると考えたハイエクに顕著に現れます。彼の考えは実際1970年代の英米にて実際の政策に強く反映されるほど影響を持つに至ったわけです。ハイエクの徹底した個人主義・自由主義は、オークショットのような個の偏重への懐疑を受けたりはしますが、結局両者は理念・理想を追求するような規範的な'high' politicsが危険なゲームであり、関心を'low' politics、つまり富の再分配、権利、市民生活のための場所と機会の供給などへと向けることでは方向性は似ていたといえます。
国家理念の追求を避けるようになった現代政治哲学では、しかしロールズの正義論を契機として、自由と平等という二つの政治的価値の間で議論が展開していきます。一方ではノージックに代表される自由を重視する方向、他方ではドォーキンら平等を重視する方向という二極というように。
著者はこのようにフランス革命以来の政治思想史を、理念政治とそれへの反動の応酬という形で捉えます。フランス革命の理念への政治的熱狂、ナショナリズム、全体主義など、幾多の理念政治の悲惨な結末を経験してきた現代の我々は、政治における理念あるいは観念の危険性に(時に偏執狂的にあるいは懐疑論者的に)十分自覚的になりました。ゆえに、現代の政治哲学は社会構造や政治理念などよりも、再分配・権利保障などのミクロな問題に関心を集中する傾向が強まっています。しかし、アイデンティティー、ジェンダー、文化などの現代世界の政治で問題となっている課題は、まさに政治判断に際しての基準に関わる問題であり、社会のなかの個々人のバックグランドを捨象した単純な再分配・権利保障などの対策では解決できる問題ではない。また、個々の文化・アイデンティティ・ジェンダーなどの価値が拡散しそれぞれの行為者が気ままにcontingentな行動をする現代世界は、制御不能に陥る危険を孕んでいる。したがって、ロールズが晩年に述べたように、いかに規範的理論が過去に惨禍をもたらしてきたとしても、私たちはそれでも常に政治的な判断をしなければならず、その判断の過程において、参照すべき権威なり基準なりを考えることは不可避であるというのが筆者の結論です。
(*かなり大雑把な要約になりました。すみません、先生。)
筆者の取り上げる政治的判断と行為の関係性の問題は、philosophy of actionの分野においても、次のような問いとしてより本質的に問題となっているようです。
‘What is it for a person or some other organism to be an agent of autonomous action? And, how do we explicate the special force of reasons for autonomous action in practical reasoning—a “force” quite different from the motivating impact of an overmastering desire?’ (‘action’, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/action/)
私の研究テーマであるコリングウッドの実在論批判とは、じつはまさにこのactionとtheoryの関係性が核心部であるといえます。戦間期のイギリス哲学の主たる潮流であり戦後の分析哲学の源流たる実在論は、theory of knowledge、つまり政治哲学的に言えば政治的価値についての知識は、actionにはいかなる影響も及ぼさないと主張し、actionに関わる規範性を否定しました。このような主張は、第一次世界大戦を経験し、nationという政治的理念の恐ろしさを身に染みて痛感していた当時の時代の気分によくマッチしたのかもしれません。1930以降、ファシズムとコミュニズムというイデオロギーの政治が再び脅威を増していた状況下で、1943年の死まで一貫して実在論を厳しく批判し、「危険な」theoryとactionの連関、actionにおける規範性の擁護を試みたコリングウッドの真意はどこにあったのか?彼がファシズムを早くから一貫して執拗に批判し続けていることから、いかなる意味でもナイーヴなファシズム礼賛ではないことは当然明らかです。この答えは、彼の規範理論における、actionが参照する規範の3形式, utility, right, dutyのうちで最高の位置を占める彼のdutyの概念にあるという心証を強めています。このduty概念は、rightから区別されている点でユニークであり、規範としてのdutyがその適用対象を具体的に特定する性質のものであり、それを知るための方法として歴史的方法が重視されるなど、豊かな含意をもった概念です。このdutyの含意という課題は、最近のコリングウッド研究のフロンティアのひとつでもあります。したがって、本書によって得た政治哲学的文脈、philosophy of actionでの文脈をある程度意識しつつ、この彼のdutyの政治哲学的含意を実在論批判という視角から光を当てることが私の論文の最後の課題となりそうです。














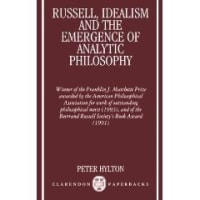
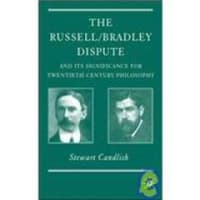




まぁいろいろ考えさせれるんですが、なかなか難しくて、どうも。
>dutyの政治哲学的含意を実在論批判という視角から光を当てる
大変興味があります。
最近、広範な哲学史的知識の重要性を改めて感じていて、古典を順々に読み直しているんですが、やっぱり難しいよね(英語ということもありますが)。まあでも、やるほどコリングウッドが分かってくるので、こつこつと続けていこうと思っています。あと、英語圏の教科書は、以前紹介した本もそうだけど、著者の関心に沿ってとても頭に残る形で書いてある本が多いので、とても助けになりますよ。邦訳が出ているものもあると思うので、たまにそんなのを読んでみると、一気に啓ける場合があります(笑
dutyの政治的含意は、まだまだ自分の中でも曖昧だけど、カントの義務概念よりかは、行為者(agent)に近いというか、ある場面で義務としてとるべきactionが、その行為者、動機、内容などまで具体的なものとして考えられているんだよね。このような具体的な義務を知るために必要とされるのが、歴史的理性というか想像力なんです。ある場面で、その場面に至るまでの歴史的背景などを踏まえて、とるべき行為を決定しなければならない、というわけなんですが、まあ、まだまだ理解が曖昧です(汗
体系とか。
ヘーゲル的な(?ヘーゲルよくわかりませんが)歴史とかもちょろっと解説されてたり…・
扱ってるテキスト通り、シェリング自由論が本論みたいですけど。アレント読んでてよくわかんないところがあったもんで、試しに読んでるんですけど。
カントとかドイツ観念論の解説が今のところおもしろいです。
ヘーゲル的な歴史というのはコリングウッドでも重要な位置を占めるので、ちょっと気になります。