6/25「授業づくり一日講座」当日の様子Part2(2時限目 講座 A~F)です。
午後からは分野別に分かれて講座がおこなわれました。アンケートに寄せられたコメントをご紹介します。
A : 学級づくり(高) / 岡本美穂 先生(学力研)

B : 国語(AL) / 南惠介 先生(岡山県小学校教諭)

C : 道徳 / 吉永幸司 先生(京都女子大学)

D : 社会(UD) / 宗實直樹 先生(関西学院初等部)

E : 算数 / 何森真人 先生(数教協)

F : 特別支援 / 山田充 先生(特別支援教育士)

授業研ニュース、出来上がりました。近日中に皆様のお手元に届く予定です。
次回は3時限目(講座 G~L)の様子をご紹介します。
午後からは分野別に分かれて講座がおこなわれました。アンケートに寄せられたコメントをご紹介します。
A : 学級づくり(高) / 岡本美穂 先生(学力研)
高学年でも「授業が楽しい!」といえる子どもとは?
子どものやる気と自信を引き出す指導法についてお話しいただきました。
子どものやる気と自信を引き出す指導法についてお話しいただきました。

音読や板書(ノート)の指導ポイントがハッキリとわかって良かったです。高学年女子、男子が楽しく思えるように、成功体験を増やしていけるように、しかけていきます。(O先生)
若い女性の先生の高学年の学級づくりについての研修は初めてだったので、「分かる、分かるー!」ということが多く、とてもためになりました。(N先生)
将来的に高学年をもつ不安でいっぱいでしたが、今日のお話を聞いて、「高学年」というだけでおびえてた自分にさようならできるように、がんばろうと思いました。(H先生)
― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ―
B : 国語(AL) / 南惠介 先生(岡山県小学校教諭)
国語科授業はテンポよく
「主体的・対話的で深い学び」アクティブ・ラーニングを実現する授業のパターン化についてご紹介いただきました。
「主体的・対話的で深い学び」アクティブ・ラーニングを実現する授業のパターン化についてご紹介いただきました。

インクルーシブとの関連で教えていただけたことがとても参考になりました。パターン化と国語の用語、系統について自分の使っている教科書をもとに(他の教科書とも比べながら)大切なところをよく吟味して、実践していきたいと思いました。(T先生)
支援の必要な子どもをすごく意識されていると感じました。研究への情熱を真似します。国語授業、即活用します。(M先生)
この講座自体がアクティブ・ラーニングでとても楽しく、学びの多い時間となりました。インクルーシブを考えた手立て、声かけを教えていただき、普段の私の授業を改めて振り返るいい機会となりました。(D先生)
― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ―
C : 道徳 / 吉永幸司 先生(京都女子大学)
子どもたちの心に残る道徳とは?
長年子どもたちと接してきた吉永先生ならでは、深みのあるお話をうかがいました。
長年子どもたちと接してきた吉永先生ならでは、深みのあるお話をうかがいました。

おだやかで心温まるエピソードをたくさん教えていただき、授業の実際も見せていただいてとても勉強になりました。(N先生)
「道徳」といっても、特別なものではなく、日常の授業を大切にしていかなければいけないと知り、安心しました。(D先生)
授業の最後でどうすればいいのか悩んでいたので、教えていただいて自信をもって道徳の時間をおこなうことができます。吉永先生のように優しく語ることができるように心がけたいです。(T先生)
― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ―
D : 社会(UD) / 宗實直樹 先生(関西学院初等部)
信号機の並びは、なぜ車道側が赤なの?
ユニバーサルデザインの視点から、身近な題材を使った興味のもてる社会科授業をご紹介いただきました。
ユニバーサルデザインの視点から、身近な題材を使った興味のもてる社会科授業をご紹介いただきました。

社会の授業ですぐに考えたくなったのは初めてです。子どもたちは社会が好きなので、子どもの力も借りてがんばりたいと思います。(T先生)
先生の講座が面白すぎて、明日からすごく社会をやりたくなりました。面白い面白いと思いながらゴールにたどりつけたので、こんな授業だと子どもたちも社会好きになるだろうなと思います。(T先生)
視覚化、共有化などの言葉にとらわれすぎず、目の前にいる子どもたちと向き合って授業を作り上げていくことの大切さを改めて実感しました。(O先生)
― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ―
E : 算数 / 何森真人 先生(数教協)
〈水道方式〉と〈量の理論〉にもとづく楽しい授業
量を視覚化する教具の取り入れ方や、気をつけるべきことなどをお話いただきました。
量を視覚化する教具の取り入れ方や、気をつけるべきことなどをお話いただきました。

視覚に訴える方法、問題作りで大切な視点を学べました。(Y先生)
具体的に活動することで、目的がよくわかった。量について何が難しいのかがわかり、今後の指導に活かせると思います。(K先生)
今の教え方ではわかったつもりになっている子、わかっていない子が置いてけぼりになっているなと思いました。視覚化することの大切さを、今日のお話を通して感じました。明日から早速活かせるように頑張りたいと思います。(H先生)
― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ― ☆ ― ― ―
F : 特別支援 / 山田充 先生(特別支援教育士)
できないからといって、ころころと教材を変えることは、子どもの自信低下を招く
誤答の分析方法と、障害の特性に沿った支援の方法についてお話いただきました。
誤答の分析方法と、障害の特性に沿った支援の方法についてお話いただきました。

アセスメント(分析)をしっかりしたうえで、苦手なところをピンポイントで指導することが大切なのだと感じました。(I先生)
私は今まで子どもの分析より先にいろいろな方法を使っていたかもしれないと気づきました。想起困難や不注意優勢型ADHDは今回初めて知り、私が今担任させていただいている子もその可能性があるかもしれないと思いました。(H先生)
アセスメントが全く不十分だったということがわかりました。わがクラスのLDの子、ADHDの子の対応をもう一度よく考え直してみたいと思いました。(Y先生)
授業研ニュース、出来上がりました。近日中に皆様のお手元に届く予定です。
次回は3時限目(講座 G~L)の様子をご紹介します。












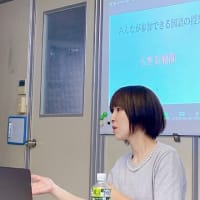
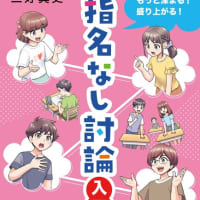
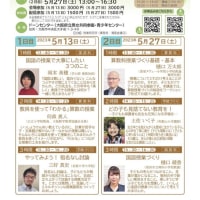

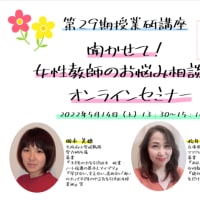


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます