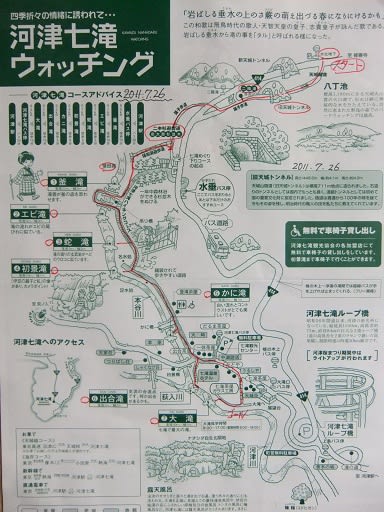2011年11月21日:秋晴れの一日、富士五湖と富士山の展望台、山梨県「王岳1623m」に登った。マイカーで中央道「河口湖IC」で下り139号線を走り根場「いやしの里」駐車場に駐車する。駐車場からは富士山は勿論これから登る王岳も見える。早速身支度を整えて、駐車場を出発する。先ずは茅葺屋根の民家が並ぶいやしの里に向かって行く。

いやしの里駐車場から見た王岳。

身支度を整えたら、富士山を背にいやしの里へ向かう

かつての根場を再現した茅葺屋根の家群のいやしの里に出る。

いやしの里で左折して行くとここ王岳登山口方面の鍵掛峠登山口の標識を見る。

薬明大神の前を通り、簡易舗装の林道をしばらく登って行くと右手に「鍵掛峠・王岳」登山口の標識を見る。ここから狭い山道に入る。

時折眼下に根場のを眺めながら、最初は緩やかだが徐々にきつくなる登山道を行く。岩混じりのごつごつした急登になると「鍵掛峠」は近い。鍵掛峠の稜線に出る。右手に行くのは鬼ヶ岳への道。我々は左に王岳を目指す。

少し下った所から眼下に根場そして大きく富士山が見える。

ここからは西湖と富士山を眺めながらの稜線歩きだが、小さなピークをいくつも越えることになる。

王岳山頂は小広く開けた山頂だ。富士山、西湖、遠く山中湖そして河口湖もわずかに見える。また本栖湖も見える。八ヶ岳、南アルプスは木の間越しに見え隠れしている。

王岳山頂から鬼ヶ岳、山中湖、河口湖方面を望む。

正面に富士山が大きい。

小広い王岳山頂。ここで昼食タイムとした。

十分、景色を楽しんだら根場へ下る。山頂をわずかに下ったところに根場への下る標識がある。ここから一気に下って行く。林道に下りつけば根場はもう少しだ。

いやしの里駐車場から見た王岳。

身支度を整えたら、富士山を背にいやしの里へ向かう

かつての根場を再現した茅葺屋根の家群のいやしの里に出る。

いやしの里で左折して行くとここ王岳登山口方面の鍵掛峠登山口の標識を見る。

薬明大神の前を通り、簡易舗装の林道をしばらく登って行くと右手に「鍵掛峠・王岳」登山口の標識を見る。ここから狭い山道に入る。

時折眼下に根場のを眺めながら、最初は緩やかだが徐々にきつくなる登山道を行く。岩混じりのごつごつした急登になると「鍵掛峠」は近い。鍵掛峠の稜線に出る。右手に行くのは鬼ヶ岳への道。我々は左に王岳を目指す。

少し下った所から眼下に根場そして大きく富士山が見える。

ここからは西湖と富士山を眺めながらの稜線歩きだが、小さなピークをいくつも越えることになる。

王岳山頂は小広く開けた山頂だ。富士山、西湖、遠く山中湖そして河口湖もわずかに見える。また本栖湖も見える。八ヶ岳、南アルプスは木の間越しに見え隠れしている。

王岳山頂から鬼ヶ岳、山中湖、河口湖方面を望む。

正面に富士山が大きい。

小広い王岳山頂。ここで昼食タイムとした。

十分、景色を楽しんだら根場へ下る。山頂をわずかに下ったところに根場への下る標識がある。ここから一気に下って行く。林道に下りつけば根場はもう少しだ。