腎臓病の方は「加工食品の取りすぎ」に要注意
腎臓病の原因はジャンクフード
https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20180620-OYTET50006/
6月9日、10日、名古屋で開催された、第6回日本在宅栄養管理学会学術集会に参加してきました。さまざまな興味深い講演やシンポジウムを聞くことができましたが、特に印象的だった「慢性腎臓病の食事療法」について、ご紹介したいと思います。
腎臓の機能が低下して「慢性透析治療」を受けている方は2016年現在で約33万人です(日本透析医学会ホームページより)。原因となる疾患では「糖尿病性腎症」が最も多く、患者さんの数は毎年増加しています。
長期間にわたり血糖値がコントロールできない状態が続くと、毛細血管がダメージを受けます。やがて目(網膜)や腎臓の毛細血管に障害が起き、網膜症や腎臓病などの合併症を発症することがあります。
腎臓病の食事療法の基本は、体に必要なエネルギーを十分に摂取しながらも、たんぱく質を取りすぎないようにすることと、カリウムやリンの摂取に気を付けることです。腎臓は、血液をろ過して余分な物質を体外に排出します。この機能が低下すると、体内で体液の濃度を一定に保つシステムがうまく働かなくなるのです。
たんぱく源となる肉や魚などの食品や、野菜や果物に多く含まれるカリウムを制限することは、腎臓病の患者さんやその家族にもよく知られていますが、意外と盲点となりやすいのが「リンの制限」です。
カリウムやリンが体にたまるとどうなるのか
カリウムやリンはミネラルの一種で、人間にとってなくてはならない栄養素のひとつですが、腎臓の機能が衰えて、血液中に過剰にたまってしまうと、「高カリウム血症」や「高リン血症」を引き起こします。
高カリウム血症になると、吐き気や嘔吐、しびれなどの症状が表れ、悪化すると不整脈から心停止を起こすことがあります。高リン血症では、血液中のリンとカルシウムのバランスが崩れ、「リン酸カルシウム」という結晶になり、身体のあちこちに沈着する「石灰化」という現象が起こることがあります。これが心臓の血管で起こると、心筋梗塞などを引き起こす恐れがあります。
また、リンにはカルシウムと結合して骨を丈夫にする働きがあります。この二つは体内で一定の濃度を保つようにバランスを取っているのですが、血液中のリンの量が過剰になって調和が崩れると、低カルシウム血症を引き起こし、筋肉のけいれんや心機能の低下によって命にかかわることがあります。
腎機能が低下している方が、薬物療法と合わせて、カリウムやリンの摂取量を抑える必要があるのはこのためです。
加工食品に含まれる「リン」に注意
カリウムやリンは、さまざまな食品に含まれていますので、普通の食事をしていれば、欠乏症になることはありません。裏を返せば、腎機能が低下していて排出機能が低下している方は、意識的に摂取を減らさないと過剰になってしまうということです。
先の学術集会で登壇された、至学館大学健康科学部栄養科学科の井上啓子教授は、さまざまな加工食品を調査し、どの食品にリンが多く含まれているのか研究されています。
例えば、たくさんの食品会社から販売されている「ソーセージ」ですが、井上教授の研究によると、メーカーによってリンの含有量にかなりの差があることがわかりました。変色を防ぎ、食品を軟らかく保つ働きをする「リン酸塩」という食品添加物が加えられており、各社でその使用量に違いがあるためと考えられています。ハムやソーセージ、かまぼこなどの練り物製品にも多く使用されていますが、使用量の表示義務が無いため、どの程度のリン酸塩が含まれているのかわからない製品が多いのが現状です。
ホームページで自社製品のリンの含有量を公開しているメーカーもあるものの、井上教授の調査によると、加工食品783品目中わずか90品目(11.5%)だったのです。腎機能が低下している方が安心して食品を選べるように、加工食品を販売している企業は、栄養素や添加物の情報公開をもっと進めてほしいと思います。
ファストフード店での注文によって、リン量に4倍の差が
何気なく選んでいるファストフード店のハンバーガーセットでも、メニューの構成によって大きな違いが出ます。井上教授の講演の中でも触れられていた話題ですが、私も某有名ファストフード店のホームページを見ながら、セットの注文をシミュレーションしてみたところ、リン含有量に4倍の差がありました。
例えば、ハンバーガー(パテ2枚入り)+チキンナゲット5個+キャラメルラテの組み合わせのリン含有量は716ミリグラム。海老カツバーガー+サラダ+リンゴジュースなら162ミリグラムでおさまります。腎機能が悪化して、透析の治療を受けている人の場合、1日のリン摂取量の目安は800~1000ミリグラム程度です(体重60キログラムの方の場合)ので、後者のセットにした方がいいですね。
なるべく加工食品を使わない食生活が理想ですが、外食時のメニューなどに情報があれば、食事に制限のある患者さんも安心です。管理栄養士としても、料理に含まれる栄養量がわからないお店よりも、情報公開されているほうを勧めたくなります。(在宅訪問管理栄養士 塩野崎淳子)












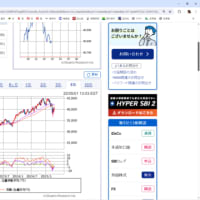














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます