大刀洗川(太刀洗川)は、貝原益軒の『筑前国続風土記』(1703)など、江戸時代にはその名で呼ばれていた記録があるが、筑後側の史料に、その名は無い。
大刀洗川は、筑前側においては数㎞しかなく、筑前の山隈原の田畑に引かれた水のいわば排水路であり、現在の水量に比べれば、はるかに小さな小川であった。
また、筑後に入ると、山隈老松宮の前あたりでは「前川(まえんかわ)」と呼ばれ、山隈原の南では、湿地や沼地を形成し、それより下流は「沼川(ぬまんかわ)」と呼ばれていた
※現在でも、俗称として野間川(のまんかわ)と呼ばれる。
「大刀洗川」という名の由来には、
平安末期に盗賊が太刀を洗ったという説。
戦国時代、花立山城を支城としていた秋月種実が、秀吉の九州征伐に対して、山隈原で交戦したが敗れ、秋月城へ撤退する際に太刀を洗ったという説。
などのいくつかの説があるが、
文政元(1813)年の、頼山陽の「筑後川を下る」という詩を根拠として、筑後川の合戦において、菊池武光が太刀を洗ったという説が定説とされるようになった。
ただし、筑後川の合戦当時の公的または私的な記録として、実際に菊池武光が太刀を洗ったという記録があるわけではない。
山隈原の戦いは、武家方が、宮方の騎馬を野間あたりの湿地や沼地に誘い込むかたちで始まったとされる。
実際に、野間あたりでは、刀剣や馬具など、戦闘の痕跡が発掘されているから、それ自体は間違いないだろう。
そこへ宮方の菊池武光が加勢したことで、武家方は徐々に後退し、戦場は、野間あたりの湿地や沼地から、山隈原(現在の北鵜木あたり)へ上がった、もしくは、戦場が山隈原へ上がってから菊池武光が加勢したとされる。
いずれにしても、山隈原の戦いは、主戦場から離れた戦いであり、宮方の総大将である菊池武光が、主戦場を離れて参戦したとは考えにくい。
また、山隈原の北の花立山に武家方の山城があり、武家方は、花立山方面へ後退し、結果としては、武家方は、花立山への撤退に失敗し、更に北の宝満岳へ逃れている。
だとすると、山隈原の戦いから、筑前依井方面へ撤退したとされる武家方というのは、本隊からはぐれた少数の雑兵であったと考える方が自然であり、菊池武光がそれを追ったとは考えにくく、仮に追ったとしても、地理的な位置関係から考えると、大刀洗川を渡ったというのはほとんどあり得ない。
記録には無い菊池渡りや太刀洗いの伝説が史実に基づくとしても、菊池武光が渡ったのは、大刀洗川ではなく、花立山の南を流れる川で、追撃をあきらめて太刀を洗ったのもそこであったと考える方が自然である。
そもそも、頼山陽の筑後川の戦いに関する詩は、川中島の戦いの詩とかなり似ていることから、川中島の戦いを元にイメージしたものといわれ、小川で太刀を洗ったという一節も、そのイメージから生まれた創作と考えられる。
江戸時代に、大刀洗(太刀洗川)という地名が、筑前のみでしか使われていない点からすると、秋月種実説の方が真実のように思われる。
飛行場を誘致するにあたり、敗戦の将である秋月種実よりも、筑後川の戦いで勝利した菊池武光が、大刀洗川で太刀を洗ったとした方が都合がよかったというのが、本当のところではないだろうか?
ちなみに、筑前の「菊池武光太刀洗いの場」とされるのは、国道500号線沿い、大刀洗川の横にあり、筑後の「菊池武光太刀洗いの場」とされ、菊池武光の銅像が立つ大刀洗公園は、筑前と筑後の国境をはさんで、その下流にある。
筑前国と筑後国、大刀洗町と三輪町(現在の筑前町)の関係や大刀洗飛行場の誘致など、利害の対立が、二つの太刀洗いの場を生んだと思われる。
大刀洗川は、筑前側においては数㎞しかなく、筑前の山隈原の田畑に引かれた水のいわば排水路であり、現在の水量に比べれば、はるかに小さな小川であった。
また、筑後に入ると、山隈老松宮の前あたりでは「前川(まえんかわ)」と呼ばれ、山隈原の南では、湿地や沼地を形成し、それより下流は「沼川(ぬまんかわ)」と呼ばれていた
※現在でも、俗称として野間川(のまんかわ)と呼ばれる。
「大刀洗川」という名の由来には、
平安末期に盗賊が太刀を洗ったという説。
戦国時代、花立山城を支城としていた秋月種実が、秀吉の九州征伐に対して、山隈原で交戦したが敗れ、秋月城へ撤退する際に太刀を洗ったという説。
などのいくつかの説があるが、
文政元(1813)年の、頼山陽の「筑後川を下る」という詩を根拠として、筑後川の合戦において、菊池武光が太刀を洗ったという説が定説とされるようになった。
ただし、筑後川の合戦当時の公的または私的な記録として、実際に菊池武光が太刀を洗ったという記録があるわけではない。
山隈原の戦いは、武家方が、宮方の騎馬を野間あたりの湿地や沼地に誘い込むかたちで始まったとされる。
実際に、野間あたりでは、刀剣や馬具など、戦闘の痕跡が発掘されているから、それ自体は間違いないだろう。
そこへ宮方の菊池武光が加勢したことで、武家方は徐々に後退し、戦場は、野間あたりの湿地や沼地から、山隈原(現在の北鵜木あたり)へ上がった、もしくは、戦場が山隈原へ上がってから菊池武光が加勢したとされる。
いずれにしても、山隈原の戦いは、主戦場から離れた戦いであり、宮方の総大将である菊池武光が、主戦場を離れて参戦したとは考えにくい。
また、山隈原の北の花立山に武家方の山城があり、武家方は、花立山方面へ後退し、結果としては、武家方は、花立山への撤退に失敗し、更に北の宝満岳へ逃れている。
だとすると、山隈原の戦いから、筑前依井方面へ撤退したとされる武家方というのは、本隊からはぐれた少数の雑兵であったと考える方が自然であり、菊池武光がそれを追ったとは考えにくく、仮に追ったとしても、地理的な位置関係から考えると、大刀洗川を渡ったというのはほとんどあり得ない。
記録には無い菊池渡りや太刀洗いの伝説が史実に基づくとしても、菊池武光が渡ったのは、大刀洗川ではなく、花立山の南を流れる川で、追撃をあきらめて太刀を洗ったのもそこであったと考える方が自然である。
そもそも、頼山陽の筑後川の戦いに関する詩は、川中島の戦いの詩とかなり似ていることから、川中島の戦いを元にイメージしたものといわれ、小川で太刀を洗ったという一節も、そのイメージから生まれた創作と考えられる。
江戸時代に、大刀洗(太刀洗川)という地名が、筑前のみでしか使われていない点からすると、秋月種実説の方が真実のように思われる。
飛行場を誘致するにあたり、敗戦の将である秋月種実よりも、筑後川の戦いで勝利した菊池武光が、大刀洗川で太刀を洗ったとした方が都合がよかったというのが、本当のところではないだろうか?
ちなみに、筑前の「菊池武光太刀洗いの場」とされるのは、国道500号線沿い、大刀洗川の横にあり、筑後の「菊池武光太刀洗いの場」とされ、菊池武光の銅像が立つ大刀洗公園は、筑前と筑後の国境をはさんで、その下流にある。
筑前国と筑後国、大刀洗町と三輪町(現在の筑前町)の関係や大刀洗飛行場の誘致など、利害の対立が、二つの太刀洗いの場を生んだと思われる。










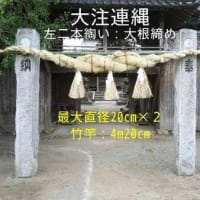
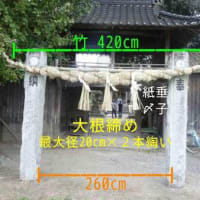



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます