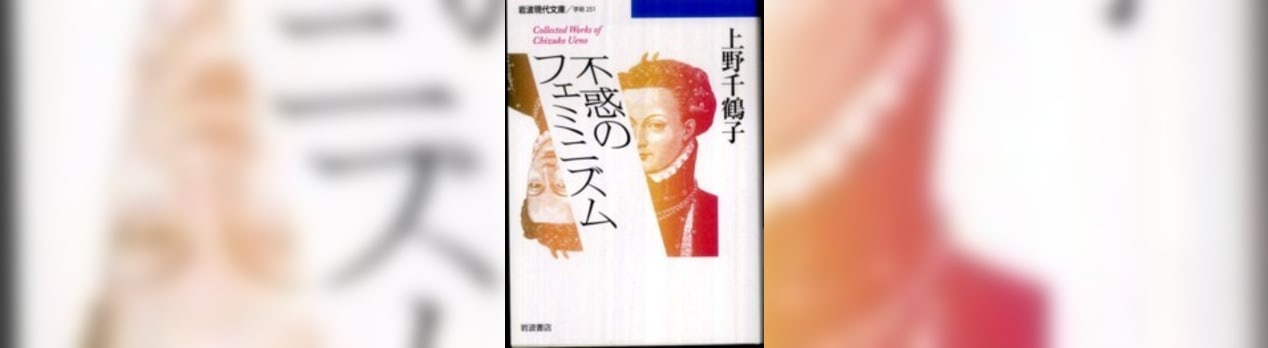上野千鶴子,2011,不惑のフェミニズム,岩波書店.(6.28.24)
売られたケンカは買い、連帯は国境や世代を超えて呼びかける―。上野千鶴子の発言は、折にふれ共感、時に物議をかもしてきたが、背景にあるのは、自身の率直な思いと、女が女であるがままの解放をめざすフェミニズム思想。四〇年間、その最前線を走りつづけてきたフェミニストの、迫力のリアルタイム発言を一挙公開。
田中美津さんが「便所からの解放」を発表した1970年を、第二次フェミニズムの起点とするなら、それから40年、日本のフェミニズムは、なにを問題にし、なにを主張してきたのか、その軌跡を、折々の「時局発言」を再録することで描き出す。
女は母か便所?ウーマン・リブのカリスマに当時3歳の私が惹かれた理由
2005年、ネオリベとジェンダー・バッシングの嵐が吹きすさぶなか、上野さんは、女が、弱者のままで尊重される社会を次のように展望する。
「こんな社会」に対する女たちの答えはすでに出ている。非婚化と少子化である。こんなところで産めない、育てられない、と女たちの集団無意識は、歴史的な答えを出している。ジェンダー・バッシングは、家族の危機に対する守旧勢力の反動だろう。だが、声高に「家族を守れ」と叫ぶほど、ネオリベの圧しつける「自己責任」の重さは、家族を崩壊させる結果になることに、かれらは気づかない。
フェミニズムはネオリベから袂を分かつことになるだろう。そうなれば、女のなかでだれが味方で、だれが敵かがはっきりしてくるだろう。処方箋はすでに練られ、考えつくされ、提案されている。
いつでもだれでも何歳からでもやりなおせる社会を。働き方を選べて、そのことで差別的処遇を受けない社会を。育児や介護が強制労働や孤独な労働にならず、その選択が不利にならない社会を。女が男の暴力やセクハラにさらされない社会を。女が家族の外でも、ひとりで安心して子どもを産み育てることができる社会を。
(pp.255-256)
上野さんが提起した課題は、現在においても、未達成のままである。
フェミニズムが対峙してきたのは、ホモソーシャルな男社会と、それがまき散らすミソジニーであった。
闘って獲得したものでなく、与えられた権利はたやすく奪われる。闘って獲得した権利ですら、闘って守りつづけなければ、足元を掘り崩される。女の元気を喜ぶひとたちばかりではない。「女は黙っていろ」、「おとなしく台所へひっこんでいろ」、「生意気だ、でしゃばるな」という声は、潜在的にはいたるところにある。グローバリゼーションとネオリベのもたらした危機のもとで、保守派はすでに余裕を失っている。そして規格にはずれた女をターゲットにする反動の戦略は、昔も今もホモソーシャルな「男同士の連帯」をつくりだすには、いちばん安直だが有効な手段だ。バージニア・ウルフはナショナリズムを「強制された同胞愛」と呼んだ。「女ではない」ことだけを男性的主体化の核に置く脆弱なアイデンティティの持ち主たちが、ジェンダーフリー・バッシングというミソジニーを、「よっ、ご同輩」と男同士の「同胞愛fraternity」のために利用するのはあまりにみえすいた構図だ。
(p.337)
わたしは、まだ20代、K大助手をしていたとき、西〇本社会学会のシンポジウム、「女性学の現在」に登壇した。
わたしの専門は、社会変動論、産業・労働社会学であるが、それらの領域においても、ジェンダーの視点、女性学の知見は欠かせないものであることを、わたしは上野さん等の仕事から学んでいた。
また、自らに期待される男役割への違和感、男であることの居心地の悪さの正体が、女性学を学べばわかるのではないかという期待もあった。
ただ、新興の学問領域である女性学に、臆面もなく参入する男たちは、嫌悪の対象でしかなかった。
こいつら、女性学をマウンティング(アカポス獲得)の道具にしている、と。
参入したくともできない、それが女性学だった。
わたしは、このころ、西日本新聞紙上での対談で、男は「(女性学でなく)男性学に取り組むべきだ」と発言している。
気後れからか、たんなる知的怠慢からなのか、それさえできなかったことに忸怩たる思いがする。
まあ、これからでもできないわけではない。
実践的な配慮を離れれば、残る問題は「男性に女性学ができるか」ということである。この問いは「白人が黒人解放に関われるか」という問いに似ている。女性学に参入する男性は、異文化を研究する人類学者に似ている(と言ったら怒る人がいるだろうか)。人類学者は、いかにして自分が属さない文化を記述することが可能かを、問う。原住民のインフォーマントに、当該文化を語らせればそれで十分ではないのか?──十分でないところに、人類学者の存在意義がある。人類学者が記述するのは、結局他者を鏡にした、自己の文化、つまり自他の文化の距離である。人類学者が異文化を記述することをとおして明らかにするのは、結局自分自身を縛る自己の文化の檻だ。逆に言えば、原住民もまた、他者を鏡にする以外に、自己の文化を記述する方法を持たないと言える。
そのひそみにならえば、女性学を研究する男性には、女を鏡にした自己認識、つまり男性学をしてくれと言うほかない。女たちは、これまでたっぷり男という鏡に映った自己像を眺めつづけてきた。それが歪んだ鏡だったので、自分たちの本来の姿(そんなものがあるとしてだが)がわからなくなるほどに。女たちは、今ようやく自分で鏡をつくろうとしている。女という鏡に映った自分を見て、男たちは、驚くだろうか。
だが女性学は、たんなる異文化理解とも違っている。それは異文化が相補的に析出した、楯の裏面だからだ。これまで男性がつくりだしてきた人間学(アントロポロギイ)は、文字どおりの人間学(捨てたものではないが)と男性学とを含んでいる。女性学は、女性の視点を鏡として、人間学の中から男性学を析出させる効果を持っている。つまり、女性学と男性学とは、人間の相補的なアイデンティティ=セクシュアリティに関わる研究だと、明確に言っておこう。小林秀雄は『Xへの手紙』の中で「女は俺にただ男でいろ(人間ではない──引用者注)と要求する、俺はこの要求にどきんとする」と書く。こんな要求に今さらどきんとしていてもらっては困るのだ。女性学に男性の研究者が関わることはのぞましい。ただし他者としての女性研究ではなく、他者の鏡に映った自分自身を認識してもらうために。カエサルのものはカエサルに返せ。男性にはほんとうは女性学より「男性学」をやってもらいたい。戦後の革命運動の中で私たちが学んだのは、解放とは自己解放のことであり、他者の解放運動に連帯する道は、自己の足許の解放でしかないということではなかったか。男たちにはこう言おう、あなた自身を救いなさい、と。
(pp.389-390)
本書は、フェミニズム40年の歴史を振り返る、格好のテキストとなるだろう。
目次
序 フェミニズムの40年
フェミニズム
おんなの運動論
1 燃えるマグマに形を―80年代
性差別をめぐる不毛な応酬
フェミニズム・いろいろ ほか
2 ジェンダー平等への地殻変動―90年代
女と男の歴史的時差
リブ・ルネッサンス ほか
3 バックラッシュに抗して―2000年代
ネオリベの下で広がる女女格差
フェミニズムは収穫期 ほか
4 女性学をつくる、女性学を手渡す
連絡会ニュース発刊のころ
初心にかえろうよ ほか