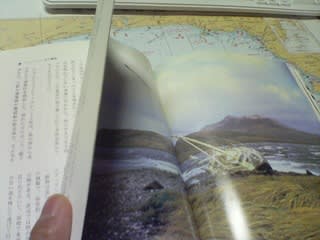ヴェ・イ・ヴォイトフ『単独航海の記録』
1971年にモスクワで出版された「海のロビンソンたち」の邦訳。
海洋航海の歴史がみっちり。
なんだか歴史の教科書を読んでいるみたい。
日本のセーリング文化の活性化を目指すには、まず教育から。
とりあえず「世界史」の一部として「海洋航海史」を!!!
------------------------------------------------------------------
p8 フランシス・ブレントン、シエラ号、カタマラン、大西洋横断航海
p13 アラン・ボンバール、フランス人医師
p29 アルフレッド・イェンセン、初の大西洋横断、1876、港町グロスターからリバプール、デンマーク人、100年号
p36 ショシン・ローラー船長が2番目、ウイリアム・アンドリュースが3番
p110 太平洋単独横断、ジョン・コールドウェル、1946、妻に会うためにパナマからオーストラリアまで、自著『向こう見ずな航海』
p112 ウイリアム・ウィリス、1954、60歳、筏、七人姉妹号、エージ・アンリミテッド号
p132 イギリスの船乗り、ブライアン・プレット、日本の漁船の漂流の道をたどる航海、1959
p134 堀江謙一、1963、「孤独は耐えがたかった。一人ぼっちの人間は不幸だ」とこのヨットマンは日記にかいた
p138 アレックス・カロッツオ、1965、ゴールデン・ライオン号
p144 ジョシュア・スローカム、スプレー号、1898
p147 アメリカ人、スローカムに次いで、ハリー・ピジョン、アイランダー号
p172 アラン・ジェルボ、世界一周、ファイアークレスト号
p173 アルフレッド・ピーターソン、ストロムウェイ号
p174 ジャック・イヴ・ル・ツレメン、クールーン号
p178 「世紀の旅行家」フランシス・チェチェスター ジプシー・モス四世
p181 アルゼンチン人、ヴィト・デュマ
p206 (チェチェスターがなぜこの航海をしたのか?と問われて…)「私はその質問に60の答えができるだろうが、そのどれ一つとして正しくはないだろう。いずれにしろ、私はこのような航海が人生を生き生きさせるものだと思っている。このようなことに取り組めば、あなたは明るく生きるだろうし、このこと一つだけでもすべてが正当化される。つまり、あなたが完全な生活を営みたければ、その手段の一つがこれなのです。」
p207 オプティ号、1966、レオニード・テリガ、ポーランド
p216 ベルナール・モアテシエ「私はプリマスへは行きません」
p218 単独無寄港世界一周、ロビン・ノックス・ジョンストン、スハイリ号
p223 ロビン・リー・グラハム、ダブ号
1971年にモスクワで出版された「海のロビンソンたち」の邦訳。
海洋航海の歴史がみっちり。
なんだか歴史の教科書を読んでいるみたい。
日本のセーリング文化の活性化を目指すには、まず教育から。
とりあえず「世界史」の一部として「海洋航海史」を!!!
------------------------------------------------------------------
p8 フランシス・ブレントン、シエラ号、カタマラン、大西洋横断航海
p13 アラン・ボンバール、フランス人医師
p29 アルフレッド・イェンセン、初の大西洋横断、1876、港町グロスターからリバプール、デンマーク人、100年号
p36 ショシン・ローラー船長が2番目、ウイリアム・アンドリュースが3番
p110 太平洋単独横断、ジョン・コールドウェル、1946、妻に会うためにパナマからオーストラリアまで、自著『向こう見ずな航海』
p112 ウイリアム・ウィリス、1954、60歳、筏、七人姉妹号、エージ・アンリミテッド号
p132 イギリスの船乗り、ブライアン・プレット、日本の漁船の漂流の道をたどる航海、1959
p134 堀江謙一、1963、「孤独は耐えがたかった。一人ぼっちの人間は不幸だ」とこのヨットマンは日記にかいた
p138 アレックス・カロッツオ、1965、ゴールデン・ライオン号
p144 ジョシュア・スローカム、スプレー号、1898
p147 アメリカ人、スローカムに次いで、ハリー・ピジョン、アイランダー号
p172 アラン・ジェルボ、世界一周、ファイアークレスト号
p173 アルフレッド・ピーターソン、ストロムウェイ号
p174 ジャック・イヴ・ル・ツレメン、クールーン号
p178 「世紀の旅行家」フランシス・チェチェスター ジプシー・モス四世
p181 アルゼンチン人、ヴィト・デュマ
p206 (チェチェスターがなぜこの航海をしたのか?と問われて…)「私はその質問に60の答えができるだろうが、そのどれ一つとして正しくはないだろう。いずれにしろ、私はこのような航海が人生を生き生きさせるものだと思っている。このようなことに取り組めば、あなたは明るく生きるだろうし、このこと一つだけでもすべてが正当化される。つまり、あなたが完全な生活を営みたければ、その手段の一つがこれなのです。」
p207 オプティ号、1966、レオニード・テリガ、ポーランド
p216 ベルナール・モアテシエ「私はプリマスへは行きません」
p218 単独無寄港世界一周、ロビン・ノックス・ジョンストン、スハイリ号
p223 ロビン・リー・グラハム、ダブ号