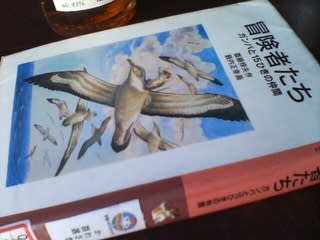ジェシカ・ワトソン『ジェシカ16歳 夢が私に勇気をくれた』
~TRUE SPILIT by Jessica Watson ~

いつもの本屋(ジュンク堂盛岡店)をブラブラしていたら、さりげなく書棚に置かれている本書を発見!
ひさびさのヨット本、即購入。ヤッホ~。
オーストラリアの、弱冠16歳の少女?が、単独無寄港世界一周という夢を叶えるまでを記録した、フレッシュな航海記。
やっぱり、その人最初の「航海記」はいいなぁ!日本なら堀江謙一さんの『太平洋ひとりぼっち』、白石康次郎さんの『七つの海を越えて』、外国ならタニア・アービー『タニア18歳 世界一周』や、ニコレット・ミルンズ・ウォーカー『アジズ号とわたし』などなど、真摯な意気込みとミズミズしくスガスガしい読後感が共通してる。特に、このジェシカさんはなんと16歳!しっかり者で、将来はヨットに止まらず、広い世界で活躍するでしょう。今後の成長が楽しみ!
訳もよくて読みやすい。訳:田島巳起子さん。
以下、メモ。
よい本だったので大量。
------------------------------------
p13 海の持つとてつもない影響力とは何なのか。…。(『マスト アンド セイル イン ヨーロッパ アンド アジア』H.ワリントン・スミス より引用)
p23 (ヨットレースのコツに気付いたときのこと)「でも、ある穏やかな日のこと、もっとうまく動けるようになるコツは、もうちょっと計画性を持ち、技を身につけ、そして根気強くなることだと気付いた。うまくなってくると、ポジション争いができるまでになってきた。」⇒やっぱりそうか…。わかっちゃいるけど、ネ!
p26 (家族でオーストラリア東海岸をクルーズしていたときのこと)「家族全員が最高の場所だと思うのは、リザード島だ。ヤシの木が海岸に立ち並び、サンゴ礁の海を持つ、息をのむほど美しいトロピカルパラダイスだ。」
p31 「ケイ・コティの『ファースト・レディ』を何度も繰り返し読んだ」(補足:女性で初の単独無寄港・無支援で世界一周を成し遂げた人。)⇒読むべし。
p31 「ジェシー・マーティンの『勇敢な人』も何度も繰り返し読み、」…⇒読むべし。
p33 「著書『勇敢な人』の終わりで、ジェシーはこう言っている。「僕たちは、周りの人々を勇気づけたり、助けたりしなければならない。どんなことでもいいから夢を持っている若い人たちに対しては、それが特に必要。すると、素晴らしいことが起きるのを目にするだろう。…、彼らを信じで励ましてほしい。その人たちが「人間の持つ最も重要な財産の一つ」を失わないように。そう、「夢見る能力」を。」⇒感動した!(古いか。)
p38 「オーストラリアの最南端にあるウィルソンズ・プロモントリー灯台。私の「また行きたい場所リスト」に間違いなく入るところ。」
p42 (スポンサーを捜すため)「…聞いてくれる人にならば誰にでも話をし、たくさんの質問をした。何らかの方法で助けてくれるんじゃないかと思える人には、手紙を書いた。クイーンズランド州首相、アンナ・ブライにまで、若い冒険家が利用できる助成金があるかどうかを確かめるために手紙を出した。首相の代わりに政策顧問の一人から返事が来た」⇒白石康次郎さんみたい。
p42 「…この旅に出るためにとても重要な人物がブルース・アームズだ。一生を航海に捧げてきた人。…」
p48 (オーストラリアの最も経験豊かな船乗りの一人、ドン・マッキンタイアの言葉)「…。オーストラリアにはヒーローが必要。そう、冒険家のことだ。…」
p49 「私は、オーシャンズ・ウォッチのCEOであり、アジア・太平洋地区のプロジェクトリーダーであるクリス・ボーンに連絡を取った。」⇒白石康次郎さんみたい。
p51 「…理想の船リストを最初にまとめたとき、私はS&S34を思い描いていた。…」
p54 マイク・パーハム(オープン50 トータルメモリー.com号で2008年に最年少単独無支援無寄港の世界一周に挑戦した人物)
p62 「十分に考えた後に決断をするなら、それが間違っていても、少なくとも後悔はない」(ドン・マッキンタイアの言葉)⇒正しすぎる…。
p71 「彼らは、どんな冒険でも、準備をきっちりすることの大切さを強調し続けた。ジェームス(・キャストリション)とジャスティン(・ジョーンズ)は、自分たちの記録的な功績の四分の三は、出発する前に成し遂げられていたの言っていると。ピート(・ゴス)も同じことを言っていた。どのレースでも、8割はレースが始まる前に勝ちが決まっていると。」⇒…はーい。
p76 ピーター・ニコル著『ボジャージュ フォー マッドメン』⇒ナイスなタイトル、読みたい。
p105 「いまから20年たったら、君は、それまでにやったことより、やらなかったことを後悔するだろう。だから、自分を縛るものから自由になって、安全な港から海へと漕ぎだそう。帆にいっぱいの風を受けて。そこにあるのは、冒険、夢、そして発見。 マーク・トゥエイン)⇒定番のセリフ、今一度胸に刻もう。
p114 「父はいつも言っていた。問題には正面から取り組み、決して先延ばしにするなと。」⇒はーい…。
p145 「赤道の熱帯無風帯を単独で航海するのは、画期的なこと。船乗りたちが語り継ぐ伝説の場所の一つ。…サミュエル・テイラー・コールリッジが書いた『老水夫の歌』が有名。これはこの無風帯の本質を描いたもの」(⇒本文に全文記載あり、割愛)
p176 「しあわせ眼鏡」「この私の楽天的な考え方」⇒やっぱり、ジェシカはどこか白石康次郎さんと似てる。
p249 「小さなヤンマーのエンジンは、その能力を証明してくれた。バッテリーをチャージしたら、まず点火しなかったことがない。…。エンジンで必要な唯一のメンテナンスは、迅速なファンベルトの締め付けと、時々、船尾のグランド(パッキン?)に潤滑油を吹きかけること。それから、先週は、燃料フィルターから少量の水を排出する必要があった」
p275 「マイク・パラムの本『セーリング・ドリーム』が、今日、イギリスとオーストラリアで発売になった。…この本は読む価値がある!」⇒読むべし!
p288 ジェイミー・ダンロス、事故で四肢麻痺となった後も、2000年のパラリンピックのソナークラスで金メダルを取ったヨットマン。「ジェイミーは自分のホームページでこう言っている。「何が起ころうと、人生は続く。それをどう考えるか、それこそが重要なことだ」
p295 「今日はトリムをして順調に航海するために、重りになっている水とディーゼル燃料をたくさん使って、船首と船尾のバランスを戻す作業をした。」⇒前後のトリム、長距離では重要なんだろうなぁ。われらがモサ号も、調整をやっぺし。
p305 「べサニー・ハミルトン(サメに左腕を喰われてから1月後に海に戻った、14歳のサーファー)の大好きな言葉がある。「勇気、犠牲、決断力、約束、強さ、心、才能、ガッツ。これで女の子はできている。シュガーとスパイスなんていらない」
p318 (シドニー帰港間近になって)「風向きが変わった瞬間に、陸地の、故郷においがしてきた。」
p322 (世界一周を成し遂げた後、)「何人かの人から、ピンクレディ号と私が、その人たちが昔にあきらめてしまったことに挑戦する後押しをしたと知らされて、とてもうれしかった。」
p327(航海を終えて、自分が変わったと思うかとの問いに対して、)「物おじしなくなった」「キャーキャー叫んで、クスクスと笑う、反応の大きな人になった」「一つに絞るならば、人生や自分のことを、あまりにも真剣にとらえすぎるなということ。航海で楽しむことの大切さを学んだのだ。当たり前のことかも。」
p329 「…。だけど、私には「願い」は必要ない。私には、夢を見る能力がある。これこそが、すべての人が「願い」や「夢」を現実にするために必要なこと。」
p329 「あなたに流れ星は必要ない。だって、自分でその願いを叶えることができるから。」
以上
~TRUE SPILIT by Jessica Watson ~

いつもの本屋(ジュンク堂盛岡店)をブラブラしていたら、さりげなく書棚に置かれている本書を発見!
ひさびさのヨット本、即購入。ヤッホ~。
オーストラリアの、弱冠16歳の少女?が、単独無寄港世界一周という夢を叶えるまでを記録した、フレッシュな航海記。
やっぱり、その人最初の「航海記」はいいなぁ!日本なら堀江謙一さんの『太平洋ひとりぼっち』、白石康次郎さんの『七つの海を越えて』、外国ならタニア・アービー『タニア18歳 世界一周』や、ニコレット・ミルンズ・ウォーカー『アジズ号とわたし』などなど、真摯な意気込みとミズミズしくスガスガしい読後感が共通してる。特に、このジェシカさんはなんと16歳!しっかり者で、将来はヨットに止まらず、広い世界で活躍するでしょう。今後の成長が楽しみ!
訳もよくて読みやすい。訳:田島巳起子さん。
以下、メモ。
よい本だったので大量。
------------------------------------
p13 海の持つとてつもない影響力とは何なのか。…。(『マスト アンド セイル イン ヨーロッパ アンド アジア』H.ワリントン・スミス より引用)
p23 (ヨットレースのコツに気付いたときのこと)「でも、ある穏やかな日のこと、もっとうまく動けるようになるコツは、もうちょっと計画性を持ち、技を身につけ、そして根気強くなることだと気付いた。うまくなってくると、ポジション争いができるまでになってきた。」⇒やっぱりそうか…。わかっちゃいるけど、ネ!
p26 (家族でオーストラリア東海岸をクルーズしていたときのこと)「家族全員が最高の場所だと思うのは、リザード島だ。ヤシの木が海岸に立ち並び、サンゴ礁の海を持つ、息をのむほど美しいトロピカルパラダイスだ。」
p31 「ケイ・コティの『ファースト・レディ』を何度も繰り返し読んだ」(補足:女性で初の単独無寄港・無支援で世界一周を成し遂げた人。)⇒読むべし。
p31 「ジェシー・マーティンの『勇敢な人』も何度も繰り返し読み、」…⇒読むべし。
p33 「著書『勇敢な人』の終わりで、ジェシーはこう言っている。「僕たちは、周りの人々を勇気づけたり、助けたりしなければならない。どんなことでもいいから夢を持っている若い人たちに対しては、それが特に必要。すると、素晴らしいことが起きるのを目にするだろう。…、彼らを信じで励ましてほしい。その人たちが「人間の持つ最も重要な財産の一つ」を失わないように。そう、「夢見る能力」を。」⇒感動した!(古いか。)
p38 「オーストラリアの最南端にあるウィルソンズ・プロモントリー灯台。私の「また行きたい場所リスト」に間違いなく入るところ。」
p42 (スポンサーを捜すため)「…聞いてくれる人にならば誰にでも話をし、たくさんの質問をした。何らかの方法で助けてくれるんじゃないかと思える人には、手紙を書いた。クイーンズランド州首相、アンナ・ブライにまで、若い冒険家が利用できる助成金があるかどうかを確かめるために手紙を出した。首相の代わりに政策顧問の一人から返事が来た」⇒白石康次郎さんみたい。
p42 「…この旅に出るためにとても重要な人物がブルース・アームズだ。一生を航海に捧げてきた人。…」
p48 (オーストラリアの最も経験豊かな船乗りの一人、ドン・マッキンタイアの言葉)「…。オーストラリアにはヒーローが必要。そう、冒険家のことだ。…」
p49 「私は、オーシャンズ・ウォッチのCEOであり、アジア・太平洋地区のプロジェクトリーダーであるクリス・ボーンに連絡を取った。」⇒白石康次郎さんみたい。
p51 「…理想の船リストを最初にまとめたとき、私はS&S34を思い描いていた。…」
p54 マイク・パーハム(オープン50 トータルメモリー.com号で2008年に最年少単独無支援無寄港の世界一周に挑戦した人物)
p62 「十分に考えた後に決断をするなら、それが間違っていても、少なくとも後悔はない」(ドン・マッキンタイアの言葉)⇒正しすぎる…。
p71 「彼らは、どんな冒険でも、準備をきっちりすることの大切さを強調し続けた。ジェームス(・キャストリション)とジャスティン(・ジョーンズ)は、自分たちの記録的な功績の四分の三は、出発する前に成し遂げられていたの言っていると。ピート(・ゴス)も同じことを言っていた。どのレースでも、8割はレースが始まる前に勝ちが決まっていると。」⇒…はーい。
p76 ピーター・ニコル著『ボジャージュ フォー マッドメン』⇒ナイスなタイトル、読みたい。
p105 「いまから20年たったら、君は、それまでにやったことより、やらなかったことを後悔するだろう。だから、自分を縛るものから自由になって、安全な港から海へと漕ぎだそう。帆にいっぱいの風を受けて。そこにあるのは、冒険、夢、そして発見。 マーク・トゥエイン)⇒定番のセリフ、今一度胸に刻もう。
p114 「父はいつも言っていた。問題には正面から取り組み、決して先延ばしにするなと。」⇒はーい…。
p145 「赤道の熱帯無風帯を単独で航海するのは、画期的なこと。船乗りたちが語り継ぐ伝説の場所の一つ。…サミュエル・テイラー・コールリッジが書いた『老水夫の歌』が有名。これはこの無風帯の本質を描いたもの」(⇒本文に全文記載あり、割愛)
p176 「しあわせ眼鏡」「この私の楽天的な考え方」⇒やっぱり、ジェシカはどこか白石康次郎さんと似てる。
p249 「小さなヤンマーのエンジンは、その能力を証明してくれた。バッテリーをチャージしたら、まず点火しなかったことがない。…。エンジンで必要な唯一のメンテナンスは、迅速なファンベルトの締め付けと、時々、船尾のグランド(パッキン?)に潤滑油を吹きかけること。それから、先週は、燃料フィルターから少量の水を排出する必要があった」
p275 「マイク・パラムの本『セーリング・ドリーム』が、今日、イギリスとオーストラリアで発売になった。…この本は読む価値がある!」⇒読むべし!
p288 ジェイミー・ダンロス、事故で四肢麻痺となった後も、2000年のパラリンピックのソナークラスで金メダルを取ったヨットマン。「ジェイミーは自分のホームページでこう言っている。「何が起ころうと、人生は続く。それをどう考えるか、それこそが重要なことだ」
p295 「今日はトリムをして順調に航海するために、重りになっている水とディーゼル燃料をたくさん使って、船首と船尾のバランスを戻す作業をした。」⇒前後のトリム、長距離では重要なんだろうなぁ。われらがモサ号も、調整をやっぺし。
p305 「べサニー・ハミルトン(サメに左腕を喰われてから1月後に海に戻った、14歳のサーファー)の大好きな言葉がある。「勇気、犠牲、決断力、約束、強さ、心、才能、ガッツ。これで女の子はできている。シュガーとスパイスなんていらない」
p318 (シドニー帰港間近になって)「風向きが変わった瞬間に、陸地の、故郷においがしてきた。」
p322 (世界一周を成し遂げた後、)「何人かの人から、ピンクレディ号と私が、その人たちが昔にあきらめてしまったことに挑戦する後押しをしたと知らされて、とてもうれしかった。」
p327(航海を終えて、自分が変わったと思うかとの問いに対して、)「物おじしなくなった」「キャーキャー叫んで、クスクスと笑う、反応の大きな人になった」「一つに絞るならば、人生や自分のことを、あまりにも真剣にとらえすぎるなということ。航海で楽しむことの大切さを学んだのだ。当たり前のことかも。」
p329 「…。だけど、私には「願い」は必要ない。私には、夢を見る能力がある。これこそが、すべての人が「願い」や「夢」を現実にするために必要なこと。」
p329 「あなたに流れ星は必要ない。だって、自分でその願いを叶えることができるから。」
以上