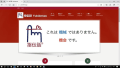作業療法部門で「低周波治療器 IVES+:Integrated Volitional Control Stimulator® (以下 IVES)」について勉強会を行いました。IVESとは電極から随意筋電を検出して、検出した筋電量に比例した強度の電気刺激を標的の筋肉に与える装置のことです。写真では前腕に電極を貼り、手指や手関節の伸展を行う筋肉を標的としています。その他にも肩の運動や足の運動に関 . . . 本文を読む
東埼玉病院のリハビリテーション科では定期的に勉強会を開いています。今回、「回復期脳卒中後うつのリハビリ」をテーマに勉強会を行いました。少しでも皆様の参考になればと考え、内容を抜粋して掲載します。
1.脳卒中後うつ(post stroke depression; PSD)とは
脳卒中後うつ(post stroke depression ; PSD)とは、脳卒中後に見られる器質性(脳の障害によるもの . . . 本文を読む
先日、作業療法科内でIT機器の勉強会があり、そこでの内容をご紹介したいと思います。
今回紹介するのが「ワンキーマウス」というIT機器です。ワンキーマウスはスイッチ1つでパソコンやAndroidのタブレット、スマートフォンを操作することができる機械で、上肢・手指の筋力低下や変形などの理由によりマウス操作ができない方が対象となります。
ピルケーススイッチやタッチスイッチなど患者さんそれぞれに . . . 本文を読む
3月2日金曜日、結ライフコミュニケーション研究所の高橋宜盟さんが勉強会講師として来てくださいました。講師をお願いした目的のひとつは「指伝話(ゆびでんわ)」というiPad用アプリについて教えて頂くため。スイッチ1つで操作することもできるので、難病の方のコミュニケーションツールとして、当院作業療法士に必要な知識技術です。もうひとつの目的はコミュニケーションの「考え方」についてお話頂くため。高橋さんと . . . 本文を読む
2月22日木曜日、吉野神経内科医院の言語聴覚士 山本直史先生が来院されました。山本先生は筆者が尊敬し、目指してきた方です。先生の「難病コミュニケーション支援」を皆に知ってほしくて、勉強会講師をお願いしました。全部をお伝えすること残念ながら叶わないので、筆者がとても大事にしている話をここでご紹介します。
【闇から光へ】
その方は筋萎縮性側索硬化症(ALS)で1年間、誰にも自分の言葉を伝えることが叶 . . . 本文を読む
7月18日業務後に埼玉県立大学理学療法学科教授の西原賢先生を招いて、超音波の基礎から実践まで勉強会を実施しました。
内容は、超音波モニターの見方、調整からプローブの操作といった基礎、上肢・下肢の筋・腱・血管・神経などの解剖学的な所見を確認し、スタッフ間で実演しました。
今日では、整形外科クリニックなどを中心に理学療法士でも超音波を用いた運動器評価が流行っている印象があります。
当院では業務上、自 . . . 本文を読む
前回記事「前半戦:感覚障害と可塑性変化」からの続きです。
第3章「感覚障害に対するリハビリテーション」の内容で後半戦が始まります。
ちょうどサッカーW杯予選をやっていたので,前半・後半の2部構成にしました。
ということで、
感覚を考える上で、まずは上下肢の機能的目的から考えてみましょう。
そもそも感覚障害は自然に回復するものなのでしょうか?
確認してみましょう。
では、誰もが考え . . . 本文を読む
久しぶりにリハ科勉強会シリーズから昔の資料を引っ張りだしてきました。
発表日を確認すると2015年8月6日でした。
今回は、この勉強会からブログ記事転載します。
ただ…例によって長いんです。全67スライド。
もちろん全て掲載するつもりはないですが、前半と後半に分けます。
この記事はその前半部分になります。
*「著作権保護!」でブロックしている画像やイラストは、私のではなく、原典の保護のためです。 . . . 本文を読む
昨年12月に実施したリハ科勉強会の概要になります。
臨床においては。一般的に脳卒中片麻痺者の歩行はどう評価しているでしょうか?
もちろん状況や設備、セラピストによっても異なるとは思いますが、代表的なものは、
• 歩行様式・パターン
• 歩行自立度(安全性)
• 歩行の運動学的パラメータ(関節角度や肢位・速度・歩幅など)
• 特徴の列挙
• 短期的な変化
• ビデオ撮影
• 歩行の評価シート
• . . . 本文を読む
去る2017年1月6日にリハ科内で勉強会を行いました。
内容はアナトミートレインの基礎的な部分から少し臨床的な部分に向けて、でした。
アナトミートレインとは、筋筋膜経線の12本(現段階で)のラインのことを列車の線路に見立てたものを例えた用語です。
最近は、筋膜という用語も一般的に浸透してきている印象がありますね。
リハの世界でも、従来の個別の筋に焦点を当てた考え方から、筋膜を介した相互の筋連結に . . . 本文を読む