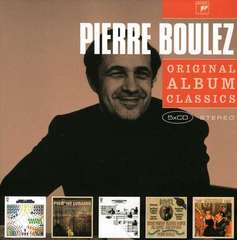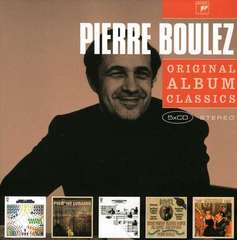
モーリス・ラヴェルの楽曲で一番好きな曲は何かって訊かれたら,
―《ステファヌ・マラルメの3つの詩》です!
って,力強く答えます。
声楽付き室内楽とでもいうのでしょうか,以下の編成で演奏される曲です。
「独唱,ピッコロ,フルート,クラリネット,バス・クラリネット,ピアノ ,ヴァイオリン(×2),ヴィオラ,チェロ」
ところで,クラシック音楽における“歌モノ”,つまり声楽曲ってことですが,何だか評判が悪いようです。「評判が悪い」という表現は適切でないのかもしれませんが,兎にも角にも人気がない。クラシック愛好家の中にも,マーラーやベートーヴェンの声楽付き交響曲を除いて“歌モノ”は聴かないよ,という人も結構います。勿体ないなぁって僕は思いますけどね。
さて,このラヴェルの楽曲ですが,たしか次のような経緯で作曲されたはずです。
シェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》を聴いたストラヴィンスキーは,ピアノ伴奏歌曲として作曲していた《日本の3つの抒情詩》を室内楽伴奏に変更した上で,我らがモーリスに言います。
「ねぇねぇ,モーリス。《月に憑かれたピエロ》って知ってる? これ凄くいいよ~。」(←想像)
へぇーっと思ったラヴェルは《月に~》の楽譜を手に入れて読み,それなら僕も書いてみるか,と思って《ステファヌ・マラルメの3つの詩》を作曲するわけです。と,まぁ,シェーンベルク・ストラヴィンスキー・ラヴェルと有名どころが繋がってるわけですが,こういうのも何だか面白いですよね。
それで楽曲ですが,何この音の響きの美しさ!...という言葉を思わず口にせずにはいられないほどの「美しさ」を湛えています。ラヴェルの楽曲は「古典的均衡のとれた…」などと解説されることが多く,確かにその通りなのですが,その「均衡」が実に危ういバランスで保たれているんですね。彼は基本的に美学的な嗜好を持った作曲家だと思うのですが,「美」の追求が「狂気」へと転がり落ちかねない点まで達していて,その稜線上でギリギリのバランスをとって歩んでいる感覚を常に感じます。
そんなラヴェルの危うさがよく表れているの曲の一つがこの《ステファヌ・マラルメの3つの詩》ではないでしょうか。僕としては,音響系とかエレクトロニカなどを好むリスナーに聴いてもらいたいなぁと思っています。この美しくも危険な音の響きに身を委ねてみるのも一興ですよ。
ところで,この曲を聴けるディスクですが,実はあまりありません。でも,3年ほど前にソニー・クラシカルから出たピエール・ブーレーズの5枚組再発アルバムの中に,ブーレーズ指揮のラヴェル声楽曲集が含まれており,そのディスクで聴くことができます。興味をもたれた方は是非聴いてみてください。
Jill Gomez(sop), Members of BBC Symphony Orchestra, Pierre Boulez(dir), <<Ravel: Trois poèmes de Stéphane Mallarmé>>, in <<PIERRE BOULEZ: ORIGINAL ALBUM CLASSICS>>, Sony Music