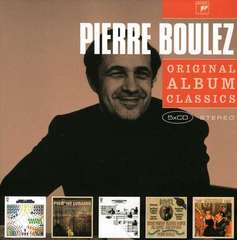バッハの鍵盤楽曲を聴くときに好んで聴くのはグールドなんですが,《平均律》に関してはグールドに馴染めませんでした。それでもバッハの《平均律》は折に触れて訊きたい曲なので,グールド以外で誰の演奏を聴こうかなぁ……ってあれこれとディスクを調べていたときに「リヒテルってどうだろう?」と思い購入したのがこのディスクです。
それで,このディスクですが,当たりかハズレかどちらかといいますと……
大当たりですっ!
とはいえ,このリヒテルの演奏が気に入らない人もいると思います。特に僕とは逆にグールドの《平均律》に馴染んでいる方の中に。リヒテルの演奏とグールドの演奏を比べてみると以下のような違いがあります。
リヒテル…ウェット/韻文詩的/ロマン派的 ,などなど
グールド…ドライ /散文詩的/ポスト・モダン的,などなど
二項対立的図式でまとめるとこんな感じじゃないでしょうか。
リヒテルの演奏は,一言でいえばロマンティックといえます。ですが,19世紀のバッハ解釈にみられるような“ロマン派”的な演奏とは異なります。バッハの楽曲構造がくっきりとみえる演奏です。ヴィクトル・ユゴーのような熱情的なロマンティックさではなく,ステファヌ・マラルメなどの象徴派詩人にみられる“冷やかなロマン”が,リヒテルの演奏には表れています。その冷やかさを通して,バッハの楽曲構造が浮かび上がってくる感覚を感じます。
音楽演奏において楽曲構造の提示を重視する姿勢について,当然のことながら,グールドはとても意識的です。しかし,グールドの《平均律》は,構造性への意識が強く出てしまったが故に“奇を衒った演奏”のように感じられるのです。一方,リヒテルの演奏は,実に素直です。彼がバッハの楽譜から読み取ったものをそのままそっと差し出した結果が,楽曲構造の意図的ではない提示に繋がったのだと思われます。
リヒテルとグールド。どちらの演奏も名演には違いないので,できればどちらも聴いて頂きたいです。
ところで,この記事の画像は国内盤ディスクのものなのですが,リンク先は輸入盤にしてあります。なぜってそちらの方が安いからです!
Sviatoslav Richter(pf), <<J.S. Bach: The Well-Tempered Clavier>>, RCA