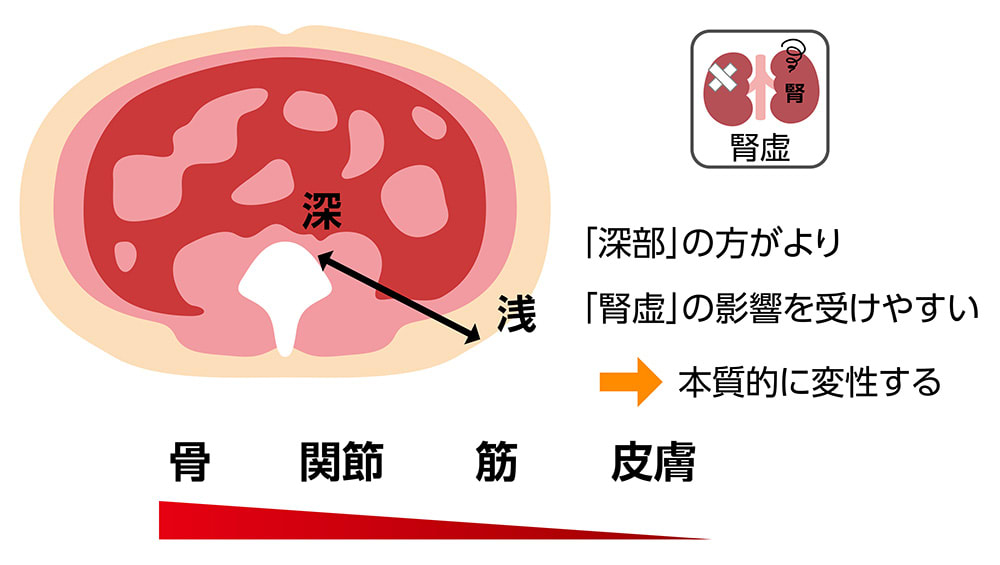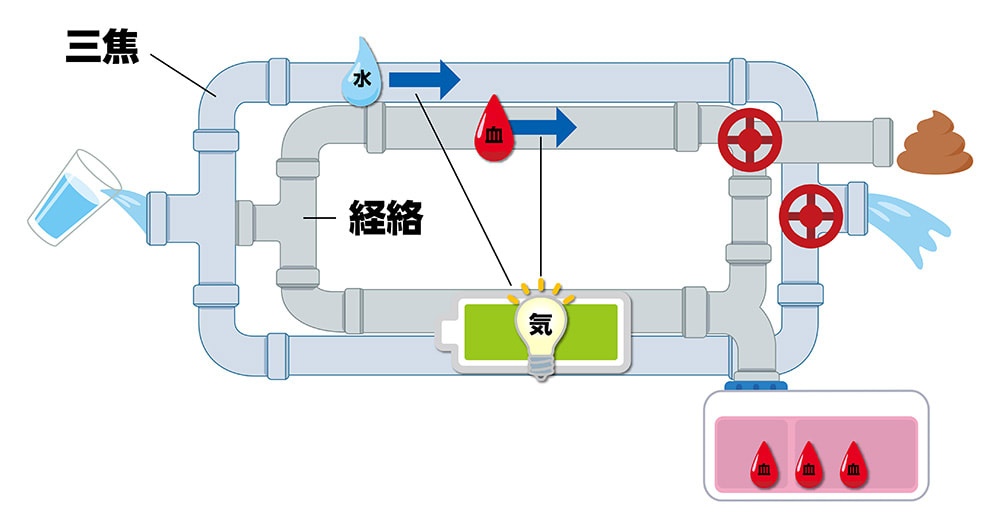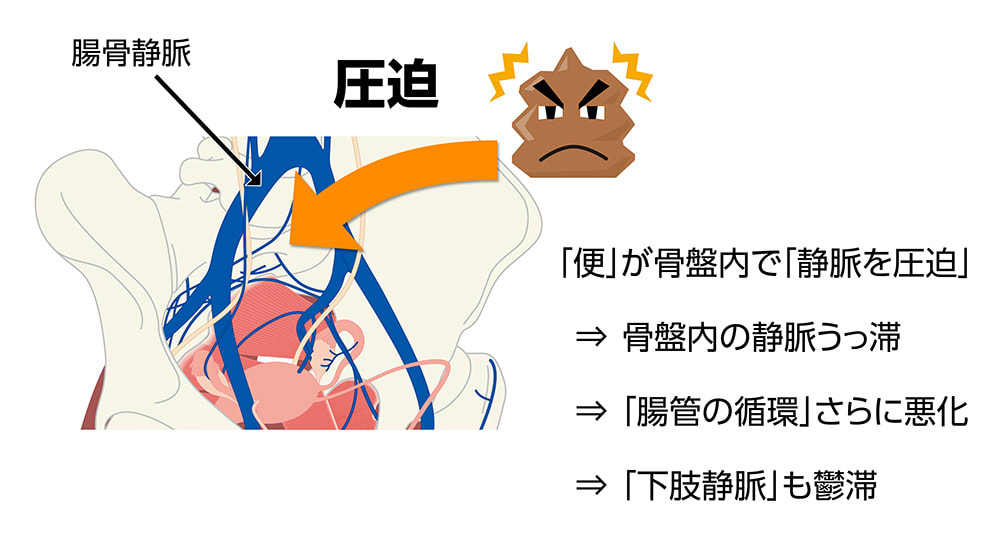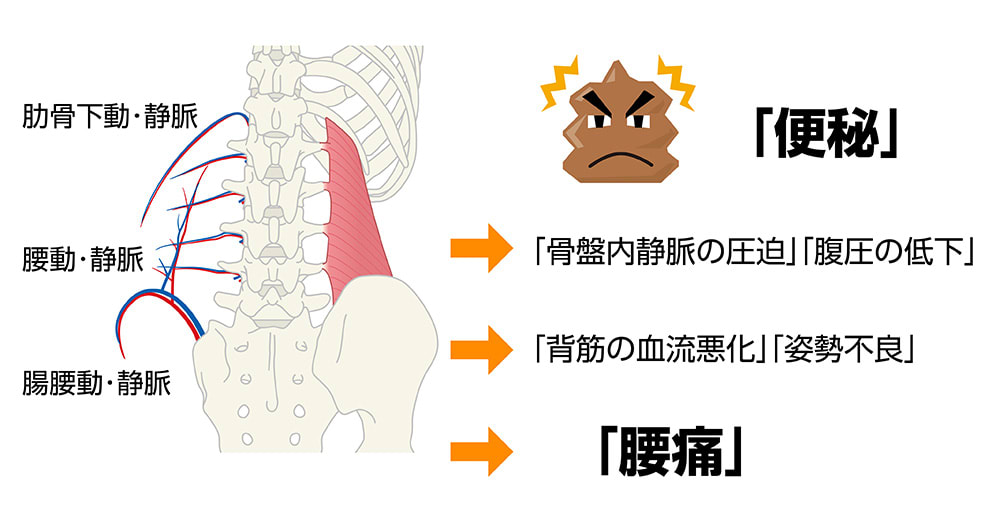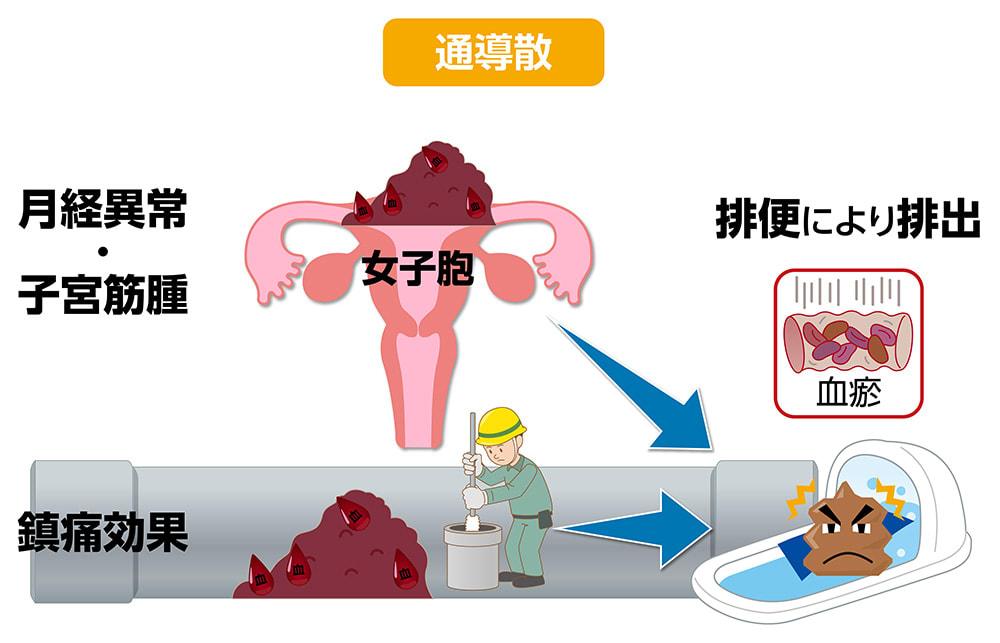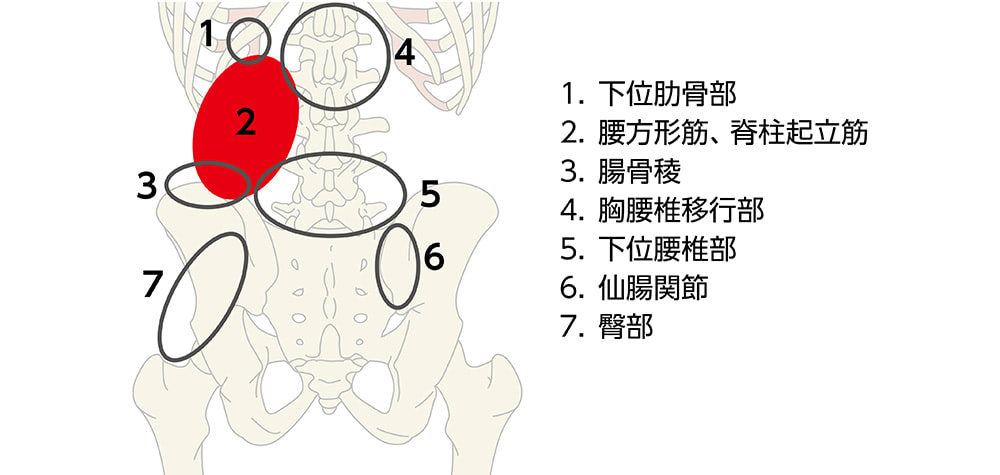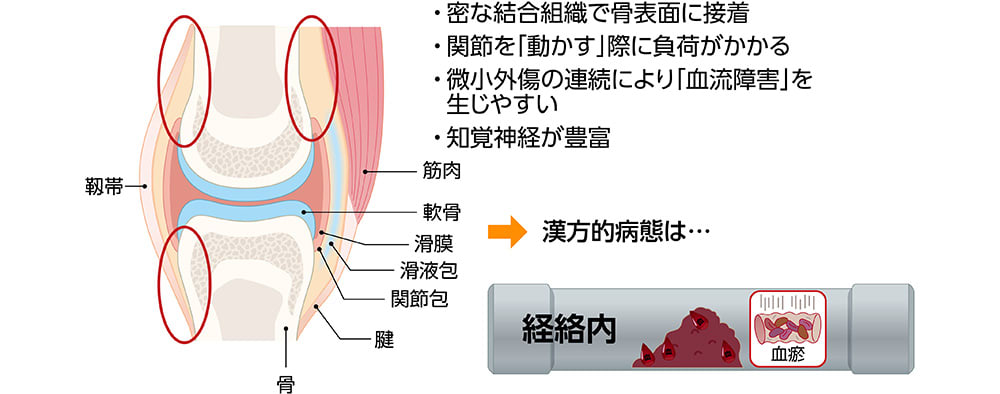漢方薬は生薬の集まりです。
大抵、基本となる方剤があり、
それをアレンジして様々な方剤が創出され、
いろいろな症状や体質に対応できるようになっています。
さらに特徴として、
構成生薬の中に「こころ」に効くものが入っています。
つまり、「体にも心にも効く」のです。
「心身一如」と呼ばれる所以です。
私は小児科医なので、子どものこころのトラブルの相談を時々受けます。
乳幼児期の夜泣き、
幼児期のかんしゃく、
幼児・学童期の反復性腹痛(過敏性腸症候群)、
等々。
みんな、検査をしても異常が検出できない訴えです。
西洋医学では「ストレスを減らして様子を見ましょう」
としか言えませんが、
漢方では対応する薬が用意されています。
なんと1800年前からあるのですよ。
昔の人も同じようなことで悩んできたのですね。
そんな薬について、整理してみたいと思います。
子どもの成長とともに心の問題(小児心身症)の症状も変遷していきます。
これはアレルギー体質の子どもが成長とともに発症する病気が変化していく「アレルギーマーチ」と似ているな、と感じます。
(乳児期)
1.夜泣き
(幼児期)
1.眠らない
2.よくお腹を痛がる
(学童期)
1.眠らない
3.よく頭を痛がる
4.起立性調節障害・不登校
(思春期)
1.眠れない
2.よくお腹を痛がる
3.よく頭を痛がる
4.起立性調節障害・不登校
以上の病態を4つにまとめると、対応する代表的な漢方薬は、
1.睡眠障害 → 甘麦大棗湯(72)、抑肝散(54)
2.過敏性腸症候群 → 小建中湯(99)、桂枝加芍薬湯(60)、四逆散(35)
3.反復性頭痛 → 五苓散(17)、柴胡桂枝湯(10)
4.起立性調節障害 → 補中益気湯(41)、苓桂朮甘湯(39)、柴胡桂枝湯(10)
となります。これらを中心に説明します。
1.睡眠障害(夜泣き・眠らない・眠れない)
(乳児期)夜泣き:甘麦大棗湯(72)、抑肝散(54)
・泣き虫、シクシク泣く、不安 → 甘麦大棗湯(72)
・怒りんぼ、ギャーギャー泣く、かんしゃくもち → 抑肝散(54)
(幼児期・学童期)眠らない・眠れない
~子どもの4₋5人に1人に睡眠問題がある。
夜10時以降に就寝する子どもの割合は、1~3歳の半分以上。
・不安・泣き虫・あくび → 甘麦大棗湯(72)
・神経質・イライラ・多動 → 抑肝散(54)
・反復性腹痛・虚弱 → 小建中湯(99)
・鼻閉・口を開けて寝ている → 葛根湯加川芎辛夷(2)
(思春期)眠れない
・不安 → 甘麦大棗湯(72)
・イライラ・興奮 → 抑肝散(54)
・動悸・ストレス・恐怖 → 柴胡加竜骨牡蛎湯(12)
・うつうつ、不安だらけ、不眠 → 加味帰脾湯(137)
・心身ともに疲れて眠れない → 酸棗仁湯(103)
2.お腹を痛がる(反復性腹痛・過敏性腸症候群)
基本編:小建中湯(99)
・虚弱体質で登園・登校前にお腹が痛くなる、
イベントの前になるとおなかが痛くなるタイプに有効
・マンガ「ちびまる子ちゃん」のキャラクターの中では「中井君」
応用編:
・桂枝加芍薬湯(60):(小学校高学年以降の)過敏性腸症候群
・柴胡桂枝湯(10):小中学生でストレスまみれ、他に頭痛やだるさも訴える
・四逆散(35):中高生でストレスが強く常に緊張、緊張で手が震える、手掌発汗
・芍薬甘草湯(68):頓服で使用
★番外編:のど・胸のつかえ感・違和感 → 半夏厚朴湯(16)
3.頭を痛がる(反復性頭痛・片頭痛)
・気圧変化(低気圧・悪天候)による → 五苓散(17)、苓桂朮甘湯(39)、半夏白朮天麻湯(37)
・筋緊張性頭痛 → 柴胡桂枝湯(10)
・神経質・イライラ・多動 → 抑肝散(54)
・嘔吐・冷え・胃腸虚弱 → 呉茱萸湯(31)
・虚弱体質(+腹直筋緊張)→ 小建中湯(99)
・月経関連頭痛 → 当帰芍薬散(23)、加味逍遥散(24)、桂枝茯苓丸(25)
4.起立性調節障害・不登校
●「朝起きられない」ときに考えるべき病気:
① 体を起こせない(起立性調節障害)
② 目が覚めない(睡眠覚醒リズム障害)
③ そもそも起きたくない(心理社会的要因)
→ 以上を考慮し、①と判断したら漢方薬の出番。
● 起立性調節障害の諸症状に合う漢方薬:
・朝起きられない、だるい、しんどい → 補中益気湯(41)
・朝起きられない、めまい・たちくらみ、車酔い → 苓桂朮甘湯(39)
+胃腸が弱い・頭痛 → 半夏白朮天麻湯
・おなかが痛い、虚弱 → 小建中湯(99)
・おなかが痛い・頭が痛い・ストレス → 柴胡桂枝湯(10)
・心身症(ストレスが主因)→ 抑肝散(54)、抑肝散加陳皮半夏(83)、柴胡加竜骨牡蛎湯(12)
・生理中に悪化傾向 → 当帰芍薬散(23)、加味逍遥散(24)、桂枝茯苓丸(25)
● 倦怠感+α に効く漢方薬:
・倦怠感(とにかくだるい)→ 補中益気湯(41)
・倦怠感 + 貧血・皮膚乾燥 → 十全大補湯(48)
・倦怠感 + めまい・頭痛 → 半夏白朮天麻湯(37)
・倦怠感 + 不安・落ち込み → 加味帰脾湯(137)
・倦怠感 + 胃もたれ・冷え → 六君子湯(43)
★ フクロウ型体質(山本巌・惠紙英昭先生)
・朝起きるのが苦手
・朝は頭がボーっとしているが、夕方から夜にかけて最も元気
・夜はなかなか寝付けない
・体力がなく疲れやすい、頭痛やめまいがある
・吐き気・胃痛などの消化器症状
→ これらの症状に苓桂朮甘湯(39)が有効、
倦怠感が強いときは苓桂朮甘湯(39)+補中益気湯(41)が有効
● 不登校になる前の体の不調
・頭痛・腹痛
・疲れやすい
・眠れない
・朝起きられない
→ 以上がやがて、不安・抑うつ・不登校につながる
● 不登校の要因ベスト5(令和4年、文科省)
① 無気力・不安(52%)
② 家庭の問題(13%)
③ 生活リズムの乱れ(11%)
④ 学校の問題(11%)
⑤ 友人関係(9%)
● 不安感に対する漢方薬
・悲しみ・パニック → 甘麦大棗湯(72)
・喉のつまり → 半夏厚朴湯(16)
・不安で心配でたまらない、体力なし、無気力 → 加味帰脾湯(137)
・ストレス、動悸、体力あり → 柴胡加竜骨牡蛎湯(12)
★「粉薬は飲めない!」という年長児には錠剤が用意されている方剤も:
・ストレスが強い・動悸・イライラ → 柴胡加竜骨牡蛎湯(12)
(抑肝散、甘麦大棗湯の代わりに)
・過敏性腸症候群 → 桂枝加芍薬湯(60)
(小建中湯の代わりに)
・頭痛・腹痛・緊張が強い → 柴胡桂枝湯(10)
・だるい・疲れた → 補中益気湯(41)
・喉のつまり → 半夏厚朴湯(16)
<方剤解説>
※ 芍薬+甘草 → 鎮痙・鎮痛作用
※ 柴胡+芍薬 → 抗ストレス作用、自律神経調節作用
10【柴胡桂枝湯】
● 構成生薬:小柴胡湯+桂枝湯
桂皮・芍薬・甘草・大棗・生姜 → 桂枝湯
柴胡・黄岑・半夏・人参・甘草・大棗・生姜 → 小柴胡湯
● 臨床応用:
・頭痛・腹痛などいろいろな症状
・ストレスがありそう
・自律神経失調症
・風邪の亜急性期
・反復性感染症
● こんな症状・体質に(広瀬滋之Dr):
・神経質・几帳面、不安傾向、ストレスに過敏
・ふだんから過緊張傾向(手掌発汗、肩こり、体が硬い)
・痛み(頭痛、腹痛、関節痛等)をよく訴える
・OD傾向あり(小症状>大症状・・・疼痛型)
・心身症に罹りやすい
・けいれん体質、周期性嘔吐症、夜尿症、チック、成長痛、不定愁訴、風邪をひきやすい
→「困ったときの柴胡桂枝湯」(新見正則Dr)
12【柴胡加竜骨牡蛎湯】
● 構成生薬:(小柴胡湯-甘草)+竜骨・牡蛎+α
柴胡・黄岑・半夏・人参・大棗・生姜 →(小柴胡湯-甘草)
桂皮
竜骨・牡蛎(精神安定、抗動悸)
茯苓(精神安定)
● 効能効果:
比較的体力があり、動悸、不眠、いらだちなどの精神症状のあるものの次の諸症:
・高血圧
・動脈硬化
・慢性腎臓病
・てんかん
・ヒステリー
・小児夜驚症
・陰萎
● こんな症状・所見に:
・体力中等度
・ストレスに立ち向かっている
・臍上悸(腹部大動脈拍動著明)
・胸脇苦満(心か部から右脇にかけて抵抗)
16【半夏厚朴湯】
● 構成生薬:小半夏加茯苓湯+厚朴・蘇葉
半夏・茯苓(気をめぐらす)
生姜
厚朴・蘇葉(気をめぐらす)
● こんな症状・所見に:
・精神症状+喉のつまり感
・咽頭や食道部の違和感(梅核気、ヒステリー球、咽中炙臠)
● 効能効果:
・不安神経症
・神経性胃炎
・つわり
・咳
・神経性食道狭窄症
・不眠症
17【五苓散】
● 構成生薬:
桂皮(温める、抗炎症作用)
蒼朮・沢瀉・猪苓・茯苓(水分代謝調節)
● 特徴:
・利水剤:脱水の時には水を保持、浮腫の時には水を排泄。
・水チャンネルであるアクアポリンに作用し水分代謝調節を行う。
● 臨床応用:
・ウイルス性胃腸炎
・頭痛(気象病・天気痛傾向)…アプリ「
頭痛-る」の活用を
・乗り物酔い
・飛行機の離着時の症状
・熱中症
・二日酔い
・めまい
35【四逆散】
● 構成生薬
柴胡
芍薬
甘草
枳実
37【半夏白朮天麻湯】
● 構成生薬:
天麻(頭痛・めまいを止める)
黄耆・人参(元気にする)
半夏・陳皮・生姜・茯苓・白朮→六君子湯
茯苓・白朮・沢瀉(利水)
麦芽・乾姜(健胃)
黄ばく(清熱)
● 特徴:
・黄耆・人参入り → 参耆剤
・六君子湯の8つの構成生薬のうち、大棗・甘草以外が含まれている。
● こんな症状・所見に:
・めまい・頭痛・嘔気
・胃腸虚弱、全身倦怠感
・冷え
39【苓桂朮甘湯】
● 構成生薬:
茯苓(水をめぐらせる、精神安定)
桂皮(気をめぐらせる、温める)
蒼朮(水をめぐらせる、胃腸を整える)
甘草
● こんな症状・所見に:キーワードは「ドキドキ・チャポチャポ」(腹診所見)
・めまい、立ちくらみ
・頭痛、動悸
・臍上悸(ドキドキ)
・胃内停水音(チャポチャポ)
41【補中益気湯】
● 構成生薬:
柴胡・升麻(下がったものを持ち上げる)
(下がったものの例)食欲、気分、精神、内臓下垂
人参・黄耆(元気にする)
人参・蒼朮・陳皮・生姜・大棗・甘草(胃腸機能改善)
当帰(血をめぐらせる)
● こんな症状・所見に:
・しんどくてやる気が出ない。
・食欲がない。
・疲れやすい。
・食後の眠気。
・風邪の回復が悪いとき。
54【抑肝散】
● 構成生薬:
釣藤鈎・柴胡(情緒安定)
茯苓・蒼朮(水のめぐりを調節)
当帰・センキュウ(血のめぐりを調節)
甘草
● こんな症状・症状に:
・神経質でイライラ、落ち着きがない。
・常に緊張を強いられている。
・やや興奮的な状態。
・どこかに怒りがある。
※ 母親もイライラしているときは母子同服を。
● 効能効果:
・虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症:神経症、不眠症、小児夜泣き、小児癇症
● 臨床応用:
・イライラ
・夜泣き、疳の虫
・睡眠障害
・チック
・神経発達症
・泣き入りひきつけ
★ 怒りの急性期には抑肝散、
長期化した怒りは、心身を損ね虚弱化させ胃腸を弱めるため、
抑肝散化陳皮半夏がよい。
72【甘麦大棗湯】
● 構成生薬:
甘草(緊張緩和)
浮小麦(情緒安定)
→ トリプトファンを含み、セロトニンやメラトニンのもとになる。
大棗(情緒安定・胃腸を整える)
● 特徴:
・すべてが食品としても使用される生薬で甘い。
● こんな症状・所見に:
・精神興奮がはなはだしく、不安・不眠・ひきつけなどのある子ども。
・「大丈夫、心配しないで」と声をかけたくなる子ども。
● 効能効果:
・夜泣き、ひきつけ(ツムラ)
・小児および婦人の神経症、不眠症(コタロー)
● 臨床応用
・不安が強い(母親分離不安も含む)
・夜泣き
・睡眠障害
・パニック、過換気
・チック
・神経発達症
・心因性頻尿
・涙があふれる
● 具体的な投与方法:
・パニック、不安予兆、過呼吸、涙があるれるとき→頓用
・登校不安など→朝、登校・登園前に
・夜泣き、ヤキョウ症、怖い夢を見る→夜、寝る前に
★ パニックに甘麦大棗湯(72)で効果が今一つの場合は、
苓桂甘棗湯(奔豚湯):甘麦大棗湯(72)+苓桂朮甘湯(39)
がおススメ。
83【抑肝散化陳皮半夏】
● 構成生薬:抑肝散+陳皮・半夏
陳皮・半夏(胃腸機能調整・気のめぐり・水バランス調整)
● こんな症状・所見に:
・抑肝散より虚弱なタイプ。
・食が細い。
・怒りで心身が弱っている。
99【小建中湯】
● 構成生薬:桂枝加芍薬湯+膠飴
桂皮(温める)
芍薬(鎮痙・鎮痛)
大棗・生姜・甘草(胃腸を整える)
膠飴(滋養・潤す)・・・麦芽糖(オリゴ糖)
● 特徴:
・虚弱児の体質改善
・腸を温めて腸蠕動を調節する
・緊張を緩和し情緒安定 → 体と心の緊張をゆるめて楽にしてくれる
● こんな症状・所見に:
・食が細い、線が細い
・何となく顔色が悪い
・腹痛の訴えが多い
・目の下のクマ、まつげが長い
・偏食で甘いものが好き
・便秘したり下痢したり
・冷え症
・緊張しやすい
・汗をかきやすい(寝汗も)
・頻尿傾向
● 参考となる漢方的腹部診察(腹診)所見:
・お腹を触ると腹直筋が緊張(=交感神経過緊張)している
・くすぐったがる子ども
・「はい、力を抜いて~」と言っても抜けない人
● 効能効果:
・小児虚弱体質
・疲労倦怠
・神経質
・慢性胃腸炎
・小児夜尿症
・夜泣き
● 臨床応用:
・反復性腹痛、過敏性腸症候群
・虚弱児の体質改善
・周期性嘔吐症
・便秘症
・遷延性下痢症
・心因性頻尿
・アレルギー疾患の体質改善
137【加味帰脾湯】
● 構成生薬:帰脾湯+柴胡・山梔子
※ 帰脾湯には四君子湯が丸ごと入っている
柴胡・山梔子(清熱)
当帰・酸棗仁・竜眼肉・遠志・木香(血を補う、精神安定)
黄耆・人参
人参・茯苓・蒼朮・大棗・生姜・甘草
● 効能効果:
虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症:
・貧血
・不眠症
・精神不安
・神経症
● こんな症状・所見に:
・顔色の悪い虚弱タイプ
・心配で思い悩んで疲れる
・オキシトシンとの関係(137はオキシトシンを増やす)