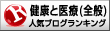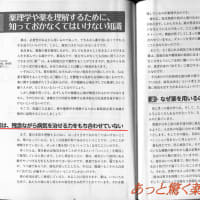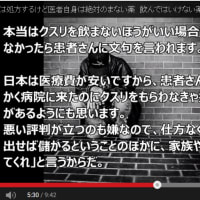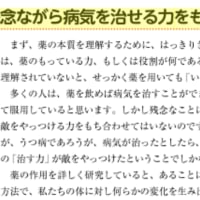以下はweb上から消えて過去のHP等を魚拓して保存しているサイトから見つかったモノです。
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
より
これから分割して、改行を勝手に加えてありますが、内容はそのままです。
2004年(平成16年)が最終更新となっていましたので、今から約十二年前の話ですが、現在においても貴重な論文だと思われますが、その後の状況の変化もありますので、最終的な取捨選択権は、もちろん!貴方にあります。
https://web.archive.org/web/20050228095921/http://www12.plala.or.jp/kusuri/page2.html
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
音声はこちらwebギョ拓1 「驚くべき医者の無知」より
1. 驚くべき医者の無知
1.頻発する医療ミス
2.構造上の欠陥
3.唯物科学の終焉
4.医学理論の致命的な過ち
1. 頻発する医療ミス
今さらいうまでもなく、医療による被害者は増加する一方です。
残念ながら公式の統計はありませんが、ある弁護士の推計によりますと、医療ミスで死亡する人は、年間17、000人から39、000人となっています。
これは、交通事故による死亡者数を明らかに上回っています。
数字に幅があるのは、事故死を病死と偽って報告するケースがあり、年次別の、正確な実態の把握が困難なためです。
連日のように報道される医療ミスには、すぐに死亡に至る場合のほか、病態をさらに悪化させる、新たにべつの病気をつくりだす、二度と元に戻らない障害を負わせるなど、さまざまな種類があることがわかります。
死亡事故は遺族にとって、障害事故は当の被害者と家族の両方にとって悲劇です。
障害の程度によっては、肉体的、精神的苦痛に打ちひしがれ、生活の基盤は奪われ、生きる希望をほとんど絶たれてしまうことも珍しくありません。
その無念さは、当人以外、たとえ家族といえども、真に理解しがたいものです。
そしてこれらの事故は、検査・投薬・放射線・手術といった医療行為そのものによって起こる、くわえて医者、看護婦、検査技師、薬剤師の能力不足、不注意や怠慢、意思疎通のトラブルで起こるなど多岐にわたっています。
さいわい障害・死亡事故にはいたらなかったものの、ほとんど公表されることのない病状悪化や合併症の誘発、後遺症の発作などは、大小あわせると年間数十万、いや、数百万単位の規模で発生しているともいわれ、医療ミスは、まさに、「明日はわが身」といってもけっして過言ではないでしょう。
この深刻な事態について、マスコミや医療ジャーナリストはつぎのように分析しています。
医者の資格認定や研修医制度の欠陥や不備
それが原因の医者の知識不足や技術不足
医療行為を監視する医道審議会の怠慢
新薬をめぐる医者と医薬品メーカーとの癒着
患者軽視の利益優先主義
『出来高払い』という不可解な診療報酬請求システム
制度を悪用する医道モラルの荒廃
しかしながら、これらの指摘では、事故との具体的な因果関係まではわかりません。
今私の手元に、医療事故にあった人たちとその家族からの相談内容を検証し、医療問題をより深く掘り下げた一冊の本があります。
慶應義塾大学医学部放射線課講師・近藤誠氏と、医療消費者ネットワークMECON代表世話人・清水とよ子氏の共著による『医療ミス』という本で、つぎにその一部を要約させていただきます。
医療事故には「うっかり型」、「能力欠落型」、「必然型」の三つの種類があり、それらが起こる原因は「個人」、「組織」、「構造」、「意識」の四つにあると考えられる。
個人とは医者、看護婦、技師などの医療従事者、組織とは病院などの医療機関の人員配置や役割分担、構造とは医療の仕組み、そして意識とは、医療従事者や一般の人々の病気や治療に対する見方のことである。
能力欠落型の医者が大量に生み出される原因は、偏差値教育、つまり医者を養成する教育システムという構造のなかにある。
偏差値教育は拝金主義を助長し、医者として不的確な人間をつくるなどの弊害を生む。
その結果、医学生は医師国家試験にうかることだけを唯一の目標にするようになる。
試験対策の手引きのようなものが教科書がわりに使われ,試験といっても、解答の選択肢のなかから正解を一つだけ当てさせるもので、勉強の仕方もそれに対応した知識つめこみ型になる。
正式の教科書も、臨床能力に乏しい老齢の大学教授が執筆したもので、内容はじつにお粗末なものだ。
日本語で書かれているため、学生は英語の勉強をしない。
そのため、最新の医学情報を知るための文献が読めない(日本の医療・医学レベルは欧米より10?20年遅れている)。
埼玉医大では、医者が簡単な英単語を読めなかったため、患者を殺してしまったという実例がある。
べつの例では、放射線治療をうけていた咽頭がんの患者が死亡した。
放射線の急性反応である口内炎で食事ができなくなり、高カロリー輸液の点滴をしていたが、医者に必須ビタミンを輸液に入れる必要があるという知識がなかったため、患者はビタミンB1の欠乏症である脚気、ないし血液が酸性に傾くアシドーシスにかかり、それが重症化したのが死因だった。
欠陥だらけの医学教育によって医学生の頭のなかはすっかり〇×式になってしまい、多様な事態に対処する能力は養われないのである。
この本ではさらに、医療行為そのもので生じる「必然型」の事故についても、多くの事実が明らかにされています。
なお、能力欠落型も必然型も、見方によっては同一視できるものだと述べ、次のような例をあげています。
脳手術では、開頭しただけで攣縮して後遺症を生じることがある。
病院には耐性菌がうようよしており、手術の種類にかかわらず、手術をすれば、(免疫低下が原因で)一定の確率で感染症にかかることは必然だ。
こういう患者から分離される黄色ブドウ球菌のうち、耐性菌とされるMRSAが占める率は、ほとんどの病院で7?8割にも達する。
もうすぐ自然に陣痛が始まるという時期に、妊婦にプロスタルモンという陣痛促進剤を点滴、服用させることがあるが、それが原因で陣痛が強くなりすぎたり、強直性子宮収縮を起こし、子宮が破裂して妊婦が死亡したり、胎児が重度の仮死状態になり、脳に障害を負うことがある。
被害にあった妊婦のほぼ全員が、そのような事故が起こりうることを知らされていない。
それどころか、「子宮口をやわらかくする薬です」くらいのことしかいわない。
2. 構造上の欠陥ー『医局講座制』・『自由開業医制』・『自由標榜制』・『出来高払い制』・『自家調
剤制』
同書はまた、医者を乱診・乱療に向かわせる、これら諸制度の弊害について述べています。
まず医局講座制について、つぎのような事実を明らかにしています(医局制度はもともと100年も前の明治時代に、当時の東京帝大が医科大学や大学病院にドイツから導入して作ったもので、これが一世紀にもわたって、西洋医学の聖域ともいえるヒエラルキー、つまり権力構造を形成してきました)。
医局講座制が取り仕切る現在の研修医制度のもとでは、医大を卒業して医師免許をもらうと、研修医となって2年間の研修をうけ、ほとんどが大学病院で研修する。
その場合、複数の診療科をまわって研修する制度をもつ医大はほとんどなく、内科なら内科、外科なら外科だけというように、単一診療科のなかだけで研修をおこなう。
したがって、耳鼻科のことしかわからない、精神科のことしかわからないという医者ができてしまう。
研修期間が終わっても、医局講座制は悪影響をおよぼす。
教授が人事権と学位権をにぎっているからだ。
人事権とは、院内において誰を助手として採用するか、誰を講師・助教授に昇進させるかという権限で、事実上、教授の一存できまる。
教授はまた、関連病院への常勤医の派遣の権限もにぎっている。
病院側には医者の選択権はほとんどない。
医学博士の学位を医者に授与するのは教授会だが、教授たちは、自分の部下が審査を受けるときに復讐されるのを恐れてだろう、教授会による審査段階では、ほぼフリーパスで学位授与を認めてしまう。
したがってその前段階である、部下が学位審査を申請することを教授が認めるか、が鍵になり、教授はそれを餌にして、部下に服従をせまるようになる。
いったい、医学博士という肩書きに、どんな効能があるのだろうか。
いろいろな博士号があるなかでも、医学博士は最も簡単にとれる学位で、"足の裏の米粒"などと揶揄されている(取っても食えないけれど、取らないと気持ちが悪い)。
このように人事権と学位権をにぎる教授は、それだけでは満足しない。
いずれ大きな学会を主宰したい、退職後は大病院の院長職につきたいなどの野望がある。
それが達成されるかどうかの鍵は、部下たちのあげた業績にかかっている。
業績とは研究論文のことで、研究成果を載せた医学誌の格が高いほど、論文の数が多いほど業績が評価される。
患者を一生懸命診るより、ネズミや細胞を使った実験をするほうが論文になるわけだ。
当然、医者は病棟に患者を訪ねるより、研究室にこもって実験に没頭しようとする。
こうして大学病院では、構造的に、優れた臨床能力を持った医者が育ちにくいのである。
業績中心で教授を選ぶ傾向は、メスをふるう外科、整形外科、産婦人科などでも同様だ。
日本では、ほとんど手術をした経験のない人間を、業績ゆえに外科系の教授にすることがよくある。
ある大学病院では、乳がんの世界的権威を外科教授として呼び戻し、紹介された患者たちに、胃がんや大腸がんの手術を始めた。
内臓の手術に慣れていなかったため、不用意に血管を切って患者が死ぬなどのトラブルが続き、教授の手術のときは以降、血管外科の医者が待機するようになった。
これではまるで、「何とかに"刃物"」だ。
自由開業医制や自由標榜制によって、医師免許さえあれば自由に開業でき、そのさい、自分がやろうと思う診療科目を勝手に決めることができる。
その科目にどれくらい習熟しているかは問われない。
たとえば、小児の診療にぜんぜん携わったことがない整形外科医でも、小児科を標榜していいのである。
出来高払い制や自家調剤制によって、健康な人にざまざまな検査をして病気を捏造し、山のように薬を処方して病気を作り出す(いわゆるレセプト病)。
そのさい、患者への売値と、仕入れ価格との「薬価差益」を利用して儲けようとする。
いかがでしょうか。
医療の世界では、こんな信じられないようなことが、当たり前のようにおこなわれているのです。
国民の多くはそのような事実があるなど知りようがありませんし、たとえそれを知ったからといって、どのように事態に対処したり改善すればいいのか、これといってなすすべがありません。
医療ミスへの反応が対岸の火事のごとく、切迫した危機感に欠けるのはそのためです。
じじつほとんどの人は、医療過誤は個々の医者、または病院の人為的なミスであって、制度や医療じたいは直接関係ないだろう、という受け止め方をしています。
ましてや医学や医学理論に欠陥があろうとは、夢想だにしないのではないでしょうか。
科学至上主義や、一世紀も続いてきた体制によって、医学にたいする信仰めいた既成概念ができあがってしまったためで、それはそれで仕方のないことかも知れません。
ところがあにはからんや、この世間の常識に相反して、 医学理論そのものが、矛盾と誤謬に満ちたものだったのです。
そしてそれこそが、医療ミスも含めて、現代医学が抱えるすべての問題の核心であると、私は考えています。
といっても信じていただけないでしょうから、ここで、その誤った医学理論を生んだ科学の歴史を概観してみます。
3.唯物科学の終焉
近代科学はガリレオ、ベーコン、デカルト、ニュートンなどによって確立されました。
地動説を支持したガリレオは、観察に加えて実験と数値測定を研究手段として導入し、ベーコンは帰納法を、デカルトは解析幾何学をそれぞれ創始して科学の方法論を定着させ、万有引力の法則を発見したニュートンは、これらの業績を総合して力学の一大体系を築きました。
このニュートン力学の完成を機に、科学は目覚しい発展を遂げることになります。
新しい発明や発見が相次ぎ、それらが産業界で実用化され、人々の生活は劇的に便利になっていき、やがて、蒸気機関や電気の利用による産業革命が起こりました。
こうしてニュートン力学は19世紀に頂点を迎え、科学は文明社会において不動の地位を占めることとなり、「科学は絶対で万能である」という科学至上主義が世界に広まり、それがそのまま人々の人生観になっていったのです。
じつは、当時の科学者はもともと、自然を精神世界と物質世界の両面から探求しようとしていました。
ところが、デカルトの懐疑的思想が科学者に強い影響を与えていたため、科学的手法になじまない精神世界はしだいに置き去りにされ、ついに物質世界だけが研究対象とされ、精神世界、つまり「意識の世界」は、心理学や倫理学の社会科学として扱われるようになった、といういきさつがあります。
デカルトやニュートンは、神や霊魂の存在を信じていたとされていますが、自然科学の探求においてはあくまで思考の合理性を重んじ、ヘーゲルの『弁証法』に由来する『要素分割還元主義』、または『二元論』と呼ばれる哲学的手法を編み出すにいたりました。
それは、まず複雑な現象を要素別に細かく分ける、次に分けたものからわずかでも疑わしいもの、客観的ではないもの、数値に表せないものを除く、そうして残ったものを研究し、再統合するという分析的な手法です。
この手法が科学の急速な発展をもたらしたことから、科学者は、物質世界は精巧な機械の集合体であり、人間を含むすべての生物は自動機械である、との確信を抱いたのです。
こうして自然界のすべての仕組みは理解できるとし、ここに、西洋思想の真髄とされる機械論的世界観が、科学の主流概念となったわけです。
ところが、20世紀の初頭になって、量子力学という、それまでの科学常識を根底から覆す科学理論が登場してきて、「物質の極限は波動であり、波動を固定して観測することはできない」と主張し、「この世界は機械論で解明することは不可能である」、と断定しました(詳しくは別途第七章に)。
ボーア、ハイゼンベルグ、シュレジンガーなどが提唱した量子力学は、アインシュタインによって「非科学的である」と非難され、両者の間でながい論争が続くなど紆余曲折がありましたが、『コペンハーゲン解釈』、『ベルの定理』による理論的実証、さらには1982年のフランスのアラン・アスペや、1986年のイギリスのハンス・クラインポッペンの見事な実験によって、ついにその真実性が認められたのです。
「現実は人間の意識が創造するものである(=この世はバーチャル・リアリティ)」、これが量子力学理論のエッセンスです。
その意味するところをわかりやすくいいますと、私たちは、自然界のすべての事象は、自分が意識しようとしまいと、現実に実在していると思っています。
しかしじつは、それらはすべて人間の意識がつくりだした幻覚であって、人の意識を離れて客観的、局所的に存在するものではない、端的なたとえでいえば、「誰も見ていないときは、そこに月は存在しない」と、量子力学は主張するのです。
いうまでもなく、私たちの常識ではとても受け入れがたい主張ですが、これは、「波束の収縮」、または「波動関数の崩壊」といわれる現象で、自然界に同時的、非局所的に遍在する無数の超微粒子(原子核以下のレベル)の波の束が、「人が見る(観察する)」という行為によって、波から個へと現実化するプロセスとして、多くの精緻きわまる実験で立証済みの事実なのです。
ようするに、人に見られるまでは宇宙全体に充満している波動が、人が見たとたん消滅して、個々の粒子(原子のレベル)にまとまり、物質として実体化する、といえばおわかりでしょうか。
この現象を量子飛躍と呼ぶのですが、その難解さを平易なたとえで説明した、有名な「シュレジンガーの猫」のパラドックスは、観察するという意識と行為がなければ、この世は存在しないと考えざるをえないと論証しています。
人間が研究しようとして観察するという行為そのものが、じつは自然を究明しているのではなく、想念によって客観的な実在をつくりだしているのだと、量子力学はいっているのです。
この量子力学の結論は、相対性理論やビッグバン理論のような単なる仮説と違って、ミクロの物質(光子や電子など)を使ってじっさいにおこなった実験検証から得られたものであり、しかもそれによる予言は、これまで一度でさえ外れたことはありません。
このことをぜひご記憶ください。
これまでの科学は、厳然と実在する自然界を、客観的な対象として研究するというのが基本姿勢であり、科学者の誰一人として、研究者自身が対象の一部でもあり、その研究者の意識が対象に影響を与え、これを変えてしまうなどとは、よもや考えたこともなかったわけです。
当然のことながら、量子力学の登場から70年もたった現在でも、科学者の大多数は、この従来の科学常識を根底から覆す、破天荒な理論に困惑し、苦悩しています。
しかしその一方で、宇宙の構造、重力(万有引力)の正体、素粒子の振る舞い、常温核融合、高温超電導、サイ現象など、従来の科学では今なお説明できない現象が数え切れないほどあり、科学者は、まさに絶望的な幻想のふちに立たされているのも事実です。
このジレンマから抜け出すには、量子力学への科学のパラダイムシフトが不可欠の条件となりますが、伝統科学に固執し、自分自身の立場を存亡の危機にさらしたくない科学者が多いことから、パラダイムシフトにはもうすこし時間がかかるのではないか、というのが専門家の共通した意見です。
しかしながら、アスペなどの実験によって物質の客観性(物質は観測者に対しそれぞれ局所的に存在する)が否定されてしまった以上、比較的近未来に、伝統科学、つまりは『ニュートン力学』や『相対性理論』が葬り去られ、それらに代わって、量子力学が科学の主流となる可能性は高いのではないでしょうか。
それが実現してはじめて、唯物科学の時代が終りをつげ、量子力学や『ブーツストラップ理論』が述べるような、全体的、包括的な科学が到来することになるのでしょう。
ブーツストラップ理論とは、「物質は実在するものではなく、ただ、素粒子間の関係性のみが存在するだけである。
この世界で生じる、あらゆる現象の全体と部分は対等、平等である」、というものです。
アメリカの核物理学者フリッチョフ・カプラは、「この次世代科学は、東洋の神秘主義(仏教思想)に通ずるものである」と述べています。
科学はこれまで、人間は脳、つまりコンピュータのようなもので思考するのだと考えてきましたが、そうではなく、心というプログラマーがべつに存在し、それが脳を操っているのだということ、そして、「この世」の実体は私たちの意識と無関係に形成されているのではなく、人間の精神と自覚そのものが「存在」を作り上げているのだということが、今や、現実に証明されつつあるのです。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
つづく