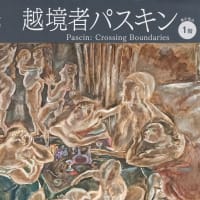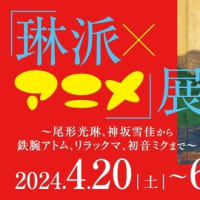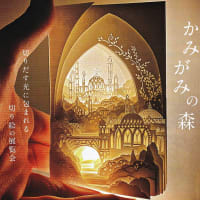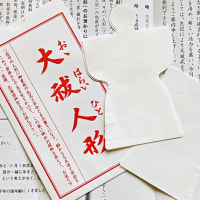世界屈指のエジプト・コレクションを誇るオランダのライデン国立古代博物館所蔵品の展覧会「古代エジプト展」。2022年7月10日(日)から8月21日(日)の予定で北海道立近代美術館で開催中です。ミイラ棺を立てた神秘的な立体展示のほか、人や動物のミイラ、彫像、パピルス、副葬品など厳選された約250点が展示されています。大変な人気です。
本日は「北海道立近代美術館」で開催されている「【特別展】ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」鑑賞です。大阪府・堺市の仁徳天皇陵古墳(大山古墳)で有名な百舌鳥耳原三陵の近くで子供の頃を過ごした何となく考古学ファンの私です。小学生の自由研究では古墳をテーマにしたのですが「考古学じゃ食えんぞ!」と父親に言われて別の職業選択をした軟弱者でもあります。そんなこともあり2020年7月の開催が中止された「古代エジプト展」の本年7月10日(日)より「北海道立近代美術館」での開催が決まり前売りチケットを購入して楽しみにしていました。当初は今週末訪問を予定していた鑑賞ですが美術館のウェブサイトを見ていると「土曜日や日曜日には、より多くの方々にご来場いただいているため、入場整理券をお配りし展示室内への入場制限を行っており、観覧まで相当の時間(場合によっては1時間以上)お待ちいただいております」と出ていました。さすがに軟弱な考古学ファンは1時間も待てないので平日の昼時を狙って出かけてきました。結果は本美術館では今までで一番の混みようでしたが入場制限はなく展示品の前に連なる列に並んで鑑賞してきました。

「北海道立近代美術館」の西側エントランス。

「【特別展】古代エジプト展」のチラシ。
“大河ナイルに育まれ、3000年もの長きにわたった古代エジプト文明。多くの王朝が栄華にきらめき、壮麗豊潤な独自の文化が花開きます。来世で永遠の生を望んだ人々は、墳墓や神殿に、豪華なミイラ棺、象形文字による碑や書、呪術的な装飾品や人形、神々の像などを捧げました。それら独自の造形は、古代エジプトの美と神秘の世界を伝えて、私たちを魅了します。
本展は、世界屈指のエジプト・コレクションを誇るオランダのライデン国立古代博物館の所蔵品から、人や動物のミイラ約250点を厳選して、様々な角度から古代エジプトの新たな魅力を紹介します”。

展示会場入り口付近。割と空いてるようでしたが展示会場に入ると展示品の前には延々と列が出来ていました。皆さん1品1品食い入りように見ているので列が動くのに時間がかかります。古代エジプト時代は何かロマンを感じるのか考古学ファンでなくとも大人気のようです。
展示会は「第Ⅰ章エジプトを探検する」、「第Ⅱ章エジプトを発見する」、「第Ⅲ章エジプトを解読する」、「第Ⅳ章エジプトをスキャンする」の4章構成で様々な角度から神秘の世界を紹介しています。場内は写真撮影禁止なのでウェブサイトより拝借した画像でその魅力の一端を紹介します。
第Ⅰ章 エジプトを探検する
18世紀末のナポレオンによるエジプト遠征以降、古代エジプトへの関心が急速に高まりました。聖なる象形文字ヒエログラフも解き明かされました。そうした初期の探検の様子や遺物、そして現在も続く遺跡調査の出土品などを紹介します。
先ず古代エジプト考古学のはじまりから紹介です。象形文字を解読したジャン=フランソワ・シャンポリオン氏、その友人であったイッポリト・ロゼリーニ氏などの調査団による遺跡のスケッチ。

「ギザの大スフィンクス」 1698年(縦29cm、横39.5cm)。当時の大スフィンクスの首から下は砂に埋もれていたことが判ります。

「ロゼッタ・ストーン」(レプリカ) 。碑文は古代エジプト語の象形文字ヒエログリフと民衆文字デモティック、ギリシア文字の3種類の文字が刻まれておりジャン=フランソワ・シャンポリオン氏らによって解読された。これによって他の古代エジプト語の記録も解読が可能になるなど古代エジプト研究の金字塔です。
シャンポリオン氏による象形文字の解読からちょうど100年目にあたる1922年には英国のハワード・カーター氏が有名なツタンカーメンの墓を発見。王墓はほぼ未盗掘の状態で黄金のマスクを含む5000点もの豪華な副葬品が出土。改めて古代エジプトへの世界の注目が集まるきっかけともなった画期的発見です。

「ツタンカーメン王の倚像」新王国時代(高さ67cm、幅33cm、奥行54cm)。頭部がありませんが背面のヒエログラフからツタンカーメン王のものと判るそうです。その背面に描かれた文字も見られるように展示されています。
オランダ王国の初代国王ウィレム1世によって1818年に設立され200年以上の歴史を誇るライデン国立古代博物館は1960年代より60年以上にわたりエジプトでの発掘調査を行なっていることでも有名。1970年代から調査したメンフィスの墓地遺跡サッカラでもツタンカーメン王の治世で高官を務めていた人びとの墓域を発見するなど多くの成果を挙げています。

「王の書記パウティのピラミディオン」新王国時代(高さ47cm、幅47cm、奥行47cm)。

「ホルミンの供養像」新王国時代(高さ125cm、幅53cm、奥行68cm)。
第Ⅱ章 エジプトを発見する
30もの王朝が栄華・壮大な歴史を刻んだ古代エジプト文明。先王朝も含め10の時代に区分される各時期の代表的な石碑や遺物、さらに数多くの神々を信奉する多神教の世界を紹介。エジプトがどのように「発見」「認識」されたかをたどります。
古代のエジプトは多神教で何百もの神々が存在。冥界の主オシリス神やその妹で妻でもあったイシス神といった人の姿を採る神もいれば、知恵の神トトや王の守護神ホルスのように頭が動物で身体が人間の半神半獣の神や、ナイル川の神ハピのように人頭に植物を載せた神もいます。

「パディコンスの『死者の書』(部分)」第3中間期(縦24.5cm、横61.2cm)。左の黒い身体の着席像がオシリス神でその背後がイシス神。神話によればオシリスは弟のセトに殺された王であったものの、妹であり妻でもあったイシスの助けで復活し、現世の王となるホルスをイシスとの間にもうけ自らは冥界の主となりました。

朱鷺(トキ)の頭を持つ知恵の神「トト神の像」後期王朝時代(高さ4.8cm、幅1.4cm、奥行2cm)。
古代エジプト人は一部の神が動物の姿をとると見なし様々な種類の動物が特定の神へミイラとして奉納されました。たとえば、エジプトマングースのイクニューモンは、邪悪なヘビを退治することから聖獣とされていました。

「イクニューモン」後期王朝時代(高さ26.8cm、幅6.8cm、奥行9.4cm)。

「猫の像」後期王朝時代(高さ40.5cm、幅10cm、奥行22.5cm)。
第Ⅲ章 エジプトを解読する
古代エジプト人は、来世での永遠の生を願いました。墓には、ミイラをともに、豪華な棺、象形文字による『死者の書』、呪術的な宝飾品や護符、人形「シャブティ」、日用品などがおさめられます。それらを通じて独特の死生観・宗教観を読み解きます。

棺の立体展示が目玉の第3章はとりわけ人気のコーナーです。第3中間期から後期王朝時代にかけての貴重な12点の木棺が立てた状態で展示。実際に前に立って見ると自分の背丈と棺の大きさを比べることが出来で判りやすく迫力の展示となっています。
ミイラが入っていた棺は物理的かつ呪術的に死者を保護するために制作され時代の変化に伴って棺の形、装飾、色合いが変化していきます。また、棺が複数の入れ子になるなど、さまざまなタイプが制作されました。

「アメンヘテプの内棺」第3中間期([蓋]:長さ185cm、幅50cm、高さ35cm / [身]:長さ185cm、幅50cm、高さ34cm)。

「金彩のミイラマスク」グレコ・ローマン時代(長さ48.5cm、幅28cm、厚さ14cm)。

「ハレレムのミイラ」後期王朝時代(長さ170cm、幅39cm、高さ25.5cm)。当初は死者にミイラ加工を施していたのはファラオ(王様)や王族のみでしたが、時を経てミイラ加工で肉体を残す習わしは広く庶民にも浸透したそうです。写真の《ハレレム》は主婦と記載がありました。それにしてもミイラが本物だということが売りですが見方を変えれば遺体が入っているということ。来世の安楽を信じた死者の魂を哀れみます。古く欧州各国ではエジプトミイラの解体ショーなどが人気を集めた庶民の娯楽だった時代もあるそうですが今の時代ですから調査を終えれば埋葬し直すとかはないのでしょうか。

「死者の内臓を納めた木箱」後期王朝時代(高さ61.5cm、幅19.5cm、奥行22.5cm)。
古代エジプト人は永遠の生を信じていましたが死後に来世へと赴く旅は危険だと考えられていました。 そのため死者には呪文や護符が与えられ、永遠の生をいったん獲得した後も死者を養うために墓の副葬品や供物が必要とされたそうです。

「ネスナクトの『死者の書』」グレコ・ローマン時代(縦29.8cm、横48.3cm)。「死者の書」には死者が永遠の生を来世で獲得するために必要な呪文が書かれています。

「護符とビーズの首飾り」新王国時代(長さ36cm)。

「ホルウジャのシャブティ」後期王朝時代(高さ27.5cm、幅7.2cm、奥行4.5cm)。《シャブティ》は死者が来世で安息できるよう身代わりに働く人形。大規模なものだと365体の《シャプティ》が副葬されたそうです。

「船の模型」中王国時代(高さ47cm、幅17cm、奥行87cm)。船の模型は来世での移動手段を提供すると考えられていました。
第Ⅳ章 エジプトをスキャンする
最新の科学技術が古代エジプト文明の深奥に迫ります。本展のために、人のミイラ3体と動物のミイラ1体をCTスキャンで調査し、新たに解明された映像を世界初公開!国際的プロジェクトでの発見や研究成果も紹介します。
「ライデン国立古代博物館」では初代館長の指示でミイラの包帯をほどくことを禁止。将来的な技術の発展を見越しての決断により博物館所蔵のミイラ(人と動物)は無傷で保存され後にCTスキャンにょりビジュアル化することができたそうです。

「センサオスのミイラ」グレコ・ローマン時代、ローマン時代、109年(長さ166㎝、幅45㎝、高さ42㎝)。ローマ人のエリート層の家系に生まれ、16歳で亡くなったセンサオスという名の女性のミイラ。大量の包帯と樹脂が用いられたため嵩張った外観をしています。

ミイラのCTスキャンの様子。「センサオスのミイラ」は1990年代にライデン国立古代博物館にて、初めて調査と3Dスキャンが行われ顔の復元も試みられた。

「センサオスの顔の復元模型」1998年(右)と「センサオスの顔の復元過程を示した模型」1998年(左)。

「蛇のミイラ」年代不詳(高さ6cm、幅9.6cm、長さ19.7cm)。

「蛇のミイラ」のCTスキャン像。蛇の種類は体長2mほどのコブラで骨が数か所折れているとともに、右下側に卵があったのでメスだと確認できたそうです。

「魚のミイラ」後期王朝時代もしくはそれ以降(高さ11.5cm、幅27.5cm、厚さ5.1cm)。

「猫のミイラ」後期王朝時代もしくはグレコ・ローマン時代(高さ41cm、幅9cm、奥行9cm)。この後、エジプトの象形文字研究の展示などを見て鑑賞終了。

ロビーのグッズ販売コーナーも人気でした。

サンエックス株式会社の人気キャラクター「リラックマ」の古代エジプトの神様やピラミッド、ミイラなどをモチーフにしたぬいぐるみなど本展オリジナルグッズが販売されています。会場限定で1人3ケまでです。

フォトスポット。ミイラ棺の実部大写真です。

玄関前の安田侃氏・作《無何有》。死者の魂に涙しているようでした。
「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展 」
会場 北海道立近代美術館(札幌市中央区北1条西17丁目)
会期 2022年7月10日(日)〜8月21日(日)
休館日/祝日を除く月曜日
開館時間 9:30〜17:00(入場は16:30まで)
※会期中の金曜日は19:30まで(入場は19:00まで)
主催 北海道立近代美術館、北海道新聞社、北海道文化放送、札幌テレビ放送、ライデン国立古代博物館
後援 外務省、オランダ王国大使館、北海道、札幌市、札幌市教育委員会、北海道PTA連合会、北海道小学校長会、北海道中学校長会、北海道高等学校長協会、北海道私立中学高等学校協会、公益社団法人北海道私立専修学校各種学校連合会
観覧料
一般:1,800(1,600)円、高大生:1,000(800)円、中学生700(500)円
※( )内は以下の割引料金です。
・前売料金 ・10名以上の団体料金 ・リピーター割引料金(当館または他の道立美術館で開催した特別展の観覧半券をご提示の場合。1枚につきお一人様1回限り有効。有効期限は半券に記載。)
・前売料金 ・10名以上の団体料金 ・リピーター割引料金(当館または他の道立美術館で開催した特別展の観覧半券をご提示の場合。1枚につきお一人様1回限り有効。有効期限は半券に記載。)
近美コレクションとの共通券/一般:2,000円、高大生:1,050円
無料になる方
小学生以下(要保護者同伴)、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(ミライロID利用可)及びその介護者(1名)など。
小学生以下(要保護者同伴)、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(ミライロID利用可)及びその介護者(1名)など。