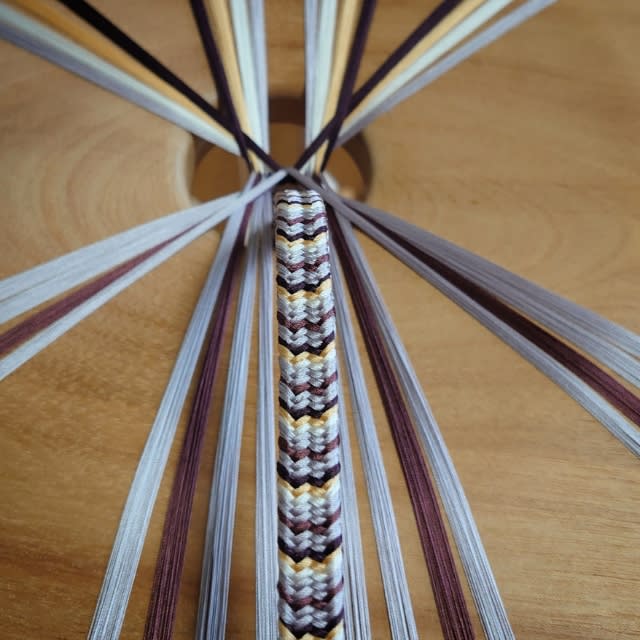自分の家の紋

我が家は「丸に一引き」

形は(勝手に)少し可愛くアレンジ

慶弔、どちらでも着装する
『家紋』をご存知ですか?
今、ちょうどお彼岸
お墓参りに行った際に墓石を見てください
家紋が刻まれています

我が家は「丸に一引き」
とってもシルプルです
着物には
紋の付いたものと
紋の付いていないものがあります
紋が付いた着物は格調を求められる場面に着用します
慶弔どちらの場面でも必須です
先程も書きましたが
我が家の家紋はシルプル
少し男らしい(=可愛くない)
華やかな席で着装する着物には
少しばかりアレンジを加えてます

形は(勝手に)少し可愛くアレンジ
色は訪問着に使用されている色から採用
華やかな一つ紋付き訪問着
とても気に入っています

慶弔、どちらでも着装する
黒の道行コート
家紋入りの反物を織ってもらい仕立てました
全体写真ではわかりにくいのですが、地模様として家紋が文様として織られています
こちらも少しばかり可愛くアレンジしてます
他にも女性の紋には
さまざまに遊ぶ「女紋」があります
『紋で遊ぶ』
着物上級者の遊びではありますが
細部までこだわって遊ぶ
着物はとっても奥深いのですね
沼です・・・