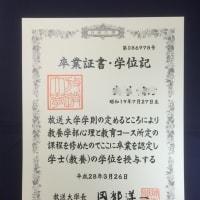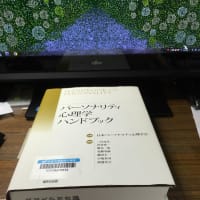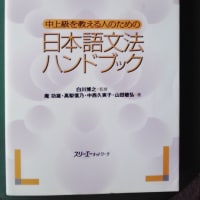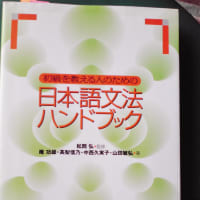~ 散歩路に咲く春の花 ~
’15.4.8(水)
本日、東京は急激に寒くなり街ゆく人々はマフラーやコート姿でした。
そのうえ氷雨のような感じで降リそそぐ冷たい雨糸が足元を濡らし、歩みも縮みがちです。
久しぶりに東京へ着いた私は、昨日までの田舎の暖かさとの寒暖差に戸惑いながら茗荷谷の駅を出ました。
神戸からやってきた女性は今朝飛行機で東京へやってきたそうです。
そして、長野からの学習者は雪で一時間ほど到着が遅れました。
こういう驚きの寒さ漂う日に卒業研究第一回目のゼミが10時半から東京文京学習センターで始まりました。
以下は、第一回目の卒研ゼミに当たり、私が昨日から今朝深夜にかけて準備した発表用資料です。
1.何を研究したいのか
2014年5月29日の朝日新聞朝刊に「心の病」名称変更へという見出しで、例えば
・「アルコール依存症」が「アルコール使用障害」に、
・「性同一性障害」は本人が実感として感じる「性別違和」へ、
・「神経性無食症」は食欲がないわけではなくやせたいという願望があるので「神経性やせ症」に、
また、
子どもの時期に多い病気を中心に「障害」という言葉を使うのを減らし、例えば
・「注意欠如・多動性障害(ADHD)は「注意欠如・多動症」に、
・「言語障害」は「言語症」に
したという報道がなされた。
同様の記事が同日の毎日夕刊や翌日の中日朝刊にも掲載された。
一体“どこ”の“だれ”が“なぜ”このように公共的な病名変更という行為をするのだろうかと深い関心を
持ちつつ記事に接したところ「日本精神神経学会」が新しい指針を作り、28日に公表したとある。
理由は、
国内でも広く使われている米国精神医学会の診断手引き「DSM-5」が昨年5月に改訂されたのに伴い、
様々な訳語が出て混乱しないように関連学会が共同で名称を検討したのだという。
とりまとめた日本精神神経学会副理事長の神庭重信・九州大学大学院教授の、
「患者の理解と納得が得られ、差別意識や不快感を生まない呼び名にするよう心がけた」
というこの発言に何か意味があるような気がしてならず、卒研申請に向けてのタイトルを
「病名(特に“心の病”)の呼称変更の歴史的時代背景と社会的意味について」
とし研究のテーマはこれしかないと決意、申請が受理されたら先ずこの記事の出所を手掛かりに
手探り研究の第一歩を踏み出そうと思いつつ今日に至ったという次第です。
2.どこまで作業が進んでいるのか、及び 収集中の文献リスト
1)新聞記事のDSM-5に準拠し日本精神神経学会主催で検討作成したという新指針の調査
① 精神経誌 第116巻第6号(2014)「DSM-5病名・用語翻訳ガイドライン(初版)」
② 日本精神神経学会・日本記者クラブ勉強会「精神疾患用語改訂の背景」での解説・2014.8.1
(YouTube)
③「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」(2014)用語監修日本精神神経学会 医学書院
④「DSM-Ⅳ-TR 精神疾患の分類と診断の手引」(2002)訳・高橋三郎ら3名 医学書院
⑤「臨床家のためのDSM-5 虎の巻」(2014)編集者・森則夫ら3名 日本評論社
⑥ 朝日新聞記事・2014.4.30「アスペルガー分類消える・発達障害自閉症に一本化」
⑦ 精神科臨床サービス第14巻3号(2014)「なぜアスペルガーが消えたのか」大西ら3名
⑧ 椙山女学園大学教育学部紀要7(2014)「DSM-5:神経発達障害と知的障害、自閉症スペクトラム
障害」宮川充司
⑨ SYNODOS 2013.6.11「自閉症の診断基準の改定とアスペルガーカテゴリーの削除について」
阪大 井出草平
2)「精神分裂病」から「統合失調症」への呼称変更に関する調査
① 日本精神神経学会・前理事長佐藤光源教授「統合失調症について-精神分裂病と何が変わったのか-」
② 精神経誌98(4)(1996)「Schizophrenieの訳語の歴史」岩舘利晴ほか
③ 精神経誌102(7)(2000)「精神分裂病はどこまでわかったか」佐藤光源会長講演
④ 厚労省・社会保障審議会障害者部会(第24回)2005.1.25「資料3:精神保健福祉法の改正に
ついて」(「精神分裂病」の「統合失調症」への呼称変更:平成17年施行)
⑤「疾病、傷害及び死因分類の正しい理解と普及に向けて~ICD-10(2003年版)準拠」2007.3厚生
労働省大臣官房統計情報部長
(法令改正等に基づく名称の変更:精神分裂病→統合失調症、痴呆→認知症)
⑥ 中井久夫著「分裂病と人類」1882、「最終講義」1998、徴候・記憶・外傷」2004
⑦ 年報 社会科学基礎論研究 第3号(2004年度)p132~147「精神障害と“人間”からの解放~精神
分裂病の呼称変更にみる~」周藤真也
⑧ 朝日新聞朝刊全面意見募集広告2001.10.7「誰の“精神”も“分裂”してはいないから」(「精神分裂
病」にかわる新しい名前をいっしょにかんがえてください)全国精神障害者家族会連合会(全家連)と
日本精神神経学会「精神分裂病の呼称委員会」の連名
⑨ 朝日新聞朝刊記事2002.6.30「統合失調症へ呼称の変更議決・日本精神神経学会」
⑩ 精神経誌98(4)(1996)「精神分裂病の概念と用語に関するアンケート調査報告」岩舘敏晴ほか
⑪ 精神経誌104(1)(2002)「DSM-Ⅲ以降の精神分裂病の展望」金吉晴
⑫ 「精神分裂病の概念~歴史と分類~」保崎秀夫(昭和57年2版)金剛出版
⑬ 放送大学研究年報 第27号(2009)p1~23「統合失調小史」石丸昌彦
⑭ 宮崎県立看護大学研究紀要4(1):1~7(2004)「統合失調症についての諸問題」布施裕二
⑮ 「看護の為の精神医学」第2版 中井久夫+山口直彦(2004)医学書院
3)「精神薄弱」から「精神遅滞」「知的障害」への呼称変更に関する調査
① 脳と発達(第147冊)26巻2号(1994)「精神薄弱の用語をめぐって」熊谷公明
② 日本障害者リハビリテーション協会発行・ノーマライゼーション 障害者の福祉15巻通巻173号p34~37
(フォーラム‘95「精神薄弱に替わる用語の問題」小出進(「日本精神薄弱者福祉連盟が出した結論:
症候名としては「精神遅滞」、身体障害等と並ぶ障害区分としては「知的障害」に位置付ける」
(厚生省の「精神薄弱にかわる用語に関する研究会」での検討結果1995.7公表:精神薄弱に替わる用語
を「知的発達障害」またはそれを簡略化して「知的障害」とする・最終結論得られず)
③ 内閣府・障害者対策推進本部決定(1995.12.18)「障害者プランの概要~ノーマライゼーション7か年
計画戦略~」(当面緊急に整備すべき目標:心のバリアを取り除くために・「精神薄弱」用語の見直し:
保護者団体その他関係者の意見を踏まえ見直しを行う)
④ 参議院法制局・平成10年(1998)9月28日法律第110号「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の
福祉を改正する法律」(趣旨:障害者に対する国民の理解を深め、もって障害者の福祉の向上に資するため、
精神薄弱者福祉法等における「精神薄弱という用語を「知的障害」に改める。
施行は平成11年(1999)11月4日)
⑤ 奈良教育大学紀要63巻1号(2014)「知的障害概念の成立過程に関する研究:ヘバー定義の成立
およびその意義と特徴」清水貞夫・玉村公二彦
4)「痴呆」から「認知症」への呼称変更に関する調査
① 厚生労働省「痴呆」に替わる用語に関する検討会(厚労省のHPよりダウンロード)
・第1回(平成16・2004.6.21)・第2回(平成16・2004.9.1)
・第3回(平成16・2004.11.19)・第4回(平成16・2004.12.24)
経緯:日本老年医学会において2004年3月に柴山漠然人が「“痴呆”という言葉が差別的である」と問題
提起したのを受け、厚労省では6月から上記の検討会を始め最後の2004年12月24日付で法令
用語を変更すべきだとの報告書がまとめられた。厚労省は同日付で行政用語を変更し、
「老発第1224001号」により老健局長名で自治体や関係学会などへ「認知症」を使用する旨の協力
依頼の通知を出した。
関連する法律上の条文は、2005年の通常国会で「介護保険法の改正」により行われた。
医学用用語としては、まず日本老年精神医学会は「認知症」を正式な学術用語として定め、
関係40学会にその旨通知した。現在の医学界では「痴呆」はほぼ「認知症」と言い換えられている。
(ウイキペディアより)
② その他、文献については探索中。
以上