ー 世も末、そろそろ捨て時かー
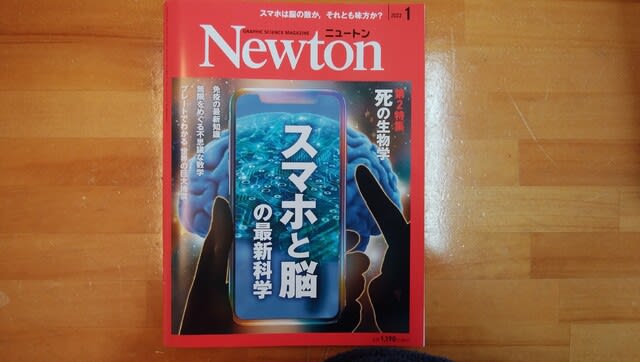
スマホと脳を取り上げた「ニュートン」2023.1
(株)ニュートンプレス
最近は外出するたびにいらだちを感じることが多くなった。最近よく耳にする 違和感 という若干意味不明なことばでは言い尽くせない感情であり、相手は決まって若い男か女である。
たとえば、つい先日、知り合いの家に届け物をした帰り、のどがいがらっぽくなったので、のどアメを買いにコンビニに寄った。「ハイ」と、アメ玉の袋をカウンターに置くと、店員はそれを手に取り、すぐにカウンターに戻して黙っている。
こちらは、「〇〇円です」ということばを待っているのにいつまで経っても値段を言わないから、業を煮やして「いくらだ」と言うと、黙って目の前の機械の画面を指さした。
見ると、金額が出ている。「画面に金額を出せば、店員は口をきかないでいいのか」と内心怒りながら、小銭の投入口らしいところに硬貨を放り込むと早々に店を出た。
この間、「いらっしゃいませ」とも「ありがとうございました」とも言わない。笑顔もない。
これではロボットを置いている方がマシである。店主は多分、「お客がカウンターに置いた品物のバーコードを機械に読み取らせるだけでいい。あとは機械がやるから」とだけ教えているのだろう。
こういう手合いが世に出てくる原因として真っ先に槍玉にあげられるのはしつけや教育である。しかし最近もっと根本的な部分に問題があるのではないかと思わせる記事に出くわした。
上掲、「ニュートン」に掲載された「スマホと脳の最新科学」という記事である。記事は「東北大学の川島隆太教授らのグループは、3年にわたって健康な小児(約200人)の脳を調査しつづけました。・・・(中略)・・・小児期のインターネット使用習慣が、言語知能の発達にともなう脳の容積増加を広範囲に障害する可能性が示されたのです。」という(「ニュートン」2023.1)。
つまり、脳が小さくなっている。古い人間は首の上に1升マスを乗せていたのに、今の若い者は5合マスしか乗せていないと言い換えたら失礼だろうか。
5号マスには5号の米しか入らない。そこへ無理して1升の米を入れようとするから耐えられなくなりパワハラだと騒ぎだす。ふとそんな筋書きが頭をよぎる。
政府は子どもの数ばかり取り上げて騒いでいるが、同時に質も考えなくてはいけない。5号マスばかりが増えたら将来生活保護受給者ばかりになって、かえって国は貧乏になってしまわないか。




