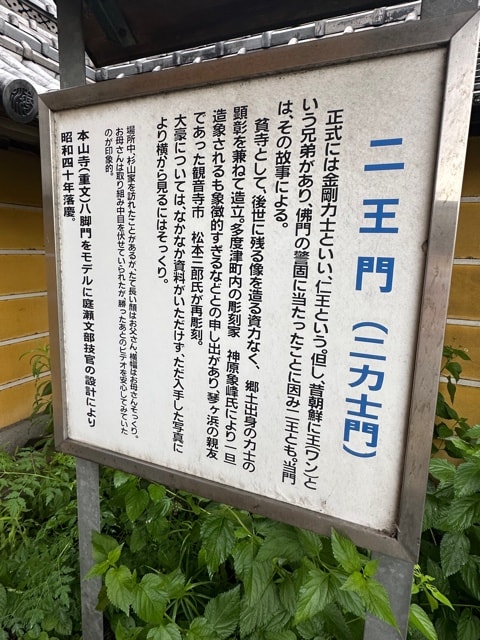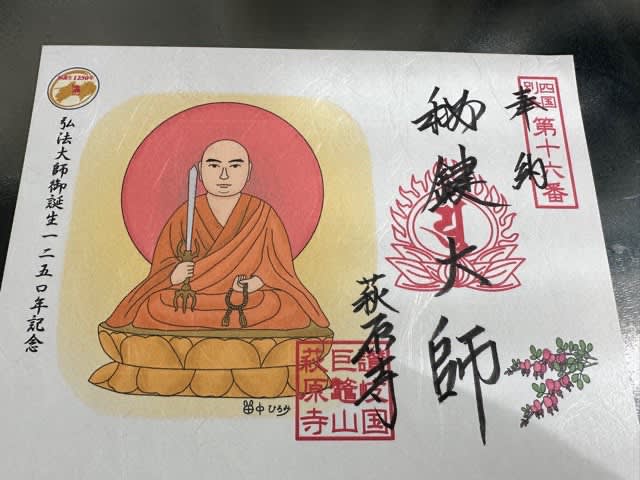淡路島にある伊弉諾尊と伊奘冉尊を祀る神社にお詣りをしようと旅を計画しました。




今回の旅は、先に続く富士山への登拝に先立ち、急に思い立ったものです。
姉と三輪山に登ることを決め、奈良に行くことになったのですが、私一人の運転だと淡路島くらいで一泊していくのが丁度良いと閃きました。
そうこう考えていると、淡路島にはおのころ神社があり、鳴門🌀と富士山🗻で陰陽☯️だから、富士山に登る前に行こう!となりました。
おのころ神社は淡路島の港から船で沼島に行かなくてはいけないのですが、先ずは本島にある、おのころ島神社に参拝しました。
こちらの大きな朱塗りの鳥居は日本三代鳥居の一つだとか。




おのころ島神社を後にして、『古事記』・『日本書紀』に記載がある中では、全国で最も古い神社、淡路国一宮である伊弉諾神宮にお詣りです。

御祭神は
伊弉諾尊(イザナギノミコト)
伊弉冉尊(イザナミノミコト)
菊理媛神(キクリヒメノミコト)
です。
黄泉の国との境界で伊弉諾尊・伊弉冉尊二神は対峙しますが、そのふたりの前に登場するのが菊理媛尊で、二神の仲裁をし、その後、天照大御神や月読尊、須佐之男尊が生れます。

おのころ島神社の正殿前に鶺鴒(せきれい)石があります。
鶺鴒石は、神様が夫婦の道を開かれた場所として縁結びのご利益があるとか。

日本の国生み神話では、太古の昔、伊弉諾尊と伊弉冉尊は、鶺鴒石につがいの鶺鴒が止まって夫婦の契りを交わしている姿を見たといわれています。
その、つがいの鶺鴒を見習って神様として初めて夫婦となり、夫婦の道を開かれて、日本国土や神々を産み出したといわれています。
鶺鴒石に縛られている白い縄と赤い縄を握ってお祈りをすると良縁を結ばれるといわれています。
拝殿にてお詣りさせて頂きました。

おのころ島神社を後にして、『古事記』・『日本書紀』に記載がある中では、全国で最も古い神社、淡路国一宮である伊弉諾神宮にお詣りです。
2回目のお詣りになります。

伊弉諾神宮にある「陽の道しるべ」を紹介します。

陽の道しるべとは、伊弉諾神宮を中心とした太陽の運行図のことです。
伊弉諾神宮を中心として、日本の主要な神社と神秘のラインで結ばれています
東・・・伊勢皇大神宮(内宮)
西・・・海神神社(対馬國一ノ宮)
南・・・論鶴羽神社
北・・・出石神社(但馬國一ノ宮)
夏至・・・日の出の方向に熊野那智大社。日没の方向に高千穂神社
冬至・・・日の出の方向に諏訪大社。日没の方向に出雲大社
太古から祀られている神社の配置が、伊弉諾神宮を中心にして、まるで計算されたように、東西南北には縁ある神社が配置されていることは不思議だと思います。
この四国のラインに、津野山も通ってるような感じがします。。。

ニ柱の神は淤能碁呂島に降り立ち「国生み」のため結婚の儀式を行います。
ところが、最初は天の御柱を左右から回り、出会ったところで女性神の伊奘冉尊から先に求愛の声をかけたため、不具の子である水蛭子(ヒルコ)が生まれ、葦船に乗せて海に流してしまったそうです。
海に流された水蛭子は摂津國(阪神間)に流れ着き、海を領する神「夷三郎殿」として西宮神社の西宮大明神となり祀られることになります。
こちらはヒルコ神の御神木。
御神気を感じます。優しい氣に満ちています。

お祭りがあるのでしょうか、御神輿を見ることができました。

こちらが本殿です。

お祭りがあるのでしょうか、御神輿を見ることができました。

こちらが本殿です。


この日は姉と二人、淡路島で一泊することにしました。