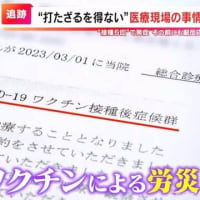オオスズメバチ (大雀蜂、Vespa mandarinia)
ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科スズメバチ属の昆虫の一種。
分布 東アジア、日本(北海道から九州、南限は屋久島、種子島近辺)
亜種 [編集]Vespa mandarinia mandarinia - 基亜種。
Vespa mandarinia japonica - 日本の北海道から九州に分布しており、南限は屋久島、種子島近辺。英名はJapanese giant hornet。
形態 [編集]体長は女王バチが40~50mm、働きバチが27~38mm、雄バチが 27~40mm[1]。頭部はオレンジ色、胸部は黒色、腹部は黄色と黒色の縞模様で、羽は茶色。雄バチは毒針(産卵管)を持たない。
以前は標準和名として『オオスズメバチ』の他に単に『スズメバチ』を用いることも多かった。
木の根元などの土中、樹洞などの閉鎖空間に巣を作る。巣は枯れ木などから集めた繊維を唾液のタンパク質で固め和紙のようにし、これを使用し六角形の管を作っていく。この管が多数集まった巣盤を、数段つらねる。
日本に生息するハチ類の中で最も強力な毒をもち、かつ攻撃性も非常に高い。オオスズメバチ日本亜種の半数致死量(LD50)は4.1mg/kgである[2]。毒針による攻撃のほか、同時に強力な大顎で攻撃対象の皮膚を大きくえぐるといった行動もあるので被攻撃者は大怪我をも伴う。またこの毒液中にはアルコールの一種からなる警報フェロモンが含まれており[3]、巣の危機を仲間に伝える役割を果たしている。狩りをする時は、時速約40kmで飛翔することができ、一日約100kmもの距離を飛翔する[4]。
夏季に幼虫に与えられる餌はコガネムシやカミキリムシといった大型の甲虫類、あるいはスズメガなどの大型のイモムシ等である。これらの大型昆虫が減少し、また大量の雄蜂と新女王蜂を養育しなければならない秋口には攻撃性が非常に高まり、カマキリの様な肉食昆虫も襲撃対象としたり、スズメバチ類としては例外的に集団でミツバチやキイロスズメバチといった巨大なコロニーを形成する社会性の蜂の巣を襲撃することで需要を満たす。これらの巣の働き蜂を全滅あるいは逃走させた後は、殺戮した働き蜂の筋肉に富む胸部も幼虫の餌となるが、こうした大量の死体は処理しきる前に腐敗が始まり餌として適さなくなるため、主に占領した巣の中から時間をかけて大量の生きたさなぎや幼虫を肉団子にしつつ運び出す。
より大型の巣を作り、多数の働き蜂を擁するキイロスズメバチの巣を襲撃した場合、オオスズメバチ側にも大きな被害が出るが、コロニー自体が巨大なため、巣の占領に成功すれば損害に見合う大量の幼虫やさなぎを獲物として収穫できる。しかしチャイロスズメバチの巣を襲撃した場合に、チャイロスズメバチは他のスズメバチ類に比べて強靭な外骨格をもつため、大顎や毒針による攻撃が必ずしも有効に機能せず、逆に撃退されることもある。

アレチウリ の蜜を吸う スズメバチ
樹液を吸うオオスズメバチまた、クヌギなどの樹液に集まり、樹液を採取する。同じく樹液を採取するカブトムシを追い払う事もあるという。
天敵としてはキイロスズメバチやクロスズメバチ類と同じように、オオスズメバチも餌にするハチクマや、本種の腹部に寄生する寄生昆虫のネジレバネの一種があげられる。また、襲撃対象のひとつであるオオカマキリに逆に捕食される事がある。
養蜂における影響 [編集]日本産亜種であるニホンミツバチを含むトウヨウミツバチ(Apis cerana)の巣を襲撃した場合、集団攻撃前に撃退されなければ、巣を占拠できる。集団攻撃前の撃退は、オオスズメバチの働き蜂が単独で偵察している段階、つまりオオスズメバチが集合フェロモンにより同じ巣の働き蜂を集結させる前の段階で、ミツバチが集団で敵であるオオスズメバチを押し包む行動によって蜂球が作られ、その内部はオオスズメバチの致死温度(44~46℃)に近い46℃にもなり、かつ蜂球内の二酸化炭素濃度が約3%ほどになり、オオスズメバチの致死温度を下げることにより、蒸し殺される[5]。
この種に対抗するすべをほとんど持たないセイヨウミツバチ(A. mellifera)の場合は攻防の関係は一方的で、養蜂家による庇護がなければ必ずといっていいほど全滅を余儀なくされる(数十匹ほどのオオスズメバチがいれば4万匹のセイヨウミツバチを2時間ほどで全滅させられる)[6]。このことが、飼育群からの分蜂による野生化が毎年あちこちで発生しているにもかかわらず、セイヨウミツバチが日本で勢力拡大するのを防ぐ要因になっている。実際、オオスズメバチの生息しない小笠原諸島ではセイヨウミツバチの野生化群が増加し、在来のハナバチ類を圧迫して減少させていることが確認されており、これらのハナバチ類と共進化して受粉を依存している固有植物への悪影響が懸念されている。
食用 [編集]詳細は「はちのこ」を参照
熊本県球磨地方[7]や宮崎県の高千穂のように、地方によっては幼虫やさなぎ、成虫を珍味として食す習慣がある。また、成虫をはちみつや焼酎につけ込んだものも見られる。成虫の場合、毒針を取り除く。
また、本種そのものを食すわけではないが、本種の幼虫が成虫に与える餌の成分を参考にして作られた栄養ドリンクやサプリメントが、日本をはじめとするアジアやヨーロッパで販売されている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%83%A1%E3%83%90%E3%83%81