古墳時代の最後は七世紀中葉であるが
突如として中央政権に八角墓が現われる。
京都市山科区の天智天皇陵と考えられる御廟野古墳
高市郡明日香村越の牽牛子塚古墳
高市郡明日香村平田の中尾山古墳
高市郡高取町佐田の束明神古墳
高市郡明日香村野口の野口王墓古墳などが知られている。
さてこの八角が何を意味しているのかだが
正確なところは判っていない。
明日香の八角墓は特別なもので天皇陵ではないかと言われているが
周辺諸国では六世紀末から七世紀初頭にかけて
いくつかの八角墓の例がある。
関東以外の例として鳥取市国府町岡益に梶山古墳がある。
被葬者については不明であるが、
八角墓であることから675年(天武4年)に因幡に配流された皇族の
麻積王であるとの説が有力となっている。
この八角墓は装飾など道教思想が濃厚であるが
この八角の持つ意味も道教的な要素を持つのではないかと考えられている。
八方位が世界を表わすのだと考えられている。
前回『酒列磯前神社の調査 No277』で
徳川光國が帝を廃帝にして自分が権力を握った則天武后に習い
則天武后の造字である圀の八方の世界観から
天下を狙って光國を光圀に替えたと記載したが
光圀の改名も現世での野望と言うより八角墓の意味を持つのかもしれない。
さて藤原家全盛の八世紀になると
八角堂がいくつも建てられている。
721年には元明天皇と元正太上天皇が不比等の冥福を祈るために
興福寺の北円堂を建てているし
739年には行信僧都が聖徳太子の威徳を偲んで
法隆寺東院の夢殿を建てている。
藤原仲麻呂は藤原南家の菩提寺の栄山寺に父母の冥福のために
現在国宝の八角円堂を建てている。
このことから八角墓に関しても
藤原氏の影響があったのではないかと推察する意見もある。
中国で最も古い木造建築塔の応県木塔は八角形となっている。
山西省朔州市応県北西の仏宮寺境内にあるが1056年に建てられている。
石の八角塔では1044年の遼寧省瀋陽市の無垢浄光仏舎利塔がある。
すくなくともこの時代の八角は仏教由来である。
八大聖地、八大菩薩、八功徳、八解脱、八宗の祖師などの仏教用語がある。
今でも香港や上海では八は縁起が良い数字とされているが
それは"発財"(金持ちになる)の"発"と"八"の発音が一緒だからだそうだ。
故宮博物館の翡翠で出来た「白菜とキリギリス」なども同じ意味を持つ。
皇位継承儀式で使われる高御座という玉座も屋根は八角形となっている。
これも八角墓の八角と同じ由来だと考えている。
まあ四方八方の方位から八角としたという考え方は非常に妥当であり
八世紀に道教思想が盛んになったからだというのは頷ける。
 『八角屋根の高御座』
『八角屋根の高御座』  『八藤と四方雲文の茵(しとね)』
『八藤と四方雲文の茵(しとね)』
ただ先ほど中国の八角形が仏教由来であるということを記したが
中国の道教的要素には八角ではなく『天円地方』という考え方がある。
天は円くて地は方形であるという世界観(宇宙観)である。
天を祭る天壇は円形で地を祭る地壇は方形である。
日本では前方後円墳がその例に倣っている。
『方格規矩四神鏡 』の
『天円地方』のあしらい方等を観るとなるほどと頷ける。
道教思想を貫くなら円は八角を破るので
わざわざ八角を持ち込む必要性は薄いような気もする。
 『大仙陵古墳』
『大仙陵古墳』  『方格規矩四神鏡 』
『方格規矩四神鏡 』
吉田一氣的には八角墓の由来について
あえて根拠の無い異説を唱えたい。
伝説の人物である役の行者(役 小角)は
舒明天皇6年(634年)- 大宝元年(701年)という伝承となっている。
彼は『八大龍王神の根源 追記 No171』で延べた通り
箕面山で八宗の祖師の龍樹菩薩の観応があり八大龍王神を感得している。
彼は天皇が奉斎する御巫八神と八大龍王神を
秩父で合祀して「八大宮」として祭祀している。
これは神道と仏教を初めて習合した超強力な国家安寧の祭祀といえる。
埼玉県秩父市中町にある「今宮神社」のことだが
明治までは神仏習合祭祀で「八大宮」と呼ばれてきた。
つまりこの八大宮にあやかり八角墓を造った可能性を
筆者は感じているのだ。
応援してくださる方はこちらをクリックお願いします。


突如として中央政権に八角墓が現われる。
京都市山科区の天智天皇陵と考えられる御廟野古墳
高市郡明日香村越の牽牛子塚古墳
高市郡明日香村平田の中尾山古墳
高市郡高取町佐田の束明神古墳
高市郡明日香村野口の野口王墓古墳などが知られている。
さてこの八角が何を意味しているのかだが
正確なところは判っていない。
明日香の八角墓は特別なもので天皇陵ではないかと言われているが
周辺諸国では六世紀末から七世紀初頭にかけて
いくつかの八角墓の例がある。
関東以外の例として鳥取市国府町岡益に梶山古墳がある。
被葬者については不明であるが、
八角墓であることから675年(天武4年)に因幡に配流された皇族の
麻積王であるとの説が有力となっている。
この八角墓は装飾など道教思想が濃厚であるが
この八角の持つ意味も道教的な要素を持つのではないかと考えられている。
八方位が世界を表わすのだと考えられている。
前回『酒列磯前神社の調査 No277』で
徳川光國が帝を廃帝にして自分が権力を握った則天武后に習い
則天武后の造字である圀の八方の世界観から
天下を狙って光國を光圀に替えたと記載したが
光圀の改名も現世での野望と言うより八角墓の意味を持つのかもしれない。
さて藤原家全盛の八世紀になると
八角堂がいくつも建てられている。
721年には元明天皇と元正太上天皇が不比等の冥福を祈るために
興福寺の北円堂を建てているし
739年には行信僧都が聖徳太子の威徳を偲んで
法隆寺東院の夢殿を建てている。
藤原仲麻呂は藤原南家の菩提寺の栄山寺に父母の冥福のために
現在国宝の八角円堂を建てている。
このことから八角墓に関しても
藤原氏の影響があったのではないかと推察する意見もある。
中国で最も古い木造建築塔の応県木塔は八角形となっている。
山西省朔州市応県北西の仏宮寺境内にあるが1056年に建てられている。
石の八角塔では1044年の遼寧省瀋陽市の無垢浄光仏舎利塔がある。
すくなくともこの時代の八角は仏教由来である。
八大聖地、八大菩薩、八功徳、八解脱、八宗の祖師などの仏教用語がある。
今でも香港や上海では八は縁起が良い数字とされているが
それは"発財"(金持ちになる)の"発"と"八"の発音が一緒だからだそうだ。
故宮博物館の翡翠で出来た「白菜とキリギリス」なども同じ意味を持つ。
皇位継承儀式で使われる高御座という玉座も屋根は八角形となっている。
これも八角墓の八角と同じ由来だと考えている。
まあ四方八方の方位から八角としたという考え方は非常に妥当であり
八世紀に道教思想が盛んになったからだというのは頷ける。
 『八角屋根の高御座』
『八角屋根の高御座』  『八藤と四方雲文の茵(しとね)』
『八藤と四方雲文の茵(しとね)』ただ先ほど中国の八角形が仏教由来であるということを記したが
中国の道教的要素には八角ではなく『天円地方』という考え方がある。
天は円くて地は方形であるという世界観(宇宙観)である。
天を祭る天壇は円形で地を祭る地壇は方形である。
日本では前方後円墳がその例に倣っている。
『方格規矩四神鏡 』の
『天円地方』のあしらい方等を観るとなるほどと頷ける。
道教思想を貫くなら円は八角を破るので
わざわざ八角を持ち込む必要性は薄いような気もする。
 『大仙陵古墳』
『大仙陵古墳』  『方格規矩四神鏡 』
『方格規矩四神鏡 』吉田一氣的には八角墓の由来について
あえて根拠の無い異説を唱えたい。
伝説の人物である役の行者(役 小角)は
舒明天皇6年(634年)- 大宝元年(701年)という伝承となっている。
彼は『八大龍王神の根源 追記 No171』で延べた通り
箕面山で八宗の祖師の龍樹菩薩の観応があり八大龍王神を感得している。
彼は天皇が奉斎する御巫八神と八大龍王神を
秩父で合祀して「八大宮」として祭祀している。
これは神道と仏教を初めて習合した超強力な国家安寧の祭祀といえる。
埼玉県秩父市中町にある「今宮神社」のことだが
明治までは神仏習合祭祀で「八大宮」と呼ばれてきた。
つまりこの八大宮にあやかり八角墓を造った可能性を
筆者は感じているのだ。
応援してくださる方はこちらをクリックお願いします。











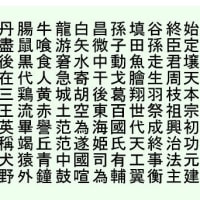

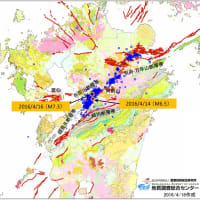

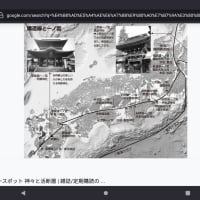
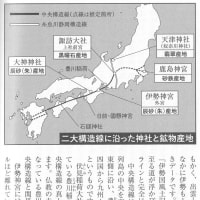

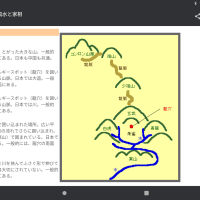






ネット情報では、田坐神社のご祭神は依羅宿祢、呉服漢織、豊宇気毘売神ということで養蚕・製糸発祥の地とも言われるとか。
依羅宿祢といえば田坐神社と阿麻美許曾神社の関連を指摘されている方もいて興味深いです。
ちょっと気になる!~大阪発史跡旅~様
https://kininarugou.blogspot.com/2019/01/blog-post_31.html
一時期、同じ松原市の柴籬神社に遷座されましたが、その後元の地に還されたとのこと。
柴籬神社は反正天皇の都である「丹比柴籬宮」の跡といわれ、反正天皇が美しい歯を持っていたことに因み歯の神が祀られ、毎年8月8日の夜8時8分に祭礼が行われているようです。
しかし養蚕で田(米)・・・。きっても切り離せないということでしょうか。
また田に坐す≒田中との説もあり、松江市の佐太神社にある田中社が気になりました。
御本社北殿の摂社で、西社は木花開耶姫命を祀り縁結、安産。東社は磐長姫命を祀り縁切、長寿の信仰があり、背中合わせのお社。しかし、両社併せると疱瘡神の神格が出てくるとの事。
日常生活の中で富士山と象が結びつく事柄がありまして・・・佐田大神(猿田彦神)の調査をすすめるよう急かされている気がしています。
記事と関係ないコメントになってしまいましたが、後から結びついてくる気がしています。
この記事は、私の先祖や私に関連することが多々含まれている記事になるのですが、、、
先ほど、流れで自分の父方先祖の事を調べて公開しましたが、、傍系になりますので、私は庶民です。
こちらのブログでお世話になり、コメントを書くことにより、私の言質など色々批判や否定もされましたので、
あえて、公開すべき指示だと思いました。
依羅宿祢も先ほど調べて出てきました
丹比神社は夢で参拝しています。金剛山に登った次の日の夢です。そこで、イヌを連れた人空海?聖徳太子?を見ます。その夢で、はいせ様が出てきました。
そうですか、、富士山と象なのですね。
また、気にかけておきます。
本日は、321でしたので、、、
本当は、空海の独鈷山を調べて、
https://www.kyoto-kankou.or.jp/culture/?act=detail&id=301&r=06a20d12795fc136731fe9ed0b6746b8
亀岡の行者山(役行者)と独鈷抛(とこなげ)山に行く予定でしたが、、上手く時間が取れず、、あしたに持ち越しです。
出来れば、亀岡の桜石(菫青石仮像)
https://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/geo/db/soi0078.html
姫島の石(乳白色の黒曜石)のお返しで、亀岡の(菫色・すみれ桜)の石を探してきます。
レッドデータやから、無理っぽいですけどね。