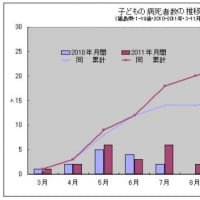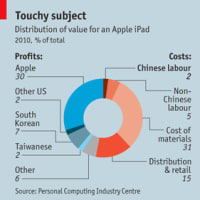今年最初の更新です。
あけましておめでとうございますというには、遅すぎですね。
仕事の担当が変わったりして忙しくなったもので。ちょっと落ち着きました。
さて、大臣日誌です。
一言、スゴイ。
竹中さんは『日本の政策決定プロセスを変えた人』と後世では評価されるのではないですかね。日本の政治システムは責任主体がはっきりせず、エニグマだと評したのはウォルフレンですが、彼は小泉政権で経済財政諮問会議を軸にした経済政策決定過程をどう評価するんでしょうね。
ただ、竹中さんが総務大臣に横滑りして諮問会議の所管を外れてからは、従来の官僚主導に戻ったそうなので、結局誰がハンドリングするかによって変わってくるということですね。仕組みだけの問題ではないのです。
で、この本、アウトサイダーが旧い組織に飛び込んで改革をするときのケーススタディーとして読めますな。日産のゴーンさんのような。魑魅魍魎の世界を小泉内閣最初から最後まで生き延びて、まだ、ああだこうだと新鮮な提言を発しておられます。普通の改革本の大リーグ版というところですかね。学者なのに政治家や官僚の生態をよく洞察し先手、先手を打ってゆく。総理を出すタイミングを見ながら根回しを行う、政治日程から逆算したプロジェクト管理。この辺、スーパー管理職、スーパーサラリーマン、て感じです。
もし大学をご卒業なら、恩師と比べられるとよろしいでしょう。どんなに学殖が豊でもこうは行きやせんぜ。
すこし驚いたのは、この本で政策上の議論になったことがいくつも紹介されていますが、どうにもシンプルで、ええっ、というような基本的なことにが大問題にされていること。成長率より金利の方が高い、ということを前提に成長率を低く見積もって増税論を展開しようとする財務省官僚サイドと、そんな前提は事実に反すると増税論に慎重な竹中さん。政策の専門家の間で、こんなことさえ議論が尽くされていない中でテキトーな前提を置いて、増税だ、減税だ、とやられているわけですな。役所が縦割りで、自分の立場に都合の良い理屈だけを取って来てテキトーな議論をでっちあげるのだ、とまでは竹中さんはおっしゃっておられませんが、そう読めます。議論の公正さを確保するためにも、特定の行政的立場でないトータルな国民の利益,という観点で政策は議論していただきたいものです。
竹中さんの悲痛な叫び。批判するのは簡単ですが『政策ってそんなに簡単なもんじゃないんですよ』。
竹中さんのこの関西ノリも政治家竹中を助けたんでしょうね。
竹中さんの政治センスを示す文章。
郵政民営化論議で『民主党が民営化に賛成するばかりでなく,我々が作った法案よりもっとラディカルな民営化プランを示したら政府はいわば挟み撃ちにあう。私が一番懸念していたのはこうしたシナリオだった』。
民主党は民営化に対してうまいポジション取りができず、結局衆院戦では大敗。民主党はプロ政治家なのに、竹中さんに政治センスで負けてたんでしょうかね。
民主党に当初同情的だった竹中さんもその後の根も葉もないスキャンダル攻勢に『絶望した』と書かれています。
一方的に竹中さんを賛美するつもりはありません。それなりにエグい面も無いとここまで生き残れなかったでしょう。随所に小泉さんを持上げるところも、『私はNo2男です』といっているようで竹中さんを小さく見せますな。No1の大変さを良く踏まえたうえで、とはいえ実質的な実務は担うぞと、なんかこすっからい感じもしますな。まあ鋭い政治感覚をお持ちの竹中さんですから、今後のことを考えた上でのご発言かも知れませんがね。小さくかわいく見せた方がお声がかりが良いですからな。学者も政策論という芸で生きてるわけで、買ってくれるだんなに売れてなんぼです。
調子に乗って竹中さんに無礼なことを書いてしまいました。
今は学者仲間からの嫉妬が強すぎて正当な評価を得られないのかも知れません。自分の研究を実政策に生かしてみたいというのは、政策学者の(普通は)果たせぬ夢でしょう。私の想像ですがね。もう、何年かしたらきちんとした評価・研究が一般読者向けにも出てくるんじゃないでしょうか。
まあ、私はもともとノンポリで支持政党無しなのですが、(経済政策本にしては、また内幕ものにしては)あまりに面白かったので、ここでご紹介させていただきました。
あけましておめでとうございますというには、遅すぎですね。
仕事の担当が変わったりして忙しくなったもので。ちょっと落ち着きました。
さて、大臣日誌です。
一言、スゴイ。
竹中さんは『日本の政策決定プロセスを変えた人』と後世では評価されるのではないですかね。日本の政治システムは責任主体がはっきりせず、エニグマだと評したのはウォルフレンですが、彼は小泉政権で経済財政諮問会議を軸にした経済政策決定過程をどう評価するんでしょうね。
ただ、竹中さんが総務大臣に横滑りして諮問会議の所管を外れてからは、従来の官僚主導に戻ったそうなので、結局誰がハンドリングするかによって変わってくるということですね。仕組みだけの問題ではないのです。
で、この本、アウトサイダーが旧い組織に飛び込んで改革をするときのケーススタディーとして読めますな。日産のゴーンさんのような。魑魅魍魎の世界を小泉内閣最初から最後まで生き延びて、まだ、ああだこうだと新鮮な提言を発しておられます。普通の改革本の大リーグ版というところですかね。学者なのに政治家や官僚の生態をよく洞察し先手、先手を打ってゆく。総理を出すタイミングを見ながら根回しを行う、政治日程から逆算したプロジェクト管理。この辺、スーパー管理職、スーパーサラリーマン、て感じです。
もし大学をご卒業なら、恩師と比べられるとよろしいでしょう。どんなに学殖が豊でもこうは行きやせんぜ。
すこし驚いたのは、この本で政策上の議論になったことがいくつも紹介されていますが、どうにもシンプルで、ええっ、というような基本的なことにが大問題にされていること。成長率より金利の方が高い、ということを前提に成長率を低く見積もって増税論を展開しようとする財務省官僚サイドと、そんな前提は事実に反すると増税論に慎重な竹中さん。政策の専門家の間で、こんなことさえ議論が尽くされていない中でテキトーな前提を置いて、増税だ、減税だ、とやられているわけですな。役所が縦割りで、自分の立場に都合の良い理屈だけを取って来てテキトーな議論をでっちあげるのだ、とまでは竹中さんはおっしゃっておられませんが、そう読めます。議論の公正さを確保するためにも、特定の行政的立場でないトータルな国民の利益,という観点で政策は議論していただきたいものです。
竹中さんの悲痛な叫び。批判するのは簡単ですが『政策ってそんなに簡単なもんじゃないんですよ』。
竹中さんのこの関西ノリも政治家竹中を助けたんでしょうね。
竹中さんの政治センスを示す文章。
郵政民営化論議で『民主党が民営化に賛成するばかりでなく,我々が作った法案よりもっとラディカルな民営化プランを示したら政府はいわば挟み撃ちにあう。私が一番懸念していたのはこうしたシナリオだった』。
民主党は民営化に対してうまいポジション取りができず、結局衆院戦では大敗。民主党はプロ政治家なのに、竹中さんに政治センスで負けてたんでしょうかね。
民主党に当初同情的だった竹中さんもその後の根も葉もないスキャンダル攻勢に『絶望した』と書かれています。
一方的に竹中さんを賛美するつもりはありません。それなりにエグい面も無いとここまで生き残れなかったでしょう。随所に小泉さんを持上げるところも、『私はNo2男です』といっているようで竹中さんを小さく見せますな。No1の大変さを良く踏まえたうえで、とはいえ実質的な実務は担うぞと、なんかこすっからい感じもしますな。まあ鋭い政治感覚をお持ちの竹中さんですから、今後のことを考えた上でのご発言かも知れませんがね。小さくかわいく見せた方がお声がかりが良いですからな。学者も政策論という芸で生きてるわけで、買ってくれるだんなに売れてなんぼです。
調子に乗って竹中さんに無礼なことを書いてしまいました。
今は学者仲間からの嫉妬が強すぎて正当な評価を得られないのかも知れません。自分の研究を実政策に生かしてみたいというのは、政策学者の(普通は)果たせぬ夢でしょう。私の想像ですがね。もう、何年かしたらきちんとした評価・研究が一般読者向けにも出てくるんじゃないでしょうか。
まあ、私はもともとノンポリで支持政党無しなのですが、(経済政策本にしては、また内幕ものにしては)あまりに面白かったので、ここでご紹介させていただきました。