伊藤ハムが12月5日、記者会見を開いたので行ってきた。調査対策委員会が発足してから1カ月がたち、5回の委員会で議論してきたことの中間報告である。主に、基準超過の原因を科学的に解明するための調査研究の内容について、説明が行われた。
既に、資料がウェブサイトで公表されているのでご覧いただきたい。
委員会の見方は、「基準超過は、井戸水そのものに問題があったわけではない。塩素添加の不足、つまり不十分な塩素処理に起因するシアンの生成が起こり、基準を超えた」というものだ。
中間報告で提示された主な事実は次の通り。
・水中のアンモニア性窒素は、塩素の添加によって塩素と結合し、さらに水中や濾過材中の有機物と反応して塩化シアンを生成する場合がある。
・伊藤ハム東京工場の井戸水は、アンモニア性窒素が多い
・再現実験で、塩素添加が不十分だとシアン生成量が増えることが確かめられた
・水質基準項目にこの4月から塩素酸濃度(0.6mg/L以下)が追加され、7月の自主検査で0.62mg/Lという数字が出て再検査したところ下がるなどしていたため、添加する塩素量を抑えめにしていた
・11月始めに濾過材を交換したところ、シアンはほぼ検出限界以下となった
これらのことから、委員会は「塩素添加が不足したことから、塩化シアン濃度が上がり基準を超過してしまった」と推測した。
だが、これだけでは原水が基準を大幅超過した(0.037mg/L)ことと話のつじつまが合わない。原水は、塩素処理前の水だからだ。
委員会は塩素注入地点と原水サンプリング地点が極めて近いうえ、塩素が逆流する可能性もある構造であることを説明。採取された原水に塩素が混入していた可能性を指摘した。
なんだかつじつま合わせの理屈のようにも見える。大幅に基準超過した試料はもう残されておらず、検証のしようがない。
しかし、この推論に二つの傍証が加わる。委員によれば、0.037mg/Lという値の大部分は、シアン化物イオンではなく塩化シアンとして検出されている。自然水に塩化シアンが含まれることはほぼなく、塩素の混入が強く疑われる。
さらに、地下水では急激な水質変化はまず生じないと考えられ、基準超過がこの1回きりで、ほかの検査では見られないことも、この検査でなんらかのアクシデントが起きたことを疑わせる。
こうしたことから、委員会は「原水自体には問題がなかった」と考えた。
私も、大筋で妥当な推論だと思う。一つだけ引っかかるのは、再現実験などで塩素処理が不十分な場合に検出したシアン濃度と、実際の基準超過濃度の間に、いくぶん乖離がある点だ。再現実験では、シアン濃度は0.002~0.003mg/L程度。実際には、この10倍程度の濃度が検出された。報告書は、ほかの悪条件も重なってシアンの量が増えたことを示唆しているが、はっきりとは書いていない。
気になって、調査対策委員会委員で再現実験を行った北里大医療衛生学部講師の伊与亨さんに尋ねてみたところ、微妙な返事だった。この、微妙という言葉を、私は良い意味で使っている。科学者として、この程度の濃度上昇は起こりうるという感触は持っているけれども、まだ公の場で明言はできない、という感じ。これから、再現実験を詳細に詰めて、学会発表や論文という形で出してほしい。
今回の事故の場合、原因を確定させることは難しい。だが、伊藤ハムは、仮説をたて再現実験などを行い検証した。この姿勢は、立派だ。記者会見でも、伊予さんらが、実に丁寧に科学的なメカニズムを説明。あくまでも仮説の検証に過ぎないことを伝え、推論をしっかりと述べ、科学的に不明であること、推測できないことは「分からない」とはっきりと示した。
委員会、伊藤ハム共に、見事な姿勢を見せてくれたと私は受け止めている。地下水を使用しているほかの企業などに極めて有益な事例研究となりつつある。委員会は今回、塩素処理に用いる次亜塩素酸ナトリウムの管理や使い方など、いくつかの提言をしている。ぜひ、ほかの企業も参考にしてもらいたい。最終報告書は、後日公表されるそうだ。
さらに二つ、私は伊藤ハムの今回の事故を契機に考えたいことがある。一つは、検査をなんのためにやるのか、ということ。もう一つは、自主回収は必要だったのか、である。
これについては、明日か明後日、また書きます。
既に、資料がウェブサイトで公表されているのでご覧いただきたい。
委員会の見方は、「基準超過は、井戸水そのものに問題があったわけではない。塩素添加の不足、つまり不十分な塩素処理に起因するシアンの生成が起こり、基準を超えた」というものだ。
中間報告で提示された主な事実は次の通り。
・水中のアンモニア性窒素は、塩素の添加によって塩素と結合し、さらに水中や濾過材中の有機物と反応して塩化シアンを生成する場合がある。
・伊藤ハム東京工場の井戸水は、アンモニア性窒素が多い
・再現実験で、塩素添加が不十分だとシアン生成量が増えることが確かめられた
・水質基準項目にこの4月から塩素酸濃度(0.6mg/L以下)が追加され、7月の自主検査で0.62mg/Lという数字が出て再検査したところ下がるなどしていたため、添加する塩素量を抑えめにしていた
・11月始めに濾過材を交換したところ、シアンはほぼ検出限界以下となった
これらのことから、委員会は「塩素添加が不足したことから、塩化シアン濃度が上がり基準を超過してしまった」と推測した。
だが、これだけでは原水が基準を大幅超過した(0.037mg/L)ことと話のつじつまが合わない。原水は、塩素処理前の水だからだ。
委員会は塩素注入地点と原水サンプリング地点が極めて近いうえ、塩素が逆流する可能性もある構造であることを説明。採取された原水に塩素が混入していた可能性を指摘した。
なんだかつじつま合わせの理屈のようにも見える。大幅に基準超過した試料はもう残されておらず、検証のしようがない。
しかし、この推論に二つの傍証が加わる。委員によれば、0.037mg/Lという値の大部分は、シアン化物イオンではなく塩化シアンとして検出されている。自然水に塩化シアンが含まれることはほぼなく、塩素の混入が強く疑われる。
さらに、地下水では急激な水質変化はまず生じないと考えられ、基準超過がこの1回きりで、ほかの検査では見られないことも、この検査でなんらかのアクシデントが起きたことを疑わせる。
こうしたことから、委員会は「原水自体には問題がなかった」と考えた。
私も、大筋で妥当な推論だと思う。一つだけ引っかかるのは、再現実験などで塩素処理が不十分な場合に検出したシアン濃度と、実際の基準超過濃度の間に、いくぶん乖離がある点だ。再現実験では、シアン濃度は0.002~0.003mg/L程度。実際には、この10倍程度の濃度が検出された。報告書は、ほかの悪条件も重なってシアンの量が増えたことを示唆しているが、はっきりとは書いていない。
気になって、調査対策委員会委員で再現実験を行った北里大医療衛生学部講師の伊与亨さんに尋ねてみたところ、微妙な返事だった。この、微妙という言葉を、私は良い意味で使っている。科学者として、この程度の濃度上昇は起こりうるという感触は持っているけれども、まだ公の場で明言はできない、という感じ。これから、再現実験を詳細に詰めて、学会発表や論文という形で出してほしい。
今回の事故の場合、原因を確定させることは難しい。だが、伊藤ハムは、仮説をたて再現実験などを行い検証した。この姿勢は、立派だ。記者会見でも、伊予さんらが、実に丁寧に科学的なメカニズムを説明。あくまでも仮説の検証に過ぎないことを伝え、推論をしっかりと述べ、科学的に不明であること、推測できないことは「分からない」とはっきりと示した。
委員会、伊藤ハム共に、見事な姿勢を見せてくれたと私は受け止めている。地下水を使用しているほかの企業などに極めて有益な事例研究となりつつある。委員会は今回、塩素処理に用いる次亜塩素酸ナトリウムの管理や使い方など、いくつかの提言をしている。ぜひ、ほかの企業も参考にしてもらいたい。最終報告書は、後日公表されるそうだ。
さらに二つ、私は伊藤ハムの今回の事故を契機に考えたいことがある。一つは、検査をなんのためにやるのか、ということ。もう一つは、自主回収は必要だったのか、である。
これについては、明日か明後日、また書きます。










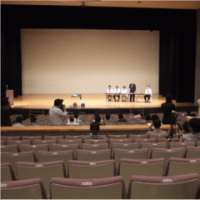





suidou-kawasan.web.infoseek.co.jp/topix/topix.htm(中段)
(日水協衛生常設調査委・シアンの検査方法を検討(11/27日本水道新聞)から引用)
『厚生労働省の○○・水道課水道水質管理官が最近の水道行政の動向について解説した。 「シアン化物イオンおよび塩化シアン」の検査では、塩化シアンの安定化のため試料採取時に酒石酸緩衝液を添加するが、これにより多くの塩化シアンが検出されることになる。そこで水質試験方法等調査専門委員会無機物部会では、これに代わる緩衝液を検討している。』(引用おわり)
伊藤ハム調査対策委員会の報告はなんだったのか。公定法の不都合を伏せるためのつじつま合わせの報告だったのだ。
科学的に報告されているんですね。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_eiken/sosiki/living/chousakenkyu/18chousakenkyu.html
にもかかわらず厚労省検査法は変わらないままであった。
そこで、伊藤ハム事件が起きた。
調査対策委員会は、そのことには触れない報告書を出した。(12/5)
しかし厚生労働省側では、内輪の会議では「検査上で酒石酸から塩化シアンが出来る」問題をすでに認めていた。 http:// ←ココsuidou-kawasan.web.infoseek.co.jp/topix/topix.htm(中段)
(日水協衛生常設調査委・シアンの検査方法を検討(11/27日本水道新聞)から引用)
『厚生労働省の○○・水道課水道水質管理官が最近の水道行政の動向について解説した。 「シアン化物イオンおよび塩化シアン」の検査では、塩化シアンの安定化のため試料採取時に酒石酸緩衝液を添加するが、これにより多くの塩化シアンが検出されることになる。そこで水質試験方法等調査専門委員会無機物部会では、これに代わる緩衝液を検討している。』(引用おわり)
伊藤ハム調査対策委員会の報告は、お粗末としか言いようが無い。
前回は検査法について追及しなかったので、ちぐはぐな報告となっていました。
今回は検査法を追及することとし、酒石酸と結合残留塩素から時間を含め塩化シアンが出来る実験をし、多くの条件を検証しました。その結果、0.035mg/Lまで塩化シアンが出来たことを再現しましたね。酒石酸が原因だったことが判明しました。
また、別の緩衝液を使った検証を実験中とのことです。調査対策委員会の今回の動きは、真摯に受け止められます。
一方、九州男児さんがリンクで示すとおり、厚労省は酒石酸が悪い事実を認めているのだから、別の緩衝液の結果後は「検査法によって出来た事件だった」と報告しても良いと思います。
公定法が間違いでも法律は正しいのだから、この事件はどうなるんだろう。
しかし、ある報道では、質の悪い塩素からシアンが出来たと報道していましたが、これは間違いで、
質が悪い塩素から出来るのは「塩素酸」です。
正しい報道をして欲しいと思います。
伊藤ハムが地下水からシアンが検出された問題について調査対策委員会の報告で、
規制のため省略
(※1)
6ページの後半に「シアンの分析方法による問題、すなわち、添加する試薬と結合残留塩素が反応してシアンが生成する問題については、追求しないこととする」と書かれているが、なぜ、追求しないのか大いに疑問を持ったので、自分なりに調べてみた。ここまで調べるには長い時間がかかってしまったが、科学的に裏づけが出来たのでまとめたので報告する。。
調査検討委員会の報告書でいう文献は、
規制のため省略
BUNSEKIKAGAKU
(※2)
ここで(緒言の7行目から引用)
「その検査法を用いた自己水源型(井水型)簡易給水水道浄水試料の16年度のCN及びCNClの検査結果では水質基準超過率が35%に達した。」(引用終わり)
厚労省方法が変わったことによりシアンが 35% も不適となるとは明らかな異常だ。
この時点で厚労省方法はおかしいと考えるのは普通だろう。
読んでいくと、「酒石酸」という試薬が書かれているがこれがくせものだったのである。
酒石酸で検索するとたくさんあった
規制のため省略
川崎研究局(※3)
www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_eiken/sosiki/living/chousakenkyu/18chousakenkyu.html
(※4)
千葉市
これらには、試料にアンモニア性窒素が含まれていた場合は塩素消毒により生じた「結合残留塩素」と、試薬で加える「酒石酸緩衝液」が反応し「シアンと塩化シアン」が出来ることが書かれている。
結合残留塩素+酒石酸緩衝液→シアン化合物
また、文献には酒石酸緩衝液の代わりに別の試薬を使えば塩化シアンが出来ないことが書かれている。
その飲料水のシアン化合物の検査方法は引用から、厚生労働大臣が定める方法(別表第12)
規制のため省略
ここで、「試料の採取及び保存」で酒石酸-酒石酸ナトリウム緩衝液を加えることとなっている。
さらに調べてみると、酒石酸から塩化シアンが出来る反応は時間とともに進む。
www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_eiken/sosiki/living/chousakenkyu/19chousakenkyu.html
(※5)
(大学の図書で本文を読むと、1時間では微量、24時間では18.6μg/Lも増加している)
調査対策委員会での再現試験では塩素(次亜塩素酸ナトリウム)を加えて2時間静置したが、酒石酸緩衝液を加えた後はそのまま測定したと考えられるので、シアン化合物は少なかった。しかし伊藤ハムの外部委託の検査所では多くの検体が集中だろうから、水をとってから分析するまでの反応する時間が延び、塩化シアンが大量に出来たのだろう。
飲料水の消毒は、
www.asahi-net.or.jp/~kv6t-ymgc/05purification/raccoon_purification_cl-disinf.htm
(※6)
○普通の水→(塩素消毒)→遊離残留塩素→ 水道法で0.1ppm以上と決められている。
○アンモニア性窒素を含んだ水→(塩素消毒)→結合残留塩素ができる。
(結合残留塩素の場合は0.4ppm以上と決められており、これでも合法)
一方、アンモニア性窒素を消すためにはたくさんの塩素が必要。(※6)
委員会の報告によると、伊藤ハムの地下水にはアンモニア性窒素が約2mg/L含まれている。
原水からシアン化合物ができたのは、原水なので、塩素消毒はしてない状態である。 厚労省方法では、前処理として塩素を加える操作が有る。その塩素を加えたことにより地下水に含まれていたアンモニア性窒素が結合残留塩素に変化し、それと酒石酸緩衝液が反応して塩化シアンができたのである。(文献参照)。また、厚労省方法では「試料に結合残留塩素が含まれていない場合には次亜塩素酸ナトリウムを加える操作を省略できる」としているので、原水の場合は加えなくても良いのであり、その場合は不検出という結果になるだろう。
文献を見ているはずの調査対策委員会では不明としている。
※2によると国は酒石酸の問題に気づき、平成17年3月に一部改正をしたが、酒石酸緩衝液を別の緩衝液に変えることはせず、結合残留塩素を消すために次亜塩素酸ナトリウムを一定量加えるだけの操作にしたが、井戸水に含まれるアンモニア性窒素の量によって必要な塩素量は違うので、アンモニア性窒素が多い水では不足する場合があり、その場合は更に塩化シアンができると書いている(※6、※2)。要するに、厚労省方法は結合残留塩素の量を測定している事になる。
調査対策委員会は、このことから塩素消毒が不十分と言っているのだが、国の間違った測定方法を保護するために、塩素を多く入れなくてはいけないのだろうか?酒石酸を使わず他の緩衝液を使えば塩素の影響は受けない(※2、※5)。
塩素は国の定めたとおりに0.4mg/L以上添加していれば責任は無いはずだ。
◎ 厚生労働省側では、11/27の発言で、酒石酸から塩化シアンが出来る問題を認めた。
suidou-kawasan.web.infoseek.co.jp/topix/topix.htm
(中段)
(日水協衛生常設調査委・シアンの検査方法を検討(11/27日本水道新聞)から引用)
『厚生労働省の○○・水道課水道水質管理官が最近の水道行政の動向について解説した。 「シアン化物イオンおよび塩化シアン」の検査では、塩化シアンの安定化のため試料採取時に酒石酸緩衝液を添加するが、これにより多くの塩化シアンが検出されることになる。そこで水質試験方法等調査専門委員会無機物部会では、これに代わる緩衝液を検討している。』(引用おわり)
これでは、伊藤ハム調査検討委員会の報告の塩素不足説は、ひっくり返ってしまったではないか。
そもそも厚労省方法が間違っていたことによる事件であったのは明白。我が食品施設もそうだが、井戸水を使用する全国の食品工場や学校、施設等はシアン問題からやっと安心できることになる。
上の結果がこれだ。
www.suido-gesuido.co.jp/blog/suido/2008/12/post_2587.html
(※7)
そもそも、検査法を作ったのは、枡添大臣ではなく、依頼している外部の検討会らしいのだが。小さな問題としておざなりにされていた検査法は科学的な根拠が有っても簡単には変えないが、伊藤ハム事件がきっかけとなり、いまさらだがさすがにまずいと感じたのだろう。
追記1)
塩素の管理が悪く質が低下したために検出されるのはシアンではなく、塩素酸である。(一部報道機関が間違った報道をしていたため)塩素剤が古くなるとその中に塩素酸ができてくるためである。
規制のため省略
追記2)
12/25の調査対策委員会の報告書では、35~36ページに酒石酸を使用した再現試験で0.035mg-CN/L(不適)もの塩化シアンが確認され、厚労省方法の欠点が証明された。今回の事件の真相は究明された。(今後は酒石酸を使わない方法で試験を行い、結果を出すようだ)
それにもかかわらず、そのことは報道には伝わっていない。
報道には酒石酸を使用した方法での(欠点を補うために)「塩素が不足していたためにシアンが出来た」と発表しているのである。(国の立場を守るためか)
報道には事実を正しく伝えるべきではないのか?
厚労省方法の酒石酸が原因で起こった事件ではないのか?
また、記者の方々は真相を突き止め、国民に正しく伝える義務があるだろう。
またひとつ、国にとって不都合な事件の真相が、国民に対して隠されたまま終わろうとしている。国の体質はいつまでたっても変わらないのか。国民をごまかす体質はこれからも受け継がれていき、子供たちの未来へと引き継がれていくのか。
社保庁問題、薬害肝炎問題などと同様に国を厳しく監視していかなければ、ごまかされて終わってしまうのだろう。
間違ったことがまかり通り、正しいことは伏せられてしまうが、それを許していいのか。
さびしい国だと感じるのは自分だけだろうか。
http://
省略してます。