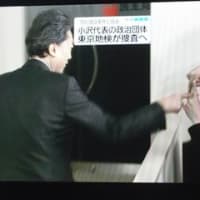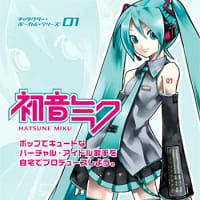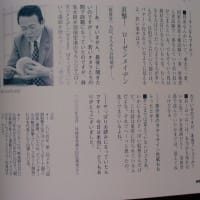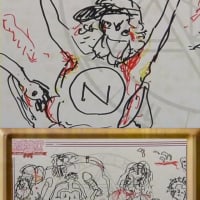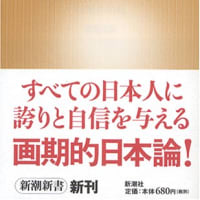前回に引き続き『ダ・カーポ』より。
ダ・カーポには毎回、私の尊敬する国語学者である金田一春彦先生の御子息であられる金田一秀穂さんのコラムが掲載されています。
金田一秀穂さんといえば最近では「タモリのジャポニカロゴス」や「マシューTV」でお馴染みの国語学者さんです。
その金田一秀穂さんのコラム「言葉のことばっかし」に気になる一文がありました。
テーマは「中華そば」という言葉について。
以下、引用。
―中華ソバという。私にとっては、子供の頃からこれが一番馴染んだ言葉なのだ。
祖母たちはシナソバと言った。
支那というのが差別語であることは後年知った。
祖母に差別意識があったとは思えない。
しかし、差別意識は使う側になくても、使われる側がその存在を決定できるのだから、使わないに越したことはない。
記事のタイトルにありますように「支那」とは決して差別語ではありません。
国語学者さんが「支那」という言葉の語源も御存知ないのでしょうか。
別段、秀穂さんを批判する事が今回の趣旨ではないのでそれは置いておくとして、
支那(しな)の語源は最初の統一王朝「秦(しん)」に由来しており、
以後、政権・王朝が代わってもその基底にある自然・民族・文化を意味する名称として「支那」は使われてきました。
西洋でもそれは同じで「China」の語源は云うまでも無く「秦」ですし、オランダ語では「Sina」と表記しています。
ローマ字読みすれば正に「シナ」ですね。
シナに「支那」という漢字を当てるのはサンスクリット語の仏典を漢訳した時に出来たものです。
「支那」という字を当てたのは当時の支那人です。
(「支」も「那」もとても良い意味を持つ漢字)
日本では江戸時代以後「中国」を指す語として蘭学者などの間で幅広く使用されてきました。
ですから、「支那」というのは歴代王朝から含めて「中国」を指す言葉です。
だから「清」も支那ですし、「隋」や「唐」も支那と言う事です。
例えば、グレートブリテン及び北部アイルランド王国を「英国」と呼ぶことと同じようなものです。
「オランダ」だってオランダ人は「ホーランド」と呼びますし、
「支那」だけなぜ差別語になってしまうのでしょうね。
さて、金田一秀穂さんは
「支那というのが差別語であることは後年知った」
と書いていますが、一体どう「知った」のでしょう?
また、「祖母に差別意識があったとは思えない。」
とも書いていますが、
そもそも「支那」が差別語ではないのですから、
差別意識がなかったのは当り前のことですね(笑)
附記:平成十八年九月十七日加筆
ダ・カーポには毎回、私の尊敬する国語学者である金田一春彦先生の御子息であられる金田一秀穂さんのコラムが掲載されています。
金田一秀穂さんといえば最近では「タモリのジャポニカロゴス」や「マシューTV」でお馴染みの国語学者さんです。
その金田一秀穂さんのコラム「言葉のことばっかし」に気になる一文がありました。
テーマは「中華そば」という言葉について。
以下、引用。
―中華ソバという。私にとっては、子供の頃からこれが一番馴染んだ言葉なのだ。
祖母たちはシナソバと言った。
支那というのが差別語であることは後年知った。
祖母に差別意識があったとは思えない。
しかし、差別意識は使う側になくても、使われる側がその存在を決定できるのだから、使わないに越したことはない。
記事のタイトルにありますように「支那」とは決して差別語ではありません。
国語学者さんが「支那」という言葉の語源も御存知ないのでしょうか。
別段、秀穂さんを批判する事が今回の趣旨ではないのでそれは置いておくとして、
支那(しな)の語源は最初の統一王朝「秦(しん)」に由来しており、
以後、政権・王朝が代わってもその基底にある自然・民族・文化を意味する名称として「支那」は使われてきました。
西洋でもそれは同じで「China」の語源は云うまでも無く「秦」ですし、オランダ語では「Sina」と表記しています。
ローマ字読みすれば正に「シナ」ですね。
シナに「支那」という漢字を当てるのはサンスクリット語の仏典を漢訳した時に出来たものです。
「支那」という字を当てたのは当時の支那人です。
(「支」も「那」もとても良い意味を持つ漢字)
日本では江戸時代以後「中国」を指す語として蘭学者などの間で幅広く使用されてきました。
ですから、「支那」というのは歴代王朝から含めて「中国」を指す言葉です。
だから「清」も支那ですし、「隋」や「唐」も支那と言う事です。
例えば、グレートブリテン及び北部アイルランド王国を「英国」と呼ぶことと同じようなものです。
「オランダ」だってオランダ人は「ホーランド」と呼びますし、
「支那」だけなぜ差別語になってしまうのでしょうね。
さて、金田一秀穂さんは
「支那というのが差別語であることは後年知った」
と書いていますが、一体どう「知った」のでしょう?
また、「祖母に差別意識があったとは思えない。」
とも書いていますが、
そもそも「支那」が差別語ではないのですから、
差別意識がなかったのは当り前のことですね(笑)
附記:平成十八年九月十七日加筆