敢えて中学生・高校生向け講座とした。一般の人は経験則で分かっているからである。
第3講 津波の力。横に動く「運動の力」である
本稿は「運動の力」を取り上げる。概念としてこの力は運動する物質の質量(重さ)とその動くスピードで決まってくる事を述べたい。一般論としてだけでなく、津波の力、津波の破壊力はどうなのかを基本的に身につけほしい。なにを基準に津波の力を測定するのか? うーん、むずかしいといえばむずかしい…
<予習>
力の概念に近づくために予備概念が必要である。原子力規制委員会に出したパブリックコメントからの部分引用を読んでみよう。
津波の「運動の力」とは? 「高さ」に還元は出来ない
一般に「運動の力」とは物質の質量とスピード(の2乗)に比例する。計算はともかく、例えば、このたびロシアのウラル地方に落下した隕石の破壊力や衝撃力には世界中が驚かされた。また、わが国では、昨年のつくば市を通過した竜巻の被害状況はまだ記憶に新しい。いずれもスピードの2乗の計算がある程度成り立ち、破壊力の概念もそこそこ理解されている。東日本大震災の津波の「運動の力」はどうであったろうか? 隕石の衝撃波にせよ、つくば市の竜巻にせよ、機能し、作用する物質はたかだか「空気」である。津波は質量が空気の1000倍の「水」である。その沿岸を撃つスピードは? その破壊力は? (私は寡聞にして今次津波のそのような情報を知らない。わずかに宮古市の川代地区で115km/h、同田老地区摂待で30km/hの新聞記事に接した程度である) 隕石にせよ竜巻にせよ、瞬間的であり局地的であるが、津波は、繰り返し襲い、範囲も比較にならないほど広大である。しかし、沿岸(原発)を撃つスピードすら分かっていない。公表もされない。報道もされない。分からないという理由だけで学者も政府も原子力規制委員会も国民に訴える事をやめている。電気事業者も津波高対策PRにはつとめているが立地を襲う津波の強さには口をぬぐっている。高さ還元主義と言える。
(引用以上)
<本講>
(1)津波の力(破壊力)=定数×質量×(スピード)の2乗
高等学校の物理で「力は質量と速度の2乗に比例する」という風に習った。さすがに それぞれの実数を代入して試算するところまでは習わなかったように思う。あまりに原理的で公式が抽象的だからである。しかし、大数の把握や比較はやっておく必要がある。
 竜巻で破壊されたつくば市街地
竜巻で破壊されたつくば市街地
(2012.5.6)
(2)空気の破壊力
平成24年つくば市で発生し猛威を振るった竜巻は時速60kmの速度で500m幅をもって15kmをかけぬけたという。竜巻の渦(うず)自体の回る風速は秒速50~69m(時速180~250km)相当といわれている。土台だけ残して破壊された建物や折れ曲がった電柱などへは、瞬間的であれ、通過速度60kmも加算された風速(240~310km)の2乗に比例した力が加わったことになる。風速の2乗という事の実態は分からないが、とてつもない数字になる事は想像がつく。風速という空気の運動とはいえ、竜巻ほどの速度になると、空疎な空気(質量)でさえ津波なみの大きな破壊力となるのである。
(3)速度の力
津波が沿岸を襲った時の早さは岩手県宮古市では2カ所で観測されている。いずれも速度は推測であるが田老摂待海岸で時速30km、 重茂半島の川代地区で115kmと報道された。前者は140トンといわれる巨石を海岸から500m陸上に運んだ計算から、後者は、沿岸に寄せる津波の連続写真からの計算だという。
まず140トンの巨石を軽々と地上500mを転がした水(質量)の力に驚いた。加速度的スピードのついた海水が発揮する力である。次いで、その田老摂待海岸の津波の速度30km(秒速8メートル)の、約4倍の重茂海岸の津波の速度115kmに驚いた。力のエネルギーに換算すると二乗という事で巨岩を動かす力の約15~16倍の力になる。140トンの15倍、2,100トンの岩を、一帯で、くり返し繰り返し、軽々と転がす事になる津波の波の力、と言ったら言い過ぎであろうか?
 津波で500メートル運ば
津波で500メートル運ば
れた140トン巨岩(宮古市田老地区摂待海岸)
 重茂川代地区
重茂川代地区
日本経済新聞(2011.4.22)
(4)津波の破壊力
水に比べたら空気は限りなく0(ゼロ)に近い重さである。真空では水の約1/1000の重さ(=空気の質量)だという。運動のエネルギーは速度の2乗に比例して大きくなるほか、質量にも比例する。速度の2乗に比例する運動のエネルギーは、空気の塊(かたまり)である竜巻でさえ、つくば市のような破壊力を発揮する。空気でなく水の塊である津波が、竜巻の渦なみの高速で沿岸を襲撃するのであるから、その破壊力は、それこそ、ある程度正確にシミュレーションしたら、想像を絶する結果が出るはずである。竜巻の渦と同じ速度なら最低でもその1000倍(質量分)! 竜巻は範囲も狭く、比較的短時間の破壊力である。津波は1000倍の力を維持して、継続して、無限広範囲で、沿岸を撃ち続ける。
(5)津波の破壊力は高さではない。絶対的イメージのちがい
長々と書いてきた理由は、岩手県や宮古市の津波被害シミュレーションが全て浸水深にかぎられているからである。侵入津波の高さ、また浸水の深さは、それだけでは津波の破壊力の大きさを表すものではないという事を言いたいからである。津波のタテの高さや深さは破壊力の大きさには必ずしも比例しないということを考えてほしいからである(運動のエネルギー的にはゼロである)。この点が、山幸彦の洪水学者や、山幸彦の県庁の役人が、故意に見落とすか、軽視しているところである。
また、波の高さに依る「寄りかかりの力」は本来の津波の力を過小評価し矮小化する過った基準である。海幸彦は子どもでも誰でも、この事は、経験上、ものの道理として感覚的に知っているのである。津波は、横への速度次第でその力は破壊の力となる。ただ木材が浮いたり水が出たり(溢流)するのは破壊のエネルギー的にはそれほどの力ではないといえる。津波が破壊的で恐ろしいのはそれが高速度で横に動くからである。2メートルで家が倒壊し30センチで人が死ぬといわれる所以(ゆえん)である。海幸彦の防潮堤に対する不信は、その高さだけを基準にしている幼稚な不合理性に由来している。
※ 高速で横に動く津波と、上下に揺れて寄せる通常波浪は、完全に似て非なるものであるがここでは論じない。

岩手県は防潮堤にかかる力を波の高さから来る「寄りかかりの力」と見ている。それは津波の力の一部でありごくごく小さい力である。こんなものは津波の力とはいえない。本当の力から見たら0(ゼロ)評価である。

本当は、津波が防潮堤を襲う力は横からの「運動の力」である。ほとんど無限長のベクトルといい得る。田老の万里の長城、釜石のスーパー堤防を軽々破壊した力である。震源地の地殻破壊で生じたエネルギーが波(というより海水)を媒介にして沿岸に達した力である。
(6)岩手県庁の言い分
これまでの巨大津波の浸水深を調べて、そこから防潮堤の高さを引き算して、それをもって浸水深シミュレーションであるとしている。目的的な幼稚なシミュレーションである。だから、そこからは、何一つ有効なものは出てこない。例えば一番大事な津波の強さ(破壊力)が導き出せないでいる。津波の多様性、跛行性、地域性などは無理。早い話が防潮堤の強度、有効性の説得は不可能なのである。強度、有効性は無視している。
この講座の冒頭に書いた「なにを基準に津波の力を測定するのか?」という事は、高さではなく、少なくとも運動の力だという事を知ってほしい。ずばり津波の寄せ来るスピードであり、津波の岸を打つスピードである。宮古湾の瓦礫の総量は80万トンと言われた、それで津波の破壊力は最低80万トンという事も出来る。浸水高や遡上高も津波の力の側面である。人的被害をいう場合もある…。どれがどうという事は言えないが未完成でも「運動の力」はそれらの諸基準の基準になる。未完成とは単にフィールド資料不足という事であるが…
















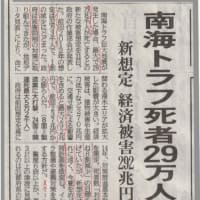







こんなん書いてたら、少なくとも技術系の行政の方は、誰も聞く耳持ってくれない。いくら防潮堤は無力だったとわめいても、僕含めて一切は戯言として捉えます。
津波の力は全て高さに変える事が出来、技術的用語でいえば水頭(すいとう)。高さ=エネルギーの大きさをさします。
たこのはま辺りを襲った津波をビデオから類推すると、10mの波高で流速20m/sの津波と思われ、これを例に計算すると、
速度水頭=流速^2/(2*重力加速度(≒10m/s2))=400/(2×10)=20m、位置水頭10m(波高)+速度水頭20m=30mとなります。
使った式は、ベルヌイの式と呼ばれる公式で、太古の昔から使われてる式です。
物理現象を説明するなら、世の中的に普遍的な式を使い、いろんな現象を説明しないといけないと思います。