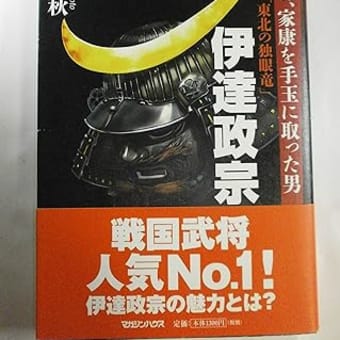人はどのようにして言語を獲得してきたのか。類人猿との違いは何かを、オノマトペの特質から入り、赤ちゃんはどのように言語を身につけるのかを考察。身振り手振りによるコミュニケーションから言語への移行、オノマトペの言語による違い、帰納法と演繹法、さらには仮説検証(アブダクション推論)による推論、AIにおける記号接地問題などを絡めて考えた一冊。ヒトがどのようにして言葉を生み出してきたかを考えた感動的ともいえる言語論。
AI研究で唱えられたのが「記号接地問題」で、AIの世界や現実世界の言語が、実世界や人間による実体験と結びつくことにより、記号や言語の本質的な意味を理解することをいう。つまりAIが宿るコンピュータは機械であり人間が実体験することで得られる本当の意味での理解はできないのではないかという問題である。例えばメロンは緑色の球体の果物で、表面には熟すと網目模様が入り、食べると瓜のような味わいの甘さがある、と記述できるが、その味わいは食べてみないことには本当には認識できないのではないか。言語も記号であり、その本質は体験できなければ認識できないのではないか、というのが記号接地問題。
「赤」という言葉には具体的に指し示す対象としての色があるので抽象的概念ではないが、赤とオレンジ、ピンク、紫との境目は結構曖昧であり、「接地」するのは容易ではない。盲目の人が「赤」の意味を理解できるか、赤ちゃんはどのようにして「赤」を理解するのか。実は赤という記号は色彩を現わす表現システムの一部なので、黒、白、緑、黄などとともに存在する全体理解が色彩というシステム理解となることで、その一部としての「赤」の理解へとつながる。「素数」や「分数」は数学的概念であり、赤のような具体的対象物があるわけではなく、数学という体系の理解が進まなければ認識できない概念である。「好き」「嫌い」「愛情」「憎しみ」などは、感情という人により認知される気持ちの表現であり、人の気持ちが分かる、感じられることと、その表現である言葉をどのようにつなげていくかは、言語発達と人間背発達が連動する領域でもある。言語表現というのは人間たる知性存在証明でもある。
オノマトペは言語依存性があり、ピースマークなどのアイコンにはそれがほとんどない。日本語のハ行には特質がある。何かが落ちる様子「ハラハラ」「バラバラ」「パラパラ」、しゃべり方の「ヘラヘラ」「ペラペラ」「ベラベラ」、軽く出かける様子の「ふらり」「ぷらり」「ぶらり」など微妙なニュアンスが表現できる。日本語の「ハ行」は古代には「パピプペポ」、その後江戸時代までは「ファフィフゥフェフォ」だったという歴史的変化があり、日本語独特の産物だという。英語、韓国語、チェコ語、ポーランド語など言語それぞれに歴史的変遷や特質があり、それがオノマトペには現れる。つまり他言語のオノマトペは理解できないものが多い。しかし共通する表現も多く、鼻にはn音、舌にはl音、粗いにはr音という対応関係が見られる。また主食の米、小麦はパ・バ・マ・ファ・ワで表されるものが多く赤ちゃん言葉が食事の元になっている可能性がある。
オノマトペの守備範囲には言語により大きな違いがある。声や音を擬音として表現するのは全言語共通だが、英語には動き、形、手触りのオノマトペはない。身体感覚や感情のオノマトペは日本語にもあるが、味や匂い、色のオノマトペは日本語にはなく、インドのムンダ語にはあり、論理的関係を現わすオノマトペはどの言語にも見られない。隠されたオノマトペが言語にはあることが分かっている。「たたく」「すう」「ふく」は「タッタッタッ」「スー」「フー」という擬音語から作られた言葉。烏、鶯、不如帰は「カラ」「ウグイ」「ホトトギ」という鳴き声擬音に「ス」という鳥を示す接辞がついてできた名前。
世界の言語には動詞表現に二種類があり、ぶらぶらと公園を横切る、という動詞枠づけが日本語、ロマンス語(フランス、スペイン、イタリア、ポルトガル)、アルタイ語(トルコ、モンゴルなど)であり、衛星枠づけでは英語のように”stroll across the park”のように表現するゲルマン語(英語、ドイツ、オランダ、デンマーク、スウェーデンなど)やスラブ語(ロシア、チェコなど)。動詞枠づけでは述語本体で動きの方向を示し、降りる、入る、横切る、超えるなど。
英語のような衛星枠づけでは動きの方向性が述語以外の、down、in、across、overなどと表現され、動詞自体にもplod(とぼとぼ歩く)、scurry(大慌てで走る)、limp(片足を引きずって歩く)などとなる。英語には歩く、走るを細かく区別する表現動詞が140以上あり、日本語と対応させると、amble(のんびり歩く)、tipple(そろりそろりと歩く)、sashay(しゃなりしゃなりと歩く)、stroll(ぶらぶら歩く)、swagger(ずんずん歩く)、toddle(よちよち歩く)など、日本語ではオノマトペで補強されることが多い。感情表現も動詞に含まれるのが英語であり、日本語の「ぺちゃくちゃ話す」「ひそひそ話す」「ぶつぶつ言う」「キャーキャー話す」は、chatter、whisper、mumble、screamなどとなる。汽車がピーっと走り去る、は英語ではThe train whistled awayとなるという具合。
赤ちゃんが言語を学ぶ時にも、母国語の音やリズムの体系、音と意味の対応付け、語彙の構造を自分で発見しながら言語を身につける。言葉は本来抽象的な記号であるのに、日本語ではオノマトペがもつアイコン性を感じながらも、抽象表現である言葉を体系化していき、抽象性を感じずに空気のような自然なものとして身体の一部であるかのように言語を身につける。このプロセスに言語体系成立の歴史があるのではないかというのが筆者の指摘。もう一つが、その言語身体化のプロセスに、帰納法と演繹法、そして仮説推論(アブダクション推論)があるという。すべての人間は死ぬ、ソクラテスは人間である、ゆえにソクラテスは死ぬ、これが演繹。これらの豆はこの袋に入った豆、これらの豆は白い、ゆえにこの袋に入った豆は白い、これが帰納。ここに仮説推論を当てはめると、この袋にはいった豆はすべて白い、これらの豆は白い、ゆえにこれらの豆はこの袋から取り出したものに違いない。この推論は正しいかもしれないが、そうでもないかもしれない。しかし人類の進歩の多くは、仮説推論から発生したと考えられ、この仮説を立てて推論してみる、その結果を検証して違う場合には訂正して仮説をたてなおす、ということができるのが人類たるゆえん、という主張である。
ヘレンケラーが言葉の存在に気づき、それを学び始めたのが、サリバン先生による"water"の教え。エレンの手に水をかけた後に、手のひらに”water"と指で書いて見せた。ヘレンは水という存在に”water"という言葉が対応するという事実に気が付くというエピソードは、上記演繹、帰納、そして仮説推論を思わせる。赤ちゃんによる言葉の学習もこうした気づきから始まる。チンパンジーも言葉を学ぶが、それは一方向の演繹と帰納であり、逆方向の理解や推論はない。チンパンジーに△印を見せた後にバナナを与え続けると、△はバナナを示すことを覚えるが、バナナを見せても△を選ぶことはない。人間の赤ちゃんはそれができるという。外の道が濡れていると、多分雨が降ったに違いない、これは推論であり、このような推論はチンパンジーにはできないという。ではAIとヒトの違いは何だろう。現時点のAIは記号接地をせずに言語体系を身につけており、その先に何があるのかはこれからの問題である。本書内容は以上。
オノマトペと記号接地問題、そしてAIについての考察は言語の本質と人間の思考についての深い洞察が本書にはある。今後の研究展開が楽しみである。