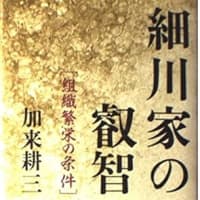「殿、利息でござる」という映画があったことは、羽生結弦さんが殿役を務めたニュースで知っていた。本書はその原作で、映画のエピソードを始めとして三人の無私の日本人を取り上げている。
一人目は穀田屋十三郎、仙台は伊達藩吉岡という宿場町の商人である。吉岡宿は藩から求められる役務で苦しみ、田畑がない住民は商売で精を出すしかないが、その商売も人が減ってくると盛りがない、街は錆びれるばかりであった。十三郎はなんとかしてこの宿場町を再び豊かにしたいと知恵を絞った。そこで考え出したのが、街の大きな商人たち同士で出資金を募り、藩に貸し出してその利息として年1割をいただくことで、役務と相殺できるのではないかということ。しかし、江戸時代、商人から藩にそのような申し出をすること自体、前代未聞のことであり、どのようにして実現できるのかもよくわからなかった。そこで、信頼できる仲間づくりからはじめ、賛同してくれそうな肝煎を探し、肝煎の総まとめをしている大肝煎をも巻き込んで、千両という大金を調達するところまでこぎつける。賛同してくれた商人や肝煎たちは自分自身の家宅さえも捨てる覚悟の大仕事で大博打でもあった。代官、出入役などの藩の官僚組織に申し入れを行うが、最初は前例なきこととして拒絶される。藩はお金に困っているのに、こうした申し入れを聞けないのはおかしい、と様々な知恵を絞る十三郎たちの努力が実り、財政難の仙台藩を救うところと成り、その利息は吉岡宿に毎年百両の利息金をもたらした。このような知恵者がいるとの評判は仙台藩の殿様にも届くことと成り、出資金を出した酒屋にまで殿が訪れ、殿命名の銘酒が生まれた。そしてこうした智慧を絞り、出資した9人の家に伝わった言い伝えは「ゆめゆめこうしたことを吹聴することなかれ、街の集まりがあっても最も下座に座るべし」というもの。家訓として今でも残っているという。
二人目は中根東里、日本一の儒者であり詩文家であったが、一切の栄達を望まなかったため、引く手あまたの仕官の口を断り続け、一生極貧で暮らしたという。自らの詩文は火にくべて燃やしてしまうため詩才溢れた詩文が殆ど残っていない。東里は村民が作ってくれた小さな小屋に暮らし塾を開いて村民たちには満巻の書から学んだ人間の道を平易に語り教えたという。
三人目は大田垣蓮月、江戸後期の歌人であり、津藩藤堂家の血を引く貴人でありながら、身分の低い武士の養女となり、結婚もしたが4人の子、そして夫とも死別、剃髪してからは蓮月流の歌人、焼き物師として名を成した焼き物で手にした金銭は飢饉の際には貧者を助けるため投げ出し、鴨川に丸太町橋を建てるために寄付もした。旧幕府軍追悼の西郷隆盛には「あだ味方 勝つも負けるも哀れなり 同じ御国の人と思えば」と自重を促した。弟子には山岡鉄舟がいて、江戸総攻撃を西郷が思いとどまったのは勝海舟の後ろに山岡鉄舟と蓮月がいたからという。
経済的に発展してきた日本ではあるが、平成の30年その勢いは昭和のそれではない。そして今日本人が考えるべき価値とは何、というという問の答えがこの無私の日本人ではないか、というのが筆者の問いかけである。落とした財布が戻ってくる、これが日本の最大の価値ではないかと。その源流は江戸時代の庶民にこそあり、それらを体現していた代表がこの三人というわけである。新元号が始まる今年に新たに考えてみても良い問いかけである。