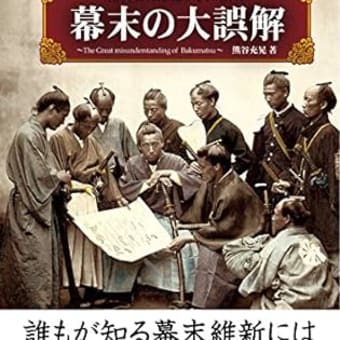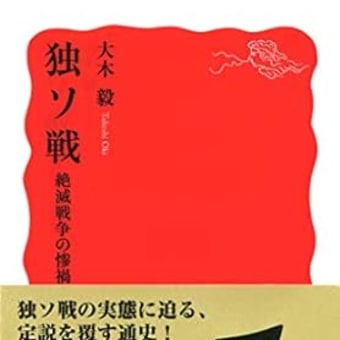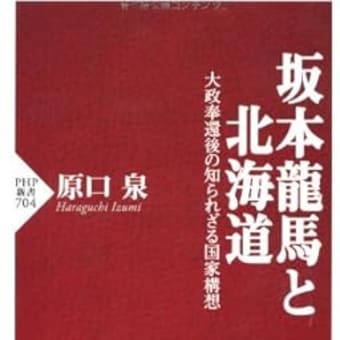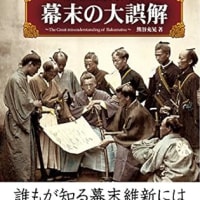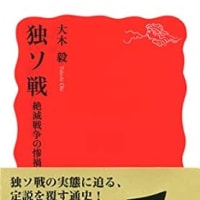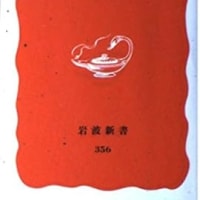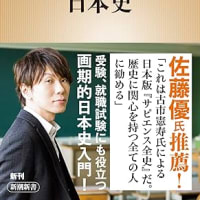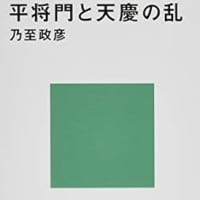本書は、第一部 「太平洋戦争、七つの謎」そして第二部「昭和史七大事件」の二部構成。
第一部、誰が開戦を決めたのか? 手続き的には御前会議だが、その前に行われていた「大本営政府連絡会議」で実質的には決まっていた。メンバーは9人。軍サイドは陸軍参謀総長、海軍軍令部総長、参謀次長で、政府側は首相、陸軍大臣、海軍大臣、企画院総裁(国務大臣)、外務大臣、大蔵大臣。しかし具体的な人名を見てみると首相は陸軍大臣兼任の東條英機で、政府側と言っても海軍大臣も軍人。軍人と文官は6人vs3人の比率であり、開戦への方向性は明らかだった。軍の意向には逆らえない雰囲気は、五・一五事件以降の各種テロや中国戦線での戦いとその報道などで一層高まっていた。さらに会議メンバーで軍人の陸軍東條英機、杉山元、海軍の嶋田繁太郎、永野修身、田辺盛武、伊藤整一はいずれも軍隊エリートであり、士官学校を優秀な成績で卒業した結果としての地位獲得であった。彼らは軍人とはいっても、戦場で泥水を飲んだ経験がない軍官僚。政府側も同じくエリートで官僚。対米英開戦の決定は、日中戦争が泥沼化する中で、こうしたエリート官僚により決定された。東條英機はそうしたエリート軍人官僚の象徴的存在であり、最前線で死んでいく兵士への目線は、兵力と戦死者として報告されてくる数字としてしか映っていない。
司馬遼太郎が指摘したように、統帥権が統治権を上回るという、ロンドン軍縮条約締結後の「統帥権干犯問題」が文民統制を不可能とし、軍サイドによる政治主導とその地位を高め、それをメディアが煽り、国民も支持してきたことが戦争判断を招いたといえる。戦争が始まったあとの、ミッドウェー海戦やインパール作戦などの作戦失敗や補給が無理な作戦も、そして特攻や玉砕の決定もこうした官僚軍人たちにより差配され、反省することなく継続された。実は、本土に残る日本人たちも、戦争初期には戦場での悲惨な状況を肌身で感じることなく、その惨たらしい惨状を知るのは戦後のこと。多くの国民が負け戦を感じ始めたのは実際に都市部への空襲が始まったころ、知り合いや親戚、家族の戦死通知がもたらされ、大本営発表の胡散臭さは誰もが感じ始めていたはずだが、見て見ぬふり、そんなはずはないはず、と信じていた国民も多かった。
それでは終戦を決めたのは誰だったのか。御前会議での評決は、ポツダム宣言受け入れと戦争継続が3対3。最終判断を迫られたのは昭和天皇。決断したのは天皇だったが、すのすべてのお膳立てをしたのは鈴木貫太郎首相。昭和20年5月に組閣された鈴木内閣は、本土決戦を主張する軍人官僚の主張の無謀さ、沖縄戦の苛酷さ、軍部官僚の無責任さを感じてのこと。昭和天皇の背中を最後に押したのは2発の原爆投下だった。
少し時代を遡ると、明治維新後の国民への掛け声は文明国を目指し、西欧諸国に追いつけ、というもの。それが日清・日露戦争での勝利の成果が国民には、戦果として報道されたほどではなく、その後の対米関係、三国干渉などでは富国強兵を誓う臥薪嘗胆を強いられた。日本メディアは消化不良のまま国際情勢を伝え、情報を受け取る国民サイドも国際政治や経済的な知識不足のまま、日本の国際的地位には不満を感じ、ナショナリズム的感覚が高まっていた。第一次大戦では戦勝国側だった日本は、その後の軍縮ムードに外交手段で対応する手腕が不足していたのだろう。大正に入り、国民の間にはリベラルな雰囲気も目覚め始めていたが、大正末期の関東大震災、東北飢饉、昭和大恐慌は国民の将来への不安も増大した。
そのころからの昭和の事件で、エポックメイキングだったのが五・一五事件。第二部では、日本を変えた昭和史七大事件(515事件、226事件、太平洋戦争、占領と憲法制定、60年安保、三島事件、ロッキード事件)を解説する。五・一五事件が起きたのは昭和7年、前の年の三月には陸軍中堅官僚によるクーデター未遂事件があり、9月には満州事変、10月には柳条湖事件の穏便収拾を図ろうとする政府方針に不満を持つ軍部官僚によるクーデター未遂の10月事件が起きていた。そして昭和7年に入ると血盟団事件で三井財閥の団琢磨と前大蔵大臣井上準之助が殺害された。この時代の軍部エリートたちは、日本の政治や外交の不甲斐なさを、武士道や農本主義の不徹底に原因を求めていたのではないか。英米流の民主主義が日本人の心を汚していると思いこんでいたフシがある。
そのころからの昭和の事件で、エポックメイキングだったのが五・一五事件。第二部では、日本を変えた昭和史七大事件(515事件、226事件、太平洋戦争、占領と憲法制定、60年安保、三島事件、ロッキード事件)を解説する。五・一五事件が起きたのは昭和7年、前の年の三月には陸軍中堅官僚によるクーデター未遂事件があり、9月には満州事変、10月には柳条湖事件の穏便収拾を図ろうとする政府方針に不満を持つ軍部官僚によるクーデター未遂の10月事件が起きていた。そして昭和7年に入ると血盟団事件で三井財閥の団琢磨と前大蔵大臣井上準之助が殺害された。この時代の軍部エリートたちは、日本の政治や外交の不甲斐なさを、武士道や農本主義の不徹底に原因を求めていたのではないか。英米流の民主主義が日本人の心を汚していると思いこんでいたフシがある。
青年将校や中堅軍人官僚の指導的立場にあった北一輝は国家統制を行う共産主義的理想国家造りを目指していた。思いの方向性は微妙に違えど、当時の政治主導では、日本は良くならないと考え、クーデターによる政府転覆を目論んでいた。五一五事件で裁かれた青年将校たちの純粋な思いに、裁判官や記者たちも心を動かされ、記事を読んだ多くの国民が刑の軽減嘆願書を裁判所に送ったという。情緒的心情優先で、動機が純粋であればテロさえも許される、という「動機至純論」は、その後のテロを是認することにもつながる。そして天皇機関説事件、国体明徴運動、2・26事件へとつながり、開戦、敗戦へとつながっていく。
戦後のGHQによる日本占領は前半の民主国家に向けた改革と後半の反共産主義への逆コースと大きく2つの時期に分けられる。占領初期に行われたいくつかの改革のなかでも日本国憲法制定は大きなエポックメイキングであり、今でもその時の論争が尾を引く。当時の日本の官僚たちはすべて皇国史観での教育を受け、エリートとして行政、司法、立法を行ってきたテクノクラートだった。GHQから要請され日本人官僚により書かれた憲法草案は、GHQから見れば明治憲法とほぼ同様の内容であり、「二度と戦争を起こさない国にするための憲法を作りたい」というGHQの考えからは程遠いものだった。
象徴天皇、主権在民、戦争放棄、基本的人権尊重、などの概念は日本人官僚の発想からは全く出てこなかった。昭和21年2月1日の毎日新聞にスクープされた日本側の憲法草案を見たGHQは2月13日にはGHQ案を日本政府に手渡した。ほとんどその内容を受け入れた憲法案が3月7日には新聞報道され、4月から8月に条文審議を行い、衆議院で賛成429、反対8で可決、10月6日に貴族院でも可決され公布された。GHQは、事前にアメリカ側草案骨子をまとめており、ドキュメント化を10日間程で行った。GHQの憲法案はよく考えられており、憲法改正は安保条約見直しや自衛のための再軍備化を国家的なレベルで見直さなければできない仕組みが組み込まれている。東京裁判に先立っては、天皇犯罪論を主張するその他戦勝国を説得する材料は、天皇の存在が日本統治のためには有効というもの。憲法は日米安保条約とペアで、日本を再軍備化させないと米国は主張したという。しかし占領後半、米国の思惑としては、朝鮮戦争と中国共産主義対応のため、占領終了後の反共産主義対応が必要だった。そのためにも、日本人により、サンフランシスコ講和条約以降に状況に応じて最適な憲法改正を行えばいい、という考えが日米両サイドにあった。実際、朝鮮戦争遂行のため米国は日本に再軍備を持ちかけたが、当時の吉田政権は「戦争放棄」条項をたてに、経済重視政策を進めた。高度経済成長の成功は、憲法改正の動きに強いブレーキを掛け続けた。
終戦時15歳以下だった人たちを戦後派と呼ぶとすると、戦後は世代が終戦時の大人たちに感じた裏切られ感が、1960年時点での為政者トップの岸総理たちへの生理的嫌悪感に継承された。六〇年安保闘争は、反米、反岸を看板にした戦前派と戦後派の世代間闘争だった。運動中に死亡した樺美智子さんは、その闘争の象徴となった。
1970年の三島事件は、その前年まで吹き荒れた大学運動が終わり、学生運動の混乱に乗じて、自衛隊が社会的転覆を目して立ち上がれ、と思い詰めていた三島由紀夫に絶望感を与えた結果だった。その思いは、5・15事件や2・26事件の青年将校の理想と根本で繋がっていた。
本書内容は以上。再び戦争をしない、という強い思いとともに、現在の世界情勢に対応した安全保障と憲法見直しが必要という状況判断が、多くの日本国民の頭に芽生えていると思う。ただし、憲法改正に関しては、本書でも明らかなように、日米安保条約との関係を正しく整理し、日本の防衛と安全保障の方向性に関して明確なビジョンを持たない限りは、着手が難しいということ。エリート官僚は現場の兵士の死に無慈悲、これは現在のロシアを見ていればよく分かる。大きな国の進路判断をエリート官僚やエリート政治家の独断に任せてはならない。もうひとつは「情緒的世論形成」のリスク。正しい考えと正しい行いはペアで語らなければならない。思いは正しかったが、行為は許されない、というイベントに対して誤った世論形成が行われ、変な結論を導いてしまいかねないということ。こちらも今起こってしまうリスクがある。歴史に学ばなければならないことは多い。