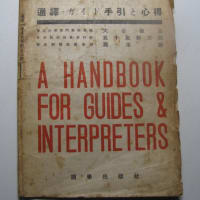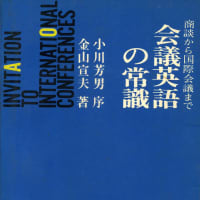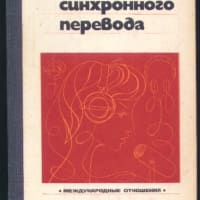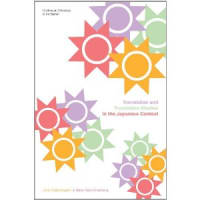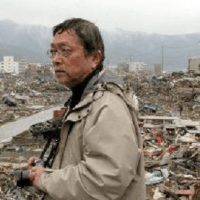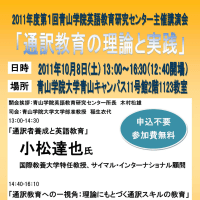■雑誌『英語教育』(大修館)2月号が「インプットからアウトプットへ」という特集を組んでいる。語学教育の問題に首を突っ込むつもりはないが、この特集の中でシャドーイングが大きな比重を占めているようなのでひとこと言っておきたくなった。まずすべての議論において、玉井(2005)が慎重に指摘した上位グループへの頭打ち効果が無視されている。この時点で一体議論の対象が誰なのかがあいまいになってしまっている。またこの特集の中の理論編とも言うべき「ボトムアップ・シャドーイングvs.トップダウン・シャドーイング」と題したコラムで、門田は「初めて接する未知の内容を素材」にしたシャドーイングにより「音声知覚を自動化」するというボトムアップ・シャドーイングの効果を称揚している。「シャドーイングによる音声知覚の自動化」が何を意味するのかはよく分からない(構音速度を高速化するのなら分かる)が、そもそもこの問題はスピーチ知覚の研究でElman and McCleland (1988)*などがトップダウンの音素回復効果を主張して以来論争が続いている大きな問題である(feedback vs. feedforward)。しかしボトムアップ派(Norrisなど)の主張もトップダウンとcompatibleであるというものだし、その差異も小さい(しかもinputとcontextを最初期のユニットとして並列している)。いくら練習したところでまったく未知の語彙を正しく認識できるはずもなく、音声と文字をまず結びつける操作が必要だと言ったのは、確か安井稔だったと思う。実際は門田の言う「初めて接する未知の内容」には多くの既知が含まれていると考えるべきだろう。
*Elman, J. L. and McCleland, J. L. (1988). Cognitive penetration of the mechanisms of perception: Compensation for coarticulation of lexically restored phonemes. Journal of Memory and Language, 27.
■この他、大学でのシャドーイングを中心とした多聴クラスの実践報告(茨城大学)もある。目的は発音をネイティブ並に鍛えることとリスニング力の向上であるが、選択科目だからいいようなものの、必修だったら逃げ出さないまでも迷惑に感じる学生はいると思う。