 |
RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語 (小学館文庫) 価格:¥ 580(税込) 発売日:2010-04-06 |
![]()
映画「RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語」公式HP
「RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語」から見える主体性とキャリア
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*-*-*-*-*
【「依存的なあり様」から「主体的なあり様】へ(3)】
依存的なあり様から主体的なあり様へと成長していく・・・その描写が小林さんの文章から見事にあらわされているのです。肇が、どのようにしてそんな成長(あるいは、取り戻す?)していったのか、そのプロセスを小林さんの描写から【 】でくくって紹介しながら見ていきたいと思います。
*************
【「大きくなったら何になりたい?
僕、ぜったいにバタデンの運転手になるんだよ。決めてるんだもん。バタデンの運転手になって運転席から母さんに手を振るんだよ。母さんはそこの庭から僕を見て、笑いながら手を振り返してくれるよね?
ええ、そうね。お前が電車の運転士さんになったら、母さんは毎日庭に出て、毎日、お前に手を振ってあげようね。とても楽しみね。
絹代はそう答えた。息子は本当に嬉しそうに顔を輝かせた。明日への希望ではちきれそうな輝きだ。それは決して残照ではなかった。」】
**********
そんなふうに、子どもの頃、肇をあたたかく包んでくれていた絹代が行商の途中、バタデンの中で倒れました。肇は店の段取りをつけてから来ることになっていた由紀子を残して、倖とともに島根の実家にもどったのです。
【「昔と同じだな。夏休みになるたびに、父さん、危ないから防波堤から降りろと言い続けてた」
「それ覚えてるんだ」
倖は言葉を発した。笑顔のまま彼女は、父の記憶の中に幼い頃の自分がまだ存在していることが、とても意外だと言うように、目を丸くしてみせた。
「当たり前だろ。覚えているに決まっている。夏になるたびにお前は婆ちゃんの所に行くと騒いだし、だから毎年連れてきてやったんだ」
自分の声に恩を売っているような響きがあると肇は気づく。それを倖が指摘して怒り、また黙ってしまうのだろうと想像したが、倖は笑顔のままうなずくだけだった。
「婆ちゃんが大好きだったの。婆ちゃんは絶対に命令口調で話さないんだよ。防波堤から降りなさい、なんて言わない。降りてきてくれたら嬉しいねえってそういう言い方をする。そして、婆ちゃんは絶対に人が話しているときに時計なんか見ないんだよ」
言われてつい時計で病院へ戻る電車の時間を確認していた肇はハッと顔を見上げる。】
***********
西田了は肇の幼なじみです。了は、宍道湖でシジミ漁をつづけ、仕事が楽しくてしかたがないと思っているのです。そんな了を倖は「シジミマンさん」と呼んで親しんでいました。
【「サッちゃん、大きなったな。幾つになった?」
「大学の三年です」
「そげか! もうそげん大きんなったんか。肇、寂しいじゃろう。もうサッちゃん嫁に出す心配しないといけんけんの!」
「その前に就職ですよ、シジミマンさん」
倖はため息をついてみせる。
「どこも雇ってくれん言ったら、俺と一緒にシジミを採ったらええがや」
了は言い、倖は本気だという顔でうなずいた。
「そしたら婆ちゃんと一緒にいられるね」
肇はその倖の言葉にハッとした。父である俺は自分の仕事、自分の乗った「時間列車」の進んでいくレールの先ばかり気にかけている。なのに娘は自分の進むレールと祖母の走るレールが重なる進路はないのか、と考えているのか? 重ならないまでも併走するレールがあるかもしれないと?】
【娘が了と話していたときのように無邪気な笑顔を見せてくれないことなど、父はまるで気にしていないぞ。他に考えなきゃならない重要なことが父には山ほどあるんだからな。】【娘と気持ちが通じないのは自分の方が娘に対して壁をつくっていたからだ。決して娘から拒絶されたわけじゃないと、そう自分を偽ったほうが、気が楽だ。そう思っているのかもしれない。】
【わかっているのだ。いまのままでは駄目だということは。親友が切り回していた工場を一方的に閉鎖させること。大勢の従業員を退職させること。そして会社の利益とその実績を取り繕うこと。妻と話らしい話もできない日々を送っていること。娘からは信用も愛情も失われていること。自分の人生はすべてうまく行っているという幻想が綻びはじめていること。俺はこのままでいいのかと一日に何回も何回も呆れるほど考えてしまっていること。そして、母親が倒れたこと。広すぎるこの家で母がひとりきりでどんな思いを抱きながら生きているのか、それを直視することができないこと。家の中も庭も畑も、すべてきちんと向き合い美しく保たせている母が、どういう人生の終え方を考えているのか、それを知ろうとすることを拒んでいるということ―。】
【どうすればいいのか肇には見えない。それが見えないうちは余計なことは考えないほうがいい。余計なこと。そう、仕事以外のすべては余計なことなのだ。】【働くことが善であり、忙しいことが善であり、仕事に人生を捧げることが善だった。高度成長時代の日本が、肇の世代にとっては理想の社会なのだから。まあ、もちろん了のような例外もいるにはいるが。】
***********
道すがらの了との出会いを通じて、肇はこんなことを考えさせられていたのでした。肇の中に、何か、変わろうとしているものが芽生えてきたのに違いありません。これは、次の描写によく現れているのです。肇と倖との会話です。
【「夕ご飯食べる? それとも仕事つづけてる?」
訊かれて肇は「食べる食べる。えらく腹が減った」とことさら大げさに言って食卓へと向かった。「すごいな。料理、上手じゃないか」
「それ皮肉かなあ。つくったのは味噌汁だけだよ」
「いや、その味噌汁がさ、うまそうにつくれてる」
言って肇はひとくちすすってみる。「うまい」即座にそう言うつもりでいた。ここで娘の機嫌をとったところで何がどうなるわけでもないのだが、今日の夕食は娘とふたり穏やかな時間を持ちたい。仕事人間で家族も顧みない父親にだったそういうひとときぐらい持てるはずだ。しかし肇はそいうご機嫌取りだめだけの「うまい」が言えない。舌に触れた味、その香りに正直戸惑う。不味いのではない。そうではない。
「・・・・・うまいな、これは・・・・」
「婆ちゃんの手づくりの味噌だよ」
「やっぱ味噌汁はこの味じゃなきゃ嘘だ。どうだ。婆ちゃんに頼んでこの味噌、東京に送ってもらおうか。そうすりゃ、うちでもこの味噌汁が飲めるだろう」
「日持ちがしない、だからいらない。送ってくれなくていい」
「え?」
「お父さんが自分で婆ちゃんにそう言ったんだよ。覚えてないの?」
倖は冷ややかに肇を見た。肇はそういうこともあったかもしれないと思い出す。手づくりの味噌には保存料も防腐剤も入っていない。だからすぐに傷んでしまう。それはその通り。だが・・・。
「保存料や防腐剤が入っている味噌の方が安全だ。お父さん、そう言ったの。お婆ちゃんそれ聞いてどんな顔したか覚えてる?」
・・・・いや、覚えてはいない。
自分の正論を述べることに夢中で、それを聞かされた相手の顔などまるで考えてはいなかったのだろう。
「じゃあ食べたら台所に食器、持ってっといてね。お忙しいでしょうけど、それくらいの時間はあるんでしょう?」
言うと倖は立ち上がる。】
****************
このとき、肇は自分をふりかえったに違いありません。なぜ、母・絹代の手づくりの味噌を東京へ送って欲しいと感じたのでしょうか。ほんとうは自分がこうありたいという自分の心が、この自らの生家で、幼なじみの了や、倒れた母・絹代への思いと交錯し、ほんとうの自分というものに触れようとしたのではないでしょうか。
そんな無意識の思いも、遅れて島根に到着した妻・由紀子との会話によって、微塵に打ち砕かれてしまいます。肇の心が爆発してしまいそうになったとき、一本の電話が肇のもとに入りました。それは、同期の川平の死の知らせだったのです。工場の閉鎖に向けて奔走していた川平が交通事故によって亡くなったのです。肇の手には、難病で寝たきりになっていた川平の息子がつくったという、空に羽ばたく鳥の彫り物が残されました。川平の死、そして、母・絹代の末期癌という事実に直面した肇は、自分の人生のポイントを切り替えようともがいていくのでした。
(6)へつづく 2011.11.30
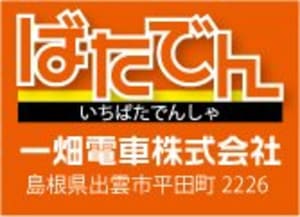
***********************************************************************************
あいあいネットワーク of HRS
ホームページURL:http://aiainet-hrs.jp/
(mail:info@aiainet-hrs.jp)
(コメント欄のメールアドレスとURLは必須ではありません。)


















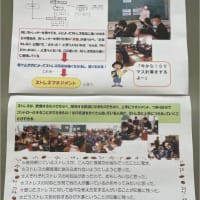






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます