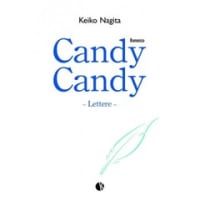キャンディキャンディFinalStoryファンフィクション:水仙の咲く頃
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
By Josephine Hymes/ブログ主 訳
第5章
隔たり
隔たり
ステア、リック、ピーター、ラリーの4人の男の子たちは、車のエンジンの音を真似ようと喉を使って様々なおかしな音を鳴らしていた。食堂のカーペットの模様がステアのミニカーコレクションのための恰好の道路になり、テーブルや椅子の脚は刺激的な衝突が起きる入り組んだ迷路になった。子供たちはしばらくこの遊びに夢中になっていた。
車が衝突するたびに、ステアは修理のために車を整備に出した。ミニカーを保管している箱が修理のためのガレージで、《故障車》をいったんその箱に置き、別の車を取り出して遊びを続けるのだ。そのような修理交換の時に、ステアはお気に入りの車が無くなっていることに気が付いた。コバルトブルーのフォード・モデルTはドアとトランクが開閉し、とても小さいタイアがついていたことから一番のお気に入りだったのだ。
レイン先生はその小さい子供たちが遊んでいるのを見守りながら編み物に忙しくしていた。レイン先生の横では、揺りかごの中で柔らかいブランケットに包まれた赤ん坊が静かに眠っていて、他の子どもたちはポニー先生の授業を受けていた。レイン先生がステアの困惑した顔を見ていた時、表玄関のドアをしっかりとノックする音が聞こえた。
「ぼくがあける、レインせんせい!」 ステアがカーペットから飛び上がって言った。
郵便配達夫だろうと思ったレイン先生は、その男の子にドアを開けるのを任せた。使用人のいる大きな邸宅ではそのようにするのだろう。ステアは大人しかできないような役割を与えられたことにわくわくしていた。
表玄関まで走ると、爪先立ちになって玄関のノブに手を届かせた。扉を開けると、そこにはバートおじさんと同じくらいの背丈の男の人が立っていた。その男の人は体を少し前屈みにして話しかけた。
「どうもこんばんは、ご主人。ここはポニーの家ですか?」 そう尋ねた声にはとても深みがあったので、ステアは、この男の人はヒキガエルでも飲み込んでしまったのだろうかと思った。そして質問には答えず、ただクスクスと笑って頭を振るだけだった。
「いいえ」 ステアはやっと笑顔で言った。
「ご主人、こちらはほんとうにポニーの家ではないのですか?」 その男の人は出来る限り真面目に見えるように努めながら再び尋ねた。
「いいえ、ぼくはこしゅじんではなくて、ぼくはおとこのこです!」 ステアはそう答えると、その男の人の後ろに青い影を見た。
子どもが顔を右に傾けると、男の人もその視線を追って後ろを振り返ったが、その動きで背後にあるものの全体像が現れた。前庭の駐車スペースに自分のお気に入りのコバルトブルーのフォード・モデルTとまったく同じ車を見つけて、ステアの目は驚きで見開かれた。目の前の車はミニカーとは違い通常の大きさだったが、子どもの有り余る想像力にとってそんなことは関係なかった。
「ぼくのくるま!」 ステアは驚きで息をのんだ。
「何だって?」 男の人はおもしろがりながら聞いた。
「ぼくのくるまをもってきてくれて、ありかとう!」 その子は満面の笑みを浮かべて説明すると、純粋な興奮とともに男の人の足に抱きついた。
「おいおい、そんなに興奮しないでくれよ。ただのレンタカーだよ」 男の人は静かに笑った。
「サンタさんのおてつだいさんですか?」 ステアは、男の人が言ったことにはお構いなく聞いた。
「まいったな!」 男の人は心から笑うと自己紹介が必要だと思い、帽子をとって子どもの目線にしゃがんで言った。「はじめまして。わたしはテリュース・グレアムと申します」 テリィは右手を差し出した。
大人のように扱われることに慣れていないステアは、この状況すべてに可笑しみを感じた。
「こんにちは、クレムさん」 ステアはもっとクスクス笑いながらテリィと握手をした。
「クレムでなくて、グレアムだよ」 テリィはゆっくりと繰り返した。
「クラアム」 子どもがそう言うと、テリィはもう一度笑った。
「G(ジー)で始まるグレアム」 テリィは説明を試みたが、子どもの当惑した表情を見て、その子が字の綴りを知るにはまだ幼すぎることに気が付いた。
「G? ミスターG?」 目にはまだ微笑を浮かべながら、子どもが顔をしかめて聞いた。
「わかったよ。きみがそうしたいならミスターGと呼んでくれ」 テリィはあきらめた。
「あらまぁ! あらまぁ!」 家の奥から女性が驚きの声をあげた。「グランチェスターさん!」
「レイン先生、事前のご連絡もなしにおじゃまして申し訳ありません」 テリィはレイン先生に丁寧にお辞儀をしながら言った。
「何を言っているのです! じゃまだなどと思うはずがないではありませんか。どうぞ、お入りになって」 レイン先生は手を差し出しながら温かく迎え入れた。テリィは握手をする代わりにその手にうやうやしくキスをした。もしテリィがレイン先生に気に入られていなかったとしても――すでに気に入られてはいたのだが――その動作でレイン先生の心をとらえたことは確かだった。
レイン先生に案内されてポニーの家の中に入ると、一目見て大きな変化に気がついた。かつて居間だった部屋が現在では玄関ホールになっていて、半開きの扉の向こうに背の高いクリスマスツリーが飾られた大きな居間が見えた。二人は居間へと入っていったが、レイン先生はテリィをそこに案内せずに、そのまま居間と同じくらいの広さの食堂へと進んだ。そこでは小さな子どもたちが、カーペット全体に散らばったおもちゃで遊んでいた。
「グランチェスターさん、居間で正式にお迎えする代わりに、こちらまで来ていただいて申し訳ありません」 レイン先生は説明した。「小さい子どもたちを誰も見ていないところに長く置いておくわけにいかないのです」
レイン先生は揺りかごの隣の椅子に座りながら、テリィに正面の椅子をすすめた。
「何かお飲みになりますか、グランチェスターさん? コーヒーかココアはいかが?」
「ココアなど久しく飲んでいませんからいただきたいですね。レイン先生さえご迷惑でなければ」
「戻ってくるまで子どもたちを見ていて下さいます?」 レイン先生は意味ありげに子どもたちの方を見ながら聞いた。
テリィは小さい男の子たちが床で遊んでいる様子を見た。
「大丈夫だと思います、レイン先生」 テリィは丁寧に返事をしたが、自分の子守りの腕前には若干の不安があった。
「よかったわ。すぐに戻りますから。わたしがいない間にイザベラが泣き出さなければいいのだけど」 台所へと急ぎながらレイン先生は言った。
「イ、イザベラ?」 部屋の中で遊んでいるのは男の子だけだったのでテリィは混乱して聞いたが、レイン先生はすでに扉の向こうへと消えてしまっていた。
「イザベラはそこだよ!」 ステアが揺りかごを指して言った。立ち上がってその揺りかごの方へ歩いていくと、テリィはその中で小さな赤ん坊が平和そうに眠っている姿を発見した。
「この子か。とても静かそうに見える赤ちゃんだけど、よく泣くのかな?」 テリィは男の子に聞いた。
「いつもだよ!」 別の男の子が答えた。
「そうなのかい?」 テリィはレイン先生がすぐに戻ってきてくれることを願いながら台所の扉を見て聞いた。「この子が泣いたらいったいどうしたらいいんだ?」
「わからないよ!」 さっき答えた男の子が肩をすぼめながら言った。
「キャンディおばちゃんは、あかちゃんをこんなふうにだっこするよ」 ステアはおもちゃの車を手に持って、赤ん坊をあやす真似をして見せた。
「キャンディおばちゃん?」 テリィはその男の子をもう一度見ながら繰り返した。その温かな笑顔と丸い眼鏡の後ろの明るい茶色の瞳には見覚えがあった。心の中で微笑みながらその子の顔を注意深く観察した。(この子がダンディー・ボーイの息子ってわけか) テリィはそう考えると、子どもの父親がその辺にいるかもしれないという可能性に警戒した。今ここでアーチーボルド・コーンウェルと気まずい再会をしたくはなかった。テリィは、今はまだ心が浮き立つ再会を期待していたのだ。キャンディの親せきにはそのうち顔を合せる日がくることはわかっていたが、それはもう少し後のことにしたかった。
「ステア」 男の子に呼びかけるとその子はすぐにこちらを向いた。テリィは自分の推測が当たっていたことを確認し、気さくに聞いた。「パパとママはどこにいる?」
「おうちだよ」 ステアはありのままの答えを返した。
「ここに一人でいるのかい?」 遊びを再開した子どもたちの横のカーペットに座りながらテリィは聞いた。
ステアは頭を思いっきり横に振りながら再び笑顔を見せた。
「キャンディおばちゃんがいっしょだよ。それからポニーせんせいと、レインせんせいと、ピーターと、リックと、ラリーとシーザーとクレオパトラも」 ステアは名前を言うたびにうなずきながら教えた。
「それで、きみのキャンディおばちゃんはどこ?」 テリィは目を輝かせて眉を持ち上げながら聞いた。
「おしこと」 ステアはそう反射的に答えると、しばらく間をおいてからとても重要な話をする口調になって付け加えた。「しってる?キャンディおばちゃんは、ころんだところをはりでぬえるんだよ」
「ぼくもぬってもらったけど、泣かなかったよ」 これまで一言も言葉を発していなかった別の男の子が、包帯の巻かれた足を見せながら話に加わった。
「それはすごい」 急に話題が変わる子どもたちの会話のペースは新鮮で、テリィは笑顔を抑えながら返事をした。
その時台所の扉が開き、レイン先生がやっとトレーを持って戻ってきた。テリィが運ぶのを手伝うと、ほどなくしてその突然の訪問に居合わせた全員がココアをおいしく飲んでいた。レイン先生は先ほどの会話の続きを始めた。
「ポニーの家を訪ねていただいてとても嬉しいですわ、グランチェスターさん。でも、あなたがお会いになりたい人は今外出しているのですよ」
「キャンディスに会いたいという望みを持ってこちらに伺ったことは否定できませんが、ぼくをこの予告なしの訪問という無礼な行為に駆り立てたのには別の動機もあるのです、レイン先生」
「そうなのですか? その動機というのはいったい?」 レイン先生はテリィの折り目正しさを心地よく感じながら聞いた。
「キャンディスが以前手紙の中で、ポニー先生に何か特別なクリスマスプレゼントを贈りたいと言っていたので、ぼくが公演旅行の合間にその贈り物を入手するということになったのです。それで今、メッセンジャー件荷物の配送人としてぼくがこうしてここにいるのです」
「それはとてもありがたいお話しですけれど、キャンディはそこまであなたにご迷惑をかけるべきではなかったですね」
「迷惑だなんてことはありませんよ、レイン先生。贈り物の購入はぼくが自分から申し出たことですし、特配便で送ることも伝えてあったのです。ただ、それがどのような特配なのかという部分は伝えていませんでしたが」 テリィはいたずらな光を目に浮かべ、少し笑顔を見せた。
「ということは、今夜驚かされるのはポニー先生だけではないのですね」 レイン先生は余念なく言った。
時間はたっぷりあることがわかると、レイン先生はテリィの公演旅行についていろいろな質問をした。テリィは母親以外の人間と長い会話をすることに慣れていなかったが、なぜかその修道女といることは心地よかった。キャンディが示す他者への真正の興味が、レイン先生の会話の術の中にも見られた。テリィはいつもの寡黙な自分を忘れ、レイン先生に公演旅行の話をたっぷりと聞かせた。ただし、キャンディとの再会の部分は細かい詳細を抜きに話した。
テリィの話は色彩豊かで、レイン先生はその話にあまりにのめり込んでしまったために、眠っている赤ん坊が体を動かし始めても揺りかごをロックするのを忘れてしまったほどだった。床で夢中に遊んでいた子どもたちでさえ、話の内容が耳に入ってきた。
どの位の時間が経ったのか誰かが気づく前にベルの音が鳴り、子どもたちの笑い声と活発な足音が授業の終了を告げた。程なくして20人前後の子どもたちの一群がどこからともなく居間に現れた。大勢の子供たちがちょこちょこ動き回る居間は、もはや広くは感じられなかった。子どもたちの登場のすぐあとに、明るい笑顔と丸いからだのポニー先生が入ってきた。テリィはその姿を見て、白くなった髪以外は1913年の冬に初めてここを訪れたときの思い出のままだと思った。
その老女は居間に立っている人物に気が付くと、驚きで口をぽかんと開け、かけていた眼鏡を一瞬はずしてまたかけ直した。両手で顔を挟んだが、それでもまだ言葉が出てこなかった。
「こんばんは、ポニー先生。またお会いできて光栄です」 お互いに相手を認識すると、テリィが最初に挨拶をしてお辞儀をした。
「まぁなんてことでしょう! グランチェスターさんなのね?」 ポニー先生は、社会の慣習などにはもはや囚われないほど長く生きた人間特有の、あけっぴろげな好奇心を示しながらその背の高い男性に近づいた。「まぁ、ほんとうに大人になって。ほら、よく見せてちょうだいな。間違いなく大人の男性ですよ。ポニーの家にようこそ来てくれました」 ポニー先生は普段通りの母性的な温かさでテリィを抱きしめ、よろこんで迎えた。
テリィは無防備に、ポニー先生の愛情深い抱擁を言葉もなく受け入れた。母親以外の人間にそのような悪意のない優しさでもてなされるのは、テリィには不慣れなことだった。初めてポニーの家を訪れたときにも、ポニー先生とレイン先生は親切に温かく迎えてくれたのを覚えている。だがその時は、突然扉の前に現れるまで二人は自分の存在さえ知らなかったので、会話の間にもある程度のよそよそしさが残っていた。しかし今は、ポニー先生は長い間留守にしていた大切な子どもが帰ってきたように自分を迎えてくれている。テリィはその歓待に圧倒されながらも、予想外な心地よさを感じていた。
「あなたはほんとうに、このわたしを驚かせてくれましたよ」 抱擁を解きながらポニー先生は言った。「でもわたしのような年老いた人間にそんなことをしてはいけませんよ。心臓に悪いですからね」
「それはお許しいただかなければなりません。ぼくはポニー先生の娘さんの使いで来たのです」 テリィは説明した。「娘さんの代わりに荷物を届けに来ました」
「娘というのはキャンディのことね?」 ポニー先生は興味を持って聞いた。
「キャンディがグランチェスターさんにポニー先生へのプレゼントを頼んだのですって」 ポニー先生がクリスマスの日の朝までプレゼントを開けずに待っていられないことがわかっていながら、レイン先生が横から言った。
「ほんとうですか? わたしのために何とご親切な、グランチェスターさん!」 ポニー先生はそう言って喜ぶと、少し間を置いてから口調を変え、いたずらっぽくウィンクしながら聞いた。「そのプレゼントを今見ることはできるのかしら?」

キャンディは自分の目が信じられなかった。魂は確かにテリィを恋焦がれていたけれど、連絡を取り合うのは彼の公演旅行が終わるまで待たなければならないという考えに、自分自身を納得させていたのだ。公演旅行が終わった後の予定についてはっきり尋ねた時に、テリィが休暇中に自分に会いたいと言ってくれなかったことに対しても、ある意味がっかりしていた。キャンディは、まだ二人の関係が確かなものではないから、きっとテリィは次にどうしたいのかを考える時間と距離が欲しいのだろうと考えていた。アードレー家に届けてくれたメッセージとそれに添付されていた写真にはドキドキしたけれど、最近では疑いの気持ちが頭をもたげていた。自分に対するテリィの関心が、時間の経過とともに薄れてしまったのではないかという密かな思いが、夜の深い眠りを妨げていた。
――いくらわたしがかつての学生時代の思い人だったからといって、彼のようにすてきで有名な男性が、こんなどこにでもいる田舎娘を相手に真剣な関係を持とうとしているなんて本気で思っているの……? 眠れない夜には心の片隅に深く根ざした不安感が目を覚まし、一度ならず何度もそのような心の声を耳に囁くのだった。――公演旅行の最後の週に、彼が魅かれるような女性に出会ってしまったとしたら……?
そんな静まらない思考に何日も悩まされてきたけれど、今テリィはポニーの家の居間に座りながら、虹色にきらめく瞳で自分を見ていた。キャンディの困惑した様子を見てテリィが楽しんでいることは、そのいたずらっぽい薄笑いから明らかだった。さらに悪いことに、そのならず者がポニーの家の全員を魅了してしまっていたことが、彼がまるで自分の家にいるように馴染んでいる様子から伺えた。
「公演旅行でお疲れのところをわざわざ訪ねて下さったグランチェスターさんに会えて嬉しくないのですか、キャンディ? この方はわたしにこの心地のよい贈り物を届けるためだけに、サンフランシスコからはるばる来てくれたのですよ」 キャンディからの贈り物に快適に座りながらポニー先生は言った。テリィの姿を見てうっとりと喜びに浸る感情と急激な怒りの感情で混乱している表情がキャンディの顔全体に広がっているのを、ポニー先生は簡単に読み取った。
キャンディは努めてテリィから目をそらしポニー先生が腰掛けている椅子を見ると、その美妙さを認めないわけにはいかなかった。カラーとバラの花の彫刻が背もたれの枠とひじ掛けの部分に精巧に彫られ、堅いオーク材で作られた揺り子は見るからに安定していて強靭そうであり、椅子と背もたれは柔らかい生地の革張りが施されていた。
「二人にお礼を言わなければなりませんね。新しい居間になって古い椅子を交換したいとは思っていましたが、買い物に行く時間がなかったのです。あなたがたの思慮に感謝しますよ」 ポニー先生は心から感謝した。
「わたしからもクリスマスプレゼントのお礼を言わなくてはいけないわね、キャンディ」 レイン先生はクリスマスツリーの下に置いてある四角い箱を指さしながら言った。「クリスマスまでは開けないでおくつもりよ」
キャンディはテリィに視線を投げかけると、レイン先生へのプレゼントは彼が用意してくれたのだとすぐに理解した。
「ポニー先生もレイン先生も、わたしの代わりにプレゼントの手配をすべて引き受けてくれたテリュースにお礼を言ってちょうだい。代金も全部立て替えてくれているんだから、わたしがちゃんとお金を返すまで、わたしへのお礼は必要ないのよ」
「構わないよ、キャンディ」 テリィが言うと、その時彼の顔がほんのり赤くなったことにキャンディは気がついた。
「ミスターGはぼくにもプレゼントをくれたよ、キャンディおばちゃん」 ステアが横から口を挟んでみんなを驚かせた。「ぼくのあおいくるまは、キャンディおばちゃんのくるまとおんなじくらいおおきくなったよ」
「それはどういう意味、ステア?」 その子がテリィにあだ名をつけていたことに驚くと同時に、発言の内容に困惑しながらキャンディは聞いた。
「長い話さ」 テリィは含み笑いをしながら言った。
「そのお話は夕食後にしましょう」 ポニー先生はそう言って話をさえぎってから付け加えた。「キャンディ、グランチェスターさんはわたしたちの招待を快く受け入れてくださって、休暇をこの家で過ごすことになりました。最初は辞退されたのですが、わたしが是非にと強くお願いしたのです。グランチェスターさんにクリスマス休暇のご予定がなかったなんて信じられますか?」
「へぇほんとに? こんな忙しい有名人なんだもん、誰もそんなこと思いもしないわね」 キャンディは声に皮肉を込めて言った。
「そうですよ! これで数日間はこの方をわたしたちで独占できるのですよ。夕食の準備をする間、キャンディはグランチェスターさんをゲストルームにご案内して差し上げてね」
ポニー先生のこの指示で、テリィはステアを抱き上げると細心の注意を払って床に降ろした。瞬間、キャンディは自分の愛する男性が子どもを世話する姿を見て、心が溶けるのを感じた。それでもまだ、テリィを無条件に歓迎するか、もしくは自分を心配させたことを叱って冗談を言うか決めかねていた。
(憎たらしいヤツ! ここまでわたしを訪ねるくらいに思ってくれていることがわかってたら、この数週間ぐっすり眠れたのに……そうでしょ?) テリィの目に悪魔的な光を見て、苛立ちを募らせながらキャンディは思った。テリィがいたずらの成功を喜んでいることも、キャンディにはわかっていた。
「わたしについて来てください」 キャンディは頭をうなずいて、さっとテリィに背を向けると廊下を案内した。
テリィは先生たちに退出の挨拶をすると、部屋の隅に置いてあったスーツケースを掴んでキャンディの後を追った。テリィには、何の予告もなしに自分が来たことにキャンディが腹を立てていることはわかっていた。どのくらい自分に腹を立てているのかは気づかないふりをするとして、怒りを宿したその瞳を見て楽しもうと思っていた。
間もなく二人はポニーの家の増築された一角に到着し、キャンディが素っ気なく一つの扉を開けた。その部屋は質素だったが、新しいスギと、洗いたてのリネンと、ナイトテーブルの上の壺に入った乾燥したラベンダーの穂の香りがした。テリィは、疲労困憊の公演旅行の後にこれ以上の魅惑的な静養場所は他にないだろうと思った。手作りのパッチワークキルトカバーがかけられた大人用のベッドを見て、この2日間ちゃんと寝ていなかったことを思い出した。
腹を立てていたキャンディは、そんなテリィの疲労の色には気づかずに、テリィがスーツケースを床に置くやいなや向かい合った。
「つまらないゲームはもう止めて、テリュース。ここに来る気があったなら、どうしてそう言ってくれなかったの?」 キャンディはそう冷ややかに言い放ち、さらに小言を言って聞かせるつもりだったがテリィの素早い動きに中断された。キャンディが阻止する前に、テリィはその息が顔にかかるほどの危うい距離まで近づいた。
「でもそうしてたら、こんな風に怒りで燃えあがる瞳は見られなかった」 テリィはキャンディの小柄な体に屈みながら耳元でささやいた。「それに、これは眼鏡をかけた小さな紳士がおれのライバルになると思わせたお返しさ」
「そ、それって……ステアのこと?」 キャンディは驚いてそれ以上口がきけなくなった。
「そうだよ。きみのかけ持ちの仕事について不平を言わないボーイフレンドのことだよ、キャンディ。おれたちシェークスピア劇の役者は、よく計画された執念深いたくらみが大好きなんでね」 テリィは得意そうにニヤニヤ笑いながら素直に認めた。
ピッツバーグでの夜に自分が彼をもてあそんだことを許していなかったのだと気づいて、キャンディは初めてすべてを理解した。
「それは……ちょっとしたジョークじゃない!」 キャンディは人差し指を立てながら自分を弁護した。追い詰められていることがわかると、その目は怒りからパニックへと変わっていた。テリィはそのどちらの表情が自分にとってより魅力的か決めかねて、本能的にさらに近づいた。
「テ、テリュース! 止めて……」 キャンディは両手をテリィの胸に当てて弱々しく抵抗しながら口ごもった。
「おれはきみにとってテリュースなのか?」 テリィはキャンディの耳たぶに唇で軽く触れ、その体に熱を送りながら聞いた。「ピッツバーグでは、おれはまだテリィだったんじゃないのか?」
キャンディは、心臓の鼓動が一秒一秒早くなるのをはっきり感じた。テリィはあっけなく両腕でキャンディを抱きしめると、その抱擁を強めた。キャンディはもはや抵抗するのは不可能だと知った。キャンディが自分に身を任せているのを感じたテリィはもっと大胆になり、羽のような口づけで彼女のこめかみや頬に火をつけた。
「会いたかった!」 テリィはこれまでとは全く違った口調でため息をつき、その息がキャンディの顔に燃えるような跡を残した。
「わたしも会いたかった、テリィ」 キャンディは目を閉じて、これまでの疑いや眠れぬ夜のことを一瞬にして忘れながらため息と共につぶやいた。
「それでいい」 テリィは微笑み、再びキャンディの唇を奪った。
二人は前よりも濃い口づけを交わした。テリィの唇がキャンディの唇を包み込むようになで、優しく触れる度にその力が強まっていった。キャンディの唇が思いがけず開くと、淡い一瞬テリィはためらったが自らの情熱に任せ中へと進んでいき、初めてそのすべてを味わった。
キャンディにとってそのような形で侵入されるのは初めてのことで、思いもよらなかったことであると同時に魅惑的だった。口づけが、このように親密なものになり得るとは想像したこともなかった。経験不足ではあったけれど、その時までにテリィへの思いは自分自身にもはっきりわかっていたので、キャンディは二人の愛情表現がより深まっていくのを歓迎した。
互いの舌が触れあいテリィに愛撫されると、キャンディはかつて経験したことのない特殊な力に取りつかれたように、テリィの首に自然に腕を回してそれに応えた。テリィは今ではキャンディを両腕できつく抱きしめていたので、胸も腰も全身がこれ以上ないほどぴったりとテリィの体に押し当てられていた。そしてその時、未知のぞくぞくとした感覚が初めに体の中で溶け、次にそれが腹部を震わせるのを知覚した。キャンディの呼吸が一秒一秒荒くなり口からうめき声が漏れると、それがテリィを一層興奮させた。テリィはキャンディの反応に歓びを感じていたが、そろそろ止めなくてはならないこともわかっていた。テリィの脈は早まっていて、キャンディが甘く身を委ねている状況に、間もなく全身が慎み深さとは程遠い反応をしてしまうだろうと思っていた。口づけを始めた時には、まさかこんなにわずかの間に熱くなってしまうとは予想していなかった。急な形で離れたくはなかったので、テリィは少しずつ力を緩めながら、ゆっくりと口づけや抱擁を解いていくことにした。
テリィはようやく唇を離すと、目を閉じたまま額をキャンディのおでこに付けた。顔にキャンディの甘く深い吐息を感じた。自分の肉体的な愛情表現をキャンディがこんなにもすんなりと受け入れてくれたことは、テリィにとって嬉しく新鮮な感覚だった。それでもまだ、今ここで起きたことはこれから起こりうることの前奏にすぎないこともわかっていた。テリィは無意識にほほ笑むと、目を開けてキャンディを見た。
「さぁアードレーのお嬢様、ぼくにはまだフェンシングマスクが必要でしょうか?」 テリィがからかうと、キャンディは頭を後ろにのけぞらせて笑い出した。テリィはキャンディが朗らかに笑う姿は何よりも愛らしいと思った。
「わたしたちがそんな時期をとっくに過ぎてしまったことは、あなたには十分わかっているはずよ、グレアムさん」 キャンディは、ピッツバーグで初めて気づいた強い光がテリィの瞳に輝いているのをじっと見ながら答えた。その瞬間ウィリアム・ブレイクの詩が思い出され、これ以上テリィの瞳を見続けたらどうなってしまうかわからなくなり目を伏せた。「そろそろ行かなくちゃ。わたしたちがいないとポニー先生とレイン先生も夕食を始められないわ」 これ以上長居はできないと思ってキャンディは言った。
「そうだね」 テリィもしぶしぶ同意した。
テリィがゆっくりと両手を離す時、その手がキャンディの腕をなぞった。制服の長袖の上からでさえ、テリィが触れた場所に震えが走った。テリィがキャンディの手を取り部屋を出ると、二人は何も言わずに、手をつなぎながら食堂へと戻って行った。

*引用の範囲を超えた当サイトのコンテンツの無断転載はお断りいたします