時代が移り変わるとき、さまざまな新しい概念が生まれます。それらは、既存の使いやすい言葉で伝え切れない場合が多いため、言葉で表現をしたときに、誤解を生む可能性が生じます。そのなかで、「融合」という言葉から、私が感じることを少し整理してみたいと思います。
近年、いろいろな「融合」についての議論があります。私自身もブログのなかで、いくつかの融合について言及をしています。例えば「コンピューターとネットワークの融合」、「制作者と視聴者の融合」、「メディア別コンテンツの融合」、「通信と放送の融合」といった各種の融合については、既に触れている通りです(「新しい産業構築に向けて」参照)。
私は、このときの「融合」という言葉について、その正確な意味をきちんと理解した上で、使っているつもりなのですが、今までのこの言葉の一般的な使われ方が、若干、それとは異なるようで、受け止め方が私の意図とずれているような気がしています。
「融合」の意味は、読んで字の如く「融けて合わさる」ということです。つまり、複数あるものが、完全に融け合って、一つのものとして交ざり合うということであり、そこには一切の垣根がありません。もう少し踏み込んで言えば、AとBが融合された後のかたちは、AでもなくBでもない、まったく新しいCというものに化けているということです。さらに別の言い方をするならば、「融合」とは、古いものの消失を伴った新しいものの誕生であるということです。
例えば、「通信と放送の融合」という言葉がありますが、現在の大手事業者の試みは、あくまでも「通信と放送の組合せ」であり、「融合」ではないと考えます。一つの携帯電話端末に電話やメールといった「通信」と、ワンセグのような「放送」の機能を載せているのは、単にそれぞれのサービスを組み合わせて、提供しているだけであり、けっしてそれらが「融合」されているわけではないと思うのです。そういう意味で、ニコニコ動画の試みは、限界を抱えながらも、一つの「通信と放送の融合」の実践であり、素晴らしかったのではないかと思います(「通信と放送の融合」参照)。
残念ながら、AとBの「融合」と言ったときに、まったく新しいCをイメージできない限りにおいて、それらはどうしても、AとBの組合せとして理解するしかありません。「融合」という言葉を使われている多くの方々には、Cをイメージしないまま、単なるそれらの組合せを「融合」と呼んでしまっている可能性がある点、注意を払って見てみると面白いかもしれません。
例えば、私が知るなかで慎重な方々は、むしろ「通信と放送の融合」はできないなどとおっしゃります。それはその方々が、まったく新しいCをイメージできていない以上、安易に「融合」という言葉を使うべきではないということに気付いているからだと、私は思うのです。
蛇足ですが、つい先日「iPhone」なる端末が発売となり、日本で大きな話題となっています。これは、あくまでも私見ではありますが、私はこの製品が、上記のような「融合」を実践したものであるとは考えておらず、一時的にブームにはなっても、けっして次時代のコンピューターやネットワークを担っていくような代物ではないと思っています。理由は、あくまでも通信業、あくまでも製造業、あくまでもコンテンツ業、それぞれの収益を満たそうというビジネスであるからです。各種の報道から、この事業に関係した方々の大変な努力は感じられるので、その点については、率直に敬意を表したいと思います。しかし、ビジネスとしては、けっして次時代型の「融合」ではなく、それぞれの業態で儲けようとする組合せの構図から生み出されているという点で、非常に大きな限界を感じるのです。
私は、次の時代においては、産業界でさまざまなものが融合していくと考えており(「新しい産業構築に向けて」参照)、「コンピューターとネットワーク融合」の結果として、まったく新しいコンピューターが誕生するであろうと考えています。そして、そのコンピューター端末の考え方を表現する言葉として、私はたまたま「シン・クライアント」という言葉を使っています(「シン・クライアントの潜在力」参照)。しかし、「シン・クライアント」という言葉は、だいぶ使い古されており、この言葉を使うことで、受け手側に、特定の異なるイメージを与えてしまっているようです。
ある方からは、私の新しいコンピューターにおける端末の概念について、「シン・クライアント」はなく、「SaaS(Software as a Service)」という言葉を使ったほうがいいというアドバイスをいただいたこともあります。しかし、どちらにしても、既存の特定のイメージを与えてしまうという意味で、どちらも同じようなことになるような気がしています。
私が「シン・クライアント」という表現を使っているのは、その和訳である「薄い端末」という概念が、これからのコンピューター端末の考え方として、時代の流れに合っており、これをゼロベースの発想で組み上げることが大切だろうと考えているからです。
これに対して、一般的に「シン・クライアント」という言葉は、重いコンピューターをいかに「薄い端末」に削り落としていくかという考え方で、使われていることが多いようです。人によっては、「シン・クライアント」という言葉に、分厚い端末をいかに削り落とすという「マイナス」の印象や限界を感じる方々もいるようです。言葉とは、つくづく難しいと思うのですが、そういう意味で、私が考える新しい端末については「シン・クライアント」ではなく、別の言葉を作る必要があるのかもしれません。しかし、残念なことにそれに相応しい言葉が思いつかないため、しばらくの間は、「シン・クライアント」という言葉を使っていこうと思っています。
「融合」していくということは、何とも厄介なことです。融合した先には、まったく別のものが生まれるであろうことを理解しながらも、それをなかなか既存の言葉で、うまく表現することができないのです。しかし、だからと言って、何の表現もしないというのも性質が悪いと思いますので、誤解を恐れず、ひとまず通じる言葉を使って、これからも私が考えていることについて、少しずつ整理していきたいと思うのでした。















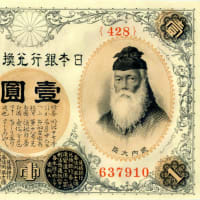
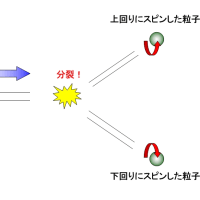
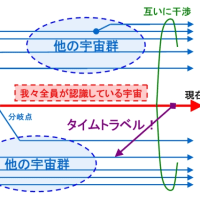
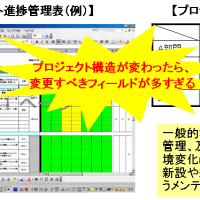
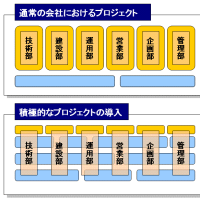






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます