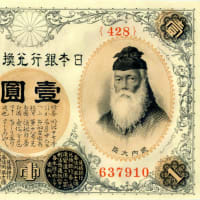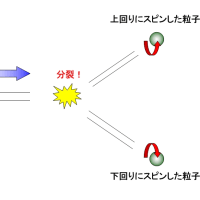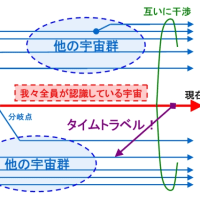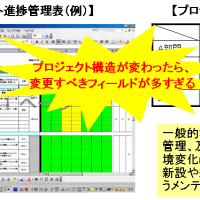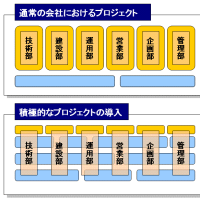サラリーマンの方々に問います。「あなたにとっていい会社とは?」
「人を大切にする会社」、「収益性の高い会社」、「将来有望な会社」、「夢のある会社」、「ビジョンのある会社」、「顧客から愛される会社」・・・。
いろいろな意見が出てくることでしょう。また、せっかく働くのであれば、やはりいい会社で働きたいと思うでしょう。
しかし、「いい会社」を選ぶということは何も社員だけに許されている特権ではありません。会社からみたときにも、まったく同じように会社にとって「いい社員」を求めるものです。「いい会社」は当然「いい社員」を求めます。「いい会社」は、他のどんな会社よりも、入社してくれた人々に対して、「いい社員」になってくれることを願います。
すなわち、「あなたにとっていい会社とは?」という質問に対して求めれば求めるほど、その会社は個人としてのあなたに厳しく求めてくるのです。「いい会社」で働くということは、各社員が「いい個人」であることを求められるということなのです。
企業は人なり。
「人を大切にする会社」を望むあなたは「人を大切にする人」でしょうか。
「収益性の高い会社」を望むあなたは「収益を上げられる人」でしょうか。
「夢のある会社」を望むあなたは「夢のある人」でしょうか。
「顧客から愛される会社」を望むあなたは「顧客から愛される人」でしょうか。
こう考えると、個人が会社に求める前に、まず自分自身がそれを求めるだけの人になることがいかに重要かが分かります。会社のあり方を論じるより先に、まず個人が、本当に社会にとって必要とされるような大きな夢を持っているか、会社のあり方を論じるほど、自分自身が個人のあり方を理解しているかが重要になってくるのです。
個人のあり方として、たとえば単に、自分は「社長になりたい」、「年収XXXX万円を目指したい」、「カリスマ経営者になりたい」といった価値観で、仕事を決めようとする人々がいます。しかし、そのような利己的な価値観で仕事をしていると、困難に直面したときに簡単に諦めるようになってしまいます。利己的な動機だけから発する仕事をしているとき、自分が諦めて迷惑するのは自分自身でしかありません。そこに社会は関係しません。
しかし仕事をする動機として、「せっかく自分が、この世で生きているんだから、何か社会に役に立つことをしたい」、「これをやらないと、社会に住まう人々が困ってしまう」といったことを考えると、そのために仕事をすること、そして生きることは、自分自身だけの問題ではなくなります。仕事をやり遂げるかどうかは、もはや自分だけの問題ではなく、社会全体の問題となり、たとえ困難な問題に遭遇したとしても簡単に諦めることができなくなってしまうのです。
仕事をしようと思うとき、このような社会に対する思い、人々の幸せを願う思いを具体的な夢やビジョンとして捉えることができたら、その人はその実現のために、非常に強い人になることができます。
「いい会社」は、そういう夢やビジョン、信念をもった人を求めます。「いい会社」は、個人に対して、各自が夢やビジョンをしっかり持って、それを実現するために、大いに会社を利用してくれることを願います。個人は、社会のために貢献したい、人々を幸せにしたいという願いから発した、自らが持つ大きな夢やビジョンを叶えるために「いい会社」に入って、それらを実現していくのです。
「いい会社」とは、そうした多くの個人の夢やビジョンをすべて受け入れ、そのなかで共通する部分を、単に会社のビジョンとして掲げるだけです。そして会社自身は個人の夢やビジョンを実現するための道具となって機能することを望みます。単なる道具であるから、主体はあくまでも「個人」となります。
こうした構図の中にある会社の危機というのは、個人の夢にとっても危機であり、個人が思い描く理想の社会にとっても危機となります。会社の危機は、けっして会社の問題だけではなく、各個人の夢の危機を意味するのです。だから、個人は会社の成功のために一生懸命働くわけです。
「いい会社」に集う「いい個人」にとって、会社の成功は、自分の夢の実現のための必要な一歩であり、社会にとっても幸せの増大を意味しています。このとき会社、個人、社会の利害は完全に一致します。
また「いい会社」は、会社そのものの存続を目的とはしません。「いい個人」が集まり、各自の夢を実現することを通じて、結果的に会社が発展すればよいだけのことです。大事なのは、「いい個人」がそこに集まり、社会のために価値を出していくというところにあるのです。
しかし現実では、なかなかこうはなりません。「いい会社」のあり方は理想論であり、夢ばかり追う「いい個人」などなかなか存在しないと一蹴されてしまいます。だからこそ、「いい会社」は「いい個人」を集めきれないし、「いい個人」もなかなか「いい会社」にめぐり会うことができないのです。現代社会では、会社は資本主義を基盤とした競争ルールのなかで成り立っています。資本主義のシステムがあってこそ、社会があり、会社があり、個人がある。これが「いい会社」と「いい個人」が、なかなか出会えない原因でもあります。
そもそも資本主義とは何か。経済に価値観の主眼を置き、一定のルールに則って、社会に最適な価値を提供する仕組みではありますが、本当に社会にとって、求められる価値の提供を保障できるほど、今の資本主義は万能ではありません。資本主義を否定する必要はありませんが、それですべてが解決すると考えるべきではないでしょう。
その資本主義のなかで、会社は既存の事業を守るためにサービスを提供していないでしょうか。業界や会社、株主の都合による顧客不在の経済活動はしていないでしょうか。会社が「いい個人」が働けるような度量を持てずにいないでしょうか。
こうした問題に関連して、たとえば「会社は誰のものか」という問いがあります。
株主のため、経営者のため、従業員のため、社会のため・・・。現代社会では、未だにこのような根本的な議論すら整理できていないような状況にあります。こうしたなか、今の資本主義の枠組みのなかで、本当に「いい会社」、「いい個人」が存在しうるのでしょうか。
答えはYesであると思います。資本主義のルールのなかでも、そのルール上の成功だけには縛られない、新しい価値観と夢を持った「いい個人」は必ず出てくるし、それらの人々が集える「いい会社」は必ず生まれてくるでしょう。
そうした輪が、広がっていったとき、今の資本主義のあり方そのものが大きく変わり、あらゆる個人、会社、そして社会の利害がピッタリと一致した、新しい時代の枠組みができ上がっていくのだと思います。