短歌はおおよそインターネット上で読んでいる。主にTwitterで、ブログやサイトも巡る。短歌系のbot(自動Tweetシステム)もさまざま斜め読みしている。個人的には「歌会たかまがはらbot」に好みの作品が多く、ここから作品を知り、名前を覚え……となることも少なくない。近頃は興味が高じて若手の歌集を買うようになってきた。「ニューウェーブ」「枡野浩一」「俵万智」というある種「いかにも」な我が家の本棚に、いきなり「新鋭短歌シリーズ」が加わった。これもまた「いかにも」な流れかもしれない。
そんな私としては、「現代短歌」は楽しそう、盛り上がっているなぁと日々感じている。ネットプリントの知らせや企画タグを見ない日はなく、合評も盛んな模様。 諸先輩方を含めた議論の一端を垣間見たり、ネットで綴ってきた方がオフラインの歌会や結社へと踏み出していく様子をこっそり眺めていると、子規が……口語で…… というような話などは、どこか別世界の御伽噺のような気がする。死んだほろびた、という実感がない。「現代詩」にもいえることかもしれないが、この広がりから、やがて深みや高みにハマッていく人が現れればよいのだろうな、そうなるのだろう、と思う。
さて。あるときタイムラインに黒崎立体氏(※)の短歌が流れてきて、驚いた。当時まだ単に「詩の方」だと思っていたせいでもあるが、作品に心惹かれて。
きらいだし(きらわせんなよ)罰として蝉の死がいを拾って帰れ
信号を無視して駆けてゆくねずみを人間たちが青白く見る
手の中の檸檬が人を殺すほど高い高い高い高い場所
一首目。「きらい」「罰」「死がい」「帰れ」と攻撃的な言葉が敷き詰められているにもかかわらず、「(きらわせんなよ)」がオセロのようにそれらを翻す。先に傷を負ったのは「きらいだし」の主体。詫びられてすぐ水に流せるほど軽くはない何かがあったのだろう。「蝉の死がいを拾って帰」る刑は虫嫌いの私にはかなりの厳罰だが、「罰」は許すために科すもの。甘んじて拾って帰り、跪くように埋めよう(証拠写真を送信して「本当に拾ったの?」と笑われたりして)。友人同士ととれないこともないが、夏の終わりにモメるとなるとやはり恋愛関係だろうか。同棲しているふたりでもおもしろい。ブラックユーモアならぬブラックなラブを感じる。
二首目。未舗装の横断歩道ではなく、よく踏み均されたアスファルトの交差点だろう。「ねずみ」を鼠と読むにせよ「リンダリンダ」的な人物像と捉えるにせよ、ただしく「信号」待ちをする棒立ちの影と、それを踏み越えていく風のような姿が浮かぶ。だが「ねずみ」と「青白く」。いずれも美化することなく、突き放すような視線が印象に残る。この歌の主体はどちらにも属していない、あるいは属したくない意識があるのではないだろうか。
三首目。指をふと弛めるだけで誰かの日常を終わらせることができる。そんな場所がこの世界にはいくつもある。火薬も仕掛けもない檸檬であれ、悪意も善意もない理想であれ。「高い高い高い高い場所」 に立つとき人は、己も対象の輪郭をも見失ってしまうのかもしれない。足の竦むような場所で「もし、ここから落ちたら」と自らの脆さを想うことはめずらしくない。自身の死や危機に、生物は(基本的に)敏感だ。「殺す」可能性を突きつけてくるこの歌を、ひやりとしながら繰り返し読んでいる。
ゆく風に名前をつけて「いつかまた頬を打たれてみたい」と言った
この歌を目にしたとき、黒崎氏の詩作品が過ぎった。
言ってしまうなまえが今は ある、
いつか忘れるとすれちがうような、さびしい距離
こうしていると花みたいだよ まちがえているだけなのに
面影すらつかめそうでつかまえられないせつなさが香る。「すれちがう」のは想いか、肉体か、時制だろうか。躊躇いながら切っ先を交えるような烈しさとさびしさが、黒崎氏の作品にはいつでも横たわっている。
最悪って言おうね、笑ってるだけはさみしい
刺し違うように光と呼んで、百年後のまぼろし
「まちがえているだけ」「百年後のまぼろし」と唱えればかなしくない、むしろ美しい。痛みと痛みを掛け合わせれば「光」が生まれる。一瞬の後、すべて過ぎ去っていく。だから大丈夫、まだ大丈夫。あるいは私自身の投影かもしれないが、そう聴こえてくるようだ。
手負いの針ねずみのような鋭さと、ほんの少しの風でふるえる花のような儚さを突きあわせて相殺する。世界を受け容れるために紡がれる。そんな言葉に愛しさを覚える。
黒崎氏の詩作品には閃光の残像に手を伸ばすような、曲を見るような、視点や立場を「定めない」ゆらめきを感じる。「定型」を得たとき、その実に出逢えた気がした。像も景も、より手ざわりをもって近寄れる。詩は詩の、短歌は短歌の合う「何か」が筆を執らせるのだろう。これからも、どちらもみていたい。
今年7月に創刊された詩人・平川綾真智氏との二人詩誌「数をそろえる」を読み、理系の素養のある黒崎氏の「詩」における「数」の生かし方を予感した。「数」と「言葉」をもって織り、裂く。そんな詩作品もまた、影ながら期待している。
※黒崎立体(くろさき りったい)略歴/Poe-Zine「CMYK」vol.1他より抜粋
1984年12月、栃木県生まれ。筑波大学自然学類数学専攻中退。2009年より詩を書きはじめる。2013年、月刊詩誌「詩と思想」による「現代詩の新鋭」のひとりに選出される。同年、ネットプリント誌「終わりのはじまり」を始める。 Web: http://kazahana.main.jp/
PDF作品集「dimensions」
*亜久津歩(あくつ あゆむ)略歴
1981年4月、東京都生まれ。第1詩集『世界が君に死を赦すから』。第2詩集『いのちづな うちなる〝自死者〟と生きる』で第1回 萩原朔太郎記念「とをるもう」賞受賞。日本現代詩人会会員。Poe-Zine「CMYK」発行人(同人/中家菜津子・黒崎立体・草間小鳥子・亜久津歩)
そんな私としては、「現代短歌」は楽しそう、盛り上がっているなぁと日々感じている。ネットプリントの知らせや企画タグを見ない日はなく、合評も盛んな模様。 諸先輩方を含めた議論の一端を垣間見たり、ネットで綴ってきた方がオフラインの歌会や結社へと踏み出していく様子をこっそり眺めていると、子規が……口語で…… というような話などは、どこか別世界の御伽噺のような気がする。死んだほろびた、という実感がない。「現代詩」にもいえることかもしれないが、この広がりから、やがて深みや高みにハマッていく人が現れればよいのだろうな、そうなるのだろう、と思う。
さて。あるときタイムラインに黒崎立体氏(※)の短歌が流れてきて、驚いた。当時まだ単に「詩の方」だと思っていたせいでもあるが、作品に心惹かれて。
きらいだし(きらわせんなよ)罰として蝉の死がいを拾って帰れ
(日経歌壇/2012年9月16日)
信号を無視して駆けてゆくねずみを人間たちが青白く見る
(日経歌壇/2013年3月3日)
手の中の檸檬が人を殺すほど高い高い高い高い場所
(歌会たかまがはら3月号採用歌)
一首目。「きらい」「罰」「死がい」「帰れ」と攻撃的な言葉が敷き詰められているにもかかわらず、「(きらわせんなよ)」がオセロのようにそれらを翻す。先に傷を負ったのは「きらいだし」の主体。詫びられてすぐ水に流せるほど軽くはない何かがあったのだろう。「蝉の死がいを拾って帰」る刑は虫嫌いの私にはかなりの厳罰だが、「罰」は許すために科すもの。甘んじて拾って帰り、跪くように埋めよう(証拠写真を送信して「本当に拾ったの?」と笑われたりして)。友人同士ととれないこともないが、夏の終わりにモメるとなるとやはり恋愛関係だろうか。同棲しているふたりでもおもしろい。ブラックユーモアならぬブラックなラブを感じる。
二首目。未舗装の横断歩道ではなく、よく踏み均されたアスファルトの交差点だろう。「ねずみ」を鼠と読むにせよ「リンダリンダ」的な人物像と捉えるにせよ、ただしく「信号」待ちをする棒立ちの影と、それを踏み越えていく風のような姿が浮かぶ。だが「ねずみ」と「青白く」。いずれも美化することなく、突き放すような視線が印象に残る。この歌の主体はどちらにも属していない、あるいは属したくない意識があるのではないだろうか。
三首目。指をふと弛めるだけで誰かの日常を終わらせることができる。そんな場所がこの世界にはいくつもある。火薬も仕掛けもない檸檬であれ、悪意も善意もない理想であれ。「高い高い高い高い場所」 に立つとき人は、己も対象の輪郭をも見失ってしまうのかもしれない。足の竦むような場所で「もし、ここから落ちたら」と自らの脆さを想うことはめずらしくない。自身の死や危機に、生物は(基本的に)敏感だ。「殺す」可能性を突きつけてくるこの歌を、ひやりとしながら繰り返し読んでいる。
ゆく風に名前をつけて「いつかまた頬を打たれてみたい」と言った
(歌会たかまがはら1月号)
この歌を目にしたとき、黒崎氏の詩作品が過ぎった。
言ってしまうなまえが今は ある、
いつか忘れるとすれちがうような、さびしい距離
こうしていると花みたいだよ まちがえているだけなのに
(黒崎立体個人誌「終わりのはじまり」vol.5)
面影すらつかめそうでつかまえられないせつなさが香る。「すれちがう」のは想いか、肉体か、時制だろうか。躊躇いながら切っ先を交えるような烈しさとさびしさが、黒崎氏の作品にはいつでも横たわっている。
最悪って言おうね、笑ってるだけはさみしい
刺し違うように光と呼んで、百年後のまぼろし
(Poe-Zine「CMYK」vol.1)
「まちがえているだけ」「百年後のまぼろし」と唱えればかなしくない、むしろ美しい。痛みと痛みを掛け合わせれば「光」が生まれる。一瞬の後、すべて過ぎ去っていく。だから大丈夫、まだ大丈夫。あるいは私自身の投影かもしれないが、そう聴こえてくるようだ。
手負いの針ねずみのような鋭さと、ほんの少しの風でふるえる花のような儚さを突きあわせて相殺する。世界を受け容れるために紡がれる。そんな言葉に愛しさを覚える。
黒崎氏の詩作品には閃光の残像に手を伸ばすような、曲を見るような、視点や立場を「定めない」ゆらめきを感じる。「定型」を得たとき、その実に出逢えた気がした。像も景も、より手ざわりをもって近寄れる。詩は詩の、短歌は短歌の合う「何か」が筆を執らせるのだろう。これからも、どちらもみていたい。
今年7月に創刊された詩人・平川綾真智氏との二人詩誌「数をそろえる」を読み、理系の素養のある黒崎氏の「詩」における「数」の生かし方を予感した。「数」と「言葉」をもって織り、裂く。そんな詩作品もまた、影ながら期待している。
※黒崎立体(くろさき りったい)略歴/Poe-Zine「CMYK」vol.1他より抜粋
1984年12月、栃木県生まれ。筑波大学自然学類数学専攻中退。2009年より詩を書きはじめる。2013年、月刊詩誌「詩と思想」による「現代詩の新鋭」のひとりに選出される。同年、ネットプリント誌「終わりのはじまり」を始める。 Web: http://kazahana.main.jp/
PDF作品集「dimensions」
*亜久津歩(あくつ あゆむ)略歴
1981年4月、東京都生まれ。第1詩集『世界が君に死を赦すから』。第2詩集『いのちづな うちなる〝自死者〟と生きる』で第1回 萩原朔太郎記念「とをるもう」賞受賞。日本現代詩人会会員。Poe-Zine「CMYK」発行人(同人/中家菜津子・黒崎立体・草間小鳥子・亜久津歩)










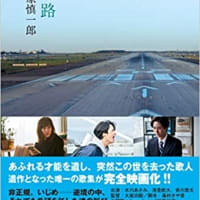
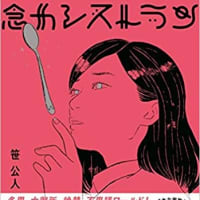
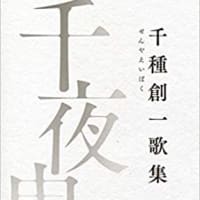
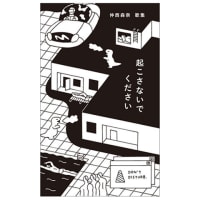
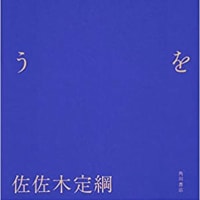
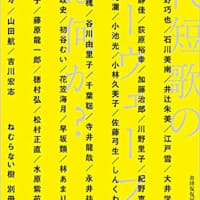

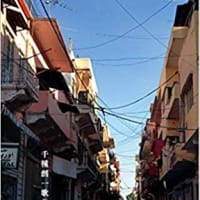

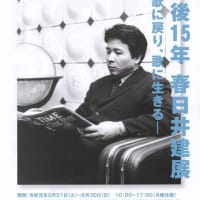
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます