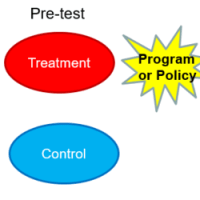大そうな題名を付けてしまいましたが、何のインプットもなくただ博士論文に追われていることから、少し英語のアカデミック・ライティングで気づいたことをまとめておこうと思いました。仕事がないことを毎回ブログで嘆いてもしょうがないので、生産的なことをしたいという気持ちもあります(^ ^; これから、留学あるいはPhDを目指される方の参考になれば幸いですm(_ _)m
学術誌に論文などを提出して審査員からコメントを頂いたり、師匠と一緒に本の章を書いたりしているなかで、英語のライティングについて学んだことがあります。日本人英語上級者用テキストにもあまり載っていないようなので、今週と来週3つぐらい(?)のテーマに沿って、ややマニアックな学術英語論文(特に文系)の上達法について考えていこうと思います。
テーマ1:類義語の使い分け
日本の社会科学系研究者の方の英文などを見て、時々気づくことなのですが、別に難しい英単語を無理に使う必要はないと思います。受験勉強を疎かにした自分より圧倒的な英単語数を持ってらっしゃるとは思いますが、やはり英文の流れの中で適切な単語の使い方を知ることが「重要だ」と感じています。
例えば、この「重要だ」を英語で言いたいときに、「important」という単語は少し陳腐に聞こえるかもしれません。ただ、上記のように大きな概念の重要性を述べるのであれば、自然な単語だと思います。一方で、より細かい理論や研究手法を述べるには適切でないことが多いでしょう。なぜなら、論文読者はどう重要なのか詳しく知りたいからです。ここが英語の難しいところで、日本語なら前後の文脈から異なる「重要」の種類を見分けるのですが、英語には「重要」に当てはまる単語がたくさんあります。
ある理論Aを説明する際に、「理論Bも理論Aに密接に関係しているので重要です」と説明するのであれば、「It is important」ではなく、「It is relevant」あるいは「It is germane」などを使う方が意図が伝わります。また、統計の有意性を示す単語は「significant」で、これを理論の重要性を説明するために使用すると「紛らわしい!」と指摘する論文審査員の方もいます。そうであれば、「substantial」などの単語をWordの類義語検索機能を使って見つけてくればいいと思います。
別の例では、「無理に~させる」という単語には「force→compel→oblige」のような強→弱順があり、文脈に沿って使い分けると文章の質が上がるでしょう。また、現在顕著に広がりつつある現象や概念を説明する際にも、それが一時的な「fad」なのか、それとも「prevalent」なのか、あるいは「ubiquitous」なのかで同現象の広がりの種類が分かるでしょう。
これら類義語の使い分けは、「英文をたくさん読んで身に着けるほかない!」という意見もあると思いますが、有名な論文がどのように類義語を使い分けているのか意識して読むことにより、上達のスピードが上がると感じています。私自身は、引用数の多い論文で使われている似たような言い回しや表現をリストとしてExcelファイルに保存しています。来週は、「テーマ2:とにかく短く!」「テーマ3:自分のスタイルを探せ!」を扱う予定です(^o^)/
学術誌に論文などを提出して審査員からコメントを頂いたり、師匠と一緒に本の章を書いたりしているなかで、英語のライティングについて学んだことがあります。日本人英語上級者用テキストにもあまり載っていないようなので、今週と来週3つぐらい(?)のテーマに沿って、ややマニアックな学術英語論文(特に文系)の上達法について考えていこうと思います。
テーマ1:類義語の使い分け
日本の社会科学系研究者の方の英文などを見て、時々気づくことなのですが、別に難しい英単語を無理に使う必要はないと思います。受験勉強を疎かにした自分より圧倒的な英単語数を持ってらっしゃるとは思いますが、やはり英文の流れの中で適切な単語の使い方を知ることが「重要だ」と感じています。
例えば、この「重要だ」を英語で言いたいときに、「important」という単語は少し陳腐に聞こえるかもしれません。ただ、上記のように大きな概念の重要性を述べるのであれば、自然な単語だと思います。一方で、より細かい理論や研究手法を述べるには適切でないことが多いでしょう。なぜなら、論文読者はどう重要なのか詳しく知りたいからです。ここが英語の難しいところで、日本語なら前後の文脈から異なる「重要」の種類を見分けるのですが、英語には「重要」に当てはまる単語がたくさんあります。
ある理論Aを説明する際に、「理論Bも理論Aに密接に関係しているので重要です」と説明するのであれば、「It is important」ではなく、「It is relevant」あるいは「It is germane」などを使う方が意図が伝わります。また、統計の有意性を示す単語は「significant」で、これを理論の重要性を説明するために使用すると「紛らわしい!」と指摘する論文審査員の方もいます。そうであれば、「substantial」などの単語をWordの類義語検索機能を使って見つけてくればいいと思います。
別の例では、「無理に~させる」という単語には「force→compel→oblige」のような強→弱順があり、文脈に沿って使い分けると文章の質が上がるでしょう。また、現在顕著に広がりつつある現象や概念を説明する際にも、それが一時的な「fad」なのか、それとも「prevalent」なのか、あるいは「ubiquitous」なのかで同現象の広がりの種類が分かるでしょう。
これら類義語の使い分けは、「英文をたくさん読んで身に着けるほかない!」という意見もあると思いますが、有名な論文がどのように類義語を使い分けているのか意識して読むことにより、上達のスピードが上がると感じています。私自身は、引用数の多い論文で使われている似たような言い回しや表現をリストとしてExcelファイルに保存しています。来週は、「テーマ2:とにかく短く!」「テーマ3:自分のスタイルを探せ!」を扱う予定です(^o^)/