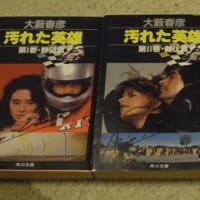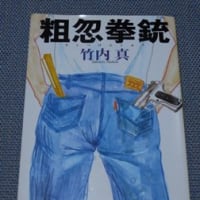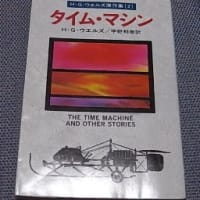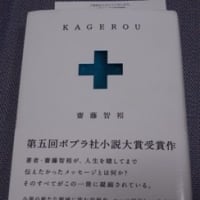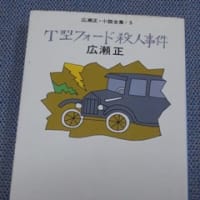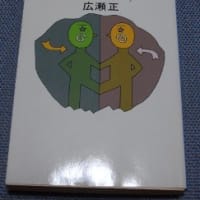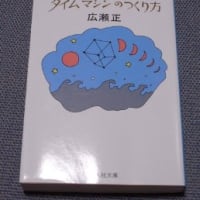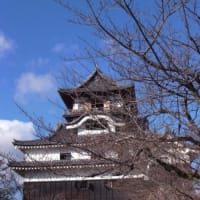本書、アシモフの単著として日本で翻訳出版されているSF長編としては最後の未読作品となります。
(「永遠の終わり」は既読です最後に読んだのが10年ほど前で感想を書いていないのでいずれ読む予定です。)
本自体は近所の古本屋で上下セットのものを購入済み。

アシモフの作家活動としては晩年の1987年発刊、映画のノベライズとして書かれた「ミクロの決死圏」と異なりこちらの方は基本アシモフの着想で書かれていますが、映画化権とのからみでいろいろしばりはあったのかなぁという感じです。
その辺は解説に書いてありますが、最初アシモフが断りフィリップ・ホセ・ファーマーに話が行きと二転三転したようです。
結局本作を基にした映画は作られなかったわけですが...もう永遠に作られないような...。
内容紹介(裏表紙に記載)
上巻;
退屈な学会の講演にうんざりしていたアメリカの神経物理学者アルバート・モリスンは、ソ連の科学者ナターリャ・ボラノーワから意外な申し出を受けた。学会から異端視されているモリスンの画期的な脳波分析の方法を証明するためにソ連に招待するという。しかも驚きはそれだけではなかった。ソ連で開発中の物体ミクロ化実験に参加して脳のなかへ這入れというのだ。モリスンは実験への協力を断るが・・・・・・巨匠アシモフの話題作
下巻
物体ミクロ化実験への参加を拒否した神経物理学者モリスンは、誘拐同然にソ連の極秘研究所へ連行されてしまった。そこで見たのは想像を超えるミクロ化技術の実態だった。さらにモリスンはいやおうなく、実験に参加させられ、生きている人体の脳のなかへと旅立つことになったが・・・・・・アメリカ人科学者が体験する、スリルとサスペンスに満ちた人体内部の冒険の旅を、巨匠が該博な科学知識を駆使し、構想も新たに描いた話題作
読後の感想。
映画の「ノベライズ」ではないですが「映画化」前提に書かれていることもあり、アシモフも「長編」として意気込まずに気楽に書いているイメージがあります。
最後にアシモフの作品らしく「オチ」がついていますが...。
短編によく見られるような割と軽い「オチ」のように感じられるます。短編的な気楽さで書いたんじゃないかなぁと推測されます。
近未来を舞台にしていますが、米ソ冷戦が基調にあり、人間関係もまぁ冷戦的な陳腐さ。
SFとしての設定、アイディアもそれほど斬新なものではなく間延びする部分もあり「長編」として今日的に読む価値があるのどうかは疑問です。
主人公モリスンやら登場する科学者のキャラ立ちは楽しめたので中編として出したらそれなりに名作という評価になったのかもしれません。
でもまぁ適度にアクションと謎解きミステリー的要素もありで気楽に読む分には楽しめる作品ではあります。
内容的には小中学生にも楽しめそうですが....米ソ冷戦にニュアンスがわからないかもしえませんねぇ....。
前述もしましたが、主人公のアメリカの神経物理学者アルバート・モリスン。
冒頭からなんとも「めんどくさい」キャラ全開で主人公=アンチ・ヒーローな設定が楽しめました。
異端の説の発表はするが、それを立証する機会があっても「怖い」ので行かない。
といって文句は多く後悔する....。
この設定アシモフ相当気に入っていたんじゃないでしょうか?楽しんで書いている気がします。
「ファウンデーションの彼方へ」の主人公トレヴィズもめんどくさいタイプでしたがそれよりさらにめんどくさいタイプに仕上がっています。
そのモリスンが最後には...「七日目に休みをとる」人間(?)となるわけですからまぁなんとも皮肉なアシモフらしいですね。
その他のソ連人科学者、リーダー格のボラノーワ、くせもの工学者デジニョーフ、美人電磁気学者カリーニナ、若き気鋭の神経物理学者コーネフもそれぞれキャラ立ちしていて楽しめましたがまぁ紋切型ですかねぇ。
カリーニナとコーネフの最後なども...。
「ミクロの決死圏」では学者でなく007ばりの「スパイ」が活躍していましたが、決して英雄タイプではない「学者が活躍する作品」というのもアシモフ博士の意思だったのかもしれません。
↓俺はめんどうくさいタイプだーという方も、その他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
(「永遠の終わり」は既読です最後に読んだのが10年ほど前で感想を書いていないのでいずれ読む予定です。)
本自体は近所の古本屋で上下セットのものを購入済み。

アシモフの作家活動としては晩年の1987年発刊、映画のノベライズとして書かれた「ミクロの決死圏」と異なりこちらの方は基本アシモフの着想で書かれていますが、映画化権とのからみでいろいろしばりはあったのかなぁという感じです。
その辺は解説に書いてありますが、最初アシモフが断りフィリップ・ホセ・ファーマーに話が行きと二転三転したようです。
結局本作を基にした映画は作られなかったわけですが...もう永遠に作られないような...。
内容紹介(裏表紙に記載)
上巻;
退屈な学会の講演にうんざりしていたアメリカの神経物理学者アルバート・モリスンは、ソ連の科学者ナターリャ・ボラノーワから意外な申し出を受けた。学会から異端視されているモリスンの画期的な脳波分析の方法を証明するためにソ連に招待するという。しかも驚きはそれだけではなかった。ソ連で開発中の物体ミクロ化実験に参加して脳のなかへ這入れというのだ。モリスンは実験への協力を断るが・・・・・・巨匠アシモフの話題作
下巻
物体ミクロ化実験への参加を拒否した神経物理学者モリスンは、誘拐同然にソ連の極秘研究所へ連行されてしまった。そこで見たのは想像を超えるミクロ化技術の実態だった。さらにモリスンはいやおうなく、実験に参加させられ、生きている人体の脳のなかへと旅立つことになったが・・・・・・アメリカ人科学者が体験する、スリルとサスペンスに満ちた人体内部の冒険の旅を、巨匠が該博な科学知識を駆使し、構想も新たに描いた話題作
読後の感想。
映画の「ノベライズ」ではないですが「映画化」前提に書かれていることもあり、アシモフも「長編」として意気込まずに気楽に書いているイメージがあります。
最後にアシモフの作品らしく「オチ」がついていますが...。
短編によく見られるような割と軽い「オチ」のように感じられるます。短編的な気楽さで書いたんじゃないかなぁと推測されます。
近未来を舞台にしていますが、米ソ冷戦が基調にあり、人間関係もまぁ冷戦的な陳腐さ。
SFとしての設定、アイディアもそれほど斬新なものではなく間延びする部分もあり「長編」として今日的に読む価値があるのどうかは疑問です。
主人公モリスンやら登場する科学者のキャラ立ちは楽しめたので中編として出したらそれなりに名作という評価になったのかもしれません。
でもまぁ適度にアクションと謎解きミステリー的要素もありで気楽に読む分には楽しめる作品ではあります。
内容的には小中学生にも楽しめそうですが....米ソ冷戦にニュアンスがわからないかもしえませんねぇ....。
前述もしましたが、主人公のアメリカの神経物理学者アルバート・モリスン。
冒頭からなんとも「めんどくさい」キャラ全開で主人公=アンチ・ヒーローな設定が楽しめました。
異端の説の発表はするが、それを立証する機会があっても「怖い」ので行かない。
といって文句は多く後悔する....。
この設定アシモフ相当気に入っていたんじゃないでしょうか?楽しんで書いている気がします。
「ファウンデーションの彼方へ」の主人公トレヴィズもめんどくさいタイプでしたがそれよりさらにめんどくさいタイプに仕上がっています。
そのモリスンが最後には...「七日目に休みをとる」人間(?)となるわけですからまぁなんとも皮肉なアシモフらしいですね。
その他のソ連人科学者、リーダー格のボラノーワ、くせもの工学者デジニョーフ、美人電磁気学者カリーニナ、若き気鋭の神経物理学者コーネフもそれぞれキャラ立ちしていて楽しめましたがまぁ紋切型ですかねぇ。
カリーニナとコーネフの最後なども...。
「ミクロの決死圏」では学者でなく007ばりの「スパイ」が活躍していましたが、決して英雄タイプではない「学者が活躍する作品」というのもアシモフ博士の意思だったのかもしれません。
↓俺はめんどうくさいタイプだーという方も、その他の方もよろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。