本作‘16年末から読みはじめ’17年に入り最初に読了した作品となりました。
‘12年ローカス誌SF長編オールタイムベスト50位、本書の前に読んだ「アルジャーンに花束を」と同位です。
本作読了で2013年からSF長編を読む指標としてきた12年ローカス誌オールタイムベスト1位から50位までの作品を34位の「Stand on Zanzibar」(未訳)以外は完読となりました感慨深いものがあります...。
前にも一度書きましたがリストに従って読む読書が上品とは思えませんが…。
自分からは決して「手に取らないだろうなぁ」というような作品を読むことができSFへのイメージが広がったような気はします。
本書もかなりマニアックな作品なのでまず自分からは手に取らないだろう作品です。
米国では1975年に刊行されディレイニーの作品の中では一番売れた(70万部を超す)作品とされているようですが、日本では永らく「幻の作品」とされていて2011年に本書が国書刊行会でやっと翻訳された作品です。
(前述の「Stand on Zanzibar」も永らく和訳されていない作品として有名らしいです。ベスト100制覇のためにはちらちら未訳・入手困難作品があるので壁ですねぇ。原書で読むにも私の英語力では…。)
本書そんなわけで値段的にもちょいと高いので図書館で借りて済ませようか、購入しようか悩んだのですが結局amazonで新品を大人買い...とはいかずamazonで古本を購入しました。

ただ、「Ⅱ」の方は古本でも値段は張ったので新品で買ってもよかったかもしれません。
内容紹介(amazon内容紹介より)
「20世紀SFの金字塔」「SF界の『重力の虹』」 「ジャンルを超えたマジックリアリズムの傑作」と称されながらも、今まで謎に包まれていた伝説的超大作がついに登場!
序文:ウィリアム・ギブスン 解説:巽孝之
都市ベローナに何が起きたのか――多くの人々が逃げ出し、廃墟となった世界を跋扈する異形の集団。二つの月。永遠に続く夜と霧。毎日ランダムに変化する新聞の日付。そこに現れた青年は、自分の名前も街を訪れた目的も思い出せない。やがて<キッド>とよばれる彼は男女を問わず愛を交わし、詩を書きながら、迷宮都市をさまよいつづける……奔放なイマジネーションが織りなす架空の都市空間を舞台に、性と暴力の魅惑を鮮烈に謳い上げ、人種・ジェンダーのカテゴリーを侵犯していく強靱なフィクションの力。過剰にして凶暴な文体、緻密にして錯乱した構成、ジョイスに比すべき大胆な言語実験を駆使した、天才ディレイニーの代表作にしてアメリカSF最大の問題作
1,2合せて966ページの大著かつエンターテインメント作品とは言い難い作品ですので通勤時読書で2ケ月かかりました。
読了後のとりあえずの感想「ベローナ」臭そう!(笑)
全編匂いたつような描写が多く清潔とはいいがたい街なので相当匂いがきつそう...。
生々しい描写は「買い」でしょうか。
ただ全体的に「名作を読んだ」満足感よりも、とりあえずこれで「ダールグレン読んだよ」と言えるようになったのが「一番うれしい」という読書体験でした。(「海外SF読んでいます」というときにハクがつくような)
翻訳家の山形浩生氏は本作を「ナルシズム全開」と本作を酷評していますが、本作ではディレイニー自身が黒人でありゲイであることを存分に使ってその辺の描写をしています。
主人公は「詩人」という設定ですしかなりの部分に自己が投影されているのでしょうね。
「黒人」の描写は黒人作家が書いたものでなければ相当物議かもしそうな感じでした。
山形氏は前半の「ひたすら引っ越し」を批判していましたが、よくも悪くも引っ越しがメインの前半は異常な状況の街に入り込んで迷走する主人公キッドや異常な状況にアルベローナを認識しようとせずに無意味な引っ越しを試みるリチャーズ家、その娘ジューンとジョージ・ハリスン(黒人のベローナのカリスマ)の関係などの描写が楽しめました。
「Ⅰ」(Ⅵ災厄の時)までで終わっていた方が「いい作品」といえたような気がします。
後半が前半の伏線から発展させた展開であればもっと「いい作品」という感想になったような気がします。
前半と後半(「Ⅱ」では主人公の性格もかなり異なってきて物語の展開・性質もかなり異なってきます。
「意図的」なものなのでしょうが、前述の通り折角前半で張った伏線は展開されず、「詩人」になったキッドが「異常な街」ベローナでどのような行動と関係性を持つかに注目していたのですが…基本コミューン的なアジトに閉じこもりセックスか内輪もめをしているか、外に出てパンクロッカー的に場当たりな行動をしているだけになっていまっているのが私には残念に思われました。
後半はキッドがベローナ新聞の発行者コーキンズの家に仲間を引き連れていく場面がクライマックスだったんだと思いますがそこもなんだか…。
最終章「アナテーマ-災厄日誌」でコーキンズとキッドはやっと直接会話するわけですが「政治」と「文学・芸術」の関係性といったものを言いたいんでしょうが響きませんでした。
また最終章では文章を混乱させ「実験的な作品」「メタフィクション」という感じにしていますがなにやら主題にダイレクトに当るところから逃げているような気がしました。
比べるのもなんですが「アルジャーノンに花束を」のチャーリーの成長に伴う文章の変化のような表現としての必然性がなく技巧に走りすぎているような…。
後半のは全体的に技巧と「黒人」「ゲイ」当時のヒッピー文化を取り込むことで終わってしまっているように感じました。
山形氏ほど自信をもって酷評するほど自分の小説鑑賞眼に自信はないですが...「幻の名作」というほどの作品ではないかなぁというのが感想です。
ただ前半部分はそれなりに面白かったです。
なおキッドは物語を通じて片足だけサンダルか靴を履いていて片足裸足です。
このスタイル同じくディレイニー作の「ノヴァ」(1968年-「ダールグレン」を読んでいるときは未読、現在既読)で副主人公が同じスタイルでした(宇宙船の無重力化で足でものがつかめるように裸足)なにか関係があるのでしょうか…。
時代が違うので同一人物ではないですが、主人公とちょっと「ゲイ」的な関係が示唆されているし、性格もまぁ似ているような…。
感想書くのにパラパラ見返していたらそれなりに印象深い場面があったなぁという感じもしましたのでもう一度読めばまた感想も違うかもしれませんが(当分読まないと思いますが…)現段階ではあまりポジティブな感想ではないです…。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。
 にほんブログ村
にほんブログ村
‘12年ローカス誌SF長編オールタイムベスト50位、本書の前に読んだ「アルジャーンに花束を」と同位です。
本作読了で2013年からSF長編を読む指標としてきた12年ローカス誌オールタイムベスト1位から50位までの作品を34位の「Stand on Zanzibar」(未訳)以外は完読となりました感慨深いものがあります...。
前にも一度書きましたがリストに従って読む読書が上品とは思えませんが…。
自分からは決して「手に取らないだろうなぁ」というような作品を読むことができSFへのイメージが広がったような気はします。
本書もかなりマニアックな作品なのでまず自分からは手に取らないだろう作品です。
米国では1975年に刊行されディレイニーの作品の中では一番売れた(70万部を超す)作品とされているようですが、日本では永らく「幻の作品」とされていて2011年に本書が国書刊行会でやっと翻訳された作品です。
(前述の「Stand on Zanzibar」も永らく和訳されていない作品として有名らしいです。ベスト100制覇のためにはちらちら未訳・入手困難作品があるので壁ですねぇ。原書で読むにも私の英語力では…。)
本書そんなわけで値段的にもちょいと高いので図書館で借りて済ませようか、購入しようか悩んだのですが結局amazonで新品を大人買い...とはいかずamazonで古本を購入しました。

ただ、「Ⅱ」の方は古本でも値段は張ったので新品で買ってもよかったかもしれません。
内容紹介(amazon内容紹介より)
「20世紀SFの金字塔」「SF界の『重力の虹』」 「ジャンルを超えたマジックリアリズムの傑作」と称されながらも、今まで謎に包まれていた伝説的超大作がついに登場!
序文:ウィリアム・ギブスン 解説:巽孝之
都市ベローナに何が起きたのか――多くの人々が逃げ出し、廃墟となった世界を跋扈する異形の集団。二つの月。永遠に続く夜と霧。毎日ランダムに変化する新聞の日付。そこに現れた青年は、自分の名前も街を訪れた目的も思い出せない。やがて<キッド>とよばれる彼は男女を問わず愛を交わし、詩を書きながら、迷宮都市をさまよいつづける……奔放なイマジネーションが織りなす架空の都市空間を舞台に、性と暴力の魅惑を鮮烈に謳い上げ、人種・ジェンダーのカテゴリーを侵犯していく強靱なフィクションの力。過剰にして凶暴な文体、緻密にして錯乱した構成、ジョイスに比すべき大胆な言語実験を駆使した、天才ディレイニーの代表作にしてアメリカSF最大の問題作
1,2合せて966ページの大著かつエンターテインメント作品とは言い難い作品ですので通勤時読書で2ケ月かかりました。
読了後のとりあえずの感想「ベローナ」臭そう!(笑)
全編匂いたつような描写が多く清潔とはいいがたい街なので相当匂いがきつそう...。
生々しい描写は「買い」でしょうか。
ただ全体的に「名作を読んだ」満足感よりも、とりあえずこれで「ダールグレン読んだよ」と言えるようになったのが「一番うれしい」という読書体験でした。(「海外SF読んでいます」というときにハクがつくような)
翻訳家の山形浩生氏は本作を「ナルシズム全開」と本作を酷評していますが、本作ではディレイニー自身が黒人でありゲイであることを存分に使ってその辺の描写をしています。
主人公は「詩人」という設定ですしかなりの部分に自己が投影されているのでしょうね。
「黒人」の描写は黒人作家が書いたものでなければ相当物議かもしそうな感じでした。
山形氏は前半の「ひたすら引っ越し」を批判していましたが、よくも悪くも引っ越しがメインの前半は異常な状況の街に入り込んで迷走する主人公キッドや異常な状況にアルベローナを認識しようとせずに無意味な引っ越しを試みるリチャーズ家、その娘ジューンとジョージ・ハリスン(黒人のベローナのカリスマ)の関係などの描写が楽しめました。
「Ⅰ」(Ⅵ災厄の時)までで終わっていた方が「いい作品」といえたような気がします。
後半が前半の伏線から発展させた展開であればもっと「いい作品」という感想になったような気がします。
前半と後半(「Ⅱ」では主人公の性格もかなり異なってきて物語の展開・性質もかなり異なってきます。
「意図的」なものなのでしょうが、前述の通り折角前半で張った伏線は展開されず、「詩人」になったキッドが「異常な街」ベローナでどのような行動と関係性を持つかに注目していたのですが…基本コミューン的なアジトに閉じこもりセックスか内輪もめをしているか、外に出てパンクロッカー的に場当たりな行動をしているだけになっていまっているのが私には残念に思われました。
後半はキッドがベローナ新聞の発行者コーキンズの家に仲間を引き連れていく場面がクライマックスだったんだと思いますがそこもなんだか…。
最終章「アナテーマ-災厄日誌」でコーキンズとキッドはやっと直接会話するわけですが「政治」と「文学・芸術」の関係性といったものを言いたいんでしょうが響きませんでした。
また最終章では文章を混乱させ「実験的な作品」「メタフィクション」という感じにしていますがなにやら主題にダイレクトに当るところから逃げているような気がしました。
比べるのもなんですが「アルジャーノンに花束を」のチャーリーの成長に伴う文章の変化のような表現としての必然性がなく技巧に走りすぎているような…。
後半のは全体的に技巧と「黒人」「ゲイ」当時のヒッピー文化を取り込むことで終わってしまっているように感じました。
山形氏ほど自信をもって酷評するほど自分の小説鑑賞眼に自信はないですが...「幻の名作」というほどの作品ではないかなぁというのが感想です。
ただ前半部分はそれなりに面白かったです。
なおキッドは物語を通じて片足だけサンダルか靴を履いていて片足裸足です。
このスタイル同じくディレイニー作の「ノヴァ」(1968年-「ダールグレン」を読んでいるときは未読、現在既読)で副主人公が同じスタイルでした(宇宙船の無重力化で足でものがつかめるように裸足)なにか関係があるのでしょうか…。
時代が違うので同一人物ではないですが、主人公とちょっと「ゲイ」的な関係が示唆されているし、性格もまぁ似ているような…。
感想書くのにパラパラ見返していたらそれなりに印象深い場面があったなぁという感じもしましたのでもう一度読めばまた感想も違うかもしれませんが(当分読まないと思いますが…)現段階ではあまりポジティブな感想ではないです…。
↓よろしければ下のバナークリックいただけるとありがたいです!!!コメントも歓迎です。










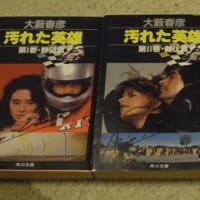
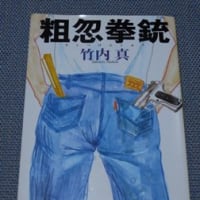
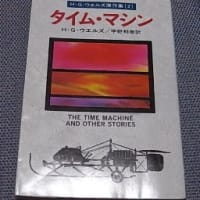
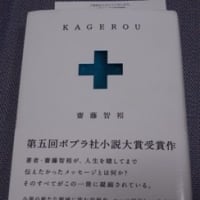
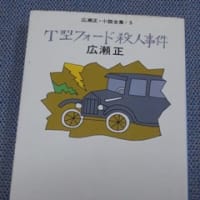
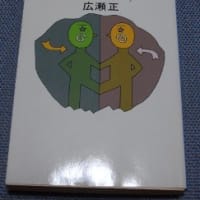


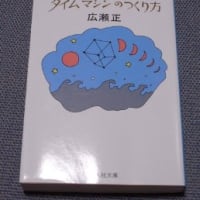
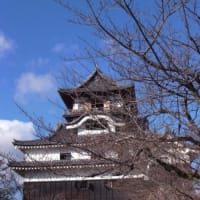
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます