「初期作品集」→「わたしはロボット」の流れで、アシモフの初期ロボットものが収録されている本書がとても読みたくなり珍しく新品を購入しました。
以前(10年前くらい)古本を入手していたつもりなのですが(読んではいなかった)自宅の本棚を探しても見つからず...謎だ。
まぁ持っていたのは「決定版」ではなかったのでダブってもいいかということで購入。

「I,ROBOT」が映画化された関係で訳文に手を加えて登場したようです。
余談ですが、ハヤカワ文庫のアシモフ作品。この「ロボットの時代」「われはロボット」「鋼鉄都市」「ロボットと帝国」「ファウンデーションシリーズ1~3」以外は絶版になっています。
SFが売れないのか、アシモフが人気ないのか....、ヒューゴー・ネピュラダブルクラウンの「神々自身」でさえ絶版、嘆かわしいです。
「ロボットと帝国」など「夜明けのロボット」を読まなきゃなんだかわからないと思うのですが...残念。
ハヤカワも時々復刊しているので大々的な復刊があることを祈っています。
(なんだか岩波文庫のようになってきた)
さて、本書「ロボットの時代」ですが原題が「THE REST OF THE ROBOTS」1950年に発行された「われはロボット」(ハヤカワに敬意を表しここでは”われは”で表記、創元は”わたしは”)が1963年に新版で発行され、残りのロボットもので一冊作ろうということで1964年に本書が発行されたようです。
表紙の「アシモフのロボット傑作集」と「”REST OF”」がなんだかアンマッチでおかしい。
構成は
・第一部 ロボットの登場
最初期のロボットもの2編
・第二部 ロボット工学の諸原則
有名なロボット工学3原則を使った初期の作品。2編
・第三部 スーザン・キャルヴィン
アシモフいわく「彼女を愛している」キャルヴィン女史出演の4編
われはロボット以降に書かれたもの
それぞれの作品の冒頭にアシモフの寸評というか書かれた経緯などが記されています。
「REST OF」ですから、特に初期に書かれた第一部、第二部収載の4編は出来は今一つな感じがします。
キャルヴィンものは「われはロボット」以降の作品のようなのでこなれた出来ですが、それほど力の入った名作という感じではありません。
どうしてもアシモフのロボットものをいっぱい読みたいという人以外にはお薦めできないような気がする本です。
(これを残すようなら他を復刊した方がいいような...)
でもまぁ私的には「アシモフ初期作品集3冊」→「われはロボット」から続けて読んだので、いろいろ楽しめました。
各編感想など、
○第一部 ロボットの登場
「AL76号失踪す」
アシモフいわく、ロボット=フランケンシュタイン(正式名称はモンスターか)的に扱われている時代に、「道化」的な人間に無害なロボットを描こうという試みの作品。
とはいえまだ三原則もはっきり確立していません。
1942年2月掲載と初期の作品です。
失踪したロボットの起こすドタバタを描いたショート・ショート的作品。
「思わざる勝利」
アシモフ初期作品集2「ガニメデのクリスマス」収載の「決定的!」の続編的作品。これも1942年
ただ前作は「科学」「異星人」が主役でしたが今回は「ロボット」対「異星人」という構図。
たわいないといえばたわいない内容ですが、この作品ですでに「人間より優れた存在」かつ「絶対服従」のロボットが描かれており後の作品のテーマを暗示しているような気もします。
○第二部 ロボット工学の諸原則
「第一条」
ロボット工学三原則が表に出てきはじめた作品。
「われはロボット」でお馴染みのドノヴァンが主人公として出てきます。
(この作品ではパウエルは出てこないで単独です)
内容的にはワンアイディアのショート・ショートという感じであまり感心できない出来です。
(ショート・ショートをバカにしているわけでなく、ヒネリが効いておらず描写も足りないという意味です)
三原則をテーマにしていますが「母性」を理屈抜きで上位概念にしています...。私的にはどんなものかなぁという感じを受けました。
「みんな集まれ」
「ロボット工学の諸原則」に分類されていますが、三原則が効いていない「ロボット破壊工作員」の登場する作品です。
東西冷戦が進んでいった近未来をテーマにした作品です。
これも星新一あたりがショート・ショートにしそうな作品。
テンポのいい作品だとは思いますが、オチは途中から予想できました。もう少しひねりがあっても...。
でも「三原則のないロボット」の存在がいかに危ないものかということは伝わってきます。
人の作ったものが「人を超え」「人に害をもたらす」というテーマはフランケンシュタインに限らず人を不気味な気持ちにさせる普遍的なテーマなんでしょうね。
ターミネーターとか最近の「猿の惑星」なんかもそんなテーマな気がしますね。
○第三部 スーザン・キャルヴィン
「お気に召すことうけあい」
これもショート・ショート的展開ですが、ロボットも主人公も魅力的でしゃれた作品に仕上がっています。
キャルヴィン女史登場の作品ですが彼女はチョイとしか出ませんがピリリとしまります。
「愛」ですね~。
「危険」
「われはロボット」収載の「迷子のロボット」の続編的作品。
ロボットが操縦するハイパー宇宙船が動かない謎をめぐるお話。
「われはロボット」に収載されても違和感はないような作品です。
キャルヴィン登場の謎解きものに分類できるかと思います。
結末はなんとなく予想できるのですが、「迷子のロボット」より後に書かれているためかこなれた感じの仕上がりです。
キャルヴィン、魅力的に描かれています。
「レニィ」
キャルヴィンもの、母性をテーマにしている点で「第一条」に通じる作品。
キャルヴィンの人間的側面を描きたかったんでしょうがちょっと無理があるような...。
「校正」
アシモフの紹介文を読んでから読むとなかなか味わい深い作品です。
ある人との共著になる生化学の教科書の三版の校正中に思いついて一気に書き上げたとのこと。
本人いわく「スーザン・キャルヴィンの登場する話の中でこれはわたしの大事な作品である。」、本人も「不合理」と認めており出来は悪くはない程度の作品だと思いますが...「趣」はあります。
さすがにアシモフ続きで飽きてきたような気もするので次は離れようと思っています。
↓よろしければクリック下さい
 にほんブログ村
にほんブログ村
以前(10年前くらい)古本を入手していたつもりなのですが(読んではいなかった)自宅の本棚を探しても見つからず...謎だ。
まぁ持っていたのは「決定版」ではなかったのでダブってもいいかということで購入。

「I,ROBOT」が映画化された関係で訳文に手を加えて登場したようです。
余談ですが、ハヤカワ文庫のアシモフ作品。この「ロボットの時代」「われはロボット」「鋼鉄都市」「ロボットと帝国」「ファウンデーションシリーズ1~3」以外は絶版になっています。
SFが売れないのか、アシモフが人気ないのか....、ヒューゴー・ネピュラダブルクラウンの「神々自身」でさえ絶版、嘆かわしいです。
「ロボットと帝国」など「夜明けのロボット」を読まなきゃなんだかわからないと思うのですが...残念。
ハヤカワも時々復刊しているので大々的な復刊があることを祈っています。
(なんだか岩波文庫のようになってきた)
さて、本書「ロボットの時代」ですが原題が「THE REST OF THE ROBOTS」1950年に発行された「われはロボット」(ハヤカワに敬意を表しここでは”われは”で表記、創元は”わたしは”)が1963年に新版で発行され、残りのロボットもので一冊作ろうということで1964年に本書が発行されたようです。
表紙の「アシモフのロボット傑作集」と「”REST OF”」がなんだかアンマッチでおかしい。
構成は
・第一部 ロボットの登場
最初期のロボットもの2編
・第二部 ロボット工学の諸原則
有名なロボット工学3原則を使った初期の作品。2編
・第三部 スーザン・キャルヴィン
アシモフいわく「彼女を愛している」キャルヴィン女史出演の4編
われはロボット以降に書かれたもの
それぞれの作品の冒頭にアシモフの寸評というか書かれた経緯などが記されています。
「REST OF」ですから、特に初期に書かれた第一部、第二部収載の4編は出来は今一つな感じがします。
キャルヴィンものは「われはロボット」以降の作品のようなのでこなれた出来ですが、それほど力の入った名作という感じではありません。
どうしてもアシモフのロボットものをいっぱい読みたいという人以外にはお薦めできないような気がする本です。
(これを残すようなら他を復刊した方がいいような...)
でもまぁ私的には「アシモフ初期作品集3冊」→「われはロボット」から続けて読んだので、いろいろ楽しめました。
各編感想など、
○第一部 ロボットの登場
「AL76号失踪す」
アシモフいわく、ロボット=フランケンシュタイン(正式名称はモンスターか)的に扱われている時代に、「道化」的な人間に無害なロボットを描こうという試みの作品。
とはいえまだ三原則もはっきり確立していません。
1942年2月掲載と初期の作品です。
失踪したロボットの起こすドタバタを描いたショート・ショート的作品。
「思わざる勝利」
アシモフ初期作品集2「ガニメデのクリスマス」収載の「決定的!」の続編的作品。これも1942年
ただ前作は「科学」「異星人」が主役でしたが今回は「ロボット」対「異星人」という構図。
たわいないといえばたわいない内容ですが、この作品ですでに「人間より優れた存在」かつ「絶対服従」のロボットが描かれており後の作品のテーマを暗示しているような気もします。
○第二部 ロボット工学の諸原則
「第一条」
ロボット工学三原則が表に出てきはじめた作品。
「われはロボット」でお馴染みのドノヴァンが主人公として出てきます。
(この作品ではパウエルは出てこないで単独です)
内容的にはワンアイディアのショート・ショートという感じであまり感心できない出来です。
(ショート・ショートをバカにしているわけでなく、ヒネリが効いておらず描写も足りないという意味です)
三原則をテーマにしていますが「母性」を理屈抜きで上位概念にしています...。私的にはどんなものかなぁという感じを受けました。
「みんな集まれ」
「ロボット工学の諸原則」に分類されていますが、三原則が効いていない「ロボット破壊工作員」の登場する作品です。
東西冷戦が進んでいった近未来をテーマにした作品です。
これも星新一あたりがショート・ショートにしそうな作品。
テンポのいい作品だとは思いますが、オチは途中から予想できました。もう少しひねりがあっても...。
でも「三原則のないロボット」の存在がいかに危ないものかということは伝わってきます。
人の作ったものが「人を超え」「人に害をもたらす」というテーマはフランケンシュタインに限らず人を不気味な気持ちにさせる普遍的なテーマなんでしょうね。
ターミネーターとか最近の「猿の惑星」なんかもそんなテーマな気がしますね。
○第三部 スーザン・キャルヴィン
「お気に召すことうけあい」
これもショート・ショート的展開ですが、ロボットも主人公も魅力的でしゃれた作品に仕上がっています。
キャルヴィン女史登場の作品ですが彼女はチョイとしか出ませんがピリリとしまります。
「愛」ですね~。
「危険」
「われはロボット」収載の「迷子のロボット」の続編的作品。
ロボットが操縦するハイパー宇宙船が動かない謎をめぐるお話。
「われはロボット」に収載されても違和感はないような作品です。
キャルヴィン登場の謎解きものに分類できるかと思います。
結末はなんとなく予想できるのですが、「迷子のロボット」より後に書かれているためかこなれた感じの仕上がりです。
キャルヴィン、魅力的に描かれています。
「レニィ」
キャルヴィンもの、母性をテーマにしている点で「第一条」に通じる作品。
キャルヴィンの人間的側面を描きたかったんでしょうがちょっと無理があるような...。
「校正」
アシモフの紹介文を読んでから読むとなかなか味わい深い作品です。
ある人との共著になる生化学の教科書の三版の校正中に思いついて一気に書き上げたとのこと。
本人いわく「スーザン・キャルヴィンの登場する話の中でこれはわたしの大事な作品である。」、本人も「不合理」と認めており出来は悪くはない程度の作品だと思いますが...「趣」はあります。
さすがにアシモフ続きで飽きてきたような気もするので次は離れようと思っています。
↓よろしければクリック下さい










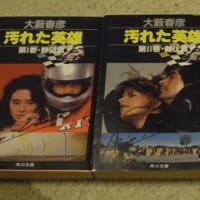
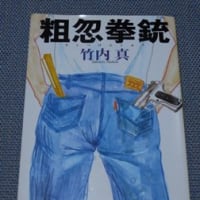
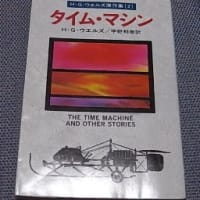
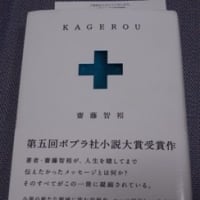
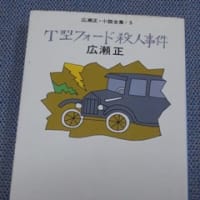
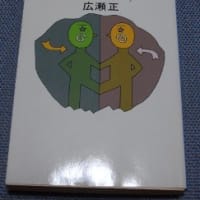


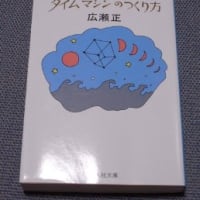
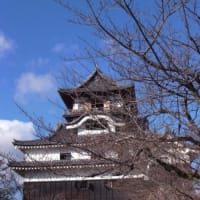
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます