
年間20ミリシーベルトの放射線を強いられる子ども達も、上限が撤廃される原発労働者もたまったものではありません!
35年間で10人労災認定 原発労働者のがん
共同通信 2011年4月28日
厚生労働省は27日、がんになった原子力発電所の労働者のうち、過去35年で10人が累積被ばく線量などに基づき労災認定されていたことを明らかにした。福島第1原発の事故を受け、初めて労災の認定状況を公表した。
1976年度以降、労災認定された10人のうち白血病が6人。累積被ばく線量は129・8~5・2ミリシーベルトだった。このほか多発性骨髄腫が2人で、それぞれ70・0、65・0ミリシーベルト。悪性リンパ腫も2人で、それぞれ99・8、78・9ミリシーベルトだった。
厚労省によると、がんに対する100ミリシーベルト以下の低線量被ばくの影響は科学的に証明されていないが、線量が増えれば比例して発がん可能性も増すとの仮説があり、同省は「100ミリシーベルト以下での労災認定もあり得る」としている。
白血病の場合は、年5ミリシーベルトの被ばくなどが認定基準となっている一方、他のがんは従事年数や業務内容、病気の経過など個別の状況に基づいて判断するという。
同省補償課は今回の事故について「相当量の被ばくをしている人がおり、労災認定は今後、増えるのでは」とみている。
よろしかったらクリックよろしくお願いいたします
http://blog.with2.net/link.php?1197203
年20ミリシーベルト未満は通常通り=福島の13校、屋外活動制限-学校の安全基準
(時事通信 2011/04/20-00:43)
政府の原子力災害対策本部は19日、福島県内の学校の安全基準について、大気中の放射線量が年間20ミリシーベルトを下回るとみられる場合は、通常通りの校舎や校庭の利用を認める暫定方針を決定したと発表した。放射線量の測定を続け、夏休みが終わる8月下旬をめどに見直しを行う。
原子力安全委員会の一部委員は「子どもは成人の半分以下とすべきだ」と指摘していたが、文部科学省は「国際放射線防護委員会(ICRP)は、大人も子どもも原発事故後には1~20ミリシーベルトの被ばくを認めている」と説明。計画的避難区域の指定基準と同じ年20ミリシーベルトを下回れば問題ないと判断した。計画的避難区域と緊急時避難準備区域に指定される地域の学校は使用しない。その他の学校のうち、通常通り屋外活動を行うと年20ミリシーベルト以上となる恐れがあるのは福島、郡山、伊達3市の13校・園(児童・生徒・園児計3560人)。文部科学省と厚生労働省は福島県教育委員会などに対し、これらの学校については校庭での活動を1日約1時間とし、活動後には手や顔を洗うことや、砂ぼこりが多いときは窓を閉めることなどを求める通知を出した。
文科省によると、現時点の放射線量が変わらず、毎日8時間は屋外に、残り16時間は木造家屋内にいたと仮定すると、校庭での放射線量が1時間当たり3.8マイクロシーベルトの場合、1年後の積算線量が20ミリシーベルトとなる。この試算から同3.8マイクロシーベルト未満の学校では、通常通りの活動を認めることにした。
一般人の線量限度は本来年1ミリシーベルトだが、ICRPは原発事故などの緊急時には年20~100ミリシーベルト、事故収束後は1~20ミリシーベルトを認めている。記者会見で鈴木寛文科副大臣は「100ミリシーベルト未満では、がんなどのリスク増加は認められない」と述べた。
共同通信 2011年4月27日
厚生労働省は27日、通常時は年間50ミリシーベルトと定めている原発作業員の被ばく線量の上限を当面の間、撤廃する方針を固めた。5年間で100ミリシーベルトの基準は維持する。原発作業に従事できるのは全国で7万人余りしかいない。各地から福島第1原発への派遣が相次ぐ中、規定の被ばく線量を超えると、ほかの原発の保守や定期点検に支障が出かねないとして、経済産業省が厚労省に特例的な措置を要請していた。
しかし、この措置は、過酷な環境下で働く作業員の安全を軽視しているとの批判も出そうだ。
厚労省は3月15日に省令で、福島の事故の応急対策に限定して緊急時の被ばく線量を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げていたが、通常時の基準は変えていなかった。
米国も、緊急時の線量上限を民間人で100ミリシーベルト、通常時は年間50ミリシーベルト、5年間で100ミリシーベルトとしている。
東電によると、福島で作業した30人が100ミリシーベルトを超えた。50ミリシーベルトを超えると、ほかの原発で働くことができなくなるため、多くは東電の協力企業側が線量を管理しているという。
こうした事態に、経産省は電離放射線障害防止規則で定められた「通常年間50ミリシーベルト、5年間で100ミリシーベルト」の基準を緩和するよう厚労省に要請。しかし、厚労省は「100ミリシーベルトを超えると白血病やがんの発生リスクが高まるという医学的な知見もある」として、5年間で100ミリシーベルトの基準は維持することにした。
| 労災申請日 | 決定日 | 認定 | 疾病名 | 期間/ 被ばく線量 |
局/ 労基署 |
施設名 | 備考 |
| 1975.3.19 | 1975.10.9 | 不支給 | 皮膚炎 | 福井/ 敦賀 |
原電敦賀原発 | 岩佐嘉寿幸さん | |
| 1982.5.31 | 不支給 | 白血病性悪性リンパ腫 | 島根/ 松江 |
||||
| 1988.9.2 | 1991.12.26 | 支給 | 慢性骨髄性白血病 | 11ヶ月で40mSv | 福島/ 富岡 |
東電福島第一原発 |
1988年2月死亡 |
| 1992.12.1 | 1994.7.27 | 不支給 | 急性骨髄性白血病 | 兵庫/ 神戸西 |
|||
| 1992.12.14 | 1994.7.27 | 支給 | 急性骨髄性白血病 | 87.7-92.12の 5年5ヶ月 |
兵庫/ 神戸西 |
九電玄海・関電大飯・高浜原発 | 定期検査作業 |
| 1993.5.6 | 1994.7.27 | 支給 | 慢性骨髄性白血病 | 81.3-89.12の8年10ヶ月で50.63mSv | 静岡/ 磐田 |
中部電浜岡原発 | 嶋橋伸之さん 1991年11月に死亡 計測装置の点検作業 |
| 1996.5.27 | 不支給 | 再生不良性貧血 | 福島/ 富岡 |
||||
| 1997.5.16 | 不支給 | 慢性骨髄性白血病 | 福島/ 富岡 |
||||
| 1998.12.22 | 1999.7.30 | 支給 | 急性リンパ性白血病 | 84.12-97.1の12年余り、129.8mSv(フィルムバッジによる測定) | 茨城/ 日立 |
原電東海・中国電島根・東電福島第一他 | 日立市の電機メーカー作業員で装置点検等に従事 人間ドッグで発見 生存 |
| 1999.10.20 | 1999.10.26 | 支給 | 急性放射線症 | 1-4.5Sv | 茨城/ 水戸 |
JCO東海村事業所 | 以下2名とともに臨界事故で被曝 横川豊さん |
| 1999.10.20 | 1999.10.26 | 支給 | 急性放射線症 | 6.0-10Sv | 茨城/ 水戸 |
JCO東海村事業所 | 篠原理人さん 2000年4月に死亡 |
| 1999.10.20 | 1999.10.26 | 支給 | 急性放射線症 | 16-20Sv以上 | 茨城/ 水戸 |
JCO東海村事業所 | 大内久さん 1999年12月に死亡 |
| 1999.11.20 | 2000.10.24 | 支給 | 急性単球性白血病 | 1988.10-1999.10まで74.9mSv(フィルムバッジによる測定) | 福島/ 富岡 |
東電福島第一、第二、原電東海第二他 | 配管・架台・構造物等の溶接作業に従事 症状のため自ら受診 死亡 |
* mSv=ミリシーベルト・Sv=シーベルト
*2002年3月までに把握した情報による










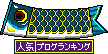















途中で基準変えるなよ(怒)。
なんのための基準だ、全く。
平時の基準年間1ミリシーベルトを20ミリにあげるって、緊急時に子どもが20倍も元気になるのかよ!!
原発労働者もいきなり不死身になる訳じゃないぞ!!!!